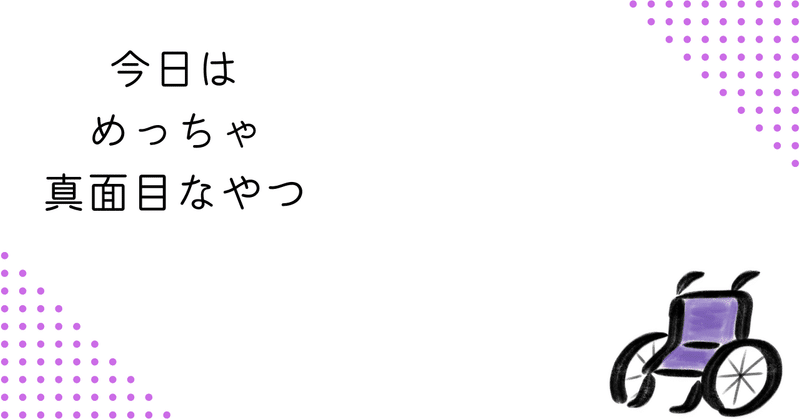
頭では先回りして、行動は「ほんのちょっと後手」という支援方法
これは生活介護事業所に限ったことではないですが、ご利用者さんの数だけ支援方法があります😊
大まかな方向性としての答えはありますが、この障害特性にはこの支援方法が絶対正解、ということはありません
ですので、こういう場合もある、と思って読んでもらえたら嬉しいです。
ここが難しい
15年近く勤めていても、未だに難しいなと感じるのが、「支援に入るタイミング」です
特に、ご利用者さんが「基本的には自分でできるけれど、場合によっては手助けが必要になる」というケースが難しいです。
自分で食べる事ができるけれど、疲れると手が止まってしまうご利用者さんの場合、どのタイミングで食事介助に移行するか判断が難しい、みたいな感じです
頭では常に「先回り」
上のケースの場合、自分で食べることができる状況が整っているという前提で、できるだけご利用者さん自身で食べてもらいます
そもそも、疲れて手が止まってしまうのは悪いことではないですし、見方を変えれば『疲れるまでは自分で食べることができる』わけです😊
ご利用者さんには自分で食べてもらいながら、頭では
・食べ始めの時間
・食事のメニュー
・ご利用者さんの直前の行動
などから、「そろそろ介助が必要かもしれないな」というタイミングを見つけ、さり気なく近くにいるようにします
あくまでもさり気なくがポイントです
あえて「ワンテンポずらす」
仮にそのご利用者さんの手が止まってしまったとします。この時に、すかさず食事介助に切り替える…だけが正解ではない場合もあります
(ここは本当にケースバイケースです)
支援者が「手が止まる=疲れた=食事介助」と思い込んでしまうと、ご利用者さんの要望と違う行動を取ってしまうかもしれません
・お腹が一杯で、「ごちそうさま」の意味で手を止めた
・手伝ってほしいけれど、伝え方がわからない
・自分で食べるために休んでいる
あえてワンテンポずらし、「お手伝いしましょうか?」と声をかける方法をとることもあります
その先の支援
そこから先、さらに「ご利用者さんとどう意思疎通をはかるか」という方法まで支援が発展していく場合もあります
頭では常に先の状況を考え、その時その時の最適解が見つけられるように…したいんですが…現実は結構シビアです
うまく行かないことのほうが多いかもしれませんが、生活介護事業所の生活支援員、思ったよりも頭を使っています🧠
「マスター、向こうにいるじゃんけん弱そうな顔した客に一杯」くらいの軽いノリでサポートしてもらえたら嬉しいです🌈「福祉の本を買う(知的に充実)」「シュークリームを買う(精神的に充実)」など、より良い記事を書くために使わせていただきます🍀
