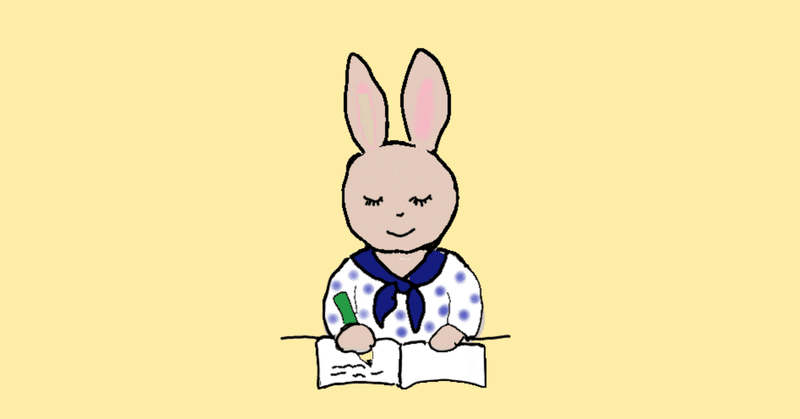
ギリギリ生存してるワーママが手のかかる小学生をどうフォローしているか
最近の小学生に関しては親がやることは多い。
スーパー手のかかる息子の毎日のフォローを乗り切っているなかで、便利なノウハウをまとめておくことにした。
親がやることって?
代表的なものとしては、宿題の丸つけ、水筒は年中持参、2年生で難易度上がる音読チェック、などなど、毎日ちょっとずつやることがある。
昔に比べ、先生の負担を減らし親が子を見る方向になっているかも?!
先生にもよるけど、うちの小2息子のクラスでは、タブレットを毎日持ち帰り充電、クラスの連絡をteamsでチェックする、などもある。
連絡帳も毎日親のサインが必要。
コロナはあけたが、給食の配膳中は全員マスクが必要ということで新年度からは給食袋にマスクを一枚入れるという業務も加わった。
なお教科書は、その日音読で使うものだけしか持ち帰らないので、次の日使う教科書をランドセルに入れる作業がないのはありがたい。筆箱の中身チェックと鉛筆を削る作業は早く子どもにやらせたいが、うちは私がやらざるを得ない状況なので宿題をやらせつつ済ませている。
その日の宿題を全て終えて連絡帳にサインをしたら、次の日提出するものを連絡袋に入れている。そして、給食袋と充電済みタブレットとともにランドセルへ入れて、ランドセルを玄関に置く。ちなみに、学童の着替えや習い事のものも同時並行で完成させ玄関に置く(白目)。
いつから全ての工程を子どもがやるようになるのだろうか…(遠い目)
ストックする
これはやっている人も多いと思うけど、いつでも学校へ持って行けるようにしている。
在庫が切れないようにしているのは、鉛筆、赤青鉛筆、消しゴム、マスク、靴下、小ぶりなティッシュ、ハンカチ、ジップロック、折り紙、のり、サインペン、絵の具、クレパス、ボンド、良い感じの空箱、ぞうきん、お名前シール。
ストックするつもりはなかったのだが、クーピーの鉛筆削りがなぜかなくなり続けたことがある(記名はしていた)。たぶん、削りながらゴミ箱に落としたのだろう。実は単体でも買えるので買った。
絵の具を洗う
密集を避けるためか、時間がないからか、はたまた低学年だからか?今の小学生は絵の具道具は家で洗うとのこと。
この作業、なにげにめんどい。
私は、家族みんながお風呂が終わった後、自分がお風呂に入る前にお風呂の洗い場で一気に洗ってしまう。
お風呂に入っている間はてきとうなタオルに広げておき、洗濯して(うちは夜洗濯)乾燥機に入れられないものを浴室乾燥に洗濯物を干す時に一緒に乾かす。筆もしっかり乾かした方が、筆入れに入れる時気持ちがいいので。
たまたま図工の時間割の翌日が週の中で荷物が少ないので、急いでやっている。
手のかかる子は、重たい荷物を持ったりたくさん荷物があることが負荷がかかる。
そのため、こうした、荷物の量と数のマネージも重要であると感じている(白目)。
少なくなった絵の具の交換
クーピーや色鉛筆、クレパスなんかは見れば量がわかるから交換は楽チンだ。
しかし、厄介なのは絵の具。
中身の量がわからない。そこで私がやっている方法は、ズバリ「重さを測る」である。

やり方は簡単。調理用のスケールに一つずつ置いていくだけ。
息子に少ないと思う色ある?と聞いて、その色を先に測る。そして、他のものも順番に測っていくと息子が言った色が最も重量が少なく、息子の感覚は凄いと思う。
上の写真のぺんてるだと20gを切ると少ないかな?と感じる。
同じ絵の具がうちにあるのでひとまず交換する。そっちも20gを切ったら、中身を統合(フィル?)したら良いと思うが、めんどくなったら新しいのを買うかもしれない。古くなると出にくくなるかもしれないし…
ドリルは写真撮影
計算ドリルと漢字ドリルが宿題に出る。
ドリル用のノートとドリルを持ち帰り宿題をすることになるのだが、ドリルを学校によく忘れてくる。
そこで、うちは、学校で新しいドリルをもらったら全て写真に撮る。
学校に起き忘れた日は写真をiPadで見せてドリルをやらせる。
ノートを忘れたら流石に宿題ができないけど、ドリルを学校に置いてきても宿題が終わる安心感はでかい。なお、ドリルは学校にしか販売されないのでスペアを買うことが出来ない。
音読をさせる
音読なんてただ読むだけ、そう思っていた私。
しかし、息子を見ているとそうでもない。
初めての文章には抵抗がある。
初めての言葉にパニックになる。
間違えるとパニックになる。
どこを読んでいるかわからなくなってパニックになる。
作者独特の表現に納得いかないと読みたくなくなる。
「は」と「が」の使い分けなど、気なることが気になって進まない
そもそもやりたくない。(目で追うのが苦手、色々考えながら口を動かす苦手さ?)
音読は高い山だった。
そんな人がこの世にいるとは知らなんだ。
どうしたら音読のハードルが下がるか息子をよく見て出した結論は、まずは、音声情報として慣れさせることだった。
一度知った文章なら特に突っかからず機械的に読めるようになるからだった。音読の質を高めるにも、まず、「読む」という動作を習得しないと話にならない。読む段階に駒を進める苦肉の策だ。
ではどうやって、文章とお知り合いになるのか?
語学学習の得意な方はよくやっている、シャドーイングというやり方だった。
私が読んだらすかさずついてきてもらう。ほぼ同時に2人が読むので集中力がいるし、こちらはなんだか疲れる。
どういうわけか、息子はこれが好きだったのである。
なぜ?!マルチタスクが嫌いなくせに、シャドーイング?!わけがわからないことばかりだが、うまくいくのでよしとする。
きっと、独特な感覚を持つ子たちは、「君は変だと言われるけど、どうしてかわからない。なんでみんな自分の感覚をわかってくれないんだろう?」と思いながら生きている。
たまには、大人が、子どもの当たり前に付き合って、居心地が悪い感じを体感するのも悪くない。
発達の気になる子の宿題
字がきれいになぞれない、空いたマスが気になってパニックになる、気に入らないと書き直したくなる、表の見比べで見落とす、時間に追われると余計にモタモタし始める、など、「なんでそんなところにつっかかる!?」と怒りたくなるシーンが常に訪れると思う。
まともに取り合って怒っていたら、怒る側も疲弊するし、宿題は終わらないどころか、「宿題なんてやりたくない」となって一家詰む。
私は、こうした、気まずい状況を毎日毎日、それこそ進学前の幼児教室時代からずっと積み重ねてきて、今思うことがある。
それは、子どもの宿題に対する態度は謎解きだということ。
宿題をするのは子の勤めだ。
だからといって、子に宿題をさせる勤めは親の勤め、とは思わない。できるようにさせるのは勤めとは思うが、なかなか難しい。
ただ、宿題は、親は子どもを読み解く謎解きのチャンスをもらってると思うとやる気になる。
卑近な例を挙げると、宿題の付き添いは夫より私の方が格段に早く終わる。私の方が謎をたくさん解いた証だと思う。教育の質は夫のほうが上手かもしれない。でも、宿題は終わってなんぼである。
始めれば終えられる、という自信をまずはつけたい。子どもが自分で始めて自分で終われるところまで持っていくのが次の目標になる。
道は遠いけど、なかなか、これはこれで味わい深い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
