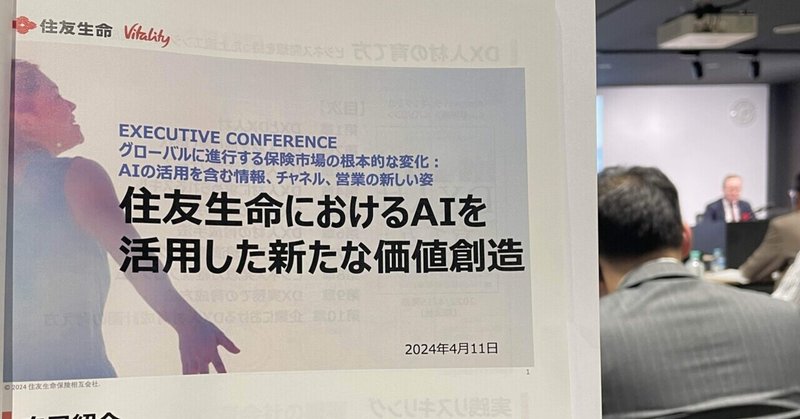
生成AIは便利だけど「問いをたてられない人が育つ」ことは避けたい件
はじめに
筆者は生命保険会社のCDOとして、社内のデジタル戦略や執行支援をする傍ら、顧問先やパートナー企業のDX支援、自治体向けのビジネス発想支援や官公庁のDX推進委員を務めており、日本全体のDX推進や人材育成のあり方を考える活動に携わっている。
先日、あるCIOエグゼクティブセミナーで講演をしたところ進行を担当された議長の方から質問をいただいた。それは
「生成AIはすでに提示された「問い」に答えを出すには便利だけど「問いをたてる」人が育たないのではないか。「問い」をたてられる教育をどうしているのか?」
というものだ。筆者はまさにそうだと思った。生成AIは便利だが、若年層、特に子供には危ないツールにもなりうると思うので今回はこれに関して考えたい。
与えられた「問い」と自分でたてる「問い」
生成AIの登場により、与えられた問いに対して正しい可能性の高いと思われる答え候補を出すことが容易になった。人はそれから自分の考えで正確な答えを出す必要があることは言うまでもない。例えば、「最新のマーケティング手法について教えてください」と聞けば、AIが膨大なデータを分析し、適切な答えの候補を提示してくれる。しかし、この便利さが人々の思考力や創造力を奪ってしまうのではないかという懸念がある。答えの候補でなく、答えに使ってしまうようになると、自分で考えることが面倒になり、自ら問いをたてる力が育たなくなる可能性も高い。
新しい価値を生み出すためには、自ら問いをたてることが不可欠だ。「なぜこの商品が売れないのか」「どうすればお客様の満足度を上げられるか」といった問いを自分の頭で考え、仮説を立てて検証することで、問題解決ができたり、イノベーションが生まれる。生成AI時代においては、この「問い」をたてる力をどのように育成するかが重要な課題となってくる。
問いをたてる人を育成する3つのポイント
1. 好奇心
子供の頃から身の回りの事象に対して「なぜ?」「どうして?」と疑問を持つ習慣を身につけさせることが大切だ。例えば、理科の実験で「なぜこのような結果になるのか」と生徒に考えさせたり、社会の授業で「この出来事の背景には何があるのか」と議論させたりすることで、問いをたてる力が育まれる。
学校教育においても、知識を詰め込むのではなく、生徒自身が問いをたてる機会を多く設ける必要がある。子供だけではなく大人も同様だ。例えば、営業担当者が「なぜこの商品が売れないのか」と疑問を持ったとする。その問いに答えるために、まずは顧客の声に耳を傾けることが大切だ。
アンケートやインタビューを通じて、顧客のニーズや不満点を深く理解する。さらに、競合他社の製品や販売戦略を分析し、自社の強みと弱みを把握する。こうした多角的な調査を通じて、「商品の機能が顧客のニーズに合っていない」「価格設定が適切でない」といった仮説を立てられるようになる。
また、エンジニアが「どうすれば生産効率を上げられるか」と問いをたてたとする。その答えを探るために、まずは現場の作業者の意見に耳を傾ける。「この工程に時間がかかっている」「この作業が負担になっている」といった声を拾い上げ、改善点を見つけ出す。さらに、他社の工場見学に行ったり、専門家のアドバイスを求めたりすることで、新たな視点やアイデアを得ることができる。
2. 多様な経験
さまざまな分野の人々と交流し、異なる価値観や考え方に触れることで、新たな問いが生まれる。例えば、営業担当者が研究開発部門の会議に参加したり、エンジニアが客先訪問に同行したりすることで、普段とは違う視点から問題を捉えられるようになる。企業や自治体は、社員や住民が多様な経験を積めるような環境づくりに努めるべきだ。
3. 失敗を恐れない
問いをたてるには、失敗を恐れずにチャレンジする姿勢も重要だ。例えば、新商品の開発に携わる社員が「この素材を使ってみたい」と提案したとする。それが今までにない斬新なアイデアだとしても、「失敗するかもしれない」と尻込みせずに、実験的に試してみる。仮に失敗しても、そこから得られる学びは大きい。「なぜ失敗したのか」「どうすれば改善できるか」と新たな問いをたて、次のステップにつなげていく。
生成AIを活用して問いをたてる
生成AIは答えを出すだけでなく、問いをたてるためのツールとしても活用できる。例えば、「新商品のアイデアを出してください」とAIに聞けば、これまでにない斬新な提案が返ってくるかもしれない。そこから発想を広げ、自分なりの問いをたてていくことができる。AIの提案をそのまま鵜呑みにするのではなく、批判的に検討し、自分の考えを深めていくことが重要だ。
まとめ
生成AIは便利だが、頼りすぎては価値創造はできない。生成AI時代に求められるのは、自ら問いをたてる力を持つ人材。教育、経験、組織の面から、この力を育成していくことが求めらる。生成AIを適切に活用することで、問いをたてるための新たな可能性も広がる。AIに支配されるのではなく、共生しながら創造性を発揮していくことだ。そのためにも、問いをたてる力を磨き続けることが必要だと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
