
『体育教師を志す若者たちへ』第2章 授業研究の面白さ ~バレーボール~
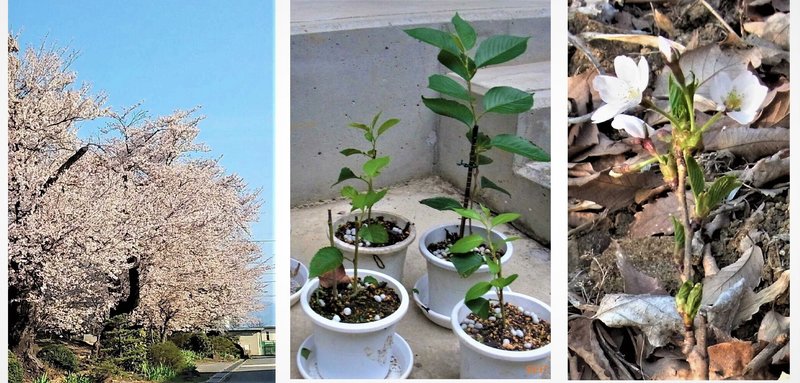
『体育教師を志す若者たちへ』、お読みいただきありがとうございます。連載を始めましたが、目次を最初に示すのを忘れていました。今回はまずは目次の紹介からです。
『体育教師を志す若者たちへ』 目次
はじめに
序章 問題提起
第1章 体育授業の難しさと醍醐味
第2章 授業研究の面白さ ~体育実技編~
1 水泳 ~人体の浮力と水泳への活用~
2 短距離走の授業で学ぶこととは?
3 バレーボール
4 バスケットボール
5 器械運動
6 武道
7 表現・ダンス
第3章 授業研究の面白さ ~体育理論編~
第4章 授業研究の面白さ ~保健授業編~
第5章 授業作り論
第6章 教材化と教育課程の編成
第7章 部活動と生徒会
あとがき
今回はバレーボールです。
第2章 授業研究の面白さ ~体育実技編~
3 バレーボール
◇国民的スポーツ
若い読者の方のなかには、中学校の体育授業でバレーボールを経験したことのない人たちがいるかもしれない。あるいは経験したとしても、ワンバウンドやキャッチOKのバレー、もしくはソフトバレーボールだったという人もいるだろう。しかし、読者の父母や祖父母でバレーボールをやったことのない人はまずいないはずだ。当時のバレーボールはどうだったのか是非聞いてみていただきたい。それはvolley(テニスやサッカーの「ボレー」と同じ)なのだから、当然のことながらボールは「落とさず、はじく」ルールだったはずだ。
バレーボールは戦前から文部省(文科省)の学校体操教授要目(学習指導要領)にもあり、戦後も多くの中学校や高校の体育授業で行われてきた。バレーボールが国民的スポーツになる起点は1964年の東京オリンピックだろう。女子が金、男子は銅メダルに輝いた。私が中学生だった1970年代では、長野県内のどの中学校にもバレー部があり、体育授業のバレーボールは3年間必修だった。
しかし近年では様々な球技が普及してきていることもあって、バレーボール人気は必ずしも高いとは言えない。学校体育でも「ネット型スポーツ」のひとつとしての位置づけにすぎず、従来の「落とさず、はじく」バレーは急速に隅に追いやられつつある。
◇バレーボールは難しいのか?
私はここで、「体育教師の教材研究」として、バレーボールの指導は難しいのかという問題と、「落とさず、はじく」バレーの魅力について考えてみたい。現在では小学校の学習指導要領にも「ネット型球技」が導入され、子どもの実態に合わせてホールディング、あるいはワンバウンドもありとすることでバレーボールのような球技も行われるようになってきた。しかし中学校以上において、過去には「国民的スポーツ」として「落とさず、はじく」バレーが盛んに行われていたにも関わらず、最近では以下の理由から指導を諦めたり、ホールディングやワンバウンドもありとする指導へと変わってきている。
私は長らく長野県教育研究集会の保健体育分科会で役員をしてきたが、近年では毎年提案されるネット型球技の指導レポートが大きく様変わりしてきた。そのことに疑問を持ち、「落とさず、はじく」バレーの授業を3年間受けてきた私の中学校の3年生に、以下のことをここ数年アンケート形式で聞いてきてた。
<生徒たちへの問いかけ>
「ボールを床に落とさずにはじくバレーボールは難しく、中学生が男女一緒の体育でそれを楽しむことは無理だという考え方があります。そしてバレーボールなどのネット型の球技の楽しさは、相手コートの空いているスペースを狙って打つことにあるという考え方から、そのために、特別ルールでレシーブやトスをワンバウンドやキャッチOKにしたり(相手コートへ返すときは打つ)している中学校があります。ボールを落とさずに返すことは無理なので、柔らかいソフトバレーボールにしている中学校もあります。
中学校によっては、バレーボールでネット型のスポーツを楽しむことは難しいと考えて実施せず、テニスのようなネット型の球技にしています。しかし、これも難しいと考え、普通のラケットを使用せず、手でボールをつかんで投げたり、バウンドさせてもいい数を増やしたりして、相手コートの空きスペースをねらって打ったり守ったりする作戦を大事にした学習にしている中学校があります。
本校では、1年生の時から落とさずにはじくバレーボールを行い・・・・3回以内ではじいて返し、三段攻撃の楽しさをみんなが味わうことを目指して学習してきました。あなたの学習してきた3年間のバレーボールはどうだったでしょうか?」(記述式で回答)
この問いの最後の方の「・・・・」に私の考案してきた指導法の説明が入るので、それは後で紹介する。数年間同じアンケートをとって分かることは、生徒たちが3年間男女混合チームで学習してきた「落とさず、はじく」バレーは圧倒的に支持されているということだ。
バレーボールクラスマッチが終わると、学年通信や学級通信で特集が組まれる。ある先生は2学年通信に次のように書いた。
「私はこれまで何校か中学校を経験してきましたが、本校のバレーボールは他の学校とは違い、とても魅力的です。一つ目は男女混合で行うところ、二つ目は特別ルールの・・・・・です。そのため、どのチームも必ずレシーブは男女関係なくセッターに向かって行い、セッターも男女関係なくトスを上げ、スパイクを打つという三段攻撃をしようとする意識が強くなります。男子どうし、女子どうし分かれてやる学校に比べてクラスみんなで応援し、仲も深まっていくのだと思います。」
「特別ルールの・・・・です」は、もちろんワンバウンドやキャッチ、ホールディングなどではない。ボールもソフトバレーボールではなく、中学生の公式ルールに近いボールを使用して「落とさず、はじく」バレーをしている。読者は「・・・・」は何だと予想するだろうか。
◇バレーボールの指導法研究
今から40年ほど前、私が新任教師になった頃はまだ、バレーボールは男女別チームで行われていた。学習のまとめとしてのクラスマッチでは、男子は2年生になると三段攻撃が頻発するようになるが、女子は3年生になってもとにかく返せ返せで試合が進んで行く。サービスエースだけで試合が進んでしまうこともよくみられた。クラス対抗だから盛り上がっているだけで、バレーボールを本当に楽しんでいるとは思えなかった。私は男子が夢中になる三段攻撃をみんなができるようにならないものかと思った。男子の場合は、1回か2回で丁寧に返していけば勝てる時でさえ、無理してでも繋いで打ちたがる生徒がいる。バレーボールという球技の面白さがそこにあるからだ。
つないで、上げて、打っていく三段攻撃中心のバレーをみんなで楽しめるようにさせたい。私は様々な文献に当たって指導法を調べた。そこで気づいたことは、バレーが国民的スポーツとなっていく1960年代から70年代にかけて、中学校現場にいた先生方は非常に緻密な実践研究を重ねていたということだ。しかし、こうした技術指導の系統性に関する研究は1980年代後半から急速に消えていく。その理由は第1章で述べたように、当時脚光を浴びていた「楽しい体育論」が技術指導を否定する方向へ動き始めたからだ。それは20年以上続いた。従ってこの時期に教員になった先生方は過去の文献に当たらない限り、戦後現場教師たちによって精力的に深められていった体育授業における技術指導の発展史を知らない。
私がこれらの文献の中で注目したのが、1982年に当時奈良教育大にいた高橋健夫氏らによる「バレーボール教材の初心者指導の方法に関する比較研究(Ⅱ)」だった。そこでは攻撃のコンビネーション学習ができてきたチームでは、オーバーハンドパスとアンダーハンドパスの比率がほぼ同数になるとあった。授業中の試合の様子を調べてみると分かるが、アンダーハンドパスとオーバーハンドパスのやり方を両方指導しても、試合になるとアンダーハンドパスの回数が圧倒的に多くなる。中にはアンダーハンドパスしか使わない生徒が何人もいる。これではオーバーハンドパスのやり方を教えても意味がない。試合の中でいかにしてオーバーハンドパスを使わせるか、これが指導ポイントになる。
そんなことを考えていたとき、たまたま休み時間に体育館へ来ていた女子生徒2人が、ネットを挟んで2人で1対1のオーバーハンドパスを楽しんでいる光景が目に入った。私はこれだと思った。オーバーハンドパスでは両手でボールを包むように触れるので、慣れてくれば接触面積の少ないアンダーハンドパスよりもボールコントロールがしやすい。彼女たちが遊びの中で自らオーバーハンドパスを楽しんでいるのは、ネットに接近した位置にいるからだ。では、ネットから離れてボールも高く上がっていった時に彼女たちはどんなパスの選択をするのだろうかと思った。
◇実験開始
私は、ネットからの立ち位置の距離、ボールの高さの違いで生徒たちはオーバーハンドパスとアンダーハンドパスをどのように選択するのか調べてみたくなった。実験は放課後の部活動のじゃまにならないように体育館のステージで行うことにした。ステージの壁の高い所に滑車をつけてひもを通し、そのひもの先にボールを吊した。もう一方を私が引いてボールを一定の高さにして止める。壁にはネットの高さがイメージしやすいようにバレーネットを2mの高さになるように貼り付け、それよりもやや高い2m75cm,3m50cm,4m25cmの3つの高さにボール上げ下げして止めた。生徒の立ち位置は壁(ネット)から2mと4m離れた2カ所にし、ボールを見た被験者の生徒がオーバーとアンダーのどちらを選択するか即答させるようにした。(下図)

アンダーハンドパスを使うか即答させる実験
実験は1人5分程度で終わる。2年生のあるクラスに協力してもらい、各自都合のつく放課後に来て実験を受けてもらうようにした。結果は図の通り。壁(ネット)から4mの位置では多くの場合アンダーハンドパスを使おうとするが、2mの位置である程度の高さのあるボールはかなりの確率でオーバーハンドパスを使おうとしている。従って生徒たちにオーバーハンドパスの有効性を説明した上で、ネットに近い距離(1対1だと数㍍程度になる)でオーバーハンドパスに慣れさせていくことが有効だと考えられた。
◇1対1の試合から始める指導
体育の授業はトレーニングの時間ではない。そこに学習の意味があり、そして楽しくなければ生徒たちは動かない。中学1年生の初心者でも早く試合がしたいだろう。そこで休み時間の女子生徒の遊びからヒントを得て、1対1のオーバーハンドパスゲームからスタートすることにした。ネットの高さは2m程度、コートの広さは3m四方程度にする。この方法だと、バレーボールが全く初心者の中学1年生でも第2時間目から審判をつけての試合ができる。そしてオーバーハンドパスがうまくなっていく。1人で返していくので、ダブルコンタクト(ドリブル)、トリプルコンタクトも認め、とにかく3回以内で返していくルールとした。冒頭に書いた私の考えた指導法、「・・・・・」のひとつはこれになる。生徒たちは審判の仕方も学習し、喜々として試合を楽しんでいく。
さて、そこからどう発展させるのか。これだけやってすぐに6人制に移っても、コートが広くなればまたアンダーハンドパスばかりになってしまうだろう。そこで次に2対2への発展を考えた。
今度は2人になるなのでダブルコンタクトは禁止していき、コートもやや広くして2人のコンビネーションで返していくようにする。しかしすぐに試合をすると、オーバーハンドパスは使うものの、とにかく1回で返せ返せの応酬となってしまう。これではバレーらしくない。卓球・テニス・バドミントンのダブルスと同じだ。ここで大事なことは、2人でパスをつなぐということになるが、1回で返すのか、2回、3回と繋いで返すのか、その判断が初心者には難しいとともに、自分はこう返していこうと考えても、ペアの相手にそれが伝わらなかったり、伝えてもそれに応じた動きが瞬時にとれなかったりする。
この2対2をどう教えるべきか。後になって分かってきたことだが、この2対2はその後の4対4や6対6へ発展していく基本的な学習内容を持っている重要な学習になる。基礎・基本という言葉があるが、基礎とはこれがまずできていないと学習がその後に発展していかないというベース・土台になる学習であり、基本とはその基礎を使いながら低いレベルから高度なレベルまで生かされていく幹になる学習であると私は考えている。先に述べた水泳では、息継ぎ・呼吸法が基礎になり、その息継ぎを使いながら様々な泳法に発展していく基本としての泳法がドル平といえる。
バレーの「基礎」はオーバーハンドパスと考え、これを1対1のゲームで指導した。次の2対2は「基本」と考え、その中身はつねに構えをボールの方向へ向け、2人のコンビネーションで相手コートへ返していくこととした。何も指導せずに2対2をさせると、2人はネットに対して平行に並んでいだり、多少の前後差をもって横に並ぶことが多い。これだとペアが1回で返すのか自分にパスをしようとしているのかが判断しにくい。バレーボールのミスは大方対応の遅れであり、早めに構えて動いていればミスを減らすことができる。構えをボールの方向へ向ける、返し方をペアに伝える、ミスに備える、この学習をしやすいようにするためには、2人はネットに対して縦(前衛と後衛)に並ぶことがよいことに気づいた。(写真)

◇特別ルール
ゲームの中で味方同士のパスを促すために、「必ず3回パスをつないでから返さなければならない」とする特別ルールを採用した研究授業を見たことがある。しかし、ネット際のボールは1回や2回で返した方が効果的なことも多く、それは「ネット際のプレー」として学習させたい大事な内容でもある。
ネットに対して縦に並ばせると、後衛にボールが行った際は前衛は180度後ろに構えを向けなければならない。後ろを見たり、横を向いたりするだけではダメで、両足を真後ろに向けるように指導する。後衛からのボールがどこへ飛んでいっても飛び出せる体勢をとる必要があるからだ。前衛が横向きに構えていると、自分の背中方向へ飛んでいったボールに対応できない。
前衛が構えを真後ろに向けることは、その都度しっかり声をかけたりペアで点検させていかないと常にできるようにはならない。それだけ面倒な動きだ。ところがせっかく構えを後ろに向けても、後衛が一回で返してしまったら後ろを向く意味がなくなり、初心者はそのうちしなくなってまたミスを生む。そこで特別ルールとして、「後衛はネットを越えてきたボールは一回で返さない」を考えた。
後衛にとっては、前衛の人がネット際のボールを1回で返そうが、ミスしてどこかへ飛ばそうが、前を向いて構えているので対応できる。一方ネットを越えてきたボールが後衛に行った際は、必ず前衛にパスされなければならないルールなので、前衛は構えを後ろに向けておく必要が出てくる。それができていなくて後衛からのボールに対応できないことはよく起こるが、その都度声をかけていくと構えを向けて対応できるようになっていく。
冒頭のアンケートに示した「・・・・・」は、オーバーハンドパスを中心にした1対1から2対2への基礎・基本学習と「後衛はネットを越えてくるボールを1回で返してはいけない」、加えて「サービスはアンダーハンドサービス」という特別ルールになる。この学習と特別ルールで1年生は4人制バレーボールへともっていく。2年生、3年生は6人制になるが、後衛の一回返し禁止ルールとアンダーハンドサービスルールは3年間採用してきた。それを生徒たちは圧倒的に支持しており、これなくしては自分たちの充実したバレーはなかったというのである。
なお、オーバーハンドパスは3年間重点的に指導していくが、アンダーハンドパスを禁止している訳ではない。アンダーだったり、片手でのプレーは自然に出てくる。面白いのは、私は3年間アンダーハンドパスは全く教えていないにもかかわらず、生徒たちは自然に覚えていく。オーバーハンドパスを優先的に使わせていく中で、どうしてもとれない低いボールに自分から対応しようとするからだろう。しかしアンダーハンドパスを教えてしまうと楽なのでオーバーハンドパスの出現率がどんどん低下していく。私は中学校の段階ではアンダーハンドパスは教えない方がよいと考えている。
こうした基礎・基本をつねに確認しながら4人制、6人制を進めていくが、ボールをどのように繋いで返していけばミスが少なく、カバーしやすく、三段攻撃をみんなが楽しんでいくことができるかを考えさせていく。
◇中学校でバレーボールを学習する意味
バレーボールは「ネット型」として他の球技とひとくくりにはできない、バレーボール独自の教材価値が存在している。バレーボールは指導の方法を工夫すれば中学生に大いに歓迎され、球技大会は盛り上がる。ここでは、他のネット型球技ではなく、なぜバレーボールを学習するのか、そしてなぜボールを落とさずにはじくVolleyなのかを考えてみたい。
まず第一に、多くの中学校にはバレーボール部があり、体育の授業の中にもその部員がいるということだ。そしてバレー部員に限らず、とかく運動部員は体育の授業は部活動に比べて楽で、手を抜いてもよいと思っている傾向がある。こうした生徒たちがワンバウンドやキャッチのバレーに真剣に取り組んでくれるのだろうかという問題がある。後述するが、私はバレー部員には部活動で日々やっているバレーよりももっとレベルの高いバレーの技能を要求するし、彼らが授業の中で学ぶべきことはたくさんあると考えている。そのことを彼らに学ばせて彼らの「バレー観」、「体育授業観」を変えたい。そしてバレー部員が手を抜かず、彼らの精一杯の奮闘によって他の初心者の生徒たちも一緒になってバレーの楽しさを追究できる授業を目指したいと考えてきた。
次の理由として、ネット型の球技の得点様式が挙げられる。特に落とさずにはじくという難しさを持ったバレーでは、ミスによって得点が加算されていく。25点対23点で勝ったということは、相手チームのミスが25回、自チームのミスが23回だったということになる。相手チームよりもミスが少なかったチームを勝ちとしているにすぎない。ミスがなければ試合は進まず、ミスすることが当たり前の球技なのだと言える。これはゴール型の球技とは大きく異なる得点様式であり、試合の最後は必ず誰かのミスによって終わる。特にバレーボールのようなチームによるネット型の球技では、その誰かのミスをチームとしてどう受け止めるのかということが問題になる。
オリンピックのメダルをかけた決勝戦でも、最後には誰かがミスをして終わる。しかしそのとき、そのミスをした人を責めるようなことは当然しない。ところが中学生のバレーの授業ではミスした人を責めることになりがちだ。バレーとはそういうものではないということを学ばせる必要があり、そこに価値を見い出したいと考えている。
◇バレー部員が授業で学ぶこと
バレー部員の話に戻そう。授業の中でバレー部員が上げたトスを打てなかった生徒がいたとする。多くは打てなかった生徒のミスと考えがちだが、そこには「バレー部員は上手、他の人は下手」という能力観がある。しかし、そのアタッカーの立場から考えてみると、初心者でも打ちやすい高さでよい位置にトスが上がっていたとしたら打てたかもしれない。私はバレー部員にそのことを要求する。
右手で打つアタッカーに対しては、正確に右肩の上〇〇cmの高さのトスを要求するのだ。部活動で彼らが上げているオープントスのような高いトスは、初心者にとってボールの落下地点が読めず、高く上がるほど落下スピードも上がるので対応できない。そのアタッカーに合ったよいトスが上がり、それで打てるようになれば二人の喜びになるし、打てなければ「いいトスが上げられなくてゴメン」ということにもなっていく。二人は対等の関係で上手くなっていくことができ、生徒たちの「能力観」に揺さぶりをかけていく。
役割を交代しよう。初心者がいいトスを上げられないのは当然であり、放っておけばアタッカーのバレー部員はそんなトスは打とうともしない。しかし、バレー部員ならどこに上がるか分からないそのトスを返球できる技能を発揮すべきと考えたい。レシーブも同様。部活動ではレシーブはセッターに送られるのが当然だが、授業の中ではレシーブはセッターに届かないのが当たり前。バレー部員ならどこへ飛んでいくか分からないそのボールを拾いに行き、トスにする。つまりバレー部員には部員にふさわしいレベルの高い技能が要求される。そのことが理解され、チームができてくると、「ミスしてゴメン」と「カバーできなくてゴメン」が対等の関係になってみんなでバレーを楽しむことができるようになっていく。
この関係が校内球技大会・クラスマッチなどで発揮されるようになるとみんなで応援し、みんなで盛り上がって楽しむバレーが男女混合の異質集団で展開されていく。そこまで持っていく教師の指導は簡単ではないが、そこに醍醐味がある。
◇生徒たちの思い
年度末に発行される生徒会誌に、ある3年生がバレーボールクラスマッチの思い出を次のように書いていた。
〇「このクラスマッチの目標は全員トス、全員アタックでした。バレーの楽しさは三段攻撃でつなぐことです。・・・最初はうまくいかず失敗してしまう場面が多かったけど、誰一人としてその人を責めることはせずに励まし合っていました。このように前向きな姿勢でプレーすることで、バレーが苦手な人でも楽しめるようになることを学びました。」
数年にわたってとってきた冒頭の3年生に対するアンケートから分かることは、落とさず、つなぐバレー、そしてそのための後衛の一発返し禁止ルールは生徒たちから圧倒的な支持を得ている。第1章でも紹介したが、バレーが苦手だったある生徒は、アンケートに次のように書いてきた。
〇「私は運動をあまりしないし、体育も苦手でバレーボールを男女別でやらないなんておかしいと思っていたのですが、1年生の時、2年生の時、だんだん学年が上がって行くにつれてバレーボールって楽しいな、と思うようになりました。初めはオーバーハンドパスさえも全然できなかったのに、今では三段攻撃やカバーができるようになってきて、協力していくことの大切さ、喜びを知れる、とてもいい学習だったと思っています。男女一緒にやるからこそ、男女の壁もなくできて良かったと思っています。また練習時や試合本番もそうなのですが、誰かがアタックをした時には『〇〇ナイス!』や『いけ~!』などの言葉、誰かがミスした時は『しかたない!』『大丈夫、大丈夫!』などの励ましの言葉。これ男女関係なく飛び交う姿は男女混合でやっていることや、みんながこの通常ルールに近い常盤中式バレーボールに熱中していることがとてもよく分かり、すごくよいチームワークだなと感じました。この中学校3年間のバレーボール学習では、とても悔しかったとき、喜んだとき、いろんなことがありましたが、とても楽しかった学習だと感じています。」
また、別の生徒は1年生からの学習を振り返って次のように書いている。〇「1年生の時からオーバーハンドパスを重視した公式と同じようなルールでやることで、バレーボールの『3回で返す』や『三段攻撃』が2年生、3年生になってから面白さがどんどん増していった。また、面白さが増すことでバレーのチームメイトとの仲が深まった。」
〇「私は男女一緒にできるだけ通常のバレーボールに近い形で行うことができて良かったと思っている。1年生の時からボールを落とさないようにするために声や体の向き、体勢などを意識してきた。それによってボールを落とさないこともけっして無理ではなかったし、ボールを落とさないようにすることによってチームプレーがより高度なものになったと思う。1対1からしっかりと練習しなければ自分は上手くバレーボールを楽しめなかったし、通常のバレーボールに近いルールでやることによってバレーボールというスポーツの面白さを深く理解できた。」
落とさず、はじき、つないで三段攻撃で相手コートへ返していくバレーだからこそ得られる価値がある。その過程ではミスもたくさん生ずるが、それを個人のせいにするのではなく、「カバーできなくてゴメン」というチームの責任として感じながらバレーを楽しんでいく。それはよりよく「共に生きる」へともつながっていくことになる。そうした価値を生徒たちは感じて追究しようとしている。
※次回はバスケットボールについて考えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
