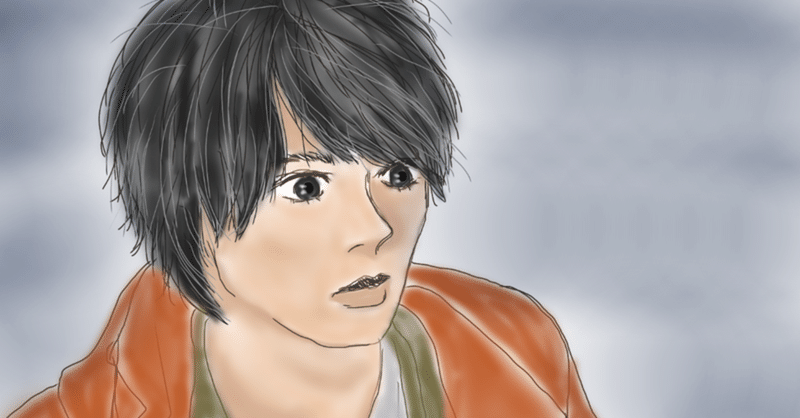
マリリンと僕24 〜風に吹かれて〜
山村さんから電話があってから2日後の朝、僕はホテルのベッドの上にいた。横には裸の山村さんが寝ている。僕もやはり、裸だ。
自分でも状況がつかめず、昨日のことを思い出そうとしたが、何か考えようとすると脳に鋭い刺激が走り、思考が強制停止させられた。どうやら二日酔いということだろう。
少しずつ断片を繋いで、記憶を辿る。
2日前、菅原と会った後に山村さんから着信があった。マリリンの出て来た夢が脳裏をよぎり、一瞬躊躇ったけれど結局電話に出ることにした。
「今度の金曜日、月野さんのご都合は如何ですか」
山村さんが端的に言った。アポ取りの電話で、特別な感情はこもっていないと取り繕うような言い方。誰か側にいるのだろう。
「その日は特別に予定はありませんよ。何時でも大丈夫です」
僕も同じように端的に返した。先日会った時、仕事以外で会えないかと山村さんから問われた僕は、「都合が合えば」と言ってしまった。事実として、金曜日は予定がない。予定がないのだから、会えない理由も、やはり無い。
そして僕は指定された午後7時に、指定された場所に向かった。それは僕が今ベッドの上にいる、四ツ谷にあるホテルだった。ホテル内のバーで食事をしながらお酒を飲み、そのまま部屋に泊まったのだ。山村さんがオーダーしてくれたお酒を、結構な量飲んだのだと思う。何故泊まることになったのだろうと考えるが、途中からの記憶は辿れない。目の前の現実として、僕は裸でベッドの上にいて、隣には裸の山村さんが寝ている。おそらく、“そういうこと”なのだろう。
時計が7時になったと同時に、山村さんのスマートフォンのアラームが鳴った。
「ごめんなさい、月野さん、先に起きてたんですね。アタシ、熟睡してしまって」
山村さんが言った。ベッドの上で、裸のままでも敬語を使う山村さんに、僕はやはり好意を感じてしまう。
「いえ、僕も起きたばかりです」
僕も同じように敬語で返した。
山村さんは僕より少し歳上のはずだ。話している感じだと30歳を少し過ぎた辺りだろうか。しかし、その裸体は若々しい張りを維持していて、女性の理想のような、メリハリのあるボディライン。それを隠しもせずに話しかけてくるものだから、思わず黙って見惚れてしまった。
「そんな風に見られたら恥ずかしいわ」
山村さんがシーツで隠しながら言った。
「あっ…すみません。見惚れてしまって…」
他に言葉が見つからず、そのままを口に出した。
「嬉しい。思っていても、なかなか直接は言ってもらえないもの。言ってくれたとしても、そこには概ね下心が含まれているの」
僕だって、普段ならこんなことは言わない。
「月野さんも、素敵だった」
山村さんが言った。
「えっ?」
僕の記憶は今、ひどく曖昧だ。
「おとなしい印象だったから、アタシがリードする感じだと思ってたけど、そんなこと無くて…、それに…ご立派だったから、驚いちゃった。ギャップがすごくて」
山村さんの視線は僕の下半身に向けられていた。僕は慌てて手で隠した。
「そんな可愛いことされたら、余計にいじめたくなっちゃうなぁ」
悪戯な視線はずっと僕のソレを捕らえている。
「アタシのカラダは…、時折メンテナンスをしているの。話してなかったと思うけど、旦那が美容外科を経営しているから、そこでね」
山村さんが既婚者なのはわかっていたが、当然ながら、その話には触れて来なかった。
「後遺症が残りそうなことは避けているわ。旦那は大丈夫って言うけど、やっぱり心配よね」
「すみません、俺、こんなつもりじゃなかったんですけど…」
夫の話をされて、急に罪悪感に苛まれた。過去にも同じ経験をしているが、学習しない自分に少し呆れる。
「そんなこと仰らないで。ウチは平気なの。旦那がね、下半身に自身が無くて、こういうことに積極的になれなくて。アタシは気にしないでって言うんだけど、そういうのって、自尊心の問題じゃない?他人に言われてもダメなのよね」
僕はそんなことを気にしたことが無かった。
「月野さんぐらいご立派なら、きっと気にせずにいられるのでしょうけどね。アタシには美容整形を薦めるくせに、自分のことになったら『怖いじゃん』って言うの。まぁ…そういうところが可愛いんだけど。そんな感じだから、アタシが外でこういうことしてるのも、わかってるけど、何も言わないの」
「そうなんですね」
それぐらいしか、返す言葉が見つからない。
「心配しないで下さい。アタシから誰かに漏らしたり、月野さんの迷惑になるようなことはしないですから。あと…、ちゃんと避妊もしてますから、その辺りも心配しないでね」
そう言って山村さんは微笑んだ。薄ら浮かんだほうれい線が、年齢相応の美しさをより際立たせた。
「さぁ、シャワー浴びて準備しないと」
土曜日だが、山村さんは仕事の打ち合わせが朝からあるらしい。シャワーを浴びて、テキパキと準備を進めた。僕は山村さんが化粧をしている間にシャワーを済ませ、元着ていた服に着替えた。
「アタシ、先に出ますね。チェックアウトだけお願いします」
山村さんは僕の正面に立ち、首に手を回して頭を下げさせた。ハイヒールを脱いだ山村さんは思ったより小柄で、僕よりも頭一つ以上小さい。そんなことを思っていたら、唇に軽いキスをされた。
「ありがとうございました。もし嫌じゃ無ければ、また誘わせて下さい」
笑顔でそう言って、山村さんは部屋を出た。一人になった僕は、しばらくボーっとして、ただ座っていた。まるで白昼夢でも見ているようだった。
静寂を破ったのは、スマートフォンの着信音だった。画面に表示されていたのは、桜井の名前。
「おい、お前何してんだ」
桜井は何だか怒っているようだ。
「え、何って、何も」
説明することなど、出来るはずがない。
「ちなみが連絡取れないって騒いでんぞ。電話もメールも返事が来ないって」
ちなみとはマネージャーの萱森さんのこと。桜井にとって萱森さんは従姉妹なのだ。僕は昨日の夜から、一切スマートフォンを見ていない。
「あっ、申し訳ない。全然気づかなかった」
仕方なく、取ってつけたような言い訳をした。
「あのなぁ、大事な仕事の前なんだから、マイペース過ぎるのはさすがにマズイぜ。事務所も入って、お前だけの問題じゃないんだからな」
「あぁ、本当にすまない。すぐに萱森さんに連絡入れるよ」
「そうしてくれ。なんか知らないけど、俺がめちゃくちゃキレられたからな、お前の代わりに。意味がわからん。俺だって今、脚本のことで頭がいっぱいなんだぞ」
桜井が恨めしそうに言って、電話を切った。
「ちょっと何してたんですか、陽太さん!」
電話に出るなり、萱森さんは怒っていた。
「すみません、気がつかなくて」
とりあえず謝るしかない。
「何してたら気づかないんですか。もしかして、アタシという者がありながら浮気ですか」
ありながらって言われても、そういう関係じゃないと思う。
「お酒飲んだら眠くなって、結局そのまま朝まで寝ちゃったみたいで」
取ってつけたような言い訳だ。さっきもした気がするが、今はそれしか出来ない。
「撮影始まったら許されませんからね」
「はい、今後は気をつけます」
「ご飯奢って下さい」
「え?」
「焼肉奢って下さい」
「えっ?ど、どういう意味ですか」
なんとなく、わかってはいるが。
「マネージャー困らせ罪です」
なんだそれは。まぁ、良いけど。
「はぁ、わかりました。でも、昨日は何の連絡だったんですか」
肝心の話を聞きそびれるところだった。
「ドラマの取材が決まりました、すぐじゃないですけど。それも含めて、今日の夜焼肉屋で話しますので。追って待ち合わせ場所もメールしますね。アタシこの後現場行くので忙しいんです」
それだけ言うと、萱森さんは電話を切った。とりあえずは怪しまれずに済んだようだ。とは言え、取材が決まっただけならわざわざ呼び出さなくても、それこそ電話かメールで良さそうに思うのだが。
釈然としない思いを抱えながら、チェックアウトを済ませてホテルを後にした。宿泊料は既に支払われていた。
午前9時、空はすっかり陽も昇り、雲ひとつ無い冬晴れだ。気持ちの良い外出日和だったが、まずは服を着替える為に、一度自宅に戻ることにした。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
