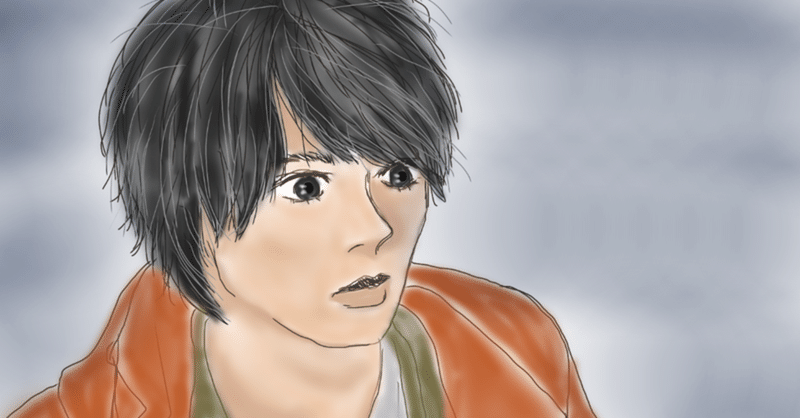
マリリンと僕22 〜定まらない体と心〜
萱森さんからの電話で急いで自宅アパートに向かうと、萱森さんと一緒にいたのは元カノの絵莉だった。
まさか僕らの関係性まで話してはいないだろうなとか、そもそも絵莉はどこまで知ってここに来ているのだろうかとか、正常に機能していない思考をぐるぐると空回りさせながら、出来る限り動揺を隠して二人に声を掛けた。
「ごめんなさい、お待たせしました」
ひとまず待たせてしまったことを詫びた。
「遅いですよー。毎回待たせてー」
萱森さんが、わかりやすく怒った顔を作って言った。その顔もまた可愛いと思うと同時に、そもそも萱森さんが毎回早いんだけどなぁと、僕は思う。
「どうせならと思って、本人連れて来ちゃいました。深谷さんもスケジュール空いてるって仰ってくれたので。ね、深谷さん」
過去のことを知らない萱森さんは僕のことを思って絵莉を連れて来てくれたのだが、僕としては複雑極まりない心境だ。絵莉はどう思っているのだろう。
「そうですね。アタシも役作りがしやすいし、良い機会だと思って。月野さんとお会いするのも久しぶりで、楽しみだったから」
それは全くの嘘だった。最後に会ってから一ヵ月くらいしか経っていないし、その日、僕らはセックスをした。ツキノサンなんて絵莉に呼ばれると、なんだか自分が自分でないような気にさせられる。
「立ち話もなんですから、部屋に入りましょー」
萱森さんがおどけて言った。
「それ、僕のセリフですよ」
僕はツッコミを入れた。
「仲が良いのね」
そう言って絵莉が笑った。その言葉に特別な意味合いは含まれていないようだった。
「でも、僕の部屋だとそんなに大きな声出せないですよ。安アパートだから、壁も薄いですし」
本当は、しばらく隣部屋は空いていて、余程じゃなければ問題はない。ただ、絵莉と過ごした期間を考えてしまって、余計に役作りどころじゃ無くなりそうな、そんな気がしたのだ。
「え、でもお隣さんいないですよね?さっきポスト見たら郵便物溜まってましたし」
バレていた。さすがだな、萱森さん。感心してる場合でも無いのだけど。
「アタシはどこでも大丈夫ですよ。月野さんにお任せします」
絵莉はそう言った。
二人でいた頃、僕はほとんどの決定権を絵莉に委ねていた。絵莉は自分で決めるのが好きだったし、僕もそれが楽だったからお互いにちょうど良かった。セックスをする時だって同じだ。それが僕らにとっての普通だった。だから、「お任せします」なんて絵莉の口から聞いたのは、もしかしたら初めてだったかも知れない。
「じゃあ、部屋で良いですか?」
別の場所に移動するのは、逃げたように思われそうな気がした。
「深谷さんも良いですか」
萱森さんが尋ねた。
「えぇ、アタシは全然大丈夫」
絵莉の表情は、それは特別なことではないのよ、と僕に伝えていた。
結局狭い部屋の中で、絵莉はソファに、僕はベッドに座って読み合わせをすることにした。
「じゃあ、後は2人にお任せしますね」
そう言うと萱森さんはその場から外れ、部屋の端にクッションを置いて腰掛けた。自分は稽古には必要ない、ということだろう。
「セリフはもう頭に入ってる?」
絵莉が僕に聞いた。
「うん、セリフ自体はもう大丈夫なんだ。ただ、もっと根本的な部分でこの役のイメージが掴めていない」
「相変わらずね。この量のセリフ、もう覚えてるなんて、アタシにはとてもじゃないけど真似出来ないわ。台本見ながらでも良い?アタシは役のイメージは大丈夫だから」
「問題ないよ」
そのようにして、僕らは読み合わせを始めた。
実際に合わせてみると、不思議な程スムーズに役に入り込めた。絵莉は絵莉であったし、僕も同じように、僕じゃないようだった。自然とそうなったような気もするし、絵莉に導かれたような気もする。いずれにせよ、2〜3回の読み合わせで、なんとなくイメージは固まった。
「めっちゃすごいじゃないですかぁ…」
こっちを見ている萱森さんは、何故だか目を潤ませている。
「2人の演技、演技じゃないみたいで、アタシ感動しちゃいました」
演技じゃないみたい…。もしかしたら、これは演技ではないのかも知れない。それなりの期間、僕と絵莉は共に過ごしたのだから、僕らが男女を演じた時に、それをゼロにすることは無理だろう。
「やっぱり俳優さんってすごいんだなって、陽太さんのこと、ちょっとだけ見直しました」
毎度発言に、何かしら毒を感じるな。
「深谷さんも本当に素敵です。もっと世の中に知られてておかしくないのにって、心から思います」
それは僕も、心から思う。
「幸運のお裾分けを頂いたのよ」
絵莉がそう言った。
クリスマスの夜、僕と絵莉は再会した。絵莉は「幸運にあやかりに来た」と言った。そしてその夜、僕らはセックスをした。絵莉から求めて来て、それはとても濃密な時間だった。きっと絵莉はそのことを言っているのだろう。無論、僕にそんな能力があるはずもない。
「幸運の、お裾分け…ですか。へぇ、私も分けてもらいたいですー。お金持ちのイケメンと出会いたいです」
表現が素直過ぎるよ、萱森さん。
「そうね、あるいはもうもらってるかも知れないわね、お裾分け」
絵莉が思わせぶりに言った。僕は内心動揺していた。萱森さんに知られるのは、出来れば避けたい。
「えー、全然ですー。現場にはイケメンいますけど、こっちから声掛けるのは軽く見られそうだし、声、掛けられないですし」
全く気づいていなかった。と言うか、そんなこと考えいたんだね、萱森さん。
「仕方ないから陽太さんで良いかなって、最近は思ってるんですけど」
陽太さんで、も気になるし、そもそもマネージャーだよね?と思いつつ、いつもの冗談なのは重々承知している。
「あら、それも良いかも知れないわね」
絵莉が言った。こちらも冗談なのだろう。さすがに僕で遊び過ぎだと、不満な顔をして見せる。
「陽太さん、そんな顔も出来るんですね。さっきのが冗談かどうかは、今日はノーコメントにしておきます。知りたかったら事務所通して下さい」
それは僕が言うコメントだよ。どこまでも二人に振り回されて、でも本当は、全く嫌な気はしていない。いや、むしろ嬉しいと思っている。僕にはこれが、自然体なのだ。
「あっ、やばっ」
萱森さんが急に顔をしかめた。
「何かありました」と僕が聞くと「アタシこの後升野さんの現場行かなきゃいけないの、すっかり忘れてました」と言って、慌てて荷物を持って飛び出して行った。去り際に「陽太さん、絵莉さんに手ぇ出しちゃダメですからね!」という言葉を残して。
「二人になっちゃったわね」
絵莉が言った。
「うん、そうみたいだ」
僕が言った。
「少なくとも、アタシは本当にアナタのおかげだと思っているの。だって、あの夜アナタと寝てからだもの。アタシは何も変わっていないのに、周りの見る目が変わった。それで急に、こんな役をもらえたのよ」
「僕はそうは思わない。君はずっと素敵だったし、君が女優として成功しないなんておかしなことだと僕は思ってた。だから、君の実力だし、君に魅力があるからだよ」
それは僕の本心だった。
「ありがとう」
絵莉が言った。
「どういたしまして」
僕が言った。
「でも、ちょっと驚いたわ。アナタがこんなに演技が上手だなんて、思わなかった」
それは現実の話なのか、演技の話なのか、僕にはイマイチわからなかった。
絵莉はソファから立ち上がり、ベッドに腰掛けている僕の横に来て、そしてキスをした。
「ダメだよ、バレたらまずい」
僕はまた、嘘をついた。
「バレないわ。それに、アタシがここにいる時点で、中で何かがあってもなくても、同じようなものよ」
「それは確かにそうかも知れない」
結局僕は受け入れてしまった。
そのまま僕らは体を重ね合わせた。
絵莉が僕の体を刺激している時、またマリリンの言葉がよぎった。
「気ぃつけなあかんで」
しかし、その言葉は快楽によってかき消されてしまった。それだけ絵莉は、僕の体のことを熟知していた。僕らは快楽に身を委ね、お互いを確かめ合うように心を溶かした。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
