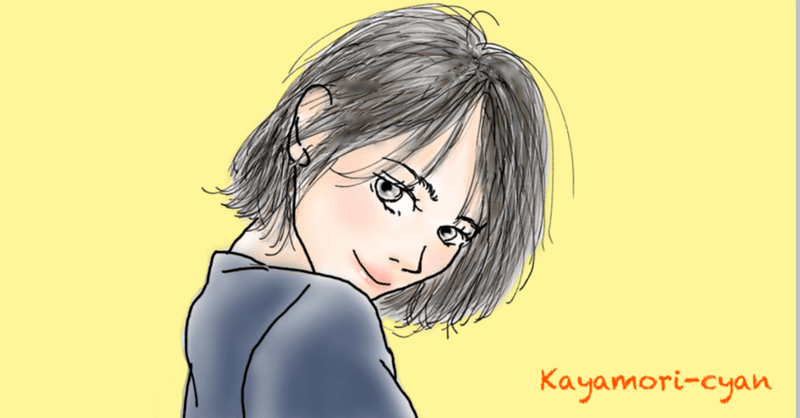
マリリンと僕30 〜恋にも演技力は必要か〜
「よ、よう…たさん、何してるんですか」
自分でもハッキリとした理由はわからないが、自然と体が動き、萱森さんを抱きしめていた。
「わかりません」
「わかりませんって…、あの、この状態でわかりませんって言われてるアタシはどうすれば良いんですか」
「えっと…嫌…ですか」
「んー、悪くはないです。悪くないし、嫌でもないんですよ。むしろ胸キュンシチュエーションですよ。だからこそ、『わからない』は最悪なんです」
この状態で説教されるとは。
「すみません」
「なんでそこだけいつも通りなんですか。『ずっとお前が好きだった』とか言われたら、アタシもノリで『嬉しい』とか返せるのに」
萱森さんは不服そうに口を尖らせているが、僕はお前なんて呼んだこと、一度もない。
「ノリ、ですか」
「そりゃイケメンにそんなことされたら、こっちも勢いで言っちゃいますよ。全く気が無ければ別ですけどね」
またこういう複雑なことを言うから困る。
「で、いつまでアタシは抱きしめられたままなんですか?車、動かせませんよ。誰かに見られたら大変じゃないですかぁ」
そう言えば、ここはまだ、テレビ局の駐車場だ。
「そう…ですね。でも、すごいしっくりくるんです、萱森さん」
心の部分も含めて、とても収まりが良い。
「なんなんですか、しっくりってぇ。もー、アタシは抱き枕じゃありませんよ。やり直しです。やーりーなーおーし」
こういうのって、やり直しがあるんですか。まるでドラマのリテイクのようだ。
車を動かして局を出た。萱森さんは帰る車の中で運転しながらも、「役者なんだから、ああいう時だってちゃんと演技してくれたら良いのになぁ」などとずっとブツブツぼやいていて、その度に僕は「すみません」と謝った。
萱森さんの本心が何処にあるのかはイマイチわからないけれど、自分の想いは、なんとなく理解し始めていた。
翌日からもハードスケジュールが続いた。
早朝に集合して、夜遅くまで撮影が続く。1時間ドラマほどではないにしても、やはりスケジュールはタイトだ。撮影場所は多岐に渡り、合間にプロモーションの為の取材やテレビ出演もある。今回僕は主要キャストで出番も多いから、完全にオフになる日はほとんど無い。移動も多いから毎日クタクタになるが、主演の影山の存在や、萱森さんが迎えに来てくれるから、充実した疲れ方だった。
「陽太君って普段全然自信無さげなのに、なんで撮影始まるとあんなにちゃんと演技出来るんすか?二重人格?」
影山にそう言われた。裏表の無い影山だから、本当にそう思ってくれているのだろうと、僕も思える。歳下ながら尊敬出来る相手と共演出来るのは、今の僕にとって一番のモチベーションかも知れない。
2話目の撮影からは絵莉との共演シーンもある。台本で把握はしていたが、いきなりベッドシーンから。僕は前貼りをしてもらったけれど、絵莉は「必要ない」と断ったらしい。監督やスタッフの誰も僕らの関係を知らないから、「すげぇ度胸だな」とか「未知の逸材見つけたな」とか、大きく株を上げたようだ。実際絵莉の演技は堂々としたものだったし、僕も役に入っていたからプライベートでのセックスを思い出すことはなかったが、監督のOKが出た後に、周りに気付かれないようにして、さりげなく僕の下半身を刺激しながら悪戯に笑う絵莉は、女優ではない、以前から僕が知る絵莉だった。
『恋人たちの教室』2話目のあらすじ。
僕と絵莉がホテルから出て来たところをたまたま通りがかった三原が目撃する。三原は影山と喧嘩したばかりだったこともあり、見知らぬ美女と親密な関係にある僕に、諦めるどころか余計に興味を深める。一方、影山と三原の喧嘩の原因は、影山と女子生徒のLINEのやり取り。女子高生とは思えない色気を放つ優麻(ゆま)からの強引なアプローチをかわせず、影山はデートの約束をしてしまっていた。
注)劇中は全員別の役名で演じています。女子高生の優麻を演じるのも、女子高生ではなく二十歳のグラビアアイドルです。
今日の僕の撮影シーンは夕方までだった。萱森さんは別のタレントに同行していて、別の若手男性マネージャーの赤井が迎えに来てくれた。
「ドラマ、話題になってますね」
車を走らせながら赤井が言った。影山の主演による話題性と、最近では珍しいラブコメというジャンル。深夜帯ということもあり、自由度の高さも期待値につながったようだ。
「観てもらえると嬉しいです」
まだ実感が薄い僕は、定型文のような返事をした。
「月野さんの引っ越し先決めるから、来週事務所に来てほしいって、松岡部長から伝言を預かりました」
松岡さんは僕がマネジメント契約している、キャッスル・エンターテイメントのマネジメント事業部のトップだ。
「そうなんですね。すっかり忘れてました。その話」
「月野さんの希望もあるから、時間かかってたみたいですよ。でも、候補が2つ上がってきたからって言ってました」
出来るだけ今の住所から離れたくない、というのが僕の唯一の希望だった。
「たぶん今日明日中に萱森さんからメールが行くと思います。今日も本当は萱森さん来たがってたんですけどね。男の僕ですみません」
僕は何も思ってないのに、赤井は勝手に謝った。いや、何も思ってないと言うのも嘘になるかも知れないと、独りごちた。
三原さん可愛いっすねとか、深谷さん艶っぽいっすねとか、よく喋る赤井の話し相手をしている間に家に着いた。
赤井に礼を言い、車が走り去ると、僕はいつもの公園に足を向けた。撮影が続いている間はなかなか夕方には帰れない。缶コーヒーを買って公園に行くと、夕闇みに溶け込むようなゴスロリのドレスに身を包んだマリリンと、黒猫のジジが遊んでいた。
「近い内に引っ越しすることになりそうだよ」
僕がそう伝えると、マリリンは細く垂れた目を限界まで見開いて、驚いた顔をした。
「兄ちゃん、ウチを見捨てるんやな…」
今度は世界が終わるかのような絶望感を顔で表現している。今にも泣きそうだ。
「結婚でもするん?ドラマ決まって人気者になって、お金ガッポリもろて、天狗になって、モデルと結婚でもするん?」
話の跳躍が酷い。
「いや、大丈夫だよ。結婚もしないし、この近くに住めるようにお願いしてあるから。ちゃんと会えるよ。それに、相変わらずお金は無いよ」
小学生相手に僕は何を言っているんだろうか。
でも、僕にとってもマリリンの存在は大きくて、マリリンを大事にしないと、全てが元に戻ってしまいそうな気もしている。だからこそ、引っ越しの話をされて唯一希望したのが、「このエリア内での移動にしてもらいたい」ということだった。無論具体的な理由は言っていないが。
「そうなん!?ほなら始めからそう言ってぇや。ひとりぼっちは嫌やて、前にも言うたやん」
「でも、卒業したらアメリカに行くんだよね?」
「うーん、わからへん。オトンからはそう言われてるけど、オカンは嫌がってんねん。仲はええねんけど、ずっと一緒はしんどいんやて。そんなんウチに言われても、普通みんな家族って一緒に住んでるんちゃうの」
「うーん、昔はそうだったろうけど、今はいろんな家族の形があるからね」
大人らしく、もっともらしいことを言ってみた。
「形?家族って形あんの?台形?平行四辺形?アカン、ウチ面積の計算式全然覚えてへんから無理や。ちっともわからへん」
伝わってないし、最後何の話してる?
「兄ちゃんも少しずつ変わって来とるな」
「え、僕?」
「そやで。こないだまで嫌な匂いしてて、女の人のやで、でもなんか薄まってんねん」
マリリンにしかわからない感覚なのだろう。僕にはそれがどういう意味で言っているのか、よくわからない。
「ドラマも見させて頂きましてんけど、まるで兄ちゃんとは思えないような、別人になってまして、すごいなぁと思いましたわ」
急に変な敬語を遣い始めた。
「あー、ウチも出てみたいわー」
それが言いたかったのね。
「出してもらえん?」
「そ、それは僕には決められないから…」
「ねぇ、出してもらえん?」
全力で物欲しげな顔をしている。今日は顔芸がすごい。
「相談…してみます」
僕も敬語になった。
「ありがとう、兄ちゃん。これでウチもハリウッドスターやな」
違うよ。
「ハリソン・フォードと共演出来るかも知れへん」
渋過ぎるし、出来ないよ。
「あんまり期待しないでね」
空を見上げながら目を爛々と輝かせているマリリンには、僕の声は届いていないようだった。
「こうしてはおれへんな。早速オカンとオトンに報告せなアカン」
「い、いや、まだ何も決まって無いから…」
「ジジーッ、行くでーっ」
僕の話を全く聞かず、一人と一匹は公園から走り去って行った。
マリリンのご両親が、マリリンの言葉を間に受けないことを祈るばかりだ。
明日も早朝から撮影だ。
僕は残りの缶コーヒーを飲み干した。公園を出ようとして電灯の側に行った時、散り始めた桜に初めて気がついた。いつの間にか冬が終わり、春になっていた。
時間の流れは一定じゃない。そんなことを考えながら、僕は帰路に就いた。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
