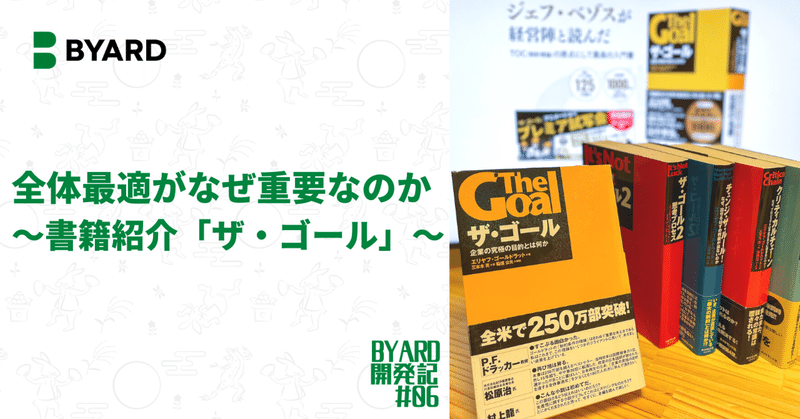
全体最適がなぜ重要なのか〜書籍紹介「ザ・ゴール」〜|#BYARD開発記 06
第6回は、BYARDの設計思想に多大な影響を与えた書籍「ザ・ゴール」をご紹介します。
「BYARD開発記」について ※本文はこの下からスタートです
株式会社BYARD・代表の武内俊介が、サラリーマンから税理士資格の取得を経て起業し、BYARDというプロダクトを作り上げるまでの開発ストーリー。
開発に至るまでの背景や、プロダクトの設計に込められた想い、起業・開発を通じて得た経験などをご紹介します。
(ヒアリング/執筆/撮影:藤森ユウワ)
「ザ・ゴール」とはどのような本か
業務設計について語るとき、私が折に触れて紹介している書籍が「ザ・ゴール」です。日本で翻訳版が発売されたのは2001年で約20年前(原作がアメリカで発売されたのは1984年でなんと約40年も前)ですが、その課題認識やソリューションは現在でも十分に通用します。
本書で紹介されているのは制約条件理論(Theory of Constraints、以下、TOC)というもの。
これは企業が「お金を儲ける」というゴールを達成するために、全体の業務プロセスを俯瞰したうえで、ゴールの達成を妨げている箇所、すなわち制約(ボトルネック)を見つけ、そこを集中的に改善することでスループット(販売を通じてお金を作り出す割合)を最大化することができる、という理論です。
本の中では舞台が「製造業の生産工場」となっていますが、TOCは製造業以外に関係ない話かというと決してそんなことはありません。
生産工場のラインは私たちの仕事が一連の流れによって成り立っているというメタファーだと考えれば、工場だけでなく小売、物流、プロダクト開発やバックオフィスまで、多くの部門や会社に応用ができる理論です。(実際に、以降の「ザ・ゴール」シリーズでは製造業を飛び出し、ITやプロジェクト管理、小売などを舞台に物語が展開されていきます。)
特にノンプロフィット部門の場合は上記のスループットの定義を「お金を儲ける」ではなく「より多くのアウトプットを出す」などに読み替えていただければ、理解しやすいかと思います。
日本企業がTOCを導入していたら、今でも“Japan as No.1”だった?
250万部を超える大ベストセラーになり、アメリカの大手企業やビジネススクールでは必読書とされてきた本書ですが、著者のエリヤフ・ゴールドラット博士はもともとビジネス畑の出身ではなく「物理学の研究者」という異色の経歴の持ち主です。
工場を経営していた知人から生産管理の改善について相談された博士は、物理学の研究を応用して見事に改善を成し遂げ、その知見をもとに生産管理ソフトウェアの製造・販売会社を立ち上げます。ソフトウェアを導入したユーザー企業はいずれも生産性の向上を果たし、会社は順調に売上を伸ばしていきます。
しかし博士はこの成果に満足していませんでした。このソフトウェアを導入すれば理論上はもっと大きな改善効果が出るはずなのに、なぜ自分の予想を下回る効果にとどまっているのか、と。
そしてその原因は、ソフトウェアの機能ではなくユーザー企業に古くからある体質や慣習にあると気が付きます。
生産管理ソフトウェアの効果を最大化し、もっと販売を伸ばすためには、まずそれを使うユーザー企業の意識を変革する必要があると考えた博士は、その啓蒙のために「ザ・ゴール」を著したのです。
余談ですが、この博士の気付きは経産省のDXレポート2 中間取りまとめにある「DXの成否はITシステムの機能ではなく、企業文化刷新の問題だ」という指摘に似ていると思いませんか。
こういう部分からも「ザ・ゴール」が扱っているテーマは古くて新しい問題で、日本企業が本書から学ぶべきことはたくさんあると、いつも感じています。

1984年に原作が出版されてから2001年に日本語版が出るまでに約20年ものタイムラグがありますが、これはゴールドラット博士本人が日本語版のみ長年翻訳を許可しなかったから、という逸話が残っています。
1970〜80年代は“Japan as No.1”といわれ日本企業が世界を席巻していた時代。しかもTOCは日本固有の「和」を尊ぶ文化と相性が良いと博士は考えていました。
日本企業がTOCを導入することで他国が追いつけなくなるほどの競争力をつけるのを恐れ、翻訳を許可しなかったのだと言われています。
Salesforce構築においても重要な「全体最適」の視点
私が「ザ・ゴール」シリーズと出会ったのは、シリーズ5作目の「ザ・チョイス」が書店で平積みされているのをたまたま見かけて手に取ったからでした。そこからシリーズを一通り読んだものの、当時はそれほど深く感銘を受けたというわけではなく、あくまで話題の本を一読したという程度でした。
しかしこのときに出会った全体最適の考え方が、後にSalesforceの構築に携わるようになってから大きな意味を持つようになります。
構築に携わるようになった当初はまだ、あまり深く考えずにエンドユーザーの要望に応じてカスタムオブジェクトや項目をどんどん作っていました。
しかし作り込んでいけばいくほど、エラーが頻繁に発生したり、1つの改善のために何か所も設定を変更したりと、開発にかかる作業時間もどんどん延びていきました。
個々のオブジェクトとしては問題なくても全体の業務の流れとしては非効率な処理プロセスが必要になる、連携機能などがうまく動かない、というケースも増えていきました。根本的な解決をしようにも、構造が複雑になりすぎて原因の特定が難しい。仕方がないので、どうにか処理を動かすためにまた新たな開発をする…という状況でした。
そうした試行錯誤を繰り返すうちにふと気が付いたのです。システム開発においては「この機能が欲しい」という目の前の要望に応えるだけではダメで、なにかもっと全体の設計図のようなものが必要なのではないか、と。

営業からバックオフィスまで社内の全体をSalesforceでつなぎ、そこにたまっていく事業活動のデータを基盤に経営の意志決定をすることを考えると、「営業」や「経理」といった業務は全体の流れの中の一部でしかありません。
だとすれば、最初に着手すべきはシステムやツールを導入することではなく、会社全体を俯瞰してデータがスムーズに流れるよう業務プロセスを設計・再構築することではないかと考えるようになりました。
開発記の第2話では歩んできたキャリアが業務設計へとつながっていったコネクティング・ザ・ドッツをご紹介しました。
税理士資格の取得を経て会計の世界に漬かり、ビジネススクールでは企業法務やマーケティングを学び、カード会社での経験やSalesforceの構築でシステムの構造について深く考えて、そして「ザ・ゴール」で全体最適の考え方と出会ったという、これらのドットのすべてが、業務設計という概念、そしてBYARDというプロダクトへとつながっていったのです。
どんなに優れたSaaSを導入しても「部分最適」では生産性は上がらない
本書の冒頭、採算悪化で閉鎖が計画された工場をわずか3か月で立て直すよう命じられた主人公のアレックスは、わらにもすがる思いで恩師のジョナに助けを求めます。
各セクションでは社員が一生懸命に働き、最新型のロボットも導入しているのに一向に採算が改善しない、と状況を説明するアレックスに、ジョナはこう投げかけます。
「ロボットを使って、工場の生産性は本当に上がったのかね」
これは書籍出版から40年後の未来を生きている私たちにも、そのまま当てはまる言葉だと感じます。
どんなに優れたSaaSを部分的に導入しても、それだけで会社全体の生産性が上がるわけではありません。業務を俯瞰して改善すべきボトルネックを見つけ、全体が最適化されるようにしなければ、それこそ「最新型のロボットを導入してもまったく効率化しない」ということになってしまうのです。

DXブームは一服してきた感がありますが、その多くが「デジタルを活用したビジネス変革」ではなく単なるITシステム導入にとどまってしまっているのは、全体最適の視点が足りないからだという気がしてなりません。
原作出版から約40年の歳月を経て、DXが叫ばれる今この時代にこそ、本書を読み直すことで多くの学びが得られるのではないかと思います。経営者やマネジャーだけでなく、SaaSのプロダクト開発に携わる人たちにもオススメの1冊です。
582ページもあって分厚く感じるかも知れませんが、小説形式なので見た目よりは読みやすいのではないかと思います。
2014年にはコミック版が出版され、そして最近アニメ映画にもなっているようですので、「気になるけど分厚い本にはなかなか手が出ない」という方は、まずそちらからチェックしてみても良いでしょう。(ちなみにコミック版では舞台が日本になっています。)
またシリーズ3作目となる「チェンジ・ザ・ルール!」では、ソフトウェア開発企業を舞台に「ITシステムを導入するだけで生産性は上がらず、本当に必要なのは従来の仕組みやマインド(すなわち、ルール)を変えることである」というストーリーが展開されていきます。
「ザ・ゴール」を読んで面白いと感じた方はぜひ、シリーズの他の本も読んでみてください。
「BYARD開発記」シリーズのご紹介
「BYARD開発記」は全13話のシリーズになっています。
BYARDそれ自体は、数ある業務用アプリケーションの中の一つですが、その背景にはバックオフィスの実務家として、事業の運営者として感じてきた想いや経験があり、それをプロダクトの設計に込めています。
BYARDでは、私たちと一緒にバックオフィスの世界を変えるようなプロダクトを作る仲間を募集しています。もし開発記をお読みいただいて、ご興味をお持ちいただけたようであれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
シリーズINDEX
第1章:BYARDへとつながった背景ストーリー
第2章:起業・開発で活用した手法
第3章:BYARDのプロダクト紹介
最終章
BYARDの採用情報は、以下のページよりご確認いただけます。
また、BYARDのこと、業務設計のこと、バックオフィスのことなど、CEO・CTOと気軽に話せるカジュアル面談も実施しております。「気になるけど、いきなり採用に応募するのはな…」という方は、ぜひこちらへお気軽にお申し込みください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
