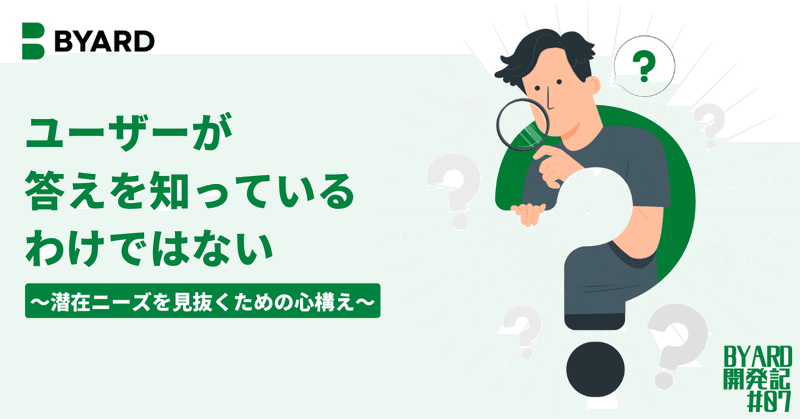
ユーザーが答えを知っているわけではない|#BYARD開発記 07
第7回は、ユーザーへのヒアリングにどのような心構えで臨んだのか、「解決すべきユーザーの真の課題」の設定がヒアリングをし直す前と後でどのように変わったのかを振り返ります。
「BYARD開発記」について ※本文はこの下からスタートです
株式会社BYARD・代表の武内俊介が、サラリーマンから税理士資格の取得を経て起業し、BYARDというプロダクトを作り上げるまでの開発ストーリー。
開発に至るまでの背景や、プロダクトの設計に込められた想い、起業・開発を通じて得た経験などをご紹介します。
(ヒアリング/執筆/撮影:藤森ユウワ)
ユーザーヒアリングの徹底的なやり直し
新しい製品やサービスを開発する際には、皆さんもいろいろな市場調査を行っていると思います。しかし調査結果の中に明確な答えが存在するわけではなく、結果をどう解釈し何をプロダクトに反映させるかは自分で決めなければならないところに難しさがあります。
SmartHRの当時のCEO・宮田さんとの面談で、事業の構想について最初にプレゼンした際、いただいたフィードバックは
「ちょっと機能にフォーカスしすぎていると思うので、ユーザーヒアリングをしてみて、もう一度、考えてみましょう」
…というものでした。これをきっかけに当初持っていたプロダクトの構想や機能はいったん捨て、半年ほどかけてユーザーへのヒアリングを徹底的に行い「ユーザーの真の課題は何か、マーケットで求められているものは何か」を見つめ直すことになりました。
(半年もの時間をかけることができたのは、第5話でご紹介した「強くてニューゲーム」のおかげでもあります。)
心構え① ユーザーが語っている課題が、本質的かどうかは分からない

ヒアリングを行うとユーザーからはさまざまな意見が出てきます。しかしユーザーが必ずしも「本当に解決すべき課題の本質」を捉えられているとは限りません。
このことを表した、アメリカの自動車王・フォードの格言があります。
もし私が何が欲しいかと聞いていたとしたら、人々は「もっと速い馬」と答えただろう
まだ自動車が普及していない時代、一般的な交通・運搬手段といえば「馬車」でした。馬車しかないのが当たり前の人たちにとって自動車のことなど想像もつきません。「もっと速く走る馬が欲しい」と言う人はいても「自動車が欲しい」と言う人は誰もいなかったのです。
ユーザーの口から言葉として発せられる表面的なニーズにとらわれず、「より速く移動や運搬をしたい」という本質的なニーズは自分で見つけ出すという心構えが必要です。
心構え② 身銭を切らない意見は当てにならない
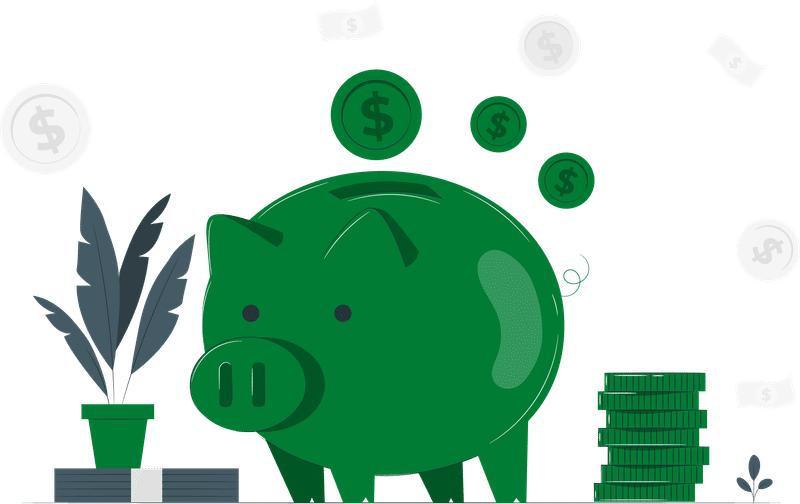
実際に自分がお金を払っていないものや、自分の損得に影響がないものについて尋ねても、本当の意見は出てきません。
「リーン・スタートアップ」や「STARTUP」、「NO FLOP!」など何冊か参考に読みましたが、どの本にも市場調査で高評価だったにもかかわらず、いざリリースしたらまったく売れなかった事例が登場します。
「いいですね!ぜひ買いたい!」とヒアリングでは答えたけど、実際に自分がお金を払って買うかと言ったらそうでもない——どう答えようが責任も損得もないのであれば、当たり障りのない意見を言ってしまうのが人間なのだと心構えしなければなりません。
心構え③ 信じるのは「意見」ではなく「データ」

とは言えユーザーがウソを付こうとしているわけではないし、ユーザーテストで身銭を切らせるわけにもいきません。では、いったいどうすればいいのでしょうか。
自分の意見や他人の意見、専門家の意見さえも信頼できないとすれば、実現させたいアイデアがあったとき、それが成功する確率をどう見きわめられるのだろう?
それには、データが必要だ!
そう、必要なのは意見ではなくデータです。「NO FLOP!」ではデータを取得するための手法としてプレトタイプ(“プロト”タイプではなく“プレト”タイプ)というものが登場します。実際にプレトタイピングをやってみてどうだったかは、次回・第8話でご紹介します。
半年間ひたすらヒアリングを繰り返したことで、ニーズの捉え方はどう変わったか

BYARDの構想のスタートは、自分自身が事業を運営するものとして、そしてバックオフィスの実務者として感じてきた以下の2つのニーズが元になっていました。
1. タスクの詳細な進捗状況と全体感を可視化したい
2. 改善のPDCAサイクルを回すための情報を集約したい
目指す方向性として大きなズレはなかったと思っていますが、半年間ひたすらヒアリングを繰り返しマーケットインの視点で再定義した結果、ユーザーが抱えている課題は大きく分けて次の2点に集約できそうだということが見えてきました。
① マネジメントサイドの「把握ができない」課題
マネジャーが業務をすべて把握するのは不可能だし、何でもかんでもマネジャーにお伺いを立てねばならないようでは日々の業務は回らない。
だから現場は、その場の状況に応じてある程度は自分で判断=属人的に動くしかない。
属人化を防ぐためにマネジャー主導で業務フロー図やマニュアルを作ったとしても、現場では更新する時間がないので「作っただけ」になってしまう。更新されず最新情報が反映されていないので、そのうち使われなくなる。
結果として管理は形骸化し、改善しようにも現場の状況が把握できず、担当者に聞いても個別の要望が上がってくるだけで根本的に全体を改善するような手が打てない。
営業部門もかつては似たような状況だったのではないかと思います。営業担当者がそれぞれ個人商店として勘と経験で仕事を回していた。そこにSalesforceが登場したことで、データをもとに科学的に分析して管理と改善を行えるようになったのです。
バックオフィスにもSalesforceのようなデータの収集・分析ができるツールがあれば、マネジャー側も管理や改善がしやすくなるのではないか、というのが1つの仮説でした。
② 現場サイドの「共有と引き継ぎがうまくいかない」課題
現場が属人的に回っているので、同じ部署内でも「何を・どのように・どこまで処理しているのか」は担当者本人にしか分からない。
担当者が不在だとその業務が止まってしまう。不在にすると業務が止まってしまうから休みづらいし、状況が分からないので周囲もサポートできない。
忙しい通常業務の合間では情報共有のドキュメントを作る暇もない。作ったとしても更新できないから、業務の実態を反映していない「使えないマニュアル」になってしまう。結果としてマニュアルは無視され、担当者が個人的に作っている“秘伝のメモ”で業務が回っている。
異動や退職で引き継ぎするときにも、すぐに渡せるよう情報がまとまっていない。引き継ぎをする側は、異動や退職が決まってから必死にマニュアルを作るか、さもなければ秘伝のメモを口頭伝承するしかない。引き継ぎを受ける側は、マニュアルは参考程度にして後は自分で試行錯誤するしかない。
引き継ぎをする側/受ける側、どちらもがんばっているのにどちらも不幸な状態である。
皆さんも業務の引き継ぎをする/受けるときに苦労した経験があるのではないでしょうか。
「ナレッジマネジメント」のような情報共有に対する考え方は古くからありますし、新しいツールもどんどん生まれていますが、それだけ情報共有は難しいし、長年みんなが悩んでいるということなのでしょう。
そもそもバックオフィス業務はマニュアルさえあればできるようなものなのか?

ヒアリングを繰り返していくなかで新たに生まれた仮説。それは「マニュアルさえあればできるバックオフィス業務など、ほとんどないのではないか」というものです。
もちろんマニュアルがあることで効率的に処理できる部分はあります。しかし実際は、すべてマニュアルどおりに進む仕事などめったにありません。状況に応じて臨機応変に対応しなければならないことがほとんどだし、誰かの気配りのおかげで回っているような部分も多い。そういうマニュアル化が難しい部分にこそ、課題の本質があるのではないかと思っています。
デジタル化というと「カチッと定義された標準的な処理プロセス」だけがクローズアップされます。
しかし真の課題解決に向けた第一歩は、相手との調整や確認などの「行間」に存在する余白の部分、いわゆる人間らしさやある種の曖昧さを許容し、可視化することではないか——
この仮説を立てたことで、BYARDは既存のTODOリストやチェックリスト、マニュアルツールなどを進化させるのではなく、全く新しいアプローチで、マネジメント側と現場をつなぐプロダクトを作る方向に進んでいくことになったのです。
「BYARD開発記」シリーズのご紹介
「BYARD開発記」は全13話のシリーズになっています。
BYARDそれ自体は、数ある業務用アプリケーションの中の一つですが、その背景にはバックオフィスの実務家として、事業の運営者として感じてきた想いや経験があり、それをプロダクトの設計に込めています。
BYARDでは、私たちと一緒にバックオフィスの世界を変えるようなプロダクトを作る仲間を募集しています。もし開発記をお読みいただいて、ご興味をお持ちいただけたようであれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
シリーズINDEX
第1章:BYARDへとつながった背景ストーリー
第2章:起業・開発で活用した手法
第3章:BYARDのプロダクト紹介
最終章
BYARDの採用情報は、以下のページよりご確認いただけます。
また、BYARDのこと、業務設計のこと、バックオフィスのことなど、CEO・CTOと気軽に話せるカジュアル面談も実施しております。「気になるけど、いきなり採用に応募するのはな…」という方は、ぜひこちらへお気軽にお申し込みください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
