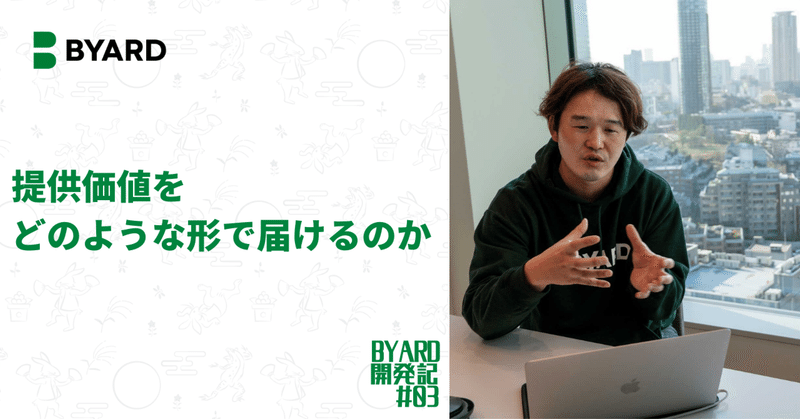
提供価値をどのような形で届けるのか|#BYARD開発記 03
第3回は、提供価値のデリバリー方法がどのように変化し、現在のプロダクトの形にたどり着いたのかを振り返ります。
「BYARD開発記」について ※本文はこの下からスタートです
株式会社BYARD・代表の武内俊介が、サラリーマンから税理士資格の取得を経て起業し、BYARDというプロダクトを作り上げるまでの開発ストーリー。
開発に至るまでの背景や、プロダクトの設計に込められた想い、起業・開発を通じて得た経験などをご紹介します。
(ヒアリング/執筆/撮影:藤森ユウワ)
大企業で、いくつもの部門をまたいで業務とデータのフローを設計したこと
会計事務所で、「会計」という裏方のフローをすみずみまで取り扱ったこと
これらの経験を踏まえて、ITツールとを組み合わせて業務プロセスを設計し、事業成長の基盤となるバックオフィスを作る——この業務設計こそが独自の強みであり提供価値なのだという手応えを得て独立・起業へと進み始めます。その提供価値がBYARDというプロダクトとして結実するのはもう少し先の話です。
コンサルティング・サービスとして届ける
コンサルティングという形で業務設計のサービスを始めたのは、税理士登録を終えた2016年のことでした。
最初から何のツテも無しに独立して食っていけるほど甘くはありませんし、家族がいる以上はベースとなる収入も確保し続けなければなりません。最初の2年ほどは会社員と税理士業、そしてコンサルタント業の比率を徐々に変化させながら、試行錯誤を繰り返す中で少しずつ受注を獲得していきました。
そして2018年12月、業務設計を看板に掲げてリベロ・コンサルティング合同会社(後に株式会社へ変更)を登記します。
このときは組織的にコンサルティング事業をスケールさせていこうと考えていたわけではなく「大手企業との取引上、法人があった方が都合がいい」という消極的な理由での会社設立であり、しばらくは1人で事業を続けていくつもりでした。しかし事業が軌道に乗り始めると、コンサルティングサービスの構造的な課題もまた、浮き彫りになってきたのです。
業務設計コンサルティングとは、シンプルに説明するならば「ヒアリングを行い、現状分析し、業務とシステムを同時に設計する」というものです。文字にするとこれだけですが、これは私がシステム企画 → 会計事務所 → ITベンチャー管理部門というキャリアで培ってきた経験と、会計・企業法務・ITの知識があることの、複雑な、ある意味で偶発的な「掛け合わせ」によって成立していました。つまり再現性がとても低かったのです。
「組織的にコンサルタントを育成し事業をスケールさせる」というイメージがまったく持てなかったため、事業としてコンサルティングは続けながらも、より再現性や代替性のある別の形で業務設計を届けられないかと考え始めました。
パッケージ化したサービスとして届ける
一方、コンサルティングを手がける中で「業務を設計し導入しても、その後の運用をやり切れないケースがある」というお客様側の課題も見えてきました。
どんなに綿密に設計した業務プロセスも、高機能なITツールも、導入しただけですべてがうまく回り出すような魔法のアイテムではありません。運用を始めてみないと見えてこない部分も必ず存在します。重要なのは導入したあと、日々の運用のなかで調整と改善のPDCAサイクルをしっかりと回し続けることです。
私はここに、バックオフィスの領域でまだ解決されていない課題があるのではないかと考えました。

ITベンチャーに勤務していた当時、管理部門のマネジャーとして採用に携わっていたころから感じていましたが、「ツールを運用するためのITスキルと、経理や労務などの実務スキルを兼ね揃えた人材」は転職市場にはほとんど存在しません。ポテンシャル採用して育成するにも、人材不足が叫ばれる今の時代では採用コストがかかりますし、そもそも採用時にポテンシャルが見抜ける保証もありません。
ならば「業務設計」と「最適な運用を回せるリソース」を1つのパッケージにして提供すれば良いのではないか、と考えたのです。
これまで業務設計コンサルティングで培った一定の成功の型——すなわち
・業務設計
・最適なITツール
・最適な運用方法
という3つを「ベスト・プラクティス」として定義し、実際に運用を回すリソースとともにパッケージ化して提供する。そして提供側のオペレーションは、チェックリストとマニュアルを充実させ、ノウハウを蓄積・改善するPDCAサイクルをあらかじめ組み込み、業務設計コンサルティングでは実現できなかった再現性と代替性を担保する。これらによってスケーラブルな事業にできないかと考えました。
こうして生まれたのが「Brownies Works」というサービスです。
Brownies Worksは特にITスタートアップ企業の「リソースが常に不足しCxOがバックオフィスを兼務している」「急激な事業成長のフェーズに応じて、バックオフィスの体制を改善し続ける必要がある」というニーズにマッチしたことで、ベンチャー・キャピタルから定期的にお客様をご紹介をいただくなど、一定の評価を得て事業は拡大していきました。

しかし契約数が伸びるに従い、また新たな課題も見えてきます。顧客ニーズは想定どおりだったものの「バックオフィス全体をパッケージ化して提供する」ことの難易度が高く、想定よりも事業がスケーラブルではなかったのです。
「バックオフィス」とひと言で言っても、お客様の業種・業態や「過去の業務プロセスの変遷」などさまざまな要素が絡み合っており、そのすべてにひとつのパッケージを適用することは困難でした。
またコンサルティングと比べれば業務を平準化できたものの、それでもコアとなる「ITスキルとバックオフィスの実務スキルを兼ね揃えた人材」の発掘や育成は難しく、受注のスピードにリソースの拡充が追いつかなくなってしまったのです。
もしBrownies Worksが資金調達によって運営していた事業であれば、サービスの中身をガラッと変えて規模の拡大を目指していたでしょう。しかし成長の宿命を背負ったわけではない自分たちにとって、それが果たして幸せだと言えるのだろうか——そう考えたとき、社員とお客様の両方にとって満足度が高いのは、規模の拡大を追わず、リファラルを中心に必要としてくれる企業だけにサービスを提供することだと結論づけました。
規模の拡大を目指さないのであれば、一つ一つのお客様に丁寧に寄り添い信頼を勝ち得ていけば事業としては成り立つはずです。このときから次の事業、新しいSaaS開発について頭の隅では考え始めていました。
SaaSとして届ける
ハーバード大学教授のロバート・カッツは、マネジャーに必要な能力を以下の3つに分類し、階層が上がるにつれて必要なスキルが変化していくという理論を提唱しています。
1. テクニカル・スキル…業務を遂行する上で必要な知識やスキル(例:経理や労務の実務スキルや、ITスキル)
2. ヒューマン・スキル…人間関係を管理するためのスキル(例:コミュニケーション力、調整力、交渉力)
3. コンセプチュアル・スキル…目の前の事象や現在の状況を概念的に捉え、問題の本質を見極めるスキル
構想を練って事業を立ち上げたり、コンサルタントとして業務を俯瞰・設計する部分、すなわち「コンセプチュアル・スキル」は私の得意領域だと思っています。一方Brownies Worksを運営する現場では、お客様の具体的な課題と向き合い、円滑にコミュニケーションを行って業務を進めていくために「テクニカル・スキル」や「ヒューマン・スキル」の方が重要です。
事業が規模の拡大を追わずお客様と寄り添う方向に行くのであれば、より適したスキルを持ったメンバーに任せて自分は自分の得意な領域で新たな取り組みをする方が良いのではないかと考え始めました。

「バックオフィスの領域で何かサブスクリプション型のビジネスを作りたい」——Brownies Worksの事業を立ち上げたときにはそんなテーマも持っていましたが、当時は「新しいSaaSを開発する」という選択肢は採りませんでした。
SaaSビジネスは事業コンセプトだけでなく、エンジニア・マーケター・セールスなどの「ヒト」や、開発投資を続けられるだけの「カネ」など、すべてのピースがそろわなければ成功が難しい世界です。また業務設計でfreee会計やSmartHRなどの素晴らしいプロダクトを導入・活用する立場だったこともあって「バックオフィスの領域でこれらに匹敵するプロダクトは今からは作れないだろう」という思いもあり、SaaSではないサービスを作りました。
しかし今度は、業務設計をより多くの人たちに届ける方法としてSaaSを選びました。
もちろんそのチャレンジができるのは、かつて畏敬の念を抱いたSmartHRが支援する立場として後ろに付いてくれているからでもあります。ただ、もしBrownies Worksを作ろうとしていた当時に支援を受けていたとしても、BYARDは生まれてこなかったでしょう。
「コンサルティング」「バックオフィス領域全体のパッケージ化」という2つの事業が先にあり、そこで試行錯誤を繰り返してきた経験こそが、今のBYARDというプロダクトを形作っているのです。
「BYARD開発記」シリーズのご紹介
「BYARD開発記」は全13話のシリーズになっています。
BYARDそれ自体は、数ある業務用アプリケーションの中の一つですが、その背景にはバックオフィスの実務家として、事業の運営者として感じてきた想いや経験があり、それをプロダクトの設計に込めています。
BYARDでは、私たちと一緒にバックオフィスの世界を変えるようなプロダクトを作る仲間を募集しています。もし開発記をお読みいただいて、ご興味をお持ちいただけたようであれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
シリーズINDEX
第1章:BYARDへとつながった背景ストーリー
第2章:起業・開発で活用した手法
第3章:BYARDのプロダクト紹介
最終章
BYARDの採用情報は、以下のページよりご確認いただけます。
また、BYARDのこと、業務設計のこと、バックオフィスのことなど、CEO・CTOと気軽に話せるカジュアル面談も実施しております。「気になるけど、いきなり採用に応募するのはな…」という方は、ぜひこちらへお気軽にお申し込みください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
