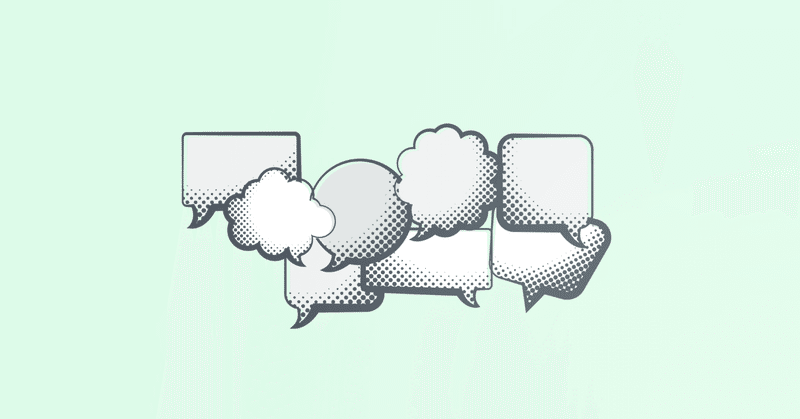
「電話が苦手」「本が読めない」理由を、「日本語の特殊さ」と「テレビ・YouTubeのテロップ」から考察してみる
以前、友人と話をしている中で、「今の若い人は、『話し言葉』と『書き文字』を同時に認識する状況が多いせいで、それぞれを単体で受け取るのが不得意になっているのではないか」という話になったことがある。
というわけで今回は、そんなテーマについて少し掘り下げて考えてみたいと思う。
まず、「『話し言葉』と『書き文字』を同時に認識する」という状況についてだが、僕はYouTubeなどの動画配信をイメージしている。僕は普段YouTubeをほとんど観ないが、たまに観てみると「喋っている内容をテロップでも表記している」ことが多いように思う。もちろんこれは、テレビのバラエティ番組でもよく見る手法だ。恐らく、バラエティ番組の手法がYouTubeにも採り入れられているのだろう。いずれにせよ、映像メディアでは「喋っている内容をテロップで補完する」というやり方が当たり前に行われていると思う。
また、「それぞれを単体で認識する」という状況については、例えば「話し言葉」であれば「電話」、「書き文字」であれば「読書」などをイメージしている。
そして僕は、「YouTubeやバラエティ番組ばかり観ることで、『電話』『読書』を苦手に感じるようになったのではないか」と主張しているというわけだ。
この点に関してはまず、「視覚優位」「聴覚優位」の話に触れておきたいと思う。
以前、「オーディオブックを聴いてみたら自分には合わなかった」というツイッターのまとめを読んだことがある。
そしてその中で指摘されていたのが、「『見る方が得意』なのか『聴く方が得意』なのか」という人間の特性の話だった。「見る方が得意」だという場合、「オーディオブック」は向かないというわけだ。
これに関しては似たような話として、「動画じゃなくて文字で説明してほしい」というまとめも読んだことがある。
こちらについては「視覚と聴覚どちらが優位か?」という話ではないのだが、いずれにしても、「物事を認識する上で何が得意なのか」という特性に関するものと言えるだろう。
私も、音声や映像よりも文字で読む方が好きで、そちらに特性があると感じる。というか、どちらのまとめでも指摘されていることだが、音声も映像も「自分の好きなペースで情報を取り込めない」ため、その点にストレスを感じているのだと思う。
さて、人間にはこのような「情報を取り入れる際の得手不得手の特性」があることを踏まえた上で、改めて先程の話について考えてみると、僕の主張も捉えやすくなるかもしれない。繰り返しになるが、「YouTubeやバラエティ番組に多く触れることで、『音声認識と文字認識を同時に行うこと』が状態化しているため、個々の力を伸ばす機会を失っているのではないか」という話だ。
ここで少し違う話をしよう。昔、立ち仕事をしていたため、割と常にちょっとだけ腰が痛かった。それで、「コルセットみたいなものをドラッグストアで買って付けてみようかな」という話を誰かにしてみたのだが、その際、「コルセットし始めると、コルセットを付けていない状態に戻れなくなるから止めた方がいいよ」と言われたことがある。「腰痛」の種類にもよるだろうが、恐らく本来的には、「腰回りの筋肉を鍛えることで腰全体を支える」みたいな対策が必要なのだろう。しかし「コルセット」を付けることで、筋肉を鍛えずとも腰を支えられてしまう。そして結局、そのままずっとコルセット付け続けなければ姿勢を保てなくなってしまうみたいなことなのだと思う。
動画の視聴についても同じように考えてみよう。例えばYouTubeなどテロップがある動画の場合、「音声で上手く捉えきれない部分があれば文字で補う」「文字で上手く捉えきれない部分があれば音声で補う」みたいなことが出来るはずだ。そして、そんな補完をし続けることによって、「話し言葉を聴く」「書き言葉を読む」という個々の能力が弱ってしまっているのではないか、というのが僕の仮説なのである。
さてここで、日本語の実に興味深い特性について紹介することにしよう。
以前何かで、「何故マンガは日本で発展したのか?」みたいな話に関連して、日本語の特殊さについての説明を読んだ記憶がある。調べたら、以下のサイトが見つかったのでリンクしておこう。
「言語」にはまず「表音文字」と「表意文字」という区別があり、世界で使用されている言語の多くが表音文字だ。英語も表音文字である。「表音文字」というのは「発音を文字にしたもの」であり、例えば「Apple」は「アップル」という発音を文字化したものだ。一方の「表意文字」は、文字一つ一つが意味を持っている。例えば「日本語の漢字」は表意文字だ。
さて、ここからが日本語の特殊さなのだが、「漢字」は「表意文字」であり、一方「ひらがな」は「表音文字」である。そしてこのように、「表音文字と表意文字を並行利用している言語はかなり珍しい」そうなのだ。
さらに興味深いことに、「表音文字」と「表意文字」では脳の処理部位が異なるという。「表音文字」では「音声を処理する部位」が働くが、「表意文字」の場合は「画像を処理する部位」が働くのである。だから、日本語のような「表音文字・表意文字をどちらも使う言語」の場合、脳のどこに損傷を負うかで「ディスレクシア(識字障害)」には複数のパターンがあり得るという。「漢字は読めるがひらがなが読めない」とか「ひらがなは読めるが漢字が読めない」みたいな状況があり得るのである。
さて、日本人はこのように、普段から「音声処理を行う表音文字」と「画像処理を行う表意文字」を並列で使っていたため、「マンガのふきだし」に抵抗感が無かったと考えられているという。一方、「表音文字」である英語の場合、「ふきだしの文字を認識するのは音声処理」だが、「絵を認識するのは画像処理」のため、この2つを同時に行うのが難しかったと言われている。今となっては、日本のマンガが世界中に広まっているので、「表音文字」の国の人も慣れたのだと思う。ただこのように、「マンガが日本で発達した背景」には、「日本語が、音声処理と画像処理を同時に行う言語だった」という特性があったのではないかと分析されているのだ。
では、この日本語の特性の話を、本記事のテーマと合わせて考えてみるとどうなるだろうか?
さて、少し気になって、「海外のYouTubeでもテロップが使われるのか」について検索してみた。というのも、「表音文字」の国では、「喋っている音声」も「テロップの文字」も、脳内ではどちらも「音声処理」されるはずなので、「過剰」「どちらかだけで十分」という感覚が強くなるのではないかと考えたからだ。
そして、こんなブログを見つけた。
僕は海外のYouTubeも当然観ることがないので、日本と海外とで有意な差があるのか分からないが、少なくとも「日本のYouTubeやバラエティ番組はテロップが多すぎる」と感じている人もいるというわけだ。
では、先程の日本語の特性を踏まえた上で、日本の動画にテロップが多い理由を考えてみよう。日本語の場合、「『喋っている音声』と『テロップのひらがな』は音声処理」「『テロップの漢字』は画像処理」ということになる。情報処理の部位が異なるため、テロップが多くても「過剰」という感覚にはならず(ただ、テロップが仮にすべてひらがなだとしたら、やはり「過剰」という感覚になるだろう)、さらに日本人は昔から音声処理と画像処理を同時に行ってきたので違和感を与えることもない。だから、「テロップがある方が理解しやすい」という感覚が「表音文字」の国の人と比べて強くなるのではないかと思う。そのため、テロップが増えていくのではないだろうか。
しかし、その「テロップがある方が理解しやすい」という感覚は、先程も書いた通り、「聞き取れなかったら文字で補う」「読みきれなかったら音声で補う」みたいなことが可能だからである。そしてそれ故に、「話し言葉単体の認識」「書き言葉単体の認識」が衰えているのではないかと感じているのだ。
そしてそのせいで、「本が読めない」「電話が苦手」みたいな状況が生まれてしまっているのではないかとも思うのである。つまり、「日本語が『表音文字・表意文字を並列使用する特殊な言語』であるために、『映像にテロップを多用する』という『分かりやすさ』が実現できてしまい、そのせいで個別の情報処理能力が失われている」と考えると、全体としてしっくり来る気がするのだ。
もちろん、今展開した話は、「結論ありきで、それを補強してくれそうな情報を繋ぎ合わせただけの議論」でしかないと思っているので、さして信憑性はないだろう。ただ、そこそこ面白い考察になっているのではないかとも思う。ただ、もしも「表音文字の国でも、本が読めない・電話が苦手みたいな状況が起こっている」なら、そもそも私の仮説はあっさり崩れるわけだが。
いかがだろうか?
サポートいただけると励みになります!
