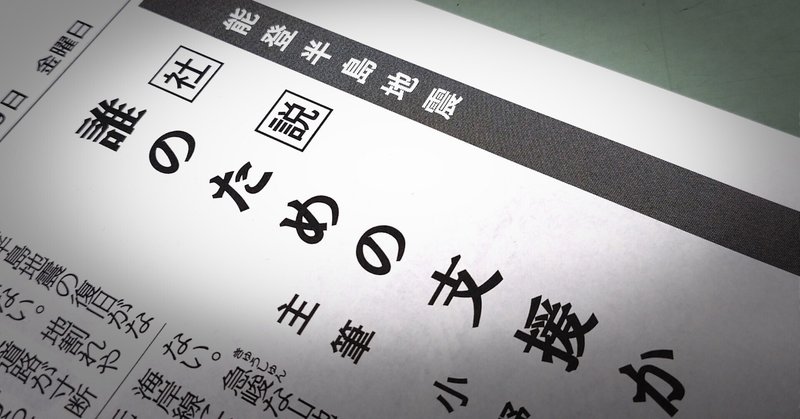
【能登半島地震】〈社説〉誰のための支援か
※文化時報2024年1月19日の掲載記事です。
能登半島地震の復旧がなかなか進まない。地割れや土砂崩れなどで道路が寸断され、被害の把握すらままならないのが実情だ。宗教界でも連絡の取れない関係者がいると聞く。心配な事態というよりほかない。
三方を海に囲まれた能登半島には、陸続きの南側からしか通常はアクセスできない。急峻(きょうしゅん)な山地と複雑な海岸線により、道路事情は元々良いわけではなく、そこへ度重なる余震と降雪がある。応急工事の遅れを覚悟する必要がある。
石川県は、能登方面への不要不急の移動を控えるよう呼び掛けている。支援に入る人々が、独り善がりでないのか、本当に被災地の役に立てるのかと自らを省みるきっかけにはなるだろう。
だが、被災した人々は一刻も早い支援を待ち望んでいる。どんな移動も「必要至急」であるはずだ。
地震発生から2週間以上が過ぎ、避難生活は長期化の様相を呈している。環境の変化で疲労やストレスがたまり、持病が悪化するなどして亡くなる「災害関連死」も出ている。
しわ寄せがいくのは高齢者や障害のある人とその家族である。周囲を気にして避難所に行けず、身を潜めるようにして暮らしている人々は必ずいる。必要な物資を直接届け、励ますことが何よりの支援になることを忘れずにいたい。
奥能登から金沢市などへの「2次避難」も始まっている。命を守り、安全な日常を取り戻すため、住み慣れた故郷を去らざるを得ない人々が増えれば、過疎化は着実に進む。
伝統教団は、こうした厳しい現実を直視しているだろうか。
1995(平成7)年の阪神・淡路大震災は「ボランティア元年」といわれた通り、宗教者もさまざまなボランティア活動を行った。2011年の東日本大震災では「心のケア」の専門職、臨床宗教師が誕生した。今回の能登半島地震も、宗教者による災害支援の在り方が、大きく変わる転機になるのかもしれない。
萌芽(ほうが)はすでに個の宗教者の行動力に見て取れる。
子ども食堂やフードドライブなどで普段から地域に貢献する宗教者たちが、得意な分野で支援に当たっている。過去さまざまな災害の現場に立った宗教者たちが、経験を生かして活動している。
残念なことに、伝統教団は突出した個の行動にブレーキをかけがちだ。他の寺院と足並みをそろえるよう指示したり、宗派・本山が許可するまで〝勝手な〟行動をしないよう求めたりといったケースは、今回も散見される。
所属寺院の被害や住職の安否確認が重要なのは言うまでもないが、教団がその先の支援を寺院の復興に限るのなら、旧態依然とした災害対応である。もし今回も同様の対応を取り続ければ、支える人のいない地域に伽藍(がらん)だけ立派な寺院が建つ、といった笑えない未来が訪れても不思議ではない。
大切なのは、教団が誰のため、何のための支援かを組織として明確にすることである。少なくとも、矢も盾もたまらず活動している宗教者の邪魔をしている場合ではないだろう。
【サポートのお願い✨】
いつも記事をお読みいただき、ありがとうございます。
私たちは宗教専門紙「文化時報」を週2回発行する新聞社です。なるべく多くの方々に記事を読んでもらえるよう、どんどんnoteにアップしていきたいと考えています。
新聞には「十取材して一書く」という金言があります。いかに良質な情報を多く集められるかで、記事の良しあしが決まる、という意味です。コストがそれなりにかかるのです。
しかし、「インターネットの記事は無料だ」という風習が根付いた結果、手間暇をかけない質の悪い記事やフェイクニュースがはびこっている、という悲しい実態があります。
無理のない範囲で結構です。サポートしていただけないでしょうか。いただければいただいた分、良質な記事をお届けいたします。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
サポートをいただければ、より充実した新聞記事をお届けできます。よろしくお願いいたします<m(__)m>
