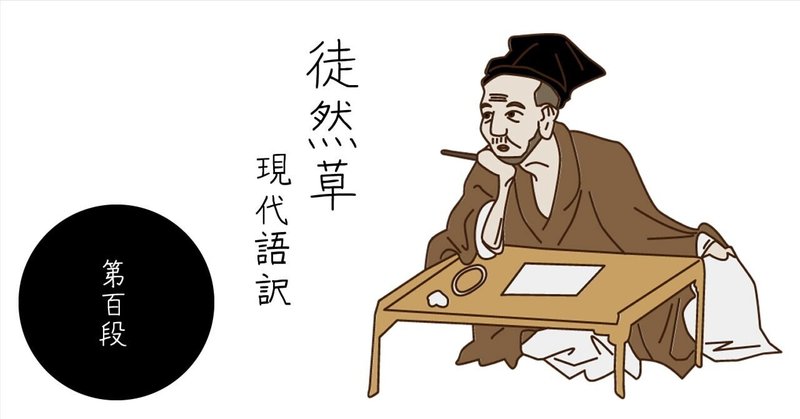
【徒然草 現代語訳】第百段
神奈川県大磯の仏像専門店、仏光です。思い立ってはじめた徒然草の現代語訳、週一度程度で更新予定です。全244段の長旅となりますが、お好きなところからお楽しみいただければ幸いです。
原文
久我相国は、殿上にて水をめしけるに、主殿司、土器を奉りければ、まがりを参らせよとて、まがりしてぞめしける。
翻訳
久我の太政大臣通光公は、清涼殿殿上にてお水を飲まれる際、主殿司の女官が土器を差し上げたところ、まがりを持ってきなさいと云って、木の器でお飲みになった。
註釈
○久我相国
こがのしょうこく。源通光(みちてる)。九十九段に出てきた基具の大叔父にあたる。親後鳥羽院派の公卿。久我家の祖にして女優久我美子さんの遠い遠いご先祖。久我美子さんは「くが」ですが、あれは芸名の読みで、ご本名は「こが」。
○主殿司
読みは「とのもづかさ」。殿上の雑用を仰せつかる女官。
○土器
読みは「かわらけ」。
○まがり
字をあてれば「鋺」。この段の「まがり」には諸説あるが、土器がNGだったことからシンプルに木の器とした。
わかったようなわかんないような段でしょう?
要するに、清涼殿殿上においては、土器はあくまでも食器、土器で水を飲むのは故実に反することだから、木製の杯子を持ってきなさいということ。
もっとも酒は平安時代からずっと土器で呑まれていたようです。
こういう(うるさい)人がいたから、宮中の秩序は「まがりなりにも」保たれていたんでしょうね。
ちなみに台所に水場(流し)が出来たのは、鎌倉時代だそうです。井戸水は争いを避けるために寺社が管理していたようです。
