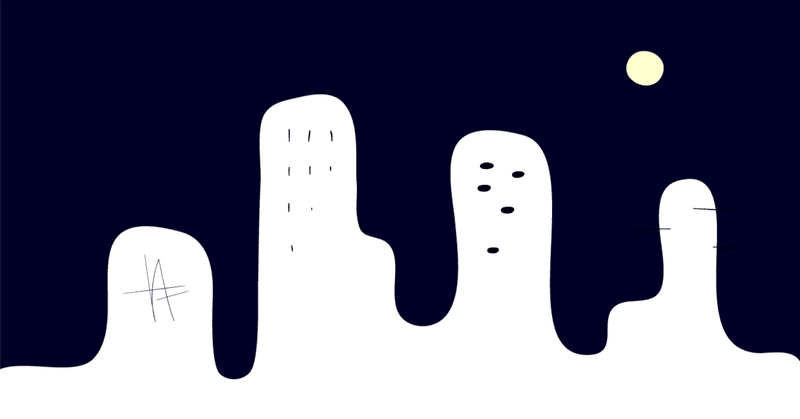
執筆前夜
どこかに行けばきっと
誰かに出会えると思ってた。
ただ漠然と僕はそう思って生きてきた。
26歳になって、誰にも会えないままに丸ノ内線に乗っていた。
誰にも会えないままだったけど、26歳の夜はいつも前夜だった。
最初それが何の前夜なのか自分でもわからなかった。
だからただ246をタクシーに乗って走っていた。
どうしても前夜から逃れたい夜なんかには、
誰にも会えないのにアルタ前で待ち合わせして、どこかに行こうとしたりもした。
村上春樹は20代のある夜に、神宮球場の外野席でナイターを見ている時に、突然、小説を書こうと思ったらしい。
僕は26歳のその夜に何も思わなかった。
ただ単に、恐ろしく前提を欠いた前夜みたいなものが僕に覆い被さってきていた。
だから暗然と中目黒で飲んで、恵比寿で飲んで、なんて長い前夜だろうって思いながらハシゴしていた。
ある店のカウンターで隣になった女の人が声をかけてきた。
同年代くらいのその人と、ときどき腕が当たっていて、そのタイミングでだった。
「何かを書くつもりなのね、そういう飲み方をしてるわ、あなた」
ジャスミンハイを飲んでたその女の人は年上の男の人を連れていた。
「僕はいつも通りに飲んでるだけだよ」
僕は生搾りのレモンサワーだった。
「あなた、さっきからレモンの絞り方がちょっと優しすぎて気になってたの」
「よく言われるよ」
「あ、もうすぐ書くんだな、この人ってピンときたの」
「逆に聞いてもいい?」僕はジョッキを傾ける。「僕は何を書けばいいんだい?」
女の人はちょっと向こう側の男の人にこっちの話の流れを説明してからまたこちらを向いた。
そしてこう言った。
「何を書けばいいかわからない時に書くものって小説とかじゃないの?」
──小説とかじゃないの。
「考えてみるよ」
前夜が前夜なうちに、ね。
✴︎
どこかに行けばきっと
誰かに出会えると思っていた。
ただ漠然とそう思って生きてきた。
もしかしたら僕は小説を書くかもしれない。
この夜が明けたら…。
なあ、教えてくれよ、前夜な人って、みんな、こんなにも前夜な気分なんだろうか。
うん、今度聞いてみよう。
誰かに。
荻窪のビルの上のバッティングセンターでフルスイングしながら26歳の終わりにそう思った。
終
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
