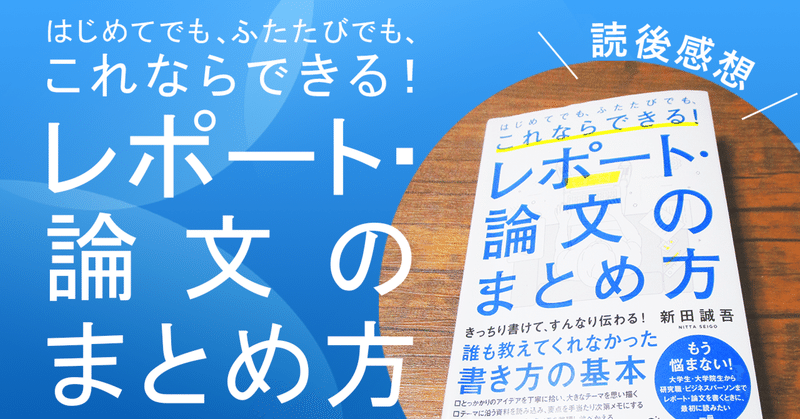
【読後感想】はじめてでも、ふたたびでも、これならできる!レポート・論文のまとめ方
著者:新田誠吾
タイトル:はじめてでも、ふたたびでも、これならできる!レポート・論文のまとめ方
発行元:株式会社すばる舎
こんにちは。
今回の読後感想本は、amazonで見つけて購入したレポート・論文のまとめ方を解説してくれる書籍です。
本の内容
小論文・レポート・論文の違いとは
小論文:設問に対して、意見とその理由を述べるものです。
レポート:レポートとは、報告、または調べたことをまとめたものです。
論文:論文は、問題提起をし、先行研究の成果を踏まえて問題解決を示すものです。
その違いを理解して取り掛かる必要がありますが、なぜレポートや論文を書く必要があるのでしょうか?
書く理由として著者は、以下の重要な役割があると述べています。
(1)問題を見極める力を付けるため
(2)自分の考えを客観的に他人に伝えるため
論文やレポートで大切なことは問題が何かを自分自身で考えることであり、本質をつかむ能力を養っていくことです。
そしてレポート・論文の基本構成を理解しておく必要があります。
論文に取り掛かる前に注意することは2点あります。
・いきなり書かない
・しっかりと資料は集める
この2点を注意しながら論文に取り掛かります。
学生が卒業論文に取り掛かり仕上げるまでに、計画をしっかり立てて情報収集し、論文を読み込んで書き上げて提出する生徒と、期限ギリギリになって論文に取り掛かる生徒に分かれます。
それにより出来上がる論文の価値は大きく変わるため、基本構成を理解しておくことが大事なのです。
論文やレポートの価値を高めるために、間違った手順にも気を付けなければなりません。
それは序論を書く→資料集め→写してまとめて本論→結論を書くことです。
論文やレポートでは正しい手順を踏むことが重要で、最初は「テーマ」を考えます。
普段から疑問に思うことや気になることがテーマになります。
それらをメモに残し、テーマの種としてストックしておくことが重要です。
そして、問題を見つけていくために資料など情報を収集していくことになります。
その調査方法は「インターネット検索」「図書館で探す」「雑誌や新聞記事」「政府統計データ」「民間の統計データ」から収集していきます。
上記の方法で集めたデータや資料から、問題点を見つけて絞り込む作業に入ります。
問題点を書きだしていき、そこから「問い」を立てていく作業になります。
「問い」を立てるのはなぜでしょうか。それは
自分の立てた「問い」に、裏付けとなる資料・データを示して「答える」ことにあります。
いわば、この「問い」の良し悪しでレポート・論文が成功するかどうかの分かれ道にもなるのです。
わたしたちは問いを立てるときにwhat(~とは)という疑問形で立てますが
whatではなく、「why」「how」「should」で考えることをすすめています。
それらを使い問いを立てれば、問いから結論に至る筋道を確認するアウトライン作成を行います。
アウトライン作成と聞いても、あまりピンときません。
調べた情報から立てた問いの分析を行い項目を絞っていきます。
例えば「少子化を食い止める方法はあるのか?」という問いがあり、
情報を調べていけば、「子育て支援の政策」や「若い年齢で結婚した成功例」など情報を見つけることができます。
その情報をまとめていき、自分で立てた問いに答えられるように構成を作っていく作業になります。
そうすることで、自分の論を組み立てていくことができるのです。
そして執筆の作業に入ります。
論文の基本構成は以下のとおりです。
序論・本論・結論(3部構成)
IMRAD(5部構成)
があります。
この構成の詳しい内容については割愛しますが、この型に当てはめて文章を記述していきます。
序論の役割は、読者に興味関心を持ってもらうことにあります。
本論は方法・先行研究(発表されている論文や新聞などの情報)・結果(得られたデータや事実)を述べていきます。
そうして問題提起したものに対して、根拠となる裏付けデータから考察した結果、問題解決をする執筆者の意見を述べていく結論へと結んでいく流れになります。
後半は主にライティングと同じ、気を付ける点や文章を読みやすくするポイント、引用・出典の使い方について述べています。
最終付録に、レポートのサンプルを記載しています。
読後感想
何冊か論文・レポートの書き方についての書籍を読ませていただいていますが、この本は初歩の考え方から、書き方の基本までしっかり解説してくれています。
他の本と同様に何度も読み返して、実戦で記述しながら理解を深めていく必要を感じましたが、わたしのように今まで論文を書いたことがない人にとって、ヒントを与えてくれる内容となっています。
記事を書いていくと、ここはどうすればよいのだろうと分からない部分が出てきます。
この本の内容でいえば、以前から序論の書き方が難しいと感じていたので、序論の基本的な説明があったのはありがたかったです。
この本を読んでも、すぐに筋道が立ったわかりやすい文章をスラスラ書くことは難しいです。
わたしのように独学で勉強している人は、この本に書かれている手順を踏んで試行錯誤しながら記事を書き続けることに意味を感じています。
今後もこの本は手元に置いて勉強していきたいと思います。
おわりに
記事を書いていると、読者にわかりやすく自分の意見を的確に伝えたいと考えます。しかし、なかなか思うように満足する文章は書けていないと思っていました。
わたしのように学生ではない人間は、学校で論文やレポートについて学べる機会はありません。
大学生とは違いますが、勉強する環境が整っていなくても、この本からは自分で学んでいく姿勢の大切さを教えてもらっているように感じます。
サポート感謝します。費用はライティングやデザインの勉強費用に使わせていただきます。
