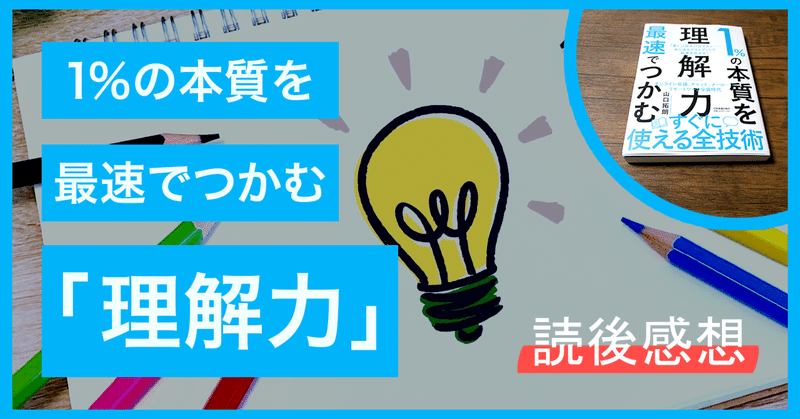
【読後感想】1%の本質を最速でつかむ「理解力」
様々なビジネスシーンで必要になる能力は、何だと思いますか?
「相手の話しを理解すること」「丁寧にわかりやすく伝えること」「ミスをしないためリスクを回避すること」などが頭に浮かんでくるでしょう。
仕事では、商談や企画会議、プレゼンテーションなど能力を発揮することを求められます。
仕事を上手く進行させるには、テーマの本質を理解してプロジェクトチームで目的を達成するために最良の道筋を立てる、
プレゼンテーションであれば、自分が企画・立案した情報を相手にわかりやすく説明し、未来予想や展望を提案してみる。
ビジネスシーンで必要になる、こういった能力を磨くにはどうすればよいか。その疑問を解決するヒントを伝えてくれるのが今回の書籍です。
わたしたちに問われている「聞く」「理解する」「伝える」という能力は、一見すると簡単なようで、上手く実践できていない人も多いと思います。
この本は人との会話が苦手で上手くいかなかったり、相手の言うことを理解できない人に必須となる能力「理解力」に焦点を当てた本となります。
著者:山口拓郎
タイトル:1%の本質を最速でつかむ「理解力」
発行元:株式会社日本実業出版社
本の要約
仕事の場で理解を間違えてしまったことにより、誤情報を記事に書いてしまう。このようなケース、誤解や見落としによって発生する重大なミスは、記事を書いた本人だけでなく、会社の信用を落とすことになります。
それを回避するために「理解力」は欠かすことができない能力です。
理解力がある人と、ない人では意識の違いがあり圧倒的な差となって現れます。
冷蔵庫とは何ですか?と質問された場合、あなたならどう答えるでしょうか。
「食品を冷蔵・冷凍保存するための電化製品」
「細くて大きい縦長の箱で、内部を低温にする機械」
といった回答が出てくると思います。
しかし、質問の内容を冷蔵庫の発祥や歴史は?と質問された場合はどう答えるでしょうか。
答えられないか、答えたとしても内容は変わってくるでしょう。
普段わたしたちが冷蔵庫を理解していると思っている内容が、単なる使用目的だとすれば問題はありません。
もし冷蔵庫の歴史を問われていたとしたら、誤った答えを導きだしてしまうかもしれません。それが今後の理解の良し悪しや、理解の程度の差となって表れます。
物事を判断するときに人は「理解の箱」に照らし合わせて考えています。
映画を見た時に表面的な部分に焦点を合わせるだけで見て、この映画はつまらない・おもしろいとジャッジしがちです。
しかし、理解ができる人はこの「理解の箱」が多種多様です。
物語の構成が意外性があってハラハラしたとか、敵の目線で物語が進む過程の中で変化していく心情に共感したといった、様々な視点で理解を深めることができます。
結果、本質的な理解へと導くことができるのです。
それが仕事になると成果に繋がり、仕事ができない人との違いとなって現れます。
理解したつもりになっている状態。すなわち、もう理解しなくていいという状態。
この状態が先ほどの映画のように、視野は断片的になり、情報の漏れや誤りに気付かなければ、本質を理解できず説明できない状態になってしまいます。
そのため、わたしたちは物事を理解したつもりになっていないか、常に問いかけるクセをつけなければならないのです。
社会人になって、仕事で経験を積んでいる人は「脳内ライブラリー」が活性化しています。営業のかけ方やクレーム処理、場面場面の対処の仕方など過去の経験によって知識が蓄えられていき、話す・書く・行動するというアウトプット力が高い状態になります。
この本で伝えている理解力とは、この「脳内ライブラリー」の充実と活性化にあるのです。
では、文章を読むときはどうなるでしょうか?
わたしたちが文章を読むとき、特に気にとめず流し読みする人もいれば、情報の結びつきを考えながら物事を理解する人もいます。
しかし、文章には見えない情報が隠れています。
見えない情報も取りこぼしがなく、本質的な理解に繋げていくために「推測力」が必要になります。
例えば人と会話をしていると、主語が抜けていたり、裏の目的があるかなど、会話の中には見えない情報が隠れていることがあります。
見えない情報は、「脳内ライブラリー」を使って自分で推測をしなければ理解に繋がりません。
推測を普段から怠っていると、比較や分析することが難しくなり、情報を読み解くことはできません。
そうすると、いざという時に推測する力を使うことができず、誤った解釈をしてしまうでしょう。
わたしたちは普段、物事を理解するために4つのアプローチを使っています。
・聞く
・読む
・体験する
・思考する
この4つのアプローチを使って読解力を高めていきます。
そしてこのアプローチだけでなく「脳内ライブラリー」を活性化するための方法についても、この本では3つのステップに分けて紹介されています。
ステップ1:言葉の理解
ステップ2:「幹→枝→葉」で理解する
ステップ3:クリティカルに理解を深める
ステップ1:言葉の理解
はじめの一歩となる言葉の理解は重要です。
言葉とは情報です。
人は「脳内ライブラリー」に情報のストックがあるほど、言葉について理解でき、推測を立てることもできます。
そうして情報を整理することで、アウトプットができるのです。
初めて聞く言葉や知らない言葉は、自分の考えをまとめることも、理解していくこともできません。
その時はわからなくても、辞書で調べたり誰かに教えてもらうなど、言葉と意味を結び付けて頭に格納していくことが大切です。
そうすると理解の箱にストックされ「脳内ライブラリー」は活性化していきます。
今度、同じ言葉に当たった時の情報処理スピードは上がり、理解力もアップするのです。
生活言語と学習言語
言葉には2つの種類があります。
・生活言語
・学習言語
です。
特に学習言語について、現代の社会人が意識できている人はどれほどいるでしょうか?
ニュース記事や論文、参考書などに書かれている「書き言葉」
この「書き言葉」を目にする機会が少ないと、仕事で必要になる報告書作成や契約書の理解には繋がっていかないのです。
この学習言語を増やしていくことで、難しい情報の理解が進み上手くアウトプットができるようになります。
言葉の定義をすり合わせる
ビジネスシーンでも、言葉の定義をすり合わせることも必要になります。
お互いの言葉の定義が違っていれば、情報の共有が図れていないので、最終的な仕事のミスに直結する惨事に発展します。
明確に説明できるか
本当に理解できているか確認する方法として、理解したとされる物事を説明できるかという点があります。
説明できなかった時に、何が理解できていないか、理解することは何だったのかを再認識できます。
要は「理解の現在地」を知ることができるのです。
言葉を理解しているかを確かめるためにも、説明をすることは不可欠で説明できなければ理解できていないことと同じなのです。
文脈理解力
また、ビジネスの会話で定義を合わせることだけでなく、文脈理解を深めていないとトラブルに発展するケースも増えます。
この本では文脈理解のエピソードが紹介されています。
「明日は雨らしい。ロケ中にタレントさんが困らないよう、よろしくな」
あなたが、この指示を受けたADだった場合、この言葉をどう理解しますか?
以下は文脈理解力が低いADと高めのADの違いです。
文脈理解力が低めのAD
タレントが濡れないようにビニール傘を持っていく。
文脈理解力が高めのAD
受けた指示の本質は「タレントを濡らさないこと」と「タレントに気持ちよく仕事をしてもらうこと」だと理解する。
天気予報をチェックすると、雨が強く降る予報が出ていたため、大きく頑丈な傘に加え、念のため、全身を包めるレインコートも準備する。
また、万が一、タレントが濡れたときのことを想定して、バスタオルとフェイスタオルも用意。身体が冷えることも予想されるため、水筒に暖かい飲み物も持っていく。
このような文脈理解力の差が生まれてしまえば、仕事ができる人・できない人の明暗がわかれることがお分かりいただけると思います。
「聞くこと」が理解を深める
人の話しを聞くとき、しっかりと聞いているようで、案外聞いていないものです。
話しを聞くことは理解の第一歩となるので、人の話しを聞くためのトレーニングとして傾聴の技術を活用します。
傾聴では、相手の立場になって耳を傾ける。
相手の非言語(仕草や雰囲気など)に注目したり、気持ちに寄り添ってみる、いわば相手に意識を向けていくことで理解力と話しを聞き流さないクセを身につけることができます。
アクティブリーディングとは?
本や小説を読むことでも理解力を養うことが可能ですが、どのようにして養えばよいでしょうか?
そのためには、ただ流して読むだけでなく、理解力が高い人のように読む際に工夫をすることが必要です。
それは能動的に読むこと(アクティブリーディング)です。
この本の目的はなんだろうと考える
結論はどこで根拠はなんだろうと考える
なぜ?どうして?どのように?誰が?と疑問を持ちながら読む
わからない言葉を調べてみる
読んだ後は要約して書いてみる
理解力が高い人は、このような能動的な読み方をしているのです。
ステップ2:「幹→枝→葉」で理解する
人は文章を読むときでも、会話をしているときでもテーマが何かわからないと理解力が下がってしまいます。
そのため、この話のテーマが何かを探るクセをつけることは大事で、まずはテーマを把握することに努めなければなりません。
ここで、あなたに質問します。
以下はある人物について話していますが、誰の話しでしょうか?
①日本人としては大柄で、身長173cm、体重70.25kgと体格が良い人物である。
②木村摂津守とはとても親しい間柄だった。
③慶應義塾(旧蘭学塾)の創設者として知られており、一万円札の人物でも有名です。
答えは「福沢諭吉」です。
①や②で答えられる人は少ないでしょう。
③の一万円札の人物が大きなヒントになっているため、多くの人が答えられるはずです。
もし、③→②→①の順番で説明されていれば、この話しは「福沢諭吉の話しをしているんだな」と早く理解でき、理解力も深まります。
このように物事を理解するためには全体(幹)を見つけることが大切で、全体から細部(葉→枝)の手順を踏むことが望ましいです。
根幹ともいえる全体情報「これはいったい何の話しであるか」を考えていけば、物事を理解できるスピードが速くなるというのです。
しかし会話をする全ての人が、いつも全体(幹)の情報を話してくれるわけではありません。
その場合は「その話しはどういうことでしょうか?」と投げかけることも大事になります。
理解力を深めるために13のアプローチも紹介されています。
①「書き出して」理解する
②「芋づる式」に理解する
③「比較」しながら理解する
④「図表」を書いて理解する
⑤「道筋・道理」から理解する
⑥「具体例」から理解する
⑦「五感で」理解する
⑧ 文章を「要約」して理解する
⑨ 最悪、「主語」と「述語」だけ押さえる
⑩「5W3H」で理解する
⑪「因数分解」して理解する
⑫「相手の立場に立つ」で理解する
⑬「理解の箱」と結び付けて理解する
それぞれの項目の説明は割愛しますが、
これらのアプローチを踏むことで理解力を高めることができます。
ステップ3:クリティカルに理解を深める
この本では「クリティカル思考」で情報を疑ってみること、自分の思考と照らし合わせて分析をする必要性を問いかけています。
情報を読んだときに鵜吞みにするのではなく、ほんとうに正しい情報かを疑ってみる。そして情報ソースを調べたり、情報に翻弄されない意識を持たなければなりません。
そのような行動ができる人は、クリティカル思考が働いている人なのです。
世の中には論理が飛躍していたり、支離滅裂な情報や論理が破上している話しや文章が少なくありません。
正しい理解をするために”「言葉の結びつきの強さ」と「結論を支える理由や根拠の強さ」”の2つを注意深く見ていく必要があります。
「言葉の結びつきの強さ」と言われても、ピンとこないかもしれません。
日本語には言葉の結びつきの強さで、この文章が論理的である・なしを判断していくことになります。
例えば、
「わたしはギターの演奏が他の誰よりも上手です。過去に1000人が参加したギターコンテストで優勝し、名だたるプロミュージシャンと一緒にステージで演奏してきました」
とあれば、ギターが上手であるという言葉に説得力があり、言葉の結びつきが強いことがわかります。
理解を深める能動アプローチ
能動アプローチの方法の例として
・文章を声に出して読む、音読を使って理解する。
・相手から必要な情報を引き出すため、質問を重ねて理解する。
・さらに必要な情報を集めるために、仮説を立てて理解する。
・伝え手自身が理解できていない可能性を考えて、反論しながら理解する。
・人とディスカッションを重ね、自分の意見との違いや、根拠・理由を探しながら理解する。
・自分自身が体験した経験を生かして理解する
・第3者からのフィードバックから理解する
・メモを残して理解する
理解力を高める必要性は、わたしたちの人生や仕事に生かすためです。
その理解した知識をアウトプットし、人に伝えると多くのことが自分に返ってきます。
それはお金や人脈、新たな情報や応援などのリターンです。
ビジネスの世界では与えられる人が成功していきます。
理解の本質を理解して相手を理解していくことが、人生の視野も広げ成功にも近づけるものとなります。
読後感想
ビジネスシーンで、なぜこの人は仕事ができるのだろうと思う人がいます。
この本に書かれている、「理解力」を鍛えているからこそ相手が話す本質を理解でき、ビジネスの場で成果を出せているのだと思いました。
本を読むときも、今までは深く考えずに読むこともありましたが
それは理解力を養ううえでは良くない事だったのです。
この本に書かれている批判的な思考を持ったり、仮説を立てていくことを実践できていれば、仕事の結果や成果もまた違ったものとなっていたと感じることが多い内容でした。
理解力を磨いて、ビジネスに生かせられるように今後も読んでいきたいと思える書籍でした。
サポート感謝します。費用はライティングやデザインの勉強費用に使わせていただきます。
