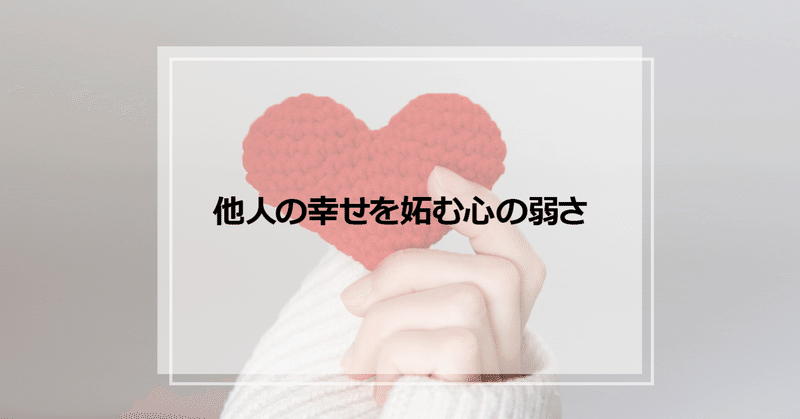
他人の幸せを妬む心の弱さ
昨今、わたしたちにとって暗い影を落とすニュースや話題が多いです。
人に対する思いやりや関心も薄れていき、人の幸せを素直に喜べない人が増えているのではないかと感じることが多くなりました。
妬むことは心の弱さと言えるのでしょうか。
心の弱さと考えるよりは、これから世間が目を向けて考えていくべき問題が表面化したものであると感じます。
なぜ人の幸せを妬むように心は感じてしまうのか、考察してみました。
日本の幸福度について
日本の幸福度は可視化されにくいです。
人によって幸せの基準値が違うため、何が正しくて正解であるかわかりにくい部分が多いです。
以下の図は、内閣府経済社会総合研究所(平成24年)の第一回 生活の質に関する調査結果による「現在の幸福感」の調査です。

このデータが示してあるように、幸福度は高いと言えるでしょう。
しかし政府が発表しているデータと世間の幸福度には、温度差があるように思えて仕方がありません。
実質経済は低迷が長く続いており、国民の負担増や貧困についてもSNSでも話題になる事が多くなっています。
財務省が発表している、租税負担率と社会保障負担率を合計した「国民負担率」は令和5年度で46,8%の見通しとなる数字です。
国民負担に財政赤字を加えた潜在的な「国民負担率」は53.9%という高い数字です。
負担だけが増大しつつある日本。
国民にほとんど還元されないことも問題ですが、政府が行う支援や対策が経済効果をもたらしているとは言えないでしょう。
財政的な負担は、日本の幸福度が上がらない・幸福度が高いと実感できない原因の一つであると思います。
今や6人に1人が貧困状態にあるといわれています。
日本は誰もが安心できる経済状況ではなくなってきているのです。
格差拡大の影響
日本の幸福度の低下は、格差拡大によって与えられた負の影響を大きく受けていると言わざるを得ないでしょう。
教育格差、恋愛格差、経済格差。
すでに日本は格差社会に突入しており、もっと格差は広がっていくものと考えられます。
現に、経済格差からくる負のスパイラルは様々な影響を及ぼすものです。
低収入層は、子供の教育を受ける機会が減り、教育をしっかり受けている層と差ができてしまいます。
大学まで進学できないと、就職の面で選択肢が狭くなります。
就職の失敗は今後の人生の計画を狂わせる問題の一つです。
そこから経済格差に陥ると、収入が低いことにより恋愛にも消極的になり、格差が広がっていきます。
恋愛において若者が恋愛に興味がないと、世間で話題になることがあります。しかしこの時代、恋愛するにもお金がかかります。
収入面の低さから結婚を諦める人は増えていますが、恋愛を諦めていくことにもつながり、より恋愛できる人とできない人の格差も広がっている状況です。
所得の格差が与える様々なマイナスの影響は疑いようのない事実です。
誰もが幸福度を得るには、この経済格差を解消することは言うまでもないでしょう。
経済格差を是正する為に、政府は何か対策を考えているのでしょうか?
内閣府によると、格差拡大是正措置として所得の格差是正には「所得再分配」が政策として行われ効果は大きく出ていると述べています。
富の再分配ともいわれ、所得の高い人の分を低所得層に配るというものですが、実感できている人はどれほどいるのでしょうか。
今の日本は給料は上がらず、物価はどんどん上昇しています。
さらに社会保障も負担が増加していて、残念ながら政府の行う「所得再分配」の効果には疑問を感じてしまいます。
所得中間層を増やす
減税される
給料が上がる
といった国民の幸福感に繋がるような施策を何十年と政府は実行できていません。
格差の問題は「自己責任」で切り捨てられやすい問題のため、より格差が広がっていることを実感している人は多いのではないでしょうか。
「自己有用感」の低下
幸福度研究ユニット(平成24年)によると自己有用感とは、
自己有用感は、「自分の属する集団の中で、 自分がどれだけ大切な存在であるかということを自分自身で認識すること」である。
人は社会や地域の中で、自分の居場所を見つけるために必死に働いてます。
社会での居場所を持つ人は、人から感謝されたり、誰かから必要とされることで自尊心も上がりますし、日々の生活の中で幸福感を得ているでしょう。
将来設計を行っていても、病気や事故、予期しないトラブルが人生には起こります。
リストラや離職に見舞われると、安心して社会復帰できるセーフティーネットは整備されていません。
財力があり、教育をしっかり受けている人は自力で立て直す力を持っているので、再び軌道修正ができるでしょう。
就職が上手くいかず、社会の中で自分の居場所を見つけられなければ、将来に希望が持てなくなった自殺や引きこもりの問題が起こります。
自己有用感を得るには、社会的に成功する必要があるため失敗した時、自分自身で幸福感を高めることは難しいのではないでしょうか。
「人の幸せを喜べる人は本当に幸せになるのか」という問い
わたしは「人の幸せを喜べる人が幸せになる」という問いに関しては疑問を感じます。
わたしは逆で、嫌な事が起こってしまった経験があります。
同じように、人の幸せを素直に喜んで幸せになりたいと思った一方、この考えには否定的な考えがどうしても強くなってしまいます。
例えば、よく目にするのが引き寄せの法則。
誰かが結婚をして幸せになる。人の幸せを一緒になって喜んでいたら次はあなたの番で幸せがやってくるといった話しです。
相手がいなければ、結婚することはありません。
経済的な理由、頑張っても恋人ができない、デートも断られる。
重篤な病気や障害で恋愛できないなど。
全ての人が自分の思うような人生を歩んでいるわけではなく、人の幸せを喜んでも幸せになる保証はありません。
出会える人を好きに選べるわけではないし、良い人だけに出会うことはできません。
人との出会いや人間関係における運の良し悪しで、人生の幸福度を左右することもあると考えられます。
職場で毎日ミスをして上司に叱られる、学校で性格が暗くて周りからは馬鹿にされるような状況だったらどうでしょう。
職場や学校の中で、周りから馬鹿にされたり信頼を失うと、人間関係を良好にするのは至難の業です。
今は成果主義・実力主義で、周りと協調性がない人、仕事ができない人は嫌われやすいです。
自分の努力で周りから認められて初めて、居場所ができたり人から信頼や評価を得ることができます。
その逆で結果がでなければ周りから冷たくされ、コミュニケーションを取ることが難しくなって人間関係が悪くなるでしょう。
そのような状況下で人の幸せを喜んで、自分を幸せにする方向に変えられるのでしょうか。
精神的に不安定になり、悲観的になってしまうと思います。
人は嫌われたりして追い込まれて孤独になった時に、その傾向が強くなると感じます。
人のせいにするな、環境のせいにするな。という声がネットやSNSの世界でも聞こえてきます。
それはそれで正しいし、真理だと思います。
自分でどうにかするのが筋だという話しになれば、ただの自己責任論になってしまいます。
はたしてそれで、人が純粋に他人の幸せを喜べるような社会に向かうのでしょうか?
人の幸せを喜ぶことが難しかったとしても、個人が意識することがあると考えます。
どうしても妬んでしまうのなら、冷静になって難しく考えず、適当に流してみるのも一つの方法ではないか。
妬むよりは流れに乗って適当に喜んでいても、無駄ではないと思います。
気分は沈んでいても少しでもプラス要素があれば、その人自身の雰囲気が良くなり、チャンスや運がめぐってくることはあり得ることだと思います。
人間が心から「幸せになる」というのは、最高の結果です。
これだけ格差も広がり、閉塞感のある時代。
経済状況は依然厳しく、自分一人で生きていくことが精いっぱいで、他人の事を気に掛けている余裕が、どんどん薄れていっているように思います。
そのような状況の中、人の幸せを妬む余裕すらない人も多くなっていると思います。
現実が上手くいっていなくても、その辛い気持ちを一旦受け入れてみる。
そこから何かに気づいたり、学ぶものがあって先に進めたとしたら、また一つ成長できます。
「人の幸せを喜べる人が幸せになる」という問いに関しては疑問を感じると書きました。一歩引いて冷静に考えてみると、それほど大げさに考えることではないのかもしれません。
今の時代は、完ぺき主義を求めすぎている社会になっているように思います。
もっと心に余裕を持った遊びや適当さを持つことが大事だと感じます。
心のゆとりがあることで、人は他人の幸せを喜ぶことができる寛容な社会に向かっていくように思います。
参考文献
内閣府 経済社会総合研究所(平成24年) 第一回生活の質に関する調査結果(インターネット調査)(検討用資料)
サポート感謝します。費用はライティングやデザインの勉強費用に使わせていただきます。
