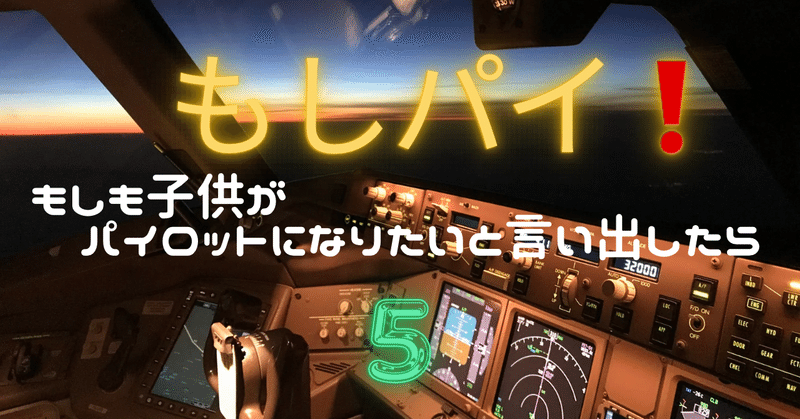
もしパイ❗️パイロットってどんな仕事?(その③)
その③ 官公庁(海上保安庁、警察、防災)
海上保安庁
自衛隊に次いで、海上保安庁もヘリコプターからジェット機まで多くの機体を保有しています。
私が自衛隊に在籍していた時期には、海上保安庁は固定翼機の初期訓練施設を自前で持っておらず、そのため海上自衛隊に訓練を委託していました。
その結果、訓練同期に海上保安庁の方もいましが、現在では海上保安庁が自身の訓練施設を持っているようです。
海上保安庁パイロットの主な任務は、海に関する警備や取り締まり、海難対応、海洋調査など多岐にわたり、これらを空から支援することです。
勤務内容は、自衛隊と似ている面もありますが、組織の性質が全く異なるため、基本的には別物と考えられます。
しかし、災害時など緊急を要する場面では、自衛隊と同様にタイトな運用が求められることがあります。
このような点を考えると、勤務条件は自衛隊と同様にハードな部分があると言えるでしょう。
自衛隊との違いで言えば、飛行手当ての支給基準が全く違うため、同じ年齢で同じ飛行時間でも結構金額に差があったように覚えています。
そのためか、当時海保では民間航空会社へ転職する場合、自衛隊のように2年間のクーリングタイムが必要なかったこともあり、免許を取得し若年退職してエアラインへ転職する方が多く、必要資格が取れる教習所のように言われていたことを記憶しています。(今は詳しくわかりませんが)
警察
警察飛行隊のパイロットの多くは、自衛隊や海上保安庁から転職した人たちで構成される傾向にあります。
退職者が出るタイミングでのみ求人が発生するため、求人が出る機会は限られており、一般にはあまり多くの求人が出ていない状況です。
実際に、私の同期がある県警で働いており話を聞いたところ、限られた人員で多くの仕事をこなしているため、長期休暇を取りたい場合や、慶事等で他県に出向く際の休暇も取得が難しく、また夜間における待機なども交代で対応しなければならないため、なかなか厳しい勤務状況だと言っていました。
このように勤務条件については、毎日家に帰れるとは言え、ハードな部分があるように感じます。
防災
一部の県では自前で航空機を保有していますが、維持や整備にかかる費用の高さから、多くは運航業務を専門の事業会社に委託しているようです。
私の後輩が勤務しているある県の防災ヘリの例では、ヘリコプターは県が所有しているものの、操縦士や整備士、運航管理者などの運航に関わる部分は使用事業会社に業務委託されています。
勤務環境については、現状では比較的負担が少ないとされていますが、パイロットの退職があると突然業務が圧迫される状況になることがあるようです。
防災航空隊も、先に述べた警察航空隊と状況が似ている面があり、特に災害が発生した場合は稼働が急増します。
そのため災害の規模や被害状況に応じて、最小限の休息を取りながらの勤務が求められることもあります。
これは、防災航空隊や警察航空隊が担う仕事の特性上、避けられない側面と言えるでしょう。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

