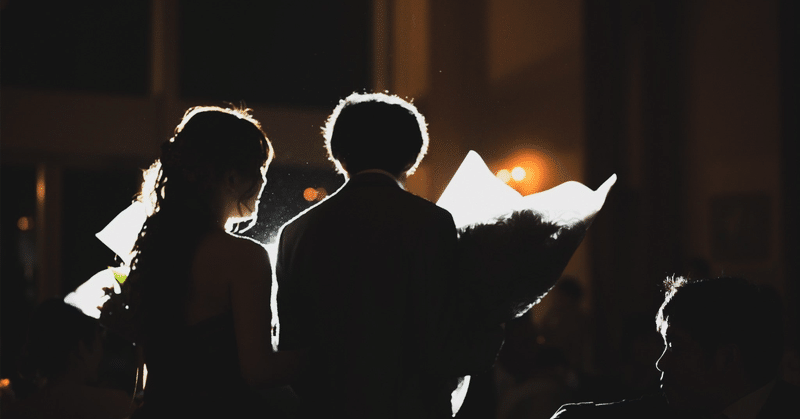
結婚披露宴のスピーチがうまい人
会社員時代、たくさんの結婚披露宴に出席しました。主賓の挨拶を述べたことも二桁はあったような。
主賓の挨拶とは、乾杯前の披露宴冒頭で喋る、あれです。主賓の挨拶なんて誰も聞いていないのはわかっているのですが、まだ場が張り詰めた状態の中で、ひとり喋るのはなかなか緊張します。
生まれて初めての挨拶はえらく緊張して、辿々しい喋りで新郎新婦には申し訳ないことになってしまいました。
二度目以降は、あの場にも慣れてきましたし、新郎新婦のどちらかが自分のスタッフなので、参列者に新郎新婦が勤務する会社と職場の紹介をする部分は大体同じにして、その社員のエピソードをひとつかふたつ追加するようにしました。
主賓は、新郎新婦双方が立てるので、ふたりの挨拶が連続することになります。
大抵の主賓は、僕と同じように何度も挨拶をしたことがある人なので、「ああ、そんな感じですね、じゃあ、こちらもこんな感じ」みたいに長さも内容も合わせるようにします。相手が少し砕けた感じできたら、こちらも柔らかい感じに修正したり。
相手も同じような挨拶なら予定調和になって良いのですが、たまにスピーチのプロみたいな人が登場することがあります。
本当にスピーチがうまい人は、テンプレなんて全くなく、いや本当はあるんだろうけど、それを一切見せないように話します。
クスッと笑えるけど、挨拶前の緊張した場を崩さない絶妙なつかみにはじまり、最後はちょっと感動するような話を差し込む。長くもなく短くもなく、帯にも襷にも使えるような完璧な長さのスピーチを繰り出します。
こちらが先なら良いのですが、スピーチマスターの後に挨拶するのは、かなりキツイです。こういう時にマスターの真似をしてフォームを崩して喋ると大体失敗します。
だけど、スピーチマスターの喋りは勉強になります。喋りがうまい人は抑揚と緩急をつけます。うまい人の話をじっくり聞くとわかりますが、一本調子で喋っておらず、リズミカルに話しながら、時々息をつき、あえて止めて人の注意を引くことをします。
スピーチをするときは、とにかく誰も真剣に聞いていないと思った方が良いらしく、わざとちょっと変わった言葉を使ったり、無言を一瞬作ったりして、人の注意を引くことをまずします。
「この人、面白いこと喋りそう」という雰囲気を作ってしまえば、あとはその雰囲気に合わせた「ちょっと面白い」ことを話せば、ウケるわけです。漫才や漫談と同じですね。
もちろん、話す内容も大事ですが、雰囲気作りがまず大事になります。
小説も同じ気がします。物語の冒頭で、「これは面白くなりそう」と読者に思ってもらう雰囲気を作ることが大事だと思います。
最初に「なんだかよくわからない」「難しそう」と読者に思わせてしまうと、その後の内容が頭に入っていかない気がします。
冒頭を面白く感じられれば、その小説のファンになってもらえます。ファンになってもらえれば、最後まで面白く読んでもらえると思います。
スピーチも小説も掴みが大事だということで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
