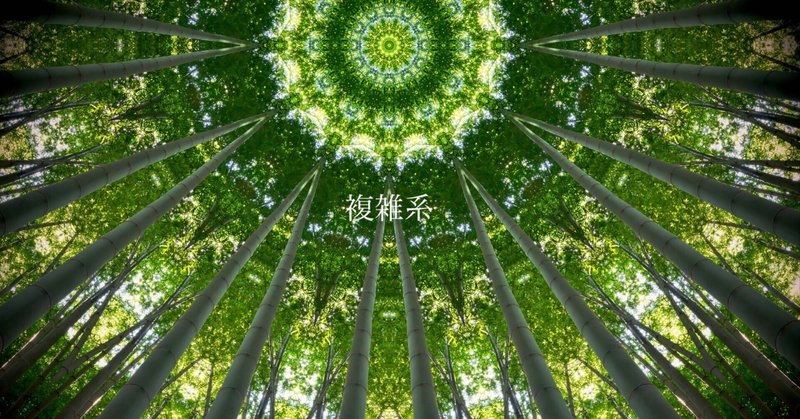
創造を可能にする場所──『複雑系』読書感想文(後編)
上記の感想(前編)に引き続き、『複雑系』について。
複雑系に取り組みと1996年当時の状況(「前編」のテーマ)
多分野をまたぐ組織のあり方(当記事「後編」のテーマ)
当記事では2つ目の「多分野をまたぐ組織のあり方」について、気になった箇所を本文より引用しながら書き留めておきたい。
サンタフェ研究所
About
Our researchers endeavor to understand and unify the underlying, shared patterns in complex physical, biological, social, cultural, technological, and even possible astrobiological worlds. Our global research network of scholars spans borders, departments, and disciplines, unifying curious minds steeped in rigorous logical, mathematical, and computational reasoning. As we reveal the unseen mechanisms and processes that shape these evolving worlds, we seek to use this understanding to promote the well-being of humankind and of life on earth.
Research Themes
組織の目的に応じてメンバーを選ぶ
サンタフェ研究所には「新しい研究を目指す、学際的で何の制限もない自由な研究施設」という設立のビジョンがあった。それに向かない人物は、メンバーの候補から除外されるなどしたという。
「われわれは世捨て人のような人間、本を書くために研究室に閉じこもってしまうような人間は欲しなかった。われわれが必要としたのはコミュニケーションであり、典奮であり、相互の知的な刺激だった」と、ヨーワンはいう。
とくに必要としたのは、ある確立された分野で真の専門技術と独創性を発揮していながら、新しいアイディアに対してオープンな人間だったと、彼はいう。しかしそれは、名のある科学者においてさえ(いや、名のある科学者だからこそかもしれぬが)、絶望的なほどまれな組み合わせだった。
新しい組織を設立する際には、目的やビジョンにあわせて人間を選ぶこともある程度必要なのかもしれないな、と。人の選別という事実は、きれいごとではない分、良い組織の作り方について考えさせられる。
「真の専門技術と独創性を発揮していながら、新しいアイディアに対してオープンな人間」……この希少な人材を集められる時点でもう勝ちのような気もするけど。
「いったんコミューケーションが成立してしまえば、こっちは、何物をも動かさずにはおかない力、つまり知性の力を行使することになる。こっちのいおうとしていることと同じことを以前からずっと考えていて、それを心底わかってくれる人と出会えれば、もうその人をつかまえたも同然だ。物理的に強制するんじゃなく、強制にも等しい知的アピールで惹きつける。急所をつかむかわりに、脳ミソをつかまえるんだ」
そういう人材を見つけるのは、以前にもまして難しかった。しかし、いないわけではなかった。そういう人物が、しだいにサンタフェに現れるようになり、その数は増え続けて──ついには、小さな修道院の建物では収容しきれない事態もしばしば起きるほどになった。
サンタフェ研究所は、そのような人材の獲得(というか惹き寄せ)に成功した。理由の一つはビジョンと問題意識の共有だと思う。
時間でもなく、ルールでもなく、「共感」をベースに集う集団が、もしかすると一番強いのかもしれない。
参考|Our Mission(Santa Fe Institute)
共通言語を探せ
皮肉にも、はじめ物理学者たちは数学的抽象性に対して懐疑的だったが、共通の言葉を授けてくれたのは数学だった。「いま振り返ると、ケンが正しい判断をしたんだと思います」と、ユージェニア・シンガーいう。はじめ彼女はケン・アローが社会学者と心理学者をグループに入れなかったことに失望していた。
「ケンは専門的にもっとも高度に鍛えられたエコノミストたちを集めました。その結果、信頼性が築かれた。物理学者たちは、エコノミストたちの専門的な知識に驚いていた。彼らが多くの専門的な概念に、しかも物理学のいくつかのモデルにも、精通していたので。だからこそ両者は、共通の言葉を使いはじめ、たがいに話を交わせるような言語を築いていくことができたんです。でも、もしそこに、そういう専門知識のない社会科学者が大勢いたら、はたして深い溝に橋を架けることができたかどうか」
数的に実証できない理論を、どれだけ理数系の研究者が疎んでいるかが何となく匂う部分。「感覚でものを言うんじゃないよ」といったところか。
異種のコミュニケーションにおいては、普遍性のある共通言語探しが大切。
雑事を疎かにしないこと
自分の時間のおよそ八十パーセントを学問以外の仕事にとられていた。これはアーサーにとって、あまり楽しい情況とはいえなかった。ある日、サンタフェの借家に戻ると、アーサーは妻のスーザンに、研究に使える時間がほとんどないといって愚痴をこぼしはじめたという。「結局スーザンはこういったよ。『まあ、愚痴はおやめなさい。これまでに、こんなに楽しかったことはないんでしょう』ってね。いわれてみれば、彼女のいうとおりだった」
まさにそのとおりだった。あれやこれやの管理的な雑事をこなしたからこそ、残りの二十パーセントがすべてを補って余りあるものになった、とアーサーはいう。
仕事には、成果との直接的な結びつきが目に見えないような地道・回りくどい・根気のいる雑事が大半を占める。
しかし、直結しているように見えないからといって劣後して良いというものではなく、それぞれが「必要な雑事」を積極的に行うことが組織運営にはとても重要だと思う。
ここで私のいう「必要な雑事」とは他者の仕事を支援する行為であり、巡り巡って組織全体や自分の仕事を向上させる行為のこと。目の前の煩わしさから逃れようというだけでこのようなことを他者にばかり押し付けたり、忌避し疎かにする人間は、結局何も成し遂げられない。
未来永劫、破綻しないシステムはあるのか
「社会の組織化に対する一党独裁的かつ中央集権的なアプローチがあまりうまくいかないことは、いまや明白だ」。長い目で見れば、スターリンが築いたシステムは、生き延びるにはあまりにも停滞していたし、あまりにも硬直していたし、またあまりにも厳しく管理されすぎていた。あるいは、一九七〇年代のデトロイトのビッグ・スリーを見てみるとよい。彼らは大きくなりすぎ、何をするにも小回りがきかなくなって、日本の自動車メーカーの挑戦が抜き差しならないところまできていることにほとんど気づかず、ましてそれに応戦することなどとてもできなかった。
だが一方で、無政府状態というのもあまりうまくいかない──かつてソ連が崩壊した際に、一部では断固としてそれを実証してみせるかのごとき動きがあったようだが──とファーマーはいう。同様に、放任方式もだめだ。ディケンズが描いたイギリス産業革命時代の恐怖、あるいはもっと最近では、アメリカにおける貯蓄貸付組合の破綻を見るがいい。最近の政治的経験はいうにおよばず、常識で考えても、健全な経済、健全な社会はともに、秩序とカオスのバランスを保ったものでなければならない──しかし、かといって、平均的でどっちつかずの、足して二で割るようなバランスでもいけない。生きている細胞と同じように、フィードバックと調節の濃密な網を張りめぐらせ、それによって自己を統制すると同時に、創造し、変化し、新しい条件に対応できるだけの十分な余裕を残していなければならない。
「進化は、柔軟性を保証するボトムアップ方式の組織を持ったシステムでよく起きる」とファーマーはいう。「だが同時に、進化は、組織を破壊しないような仕方でボトムアップのアプローチに道をつけるものでなくてはならない。そこには管理の階層構造──しかも、情報が下から上へ流れるのと同時に上から下へも流れるような構造──が必要だ」。
社会(組織)のシステムは時代によって最適なものが考案され(意図的にまたは自然に)選ばれる。いったん安定すると、現状維持バイアスがはたらくために秩序とカオスのバランスの不具合を看過する。
そしてシステムは破綻し、その反省をもとにまた新たな仕組みが生まれていく。
ファーマーがいうように、社会構造が柔軟であり、それがうまく機能して逐一不具合や変化の兆しを見逃さずに即座に修復・是正をすれば「破綻を見ないサステナブルな社会」が実現するのだろうか。
同じ方向を見据える、同じ熱量を持った人材
コーワンの念頭にあった研究プログラムは、具体的には「適応的コンピューテーション」をテーマにしたもので、これは、複雑性の科学のすべてに──もちろん経済学にも──応用できる数学とコンピューテーションのツール一式を開発しようという試みだった。「共通の概念的枠組みがあるとすれば、分析手法にも共通の枠組みがあるはずだ」とコーワンはいう。さらに、ある意味では、そういう研究プログラムをスタートさせるには、単にその分野にすでにどういうものがあるのかを調べ、それに対してより幅広い支援を与えさえすればよい話だという。ジョン・ホランドの遺伝的アルゴリズムやクラシファイア・システムのアイディアはずっと以前から研究所内に浸透しており、これがおそらく適応的コンピューテーションの中軸になると思われた。だがそのほかにも、スチュアート・カウフマンのブール・ネットワークや自動触媒セット、クリス・ラングトンの人工生命、それにブライアン・アーサーらのエコノミストたちが取り組んでいたガラス箱のなかの経済のさまざまなモデルから、似たようなアイディアがつぎつぎに生まれていた。活発な交流がいままさに進行しているところだった。
多様性というのは、ただただ雑多なものを交わらせれば良いというものでもないなと最近思うことが多いが、サンタフェ研究所のようないわゆる異種格闘技のような現場において良質で活発で発展性のある交流は、どのような土壌があれば生まれやすくなるのだろうか。
「真理の一端に辿り着きたい」──この世に生きる人間なら、誰しもぼんやりそう思うことがあると思うが、サンタフェ研究所に所属する面々は「本気」だ。
目的が同じで、見ている方向が同じで、熱量が同じ。これは、多様性のある組織がうまく成立する一つのセオリーではないか。
組織の構造や仕組みどうこう以前に、個々人のその本気──情熱が、何かを成し遂げるにはきっと必要なんだろうなと思う(という精神論みたいな結論になってしまった)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
