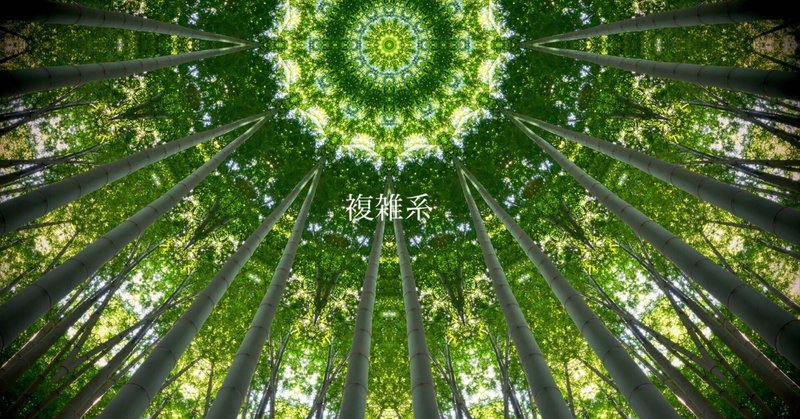
この世のすべての事象の共通項とは──『複雑系』読書感想文(前編)
知的好奇心がくすぐられ、わくわくさせられる、非常に興味深い本だった。
この1〜2年の間に物理学・生物学・経済学などの書籍を読んできたことで、超素人ながらにミクロ・マクロの不可逆性について類似点や、この世の秩序と混沌について考える機会を得られた。
この世にはまだ解き明かされていない事象が星の数ほどあるのだという気づきから、すべてが片付かない居心地の悪い気持ち悪さと、その真理へ向かう“余地”にどうしようもなく心惹かれる興奮を読書から得ることができた。
ちなみに「複雑系」とは、下記のようなことをいうらしい。
相互に関連する複数の要因が合わさって全体としてなんらかの性質(あるいはそういった性質から導かれる振る舞い)を見せる系であって、しかしその全体としての挙動は個々の要因や部分からは明らかでないようなものをいう。
要は、この世に存在するが理論でいまだ説明しきれない事象のことを差していうのだと私は理解している。
この世は(法則として解き明かされているものもいないものも含めて)同じ物理法則が適用されているフィールドで展開されている。地球を含めた宇宙のはたらきも、地球に生きる人間の活動も、すべては関与しあっている。
人類は、主に文字によって前世代の知識を引き継ぐことで、全体の知恵の総量を着実に増やしながら進歩してきた。
20世紀後半、コンピュータの発達により取り扱える情報量が指数関数的に増え、多数の人に認知できる形で明るみに出てくる事象が爆発的に増加するにつれ、ものごと単体への知識の深化だけではなく、“全体”や“相互”の結びつきまでを解き明かすことが自然と必要になってきている。
そのアプローチには分野を超えた連携が必須であり、さらにその解答は古典物理学のように法則などで美しく固定化できないことに研究者たちが気づき出したのが現代の自然科学・社会科学の研究の潮流である(最近の読書から私はそのように受け止めている)。
現代の研究者が、自身が本質的に解決したいと願っている問題解決のために取り扱う情報量は、一人の人間に担い切れる物量を遥かに超えている。だから、さらにその先に進むためにコンピュータや他分野(他の専門家)との連携が必須になっている。
研究分野の垣根を越えて、複雑な現象の根底にあるメカニズムを解明するための組織──そのような取り組みを、実態を伴って行っているのが本書に取り上げられる「サンタフェ研究所」(1983年〜)だ。
本書(日本語訳版)が発行されたのは1996年。著者であるサイエンス・ジャーナリスト、M.ミッチェル ワールドロップが行った研究所の主要メンバーへの取材を元に構成されている。
第一級の研究者たちが集う、まさに「知の殿堂」。生物学と物理学を真っ向からぶつけ合い繋ぎ合わせないと進歩しなかったであろう、現在のAI研究の萌芽ともいえる部分への言及もたくさん垣間見えて面白い。
興味深い点はたくさんあるが、私のnoteでは、
複雑系に取り組みと1996年当時の状況
多分野をまたぐ組織のあり方
という2つのテーマについて、それぞれ書き留めておきたい。
この記事では、1つ目の「複雑系への取り組みと1996年当時の状況」について、本書で気になった箇所を引用しながら記しておく。
※当記事は引用文込みで7000字あります。見出しで興味のある箇所に飛ぶなど、かいつまんでご覧ください。
経済学者ブライアン・アーサーの気づき
そして、まさにそれがアーサーの新しい経済学だった。大学で習ったような伝統的な経済学はどうみてもこの複雑さというヴィジョンからはほど遠かった。理論的なエコノミストたちがいつも口にするのは、市場の安定、そして需要と供給のバランスだった。 〜中略〜 彼らは、いわば国教のごとく、アダム・スミスの教えを受け入れていた。
しかし話が経済の不安定とか変化ということになると──そう、まさにその教えが悩みの種であることを、話題にしないほうがよいものであることを、彼らは知っているようだった。
〜中略〜
好もうと好むまいと、市場は安定していない。〈現実の世界〉は安定してはいないのだ。進化、変動、驚きに満ち満ちている。経済学はそうした動きを考慮しなければならなかった。そして、いまや彼はその方法を見いだしたと信じていた。
アーサーにとって、この地球上の無数の生物に思いをめぐらすことは、いわば啓示だった。分子レベルでは、細胞一つーつは驚くほどよく似ていた。その基本的なメカニズムは普遍的だった。しかし、遺伝子の青写真の中のほとんど検出できないほど小さな変異が、生物全体に大きな変化をもたらすことがあったのだ。 〜中略〜 小さな出来事がすべてを変化させてしまうことがある。生命は進化する。そこには〈歴史〉がある。たぶん、だからこの生物世界は自然発生的、有機的、そして、そう、生きているように見えるのだろう、そう彼は思った。
考えてみると、エコノミストたちのいう完全均衡という想像上の世界が自分にはいつも静的で、機械的で、死んでいるように見えたのはそのせいだろう。そこではけっして大したことは起こり得なかった。
市場での小さな偶然の不均衡は、起きると即座に消え去るとされていた。だがアーサーには、現実の経済以外のものを考えることはできなかった。つねに新製品、新技術、新しい市場が生まれ、古いそれらは消えていく。それが現実の経済だった。それは機械ではなく、一種の生けるシステムであり、そこにはジャドスンが分子生物学の世界で示してくれた自発性と複雑性があった。ただアーサーはその洞察をどのように使ったらよいかわからなかった。しかしそれは彼の想像力に火をつけた。
固定化できるものなど、この世の「現象」には存在しない。
そのことへの気づきが、まず第一歩だった。
※人物参考情報|ブライアン・アーサー[経済学者](wikipedia)
各々の見方で同じ問題に向き合い、練り上げる
アーサーはカウフマンと修道院周辺の道や丘を歩いていた。アーサーは、カウフマンのいう秩序と自己組織化の概念に興味を覚えずにはいられなかった。皮肉なのはカウフマンが「秩序」という言葉でいわんとするものが、アーサーのいう「混乱」──自己組織化してパターンを形成しようとする複雑系の用、つまり創発──と同じものだったこと。だがたぶん、カウフマンが正反対の言葉を使っているのはそう驚くべきことではなかった。というのも、彼はまさに正反対の方向からその概念に到達していたからだ。
それぞれが取り上げる問題意識が異なったのは、アーサーは経済学という「秩序」から思考を出発し、カウフマンは生物学という「混乱」から思考を出発していたからだ。
経済学×生物学の思考の交流。
自分の本流から見れば“異質な”思考にすぐに会える、声がかけられる、共に過ごす時間がある……なにかを創造する時は、そういう環境をつくること。そして、双方に理解し歩み寄ろうとする意識があることがとても重要だと思う。
※人物参考情報|スチュアート・カウフマン[生物学者](wikipedia)
突きつめればすべて競合ではなく協力関係
一貫性など幻想である。複雑に入り組んだ世界には、体験が一貫性をもつという保証は少しもない。環境とのゲームを演じているエージェントにとって、競合に終わりはない。「それに、経済学や生物学でいろんな研究がおこなわれてきたにもかかわらず、われわれはいまだに競合の核心を引き出していない」と、ホランドはいう。そこには、われわれがようやく理解しはじめたばかりの豊かさがある。たとえば、競合は協力に対するひじょうに強力な動機を生み出すことがあり得るという、手品のような事実。複数のプレーヤーが相互支援のために、自発的に同盟や共生的関係をつくりあげていく。
そういうことは生物の世界から経済や政治の世界まで、あらゆる種類の複雑適応系で、そしてあらゆるレベルで、起こっている。
資本主義への理解や、この社会のすべてにつながる考え方。
この世界を(思考主体である私たちは人間なので、主には人間のために)良くしていこうという命題の前では、実は競合というものは存在しなくて、必ずなにかしらの協力関係が成り立つのではないか。
※人物参考情報|ジョン・H・ホランド[物理学者](wikipedia)
複雑は、複雑から生まれるわけではない
生きているシステムは、エンジニアが機械を設計するときのようにトップダウン方式でつくられるのではなく、つねに、ずっと単純なシステムの群れからボトムアップ方式で創発してきているらしい。
〜 中略 〜
もちろん、これはまさにジョン・ホランドをはじめとするサンタフェ研究所の面々が、複雑適応系一般に関して主張しようとしていたことだった。一つ違いがあるとすれば、それは、こうした個体群的構造を、ホランドはきわめて効率的な進化のためにシャッフルしなおすことのできる構成要素の集まりと捉えていたのに対し、ラングトンはそれを、生命のような豊かなダイナミクスを生み出すチャンスと捉えていたことだ。「コンピュータで複雑な物理系のシミュレーションをしていろいろ得るところがあったが、なかでも最も驚くべきは〈複雑な行動が必ずしも複雑なルーツから生まれるとはかぎらない〉ということだ」とラングトンは強調している。「実際、ひじょうに興味深く、びっくりするほど複雑な振る舞いが、きわめて単純な要素の集まりから創発してくることも可能である」
物理研究を取り巻く周辺技術や研究そのものの進化により、物質はほぼ極限まで構造を分解することができるようになった。ミクロに分解すると単純化される要素が、相互に関係し始めるととたんに驚くほど複雑な振る舞いを見せる。まったく別物に変身するように。
それは物理の世界だけでなく、他分野においても同様であるらしい。現代の研究者たちが挑戦している、複雑怪奇な問題がここにある。
※人物参考情報|クリストファー・ラングトン[情報科学者](wikipedia)
複雑系とは何なのか
生命や精神を可能にしている不思議な「何か」は秩序の力と無秩序の力とのある種のバランスがあるということだ。もっと正確にいえば、システムを、それがどのようにできているかではなく、それがどのように振る舞うかという観点から見なければいけないということだ。そうすれば、そこで目にするのは〈秩序〉と〈カオス〉という両極端だ、とラングトンはいう。
〜中略〜
しかし、まさにこの両極端のあいだ、「カオスの縁」と呼ばれるある種の抽象的な相転移が起きる場所では、〈複雑性〉、つまり構成要素が決してがんじがらめに固定されることがなく、それでいてばらばらの混乱状態におちいることも決してないようなシステムの振る舞いを目にすることもできるのである。
(カウフマンはこう考えた)
分子は集まって生きた細胞をつくるが、その細胞は、生きているからたぶんカオスの縁にあるにちがいない。そして、細胞は集まって生物をつくり、生物は集まってエコシステムをつくり、といったぐあいに考えていくと、それぞれの新しいレベルが同じ意味において──カオスの縁にきわめて近いところにあることによって──「生きている」と考えてもさしつかえなさそうだ。
だが、これがまさに問題だった。そう考えてさしつかえないにしろ、そうでないにしろ、そもそもそのような考えを検証するにはどうしたらよいのか? かつてラングトンは、コンピュータ・スクリーン上でまぎれもなく複雑な振る舞いを示すセル・オートマトンを観察することによって、相転移という認識にたどりついた。しかし、それを現実世界の経済やエコシステムでするとなると、その方法はまるでわからなかった。ウォール街の振る舞いを見て、何が単純で何が複雑かをどうやっていえばよいのだろう? グローバルな政治あるいはブラジルの熱帯多雨林がカオスの縁にあるというとき、それは正確には何を〈意味〉しているのだろう?
秩序とカオスのはざま、カオス縁にある状態。その複雑さこそが「この世にある証」そのものではないかという発想にカウフマンたちは行き着いた。
しかし思いつきを実証することこそが研究者の仕事であり、使命である。
「きっとそうである」と見えておりわかっているのに、その証明のアイディアを得られないという事態は、恐ろしく悶々とする状況だと想像する。
測定の可能性のアイディアとしてカウフマンが思いついた解決策は、変化の法則が「ベキ法則」に従っているか否かという尺度である。
密接に相互作用するエージェントの集合は、それがどんなものでも、ベキ法則に従った変化のなだれをともなう自己組織化臨界の状態に自己を導くことが予想されるのである。
あらゆる事象は、最大限の安定状態に自らを導く(カオスの縁)。
永遠の安定はなく、臨界が訪れると再び変化の状態が起き、しかし再び安定状態へ自ずと向かう。
「そう、これはわれわれ自身の物語なんだ。いまに至るまで、進化は最良の道を歩んできた。われわれは宇宙の申し子だ。といっても、べつに底抜けの楽天主義を説くつもりはない。なぜなら、それは多くの痛みをともなうものだからだ。絶滅もあれば破産もある。しかし、われわれがカオスの縁にいるのは、そこがおおむね、われわれみんながベストをつくせる場所だからだ」
複雑系の応用
複雑系を解き明かすことで、何ができるのか。
それは、人類の“宗教・倫理・道徳”といった一見科学とは何の関係もないような問題にも波及する。
疑う余地のない複雑性の成長が理解できたところで、それで完全に科学的な道徳ができるわけではない、とファーマーはいう。だが、もし新しい第二法則が、われわれがだれであってまた何であるのかを理解するための力となり、さらに、われわれが脳や社会構造を持つに至ったプロセスを理解するのに役立つとすれば、道徳について、いまよりずっと多くの知識が得られるかもしれない。
「宗教は道徳律を石板に書きつけることによって強制しようとする」とファーマーはいう。「われわれはいま、たいへんな問題を抱えている。なぜなら、従来の宗教を捨てた場合、これから先どんな道徳律に従ったらよいのかがわからないからだ。しかし、すべてを剥ぎとったときに見えてくるのは、宗教や倫理は、どうすればまともに機能する社会が成り立つように人間の振る舞いを構築することができるのかを教えているということだ。私の感じでは、道徳はすべてこのレベルで作用している。これはある種の進化のプロセスであって、そこでは、社会はたえず実験を繰り返し、その実験の成否によって、将来どんな文化思想や道徳律が広まっていくのかが決まってくる」。もしそうなら、共進化するシステムがどのようにカオスの緑へ動かされていくのかを厳密に説明する理論があれば、それによって、文化のダイナミクスや、社会が自由と管理のあいだの微妙に変化しつづけるバランスにどのようにして到達するかといった問題に関して、多くのことがわかるかもしれない、とファーマーはいう。
模索を繰り返しながら文化は成熟し安定するが、いずれ臨界点を迎えると変化し、新たな安定に向かって最適化の道を歩む。
※人物参考情報|J・ドイン・ファーマー[物理学者](wikipedia)
結果、見えてきたものは
そして話が創発におよび、だれかがこう尋ねた。創発にはいくつか〈種類〉があるのか?もしそうだとすれば、いくつの種類があるのか?ラングトンはいったん答えはじめたが、やがて言葉をとぎらせ、しまいには笑いだした。「賭けでもするしかなさそうだな」とラングトンはいった。「ぼくにはちょっと答えられない。創発、生命、適応、複雑性──こういった問題はすべて、われわれがまだ答えを模索している段階にあるんだ」
2024年の現在においても本質的な解決は「していない」と。ラングトンはそういうのではないかと思う。
経済学・物理学・生物学・情報科学が進歩していないということではない。それぞれの取り扱うデータは爆発的に今もなお増え続けているし、研究は日進月歩で進んでいる。
世界中がオンラインネットワークで結ばれ、物理的距離をものともしないリアルタイムの対話が可能になったことで、サンタフェ研究所で行われているような分野をまたいだ意見交換・調査・研究は90年代の比にならないほど活発化しているのだろう。
それでもなお、わからないことはわからないまま。
このような永遠にも思える謎が、研究者たちの情熱を常にカオスの縁に向かってかき立てているのかもしれない。どこにも永遠の安定は、ないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
