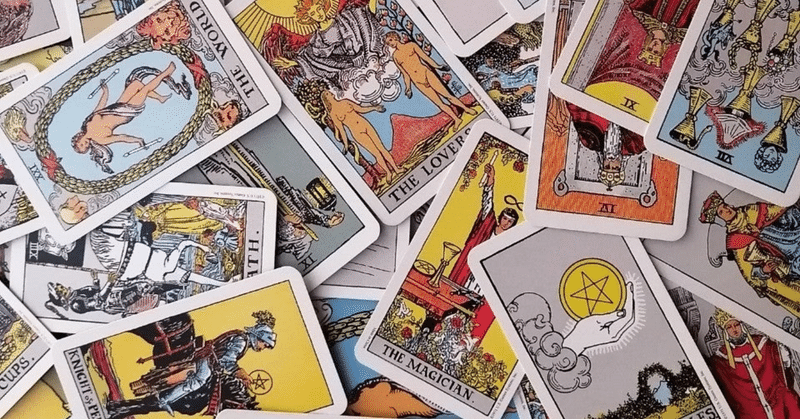
タロットは元々ゲーム用だったらしいので実際に遊んでみた
タロットでゲーム
タロットカードは元々ゲーム用カードだったらしい。本当だろうか?
「タロット」と聞けばまず占いが思い浮かぶし、検索すれば耽美で幻想的なスピリチュアル世界が手招きしている。
映画や物語に出てくるタロットならこんな感じ。馬車の荷台をキャンピングカーのように改造して、その中を妖しげな占い部屋にしたロマ民族の女性が「逆さの塔…これはよろしくない」などと言う。そして時には謎のお守りを高値で売りつけたりする。
しかし現実でも映画でも、タロットでゲームしている姿なんて見たことがない。
タロットカード自体は日本国内でも簡単に手に入る。本当にいろいろな種類があって、ハーレクイン本の表紙みたいな絵柄のもの、伝統的なもの、犬や猫のかわいいの。多種多彩だ。しかしゲーム用というのは見つけられなかった。
適当に選んで2種類買ってみた。もちろん占いをするためではない。
ゲームのためだ。

イメージと違ったタロットの歴史
気になったのでタロットの歴史を調べてみたら、占いアイテムとしての歴史が思いのほか浅くて驚いた。ゲームグッズとしての歴史の方がはるかに長い。
考古学的な証拠があって、学術的な根拠や裏付けがある範囲でわかっている最も古いタロットの情報は1400年ごろのもので、イタリアで使われていたもの。
最初期はもっぱらゲーム用カードとして貴族に使われていて、印刷技術も普及してなかったので超豪華な一点物で遊んでいたらしい。その後、印刷によって貴族以外の人々も入手できるようになり、イタリア戦争にカードを持って行った兵士たちによって近隣へ伝播していったという。
この頃のタロットはまったく占いに利用されていない。というかできない。中世のキリスト教勢力圏で占いなんかしたら異端審問だったはずだ。
それからかなり時代を隔てた1800年頃になってようやく神秘主義の流行に伴い、フランスのオカルティスト達が象徴絵柄などを追加したカードを整備して占いに使い始めた。東洋の神秘やオリエンタリズムが流行したのでそれに乗り、エジプトやインド、中国などの占術との繋がりを主張していたらしい。現在その手のあやしげな起源説は否定されている。
同時期にゲームとしてのタロットは最盛期を迎え、フランスを中心にヨーロッパ各地の一般市民にも広まっていった。
そして現在もヨーロッパの多くの地域で遊ばれ続けている。

トリックテイキングというゲームルールを知っていますか
じゃあその遊ばれていたゲームとはどんなゲームなのか。ここからが今回の話の本題だ。
まず「トリックテイキング」というカードゲームの定番ルール、というか一大ジャンルがあるのだが、ご存じだろうか。タロットはこのトリックテイキングというルールで遊ぶためにデザインされたものだ。
日本ではあまり馴染みがないかもしれないが、トリックテイキング(以下トリテと略す)のゲームはトランプに大量にあるし、ボードゲーム系のカードゲームとしても数えきれないほど売られている。
そうそう、昔のWindowsには「ハーツ」というトランプゲームが最初から入っていたので、遊んでいた人もいるかもしれない。あの「ハーツ」はトリテだ。
トリックテイキングの基本的なルール
トリックテイキングの基本的なルールは超簡単なので、聞いても何が面白いのか全然わからないくらいシンプルだ。
以下は本当に基本的なトリテのルール。知っている人は読み飛ばしてOK。
1、カードを配り切りでプレイヤー4人に配る。スタートプレイヤーが1枚カードを手札から場に出す。

2、時計回りに手札から1枚ずつ出すが、スタートプレイヤーが出したカードと同じスート(マークや色柄のこと。上の画像の場合はスペード)のカードでなければいけない。
もし、スタートプレイヤーが出したカードと同じスートのカードが1枚も手札になかったら、他のスートのカードをどれか選んで出す。

3、全員が場に1枚カードを出したら、場に出ているカードの中で最も大きい数字のカードを出したプレイヤーが場のカードをすべて引き取る。
このとき、スタートプレイヤーが出したカードと異なるスートのカードは最も小さい(弱い)数字として扱う。
※引き取ったカードは手札に加えず、自分の前に裏向きに置いておく。

4、場に出されたカード(トリック)を引きとった(テイキング)プレイヤーが次のスタートプレイヤーとなる。これを繰り返して最初に配られた手札がなくなったらゲーム終了。
以上が基本となるマストフォロー(スタートプレイヤーが出したスートと同じカードを出す)のトリックテイキング。場のカードをたくさん取った方が勝つルールもあれば、場のカードを取るとマイナスになるルールもある。絵札などの特定のカードに点数が付いていることもよくある。
実際の各種ゲームでは、上の超シンプルなルールに「切り札」というルールが頻繁に加わる。
切り札はスタートプレイヤーが出したカードのスートを持っていなかったときでも勝てるスートのカードで、最も大きい(強い)数字として扱う。切り札を複数のプレイヤーが同時に出した場合は切り札の数字の大小で決める。
トリテの基本ルールはこれだけ。あまりにも簡単すぎるので未経験だといったい何が面白いのかわからないだろう。当然この基本ルールだけで遊ぶわけではなく、それぞれのゲームの特徴的な追加ルールを楽しむ面もある。
スマホ用アプリにもあるトランプの「ハーツ」などを実際に数回やってみると、戦略性が高くて面白いことに気づくはずだ。シンプルなルールにもかかわらずトリテは高度な推理と記憶のゲームで、運の要素も大なり小なり含まれるのが面白さを深めていると思う。
タロットカードとトランプの違い
実際にゲームをする前にタロットカードの内容について。トランプと同じようなものなのだが、トランプにはない要素が3つほどある。
トランプと違うところ その1
ナイト(カバロとも言う)という絵札が追加される。強さ順で言うと
ジャック、ナイト(カバロ)、クイーン、キング、の順に強くなる。
トランプと違うところ その2
スートがスペードやハートではない。
タロットによって違うが、ライダー版だと杖、コイン、カップ、剣の4種類。絵柄が違うだけでトランプのスートと同じようなもの。

トランプと違うところ その3
22枚の大アルカナと呼ばれる特殊なカードがある。上記のトリテ基本ルールで書いた「切り札」専用のスートであり、それぞれ0番の「愚者」から21番の「世界」まで固有名がついている。ちなみに「世界」つまりザ・ワールドがタロット最強のカード。
タロットと言われて想像するのは一般的にはこれらだと思う。

この他はジョーカーがないくらいで、そんなに突拍子もないカードセットではない。とりあえずトランプに毛が生えた程度のものだと思って良い。
タロットゲーム「パパユー」のルール
それではいよいよ今回遊ぶタロットのゲーム「パパユー」のルールだ。難しくはない。
上記のトリテ基本ルールに追加ルールとして
・最初のスタートプレイヤーがそのラウンドに手札を何枚ずつ配り、何枚を隣の人に渡すか決めてから全員に配る。
例:「7枚配ります。左隣に2枚選んで渡してください」
・大アルカナの22枚は切り札として扱う。切り札同士が場に出たときの強さ順は、1番が最弱で21番が最強。
・大アルカナ0番の「愚者」だけ特別で、基本ルールを無視していつ出してもよく、常に負ける最弱カードとなる。場に出た最初のカードが愚者だった場合、次の手番のプレイヤーは何を出してもよく、それをラウンド最初の一枚とする。
数トリック行って手札がなくなったら次のラウンドへ。スタートプレイヤーが右隣へ移動し、場に残っている山札から何枚ずつ配って何枚を隣の人に渡すか決めて全員に配る。
山札がなくなったらゲーム終了。最終ラウンドに配った時に余ってしまった山札は、最後のトリックを取ったプレイヤーがすべて引き取る。
ゲーム終了したら得点計算を行い、マイナス点が最も少ないプレイヤーが勝利する。
・得点計算
引き取ったカードのうち、大アルカナの切り札カードはそれぞれの番号がマイナス点となる。たとえば21番の「世界」ならマイナス21点。
4種類のクイーンはそれぞれが各マイナス50点。
実際に遊んでみた
さて、ライダー版タロットで「パパユー」を遊んでみた。普段からボドゲで遊んでいる友人たち4人とプレイ。
最初の感想は「遊びにくい」だ。プレイ開始10秒で全員が声に出していた。
カードがトランプよりはるかに巨大で、しかも四隅に数字もスートも書いていない。
数字は上部中央にお気持ち程度にローマ数字で書いてある。そして剣のカードなのか杖のカードなのか、そのスートは絵を凝視して判断しなければいけない。

カードゲームを遊ぶときは手札を扇状に持つと思うのだが、そうやると自分の手札が全く認識できない。この時点で全員が頭を掻きむしってストレスを表明していた。「トランプで遊ばせろ」と。
それでも最低1ゲームは、ということでやり切った。非常に疲れた。途中から手で持たずにカードスタンドを使い始めたが、やっぱり何のカードを持っているのかさっぱりわからない。

下は得点計算の様子。タロットだと得点計算していても何か儀式めいたものを感じなくもない。実際の現場はローマ数字は計算しにくいと不満噴出だった。

プレイヤー達の遊んでみた感想は「二度とやりたくない」「中世だろうが欧州だろうが、こんなので遊んでるはずがない」と言うさんざんなもので、僕自身もユーザーインターフェースがひどすぎるという感想しか出てこなかった。ゲーム自体の評価などできないくらいデザインが悪い。
しかし、だ。今現在もヨーロッパ各地ではタロットカードでトリテを遊んでいる地域が多数あるのはどういうわけだ。今この瞬間だってタロットトリテで遊んでいる人たちが大勢いるはずだ。
そう、おそらく彼らはこのライダー版タロットで遊んでいないのだろう。間違いなくこのタロットはゲーム用ではない。
そして2年後…
実はここまでは2021年頃の体験談だ。その頃は日本国内でゲーム用タロットは非常に入手が困難で、ほぼ手に入らなかった。だからライダー版で遊んだのだが、なんと2023年現在、数種類のゲーム用タロットが容易に手に入るようになった。さっそく2種類買ってみた。

2年前に僕が「視認性が悪すぎてゲームには使えない」と判断したいわくつきのライダー版タロットをゲーム用にデザインしたという「Rider Waite Playing Card Deck」と、ロカ・タロット「The Tarot of LOKA」という最初からゲームをするためにデザインされたタロットの2種類を購入した。

ところがライダー版プレイングカードの方は開封してみたところ、タロットとして問題があることがわかった。
見慣れたライダー版タロットの絵柄が縮小されて、トランプで言うジャンボインデックスのような感じにデザインされている。とても遊びやすそうに見えたのだが…。

なんと4つのスートすべてのナイト(カバロ)が、ジョーカー扱いになっている。これではタロットのゲームで使えない。
タロットは絵札が J・N ( C )・Q・K の4枚あるはずで、それを前提で作られたゲームルールで遊ぶもの。そもそもタロットにジョーカーはないので、これでは普通のトランプになってしまっている。

ということでライダー版プレイングタロットは、相変わらずタロットのゲームを遊ぶには適していなかった。買った意味なし。
幸いなことにもう一つのゲーム用タロット、ロカタロットの方は問題なくタロットで、見た目もわかりやすい。
こちらはナイトではなくカバロ表記でスートも杖やカップではないが、とても分かりやすい4色の4スートだった。これはよさそう。

パパユーふたたび
このゲーム用タロットでリベンジしてみよう。
2年前と同じメンツを集め、また4人でタロットをやろうと提案したら全員に激しく拒絶された。トラウマになっているらしい。まぁまぁとなだめる。
今回は違うから。ゲーム用のだから。パパユーやろう。
「うわあ」「ぱぱゆう!2年ぶりに聞いた!」「やりたくねえ」
一回だけ一回だけ。
ということで「パパユー」をロカタロットで遊んでみた。
配られた手札を見るだけでわかる遊びやすさよ。カードが遊びやすくデザインされているだけでこんなに違うとは思わなかった。以前遊んだ時の10倍くらい面白く感じる気がする。
ルール自体、トランプトリテの「ハーツ」の亜流くらいに思っていたが、これは切り札の多さがスパイスになってまるで別物だった。また、ゲーム終了まで同じ山札をシャッフルなしで配り続けるので、後半になるとまだ場に出てないカードは何かが重要になってくる。
数分で「これ面白いな」と誰かが口にした。

カードの枚数がトランプより多いので、カウントはあきらめようかと思っていた。ところが遊んでみたらトランプと違って切り札スートに固有名があるので、結構簡単に記憶できる。
これが数字だけのトランプとの大きな違いで、(戦車カードはさっき見たな)とか(塔カードはまだ見てないな)という感じで簡単に覚えられる。
これは慣れれば慣れるほど大アルカナ切り札の固有名と数字まで把握して面白くなっていくだろうと思った。
やっとタロットでトリテをする面白さと意味がわかってきた。本当にトリテ用カードなんだ。
プレイヤー達の感想は、「普通に楽しい」「前と同じゲームやってる気がしなかった」「もう一回やってもいい」と言う感じで、前回の忌々しい記憶を払拭できたようだ。

ゲーム用タロットで遊んでみた結果
タロットで遊ぶゲームは結局のところ面白いのか。
結論から言うととても面白い。ただしゲーム用のタロットカードを使ってはじめて面白さがわかる。
切り札スートが22枚も完全に別枠で用意されていること、それらに固有名が付いていること、個人的にはこれが大きかった。
固有名詞による記憶の容易さがプレイしやすさにつながるので、タロットのトリテに複雑そうなルールのゲームが多い理由もわかる気がする。慣れたらちょっと複雑なぐらいでちょうど面白いのかもしれない。
ちなみにタロットで遊べるゲームは大量にあり、その中でもパパユーはかなり簡単なゲームだ。難しいものになると正体隠匿のチーム戦だったりする。トランプなどの正体隠匿系トリテは慣れると超面白いので、タロットでもそのうち遊んでみようと思っている。

まとめ
もしあなたがタロットで遊びたいならゲーム用タロットを買おう。それ以外の占い用タロットでは楽しく遊べない。
それからカードそのものの話になるが、ライダー版プレイングタロットもロカ・プレイングタロットも、残念ながらカードの質としてはバイシクルなどの一般的なトランプカードに遠く及ばない。
今回僕が購入したタロットはどれも単につるつるした厚紙なので、シャッフルしにくく長持ちもしなさそうだ。それでもトランプにはない魅力があるので、一度遊んでみてほしい。
ただし、何度も言うがゲーム用のタロットカードでなければ悲惨なことになる。また、ライダー版はゲーム用であってもおすすめできない。タロットで遊ぼうと思ったならロカ・ゲームタロットのようなタイプを探してみてほしい。
このテキストは筆者のブログの記事を加筆再構成したものです。内容に関しては筆者の見解であり、絶対的なものではありません。加筆するにあたって「David Sidney Parlett. "The Oxford Guide to Card Games" Oxford University Press, 1990.」などを参考文献にしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
