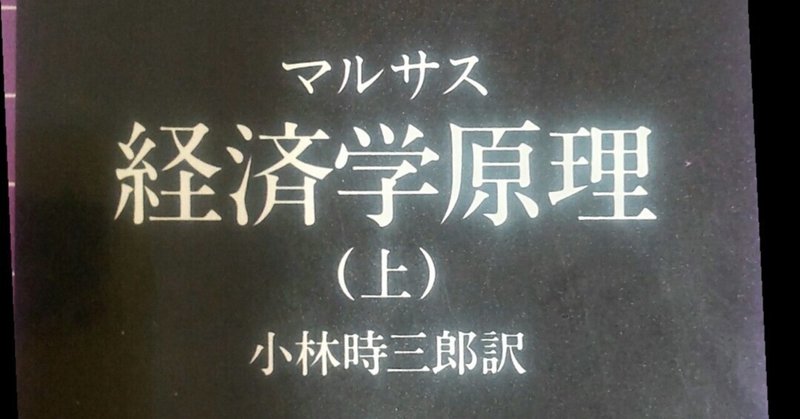
労働価値説と交換価値の一尺度③〜経済学原理第二章第四節〜
この節での138ページにとても興味深い記述がある。引用すると以下の通りである。「通商が少しでもおこなわれていれば、外国貨物(foreign commodities)は、それに充用される労働および資本の分量によって規制されるものではないことが認められているが、その外国貨物は多くの製造品の原料を形成しているのである」(小林時三郎、1968年1月16日、マルサス経済学原理上、P138)
おそらく「外国貨物は〜」からの綴りは正確には、「外国貨物の価格は〜」という意味なのだと思う。すると、「生産される際に必要な、労働と資本の分量に規制されない価格になってしまう貨物(商品)」とはなにかという話になる。世の中に数多く存在している商品の価格は、これらの分量に規制されやすい場合とそうでない場合がある。しかし、ここで「規制」という言葉が使われているので、その意味は割と分かりにくいと思う。これはようするに、商品を作るときにかかった費用(労働と資本「道具など」)の分量によって、価格の範囲が制限されるということだろう。現在でも、原材料や人件費等の高騰で、生産費が上がり商品が高値になること(低価格にできる範囲が制限されること)はよくある。
問題はマルサスが、「外国の貨物は、それらの分量で規制されるものではないことが認められている」と述べていることだ。さすがに全く規制されていなかったとは考え難い。しかし当時の英国が、自国と比較したら規制されていないように見えるほど、相手国から安く買い叩いていたというなら確かに説得力がある。
故宇沢弘文先生は、「当時のイギリスは自国の海軍力を用いた海賊的資本主義だった」という趣旨の主張もしていたが、マルサスも内心はそう思っていたのかもしれない。今回の記事はある意味マルクス主義的な意見を述べることになってしまうが、古典派経済学の研究においては、そのような分析を避けるのは難しいのだともいえる。マルサスは文明諸国の農作物(食用植物)の原価は、地代の割合は極めて少ないのが、間違いなく真実だと述べている。しかしこれは言い換えれば、文明の進んでいない国の場合は、その地代の割合はそれなりに多くあることになる。文明が進むに連れて、地力の限界を補うための資本と労働が増加する。農地の優劣を補う技術の発展と、それに必要な投資が実現したのであれば、ごく自然の成り行きといえる。この現象は当時はやはりイギリスが顕著で、ドイツ出身のマルクスの見解は、「ポメラニア(ドイツ北東部からポーランド北西部にかけて広がる地域)の地主なら、イギリスの経済学者が、農業に対する資本不足を全く懸念しないことを不思議に思う。イギリス人は農業での資本不足で困ることはなくても、土地不足で困っている」というもので、大英帝国の資本力は19世紀の西欧列強のなかでも、非常に抜きん出ていたことが伺える。
