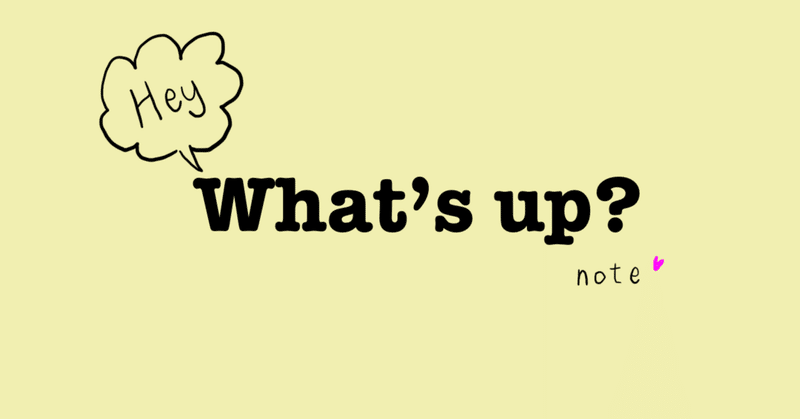
Differentiation
全員で同じことを同じペースでやっていく。
それって美しいし、差を生み出さないし、平和かもしれない。
一方で、主体的、対話的で深い学びを目指していく。そのために、個別最適な学びや協働的な学びに焦点が当てられてきている。
個別最適な学びの有用性を感じる声がある中、疑問を感じている声もちょこちょこ…?
今、思っていることを書いてみようと思います。
Differentiationがカギ
タイトルにもある「Differentiation」。聞いたことありますか?
辞書とかで調べてみると、多分「差別化」とかって出てくるのかな。
この意味だけを見ると、「え、やばいやつなんじゃ?」って思うかもしれない。僕も最初はしっくり来てなかった。
けど、この単語を教育の文脈で使うと、「個に応じた支援をしましょうね。」ってことなんだよね。
…あれ?「個別最適な学び」じゃん?
それぞれの個に合うよう、学習をデザインしていく。
それぞれが最大限の力を発揮できるような環境、学習の流れを作ることができたら理想なんだよね(そこが一番難しいところなんだけど…)。
個別であって、別ではない
あくまで推測だけど、疑問を感じている声が出るのは「個別」という言葉が原因なのかな…と思うわけなんです。
「個別」と聞くと、それぞれが1人で学習を進めていくようなイメージをもつ人がいるのではないかと思うわけなんです。
でも、個別最適は「1人で進めなさい」ってことではないはず。
友達と話しながら進めたい。
先生に隣にいてもらって進めたい。
文章じゃなくて、絵でまとめたい。
スライドにまとめたい。
とか、一番快適な学習方法を学習者が選べるということなんじゃないかと思うんです。
だから、
みんな一緒じゃなくていい。
約束の中で、自分で考えて進める。
自分の学習に責任を持つ。
実現させるための計画
子どもたちが、自分の学習に責任を持てるようにするために計画を立てるとどうだろう?
全体指導をして、方向性を確認したら、それぞれのペースで進めるとかね。
レベルごとでワークシートを分けてみるとかね。
そして、振り返りを充実させる。対話の時間も必ずとる。教員はひたすら様子を見て回る。
それが保証されていれば、少しは心配なことはなくなるんじゃないかな?
何を大切にするか
まあ、いろいろ書いたけど、結局は授業者が何を大切にしたいか。
いろんな教授法があって、正しい方法なんてのはない。どう組み合わせて使っていくか。カードゲームみたいな感じ。
教授法に使われない。うまく活用していきたいね。
Please enjoy my other post when you have the time🥰
カードゲームって言ったけど、頭の中はこんな感じ↓
俺は手札から魔法カード、自由進度学習を発動するぜ!このターン、子どもたちは自分のペースで学習を進められる。
そして、トラップカード、突然の共有タイム!子どもたちはここまで進めた学習を隣の子に説明しなければならない!
最後に、次の学習計画ワークシートを召喚して、ターンエンドだ!
こんなイメージ笑
そんじゃ!Have a good one😘
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
