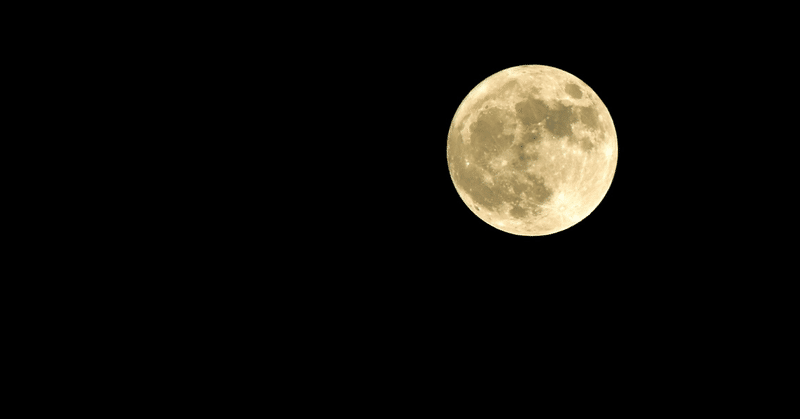
800年前、鴨長明が「方丈記」に書いたM7.4の地震。読んでおきたい「地震の段」を、わかりやすく解説するよ。【現役ライターの古典授業05】
最近、日本のあちこちで地震が起きています。
先日も私が住んでいる宮崎で、震度5弱の比較的大きな地震がありました。
(あの緊急地震速報の音、何度聞いても恐ろしいですね・・・)
幸いにも被害はありませんでしたが、いつ何時、地震がくるかわかりません。
特に、起きる起きると言って騒がれているのが「南海トラフ巨大地震」。
その被害想定は220兆円を超えるとも言われています。
その地震が、一体どれくらいの規模なのか?
どんな被害が出て、どれくらい揺れて、街はどうなるのか?
それらは今現在、最先端の研究と情報をもって予測されていますが、実は、800年以上前の「方丈記」に、地震に関する記述があるのです。
これは琵琶湖の堅田断層の説もありますが、南海トラフ巨大地震であるとの説もあります。
いずれにせよ、当時かなり大規模な地震が起きたことは、方丈記以外の文献を確認する中でも明らかです。
その箇所をちょうど授業でも取り上げたので、少し解説してみたいと思います。
◆本日の授業:800年前の大地震はどれほどの規模?鴨長明「方丈記」の“大地震”の記述を探る!
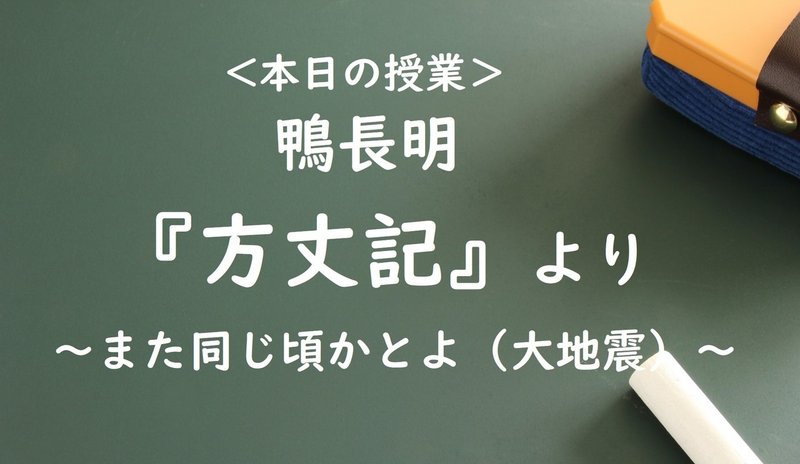
昨日地震あったなぁ。みんな大丈夫やったか?
今やってる「方丈記」やねんけどな。実は教科書には載ってへんけど、地震に関する記述があんねん。今日はそこやるわ。
え?教科書の続き? そんなん次やればええねん! やるべきときに、学ぶべきものを学ぶんや! はい、資料後ろ回してー。
んじゃ、見てみよか。
また同じころとかよ、おびただしくおおなゐ(大地震)ふること侍りき。
はい。この「同じころ」ってのはな、この前の段で飢饉の話をしてるんや。
西暦1185年頃やと言われてる。文治地震、とも呼ばれてるな。
地震のことは昔「なゐふる」って言ったんやな。「なゐ」が「地面、地盤」っていう意味で、そこが「ふるえる」から「なゐふる=地震」ってことや。
それを「おおなゐ」って言うくらいやから、規模が大きかったんやろな。
その様子を見てみよか。
そのさま世の常ならず、山は崩れて河を埋み、海は傾きて陸地をひたせり。
土裂けて水湧き出で、巌(いわお)割れて谷にまろび入る。
なぎさ漕ぐ船は波にただよひ、道行く馬は足の立ち処を惑はす。
どや。案外、何言ってんのか理解しやすいんやないかな。
まず「山は崩れて河を埋み」って、どう言うことや?何が起こってる?
生徒A:山崩れ・・・土砂崩れ。
正解。土砂崩れ。まずは土砂災害や。
「河を埋み」ってことやから、地震が起きて、崩れた土砂が川に入り込んだってことやな。
次、「海は傾きて陸地をひたせり」ってのは?
生徒B:津波。
せや。津波。
普段は穏やかな水平線が、傾くくらいの大きな波が陸に押し寄せたってことや。浸水被害が出たんやな。
そのあとに「なぎさ漕ぐ船は波にただよひ」ともあるしな、この時の地震は、津波を併発した地震と読み取ることもできる。
てことは、もしこれが事実やとすればな。
このとき起きた地震は、直下型やのうて、南海トラフみたいな海洋に震源がある地震の可能性もあるわけや。
実際に周期的に見ても、南海トラフの可能性はあるみたいやな。琵琶湖関連の説もあるし、確定的なことは言えんけど、この方丈記からは津波の様子が読み取れる。
さらに「土裂けて水湧き出で」。地割れやな。水が湧くから、今で言うなら液状化現象。
「巌割れて谷にまろび入る」。これもさっきの土砂崩れやな。でかい岩が転がってくるんやから、それで被害も出たかもしれん。
既にこれだけの災害が書かれてる。
んじゃ、街の状況はどうやったんやろ。
都のほとりには、在々所々堂舎塔廟ひとつとして全からず、或は崩れ或は倒れぬ。塵灰たちのぼりて、盛りなる煙のごとし。
「ひとつとして全からず」っていうんは、「ひとつとして無事なものはなかった」ってことや。崩れるか、倒れるか。砂煙が立つぐらいの建物倒壊がおこったんや。
まぁ昔やから耐震性工事もへったくれもない。けど、「堂舎塔廟」ってことやから、割と作りがしっかりしてるはずのお寺さんが崩れたってことを示してる。相当の揺れやったんたろな。
地の動き、家の破るる音、雷に異ならず。
家の内にをれば忽にひしげなんとす。走り出づれば、地割れ裂く。
羽なければ、空をも飛ぶべからず。竜ならばや雲にも乗らむ。
「地面の揺れる様子や、家が壊れる音は、まるで雷のようだ」って言ってるな。
家の中におったら崩れてまう。けど、外に出たら地割れや。
人間は羽なんかないからな、飛んで逃げることもできへん。竜なら雲にまで上って逃げるのになぁって言ってる。
けど、ホンマにそうやと思うわ。
人間、最後は足なんや。車とか自転車とか、そんなんあっても最終的には自分の足で、自分の力で逃げなあかん。
飛んで逃げたいけど、そんなん言っても始まらん。自力で身の安全を確保して、生きなあかんねん。
そこに、この一文が続くんや。
恐れのなかに恐るべかりけるはただ地震(ない)なりけりとこそ覚え侍りしか。
これなー。
ハッとしたわ。
「恐れるものは世にたくさんあるけれど、中でも恐れるべきは地震である」って、800年以上前の鴨長明が実感を込めて言ってるんや。
あ、ちなみに「なりけり」の「けり」は詠嘆な。地の文とか会話文に限らず、「〜なりけり」って表現がきたらほぼ詠嘆やと思っていい。
津波に土砂崩れに建物倒壊に、災害という災害が一気に起こるんが地震の恐ろしさや。
現代やと、ここに水道ガス電気のライフラインが断絶するとか、原発がどうとか、不安要素がてんこ盛りになる。
地球は生きてるからな。地震は起こるねん。
地球さんだってくしゃみもするし、寝返りも打ちたくなる。
人間含めて地球さんに住まわせてもらってる以上、地震起こるのはしゃーないから、起きたときにどう対処して、どう生きるかが大事やな。
この段はこれで終わりやないで。
次も結構大事なところや。
かくおびただしくふることは、しばしにて止みにしかども、その名残しばしは絶えず、世の常驚くほどの地震、二三十度ふらぬ日はなし。
十日二十日過ぎにしかば、やうやう間遠になりて、或は四五度、二三度、もしは一日まぜ、二三日に一度など、おほかたその名残三月ばかりや侍りけむ。
これ、何のことか分かるか?
二三十度、十日二十日、四五度・・・とか色々書いてあるけど。
生徒C:ええと・・・地震がその後も、何回か続いたってこと。
おっ!つまり?
生徒C:余震?
そう! 余震や。鴨長明、余震にまで触れてんねん。
「かくおびただしくふることは、しばしにて止みにしかども」てことやから「最初の震度7ぐらいの地震は、しばらくして止んだ」んや。
けど、「その名残しばしは絶えず、世の常驚くほどの地震、二三十度ふらぬ日はなし」。
世の常驚く、つまり「普段ならびっくりするぐらいの、震度3~4ぐらいの地震が、2~30回、毎日のようにあった」んや。しかも10日間ぐらい続いたらしい。
それが半月もすると、4・5回に減って、1日おきになって、3日おきになって・・・って、その収まり具合もよく分かる。
これが「三月ばかりや侍りけむ」、「三ヶ月ぐらい余震が続いたでしょうか」って言ってるな。この「けむ」は過去推量の助動詞やな。
やから、大規模な地震、それこそ南海トラフレベルの地震の場合、「余震はしばらくは毎日のようにあり、収まるまで三ヶ月はかかる」ってことが見えてくる。
前の熊本地震のときもそうやけど、本震やと思ったら前震で、最初は大丈夫やった建物が、二回目の揺れで崩れたって話が幾つもあった。
一回の揺れで安心してたらあかん。揺れが何ヶ月も続くと思ってなあかんのやな。東日本大震災のときも、しばらくはずっと震度3レベルの揺れはあったし、別段大げさな話やないと思う。
そして、この段の最後や。
すなはちは人みなあぢきなき事を述べて、いささか心の濁りもうすらぐと見えしかど、月日かさなり、年経にし後は、ことばにかけて言ひ出づる人だになし。
「すなはちは」っていうんは、直訳すると「すぐには」。つまり「地震直後は」ってことや。
「あぢきなき事」は「無力だ、甲斐がない」っていう意味やから、この文を意訳するとな。
「地震直後は皆『地震怖いなぁ、人間って無力や』って言い合って、ちょっとは人間的にマシになったかと思うけど、月日が経てば地震のことを口に出す人さえいなくなる」
って意味になる。
すげー。
いやホンマこれ、仰る通りやと思わへん?
だって地震直後の世の中って、自然の驚異にさらされて「地震怖い、人間ってマジ無力」って感じるんやけど、時間が経つと忘れてまうやん。
ほんまに人間て、忘れっぽい生き物や。
口じゃ忘れるから、書いて残す。
過去が未来に残したもの、それが古典や。
けど東日本大震災のとき、過去に「津波がくるからここから下には家を建てるな」っていう言い伝えがあって、石碑まで立てたけど、そんなん忘れて崖の下に家建ててたって話や。
どんだけ過去からの警告があっても、今を生きる人に聞く耳がなかったら、何の意味もない。
地震予知、緊急警報とか、地震の研究はどんどん発達してる。
でも、誰でもできることは、過去に学ぶことや。
古典を学べば、未来がわかる。
そのための、自分の足で、自分の力で過去の人の言葉を聞くためのツールが古文単語であって助動詞なんや。
何も受験勉強のためだけやないんやで。
地震は起きる。津波は起きる。山は崩れる。建物は倒れる。
地面が割れて、水は吹き出すし、三ヶ月も余震が続く。
それでも生きなあかん。
そうやって人間は、過去から未来に生きてきたんやから。
古典を知って、未来に託した想いを知って、先人の言葉に、耳を傾けられる人であってな。
(キーンコーンカーンコーン)
もう時間か。
こうやって見ると、鴨長明「方丈記」も面白いよなぁ。
無情無情ああ無情、って言ってる本やと思ってたらつまらんよ。
他にも色んな段があるし、また機会あれば話すわ。
いっぱいいっぱい、勉強になるで。
「おもしろかった」「役に立った」など、ちょっとでも思っていただけたらハートをお願いします(励みになります!)。コメント・サポートもお待ちしております。
