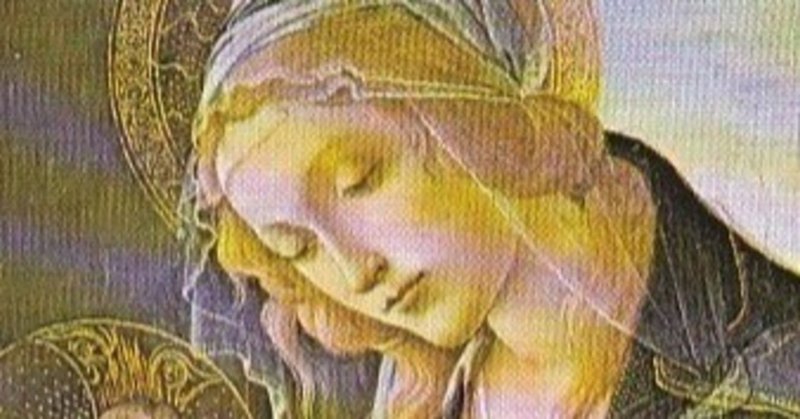
霧の宴 ミラノ Ⅲ クレリア夫人 副題( Stabat Mater )

「確かに、テーマがドラマティックであることから<スタバト マーテル>は、現代人が聴いても作品として形が美しく整っていて、分かりやすいかもしれません。<サルヴェ レジーナ >はコンサートで演奏するのには、ちょっと中途半端な感じだし、、、<サルモ 126>は、わたしのテクニックでは、無理でしょう、、、ということで、一番無理のないのは、やはり
<スタバト マーテル>に落ち着くと思うのですが、、、」
友人の作曲家は、何時になくしおらしいマリアムを、質問に答えられなくてまごついている生徒を教壇の上から意地悪く眺めている教師の様に、暫らく無言で薄笑いを浮かべて見ていたが、
「だから言っただろ、そんなところだ、と。それにしても、もっともっと歌いこなさなければならないと思うよ」と付け加えた。
(いつも一言多い、そんなことはわたし自身が最も分かっている、今更貴方に云われるまでもない)とマリアムは心の中で気色ばんだ。
何故かこの友人と話す度に、彼女の中に反発心が湧く。おそらく彼の少々皮肉な態度を伴った、正論でありながら、どこか人を見下すような皮肉な言い回しによるのであろう。
友人の家を出て表通りを歩きながら(フン、人を馬鹿にして、そりゃあ,わたしはアマチュアですよ、でも見ていてい御覧なさい、今に吃驚させてあげるから、、、)と息巻いた。
演奏会でA.ヴィヴァルディの<スタバト マーテル>を歌う。なんと大それたことを、とマリアムは自分の身の程知らずともいえる挑戦に恐れを感じた。果たして、自分の未熟さゆえにA.ヴィヴァルディの美しさを損なうことはないだろうか?しかし、他ならぬクレリア夫人の為なのだから、と自分を納得させようと努力した。そして、あの美しい公爵夫人との最初の出会いを思い出し、それがポルディ ペッツォーリ美術館であったこと、S.ボッティチェッリの死せるイエズス クリストを膝に失神状態の聖母マリアの<嘆き>の前であったことに、見えない糸に操られている、ある運命を感ずるのであった。
その夜、マリアムはクレリア夫人に電話をした。
「私共の家で美しい音楽が聴けますのも、貴女がドクトルのような方をご紹介くださったお陰です。思いがけず長年の願いがかなって私、本当に感謝致しております。公爵も、あまり口には出しませんが、内心ではとても喜んでいるようです。貴女が彼のために動物を歌って下さるというので、心待ちにしておりますのよ」
「公爵様のお気に召す動物たちかどうかわかりませんが、、、、空を飛ぶ蛇の歌がありませんので、、、」と、少しおどけて云うと、受話器の向こう側から華やいだ夫人の笑い声が聞こえてき
「まあ、そのような歌がありましたら、彼は音楽通になってしまうかも知れませんわ」
「奥様、お好きなA.ヴィヴァルディを歌わせていただく決心を、今日致しました。<スタバト マーテル>です。
「あゝ、何とご親切に!貴女がとてもお忙しくしていらっしゃるのを存知ておりますので、私は、無理なお願いは出来ないと思っておりましたの。そうしましたら、あのお優しいドクトルが、貴女がヴィヴァルディをお勉強なさっているのをお聞きになったことがおありで、とても素晴らしかったから、ご自分が貴女にリクエストして下さるおっしゃったのです。でも、ご迷惑ではないでしょうか?」
「いいえ、そのような意味では少しも迷惑ではありませんが、ご存知のようにわたしは専門家ではありませんから、奥様にご満足いただけるような演奏が出来ますか、とても心許ないのです。A.ヴィヴァルディのエレガントな美しさをお伝えできるようにしなければ、と心しております。
奥様、憶えていらっしゃいますか?初めて奥様にお目にかかりましたのは、S.ボッティチェッリの<嘆き>の前でした」
「ええ、勿論よく憶えておりますわ。ポルディ ペッツオーリ美術館で、私の大好きなあの絵を、身動きもなさらないでじっと食入るように長いこと見詰めていらっしゃいました。そのお姿がとても印象的でした。それで選んでくださったのでしょうか<スタバト マーテル>を? 何とご親切に、、」
確かに、<嘆き>のテーマは、イエズスの死に直面した聖母マリアの究極の苦悩を描いている場面で、数々の芸術家が絵画に、彫刻に、そして音楽に創作しているが、このテーマの最も有名な作品はヴァティカンのサン ピエトロ大聖堂にあるミケランジェロ ボナッロティ(二十代半ばの作品)の
<ピエタ>であろう。マリアムはしかし、小品ながらジョヴァンニ ベッリー二の<ピエタ>にも心打たれる。茨を冠った死せるイエズスの顔をそっと覗き込む聖母マリアの表情があまりにもリアルで、思わず涙ぐんでしまう。
S.ボッテイチェッリの<嘆き>とA.ヴィヴァルディの<スタバト マーテル>も、同じ劇的な場面をテーマとしていることから、クレリア夫人は、マリアムの心遣いから選曲されたものであろうと想像したのであるが、実は自分の声楽上のテクニックの問題で、行き掛かり上そうなった、ということをマリアムは言いそびれてしまった。クレリア夫人が、あまりにも幸せそうであったからである。
ミラノⅣ 宴 につづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
