
東大の肩書きを使えるうちに使っておこう
下心丸出しですみません。とうとう東京大学の大学院を修了し、長らく通った東京大学ともお別れしました。といっても学生証を返却し忘れたので、おそらくもう一度行かないといけないのですが。
社会人になる前って、「学生のうちにしかできないことをやれ」みたいな言葉をよく聞くのですが、正直学生のうちにしかできないことってそんなになくないか?と思っています。例えば長期の旅行は休みを取りづらくて行けないと言っても、極論仕事を放り出しさえすれば行けるわけですし。馬鹿騒ぎするみたいなのも、恥を捨てれば社会人でもできるし、というか別に馬鹿騒ぎ自体は学生という肩書きを持ってしても恥ずかしいことに変わりはないわけですし(こんな言い方をすると誤解されそうですが、筆者は馬鹿騒ぎするの大好き)。
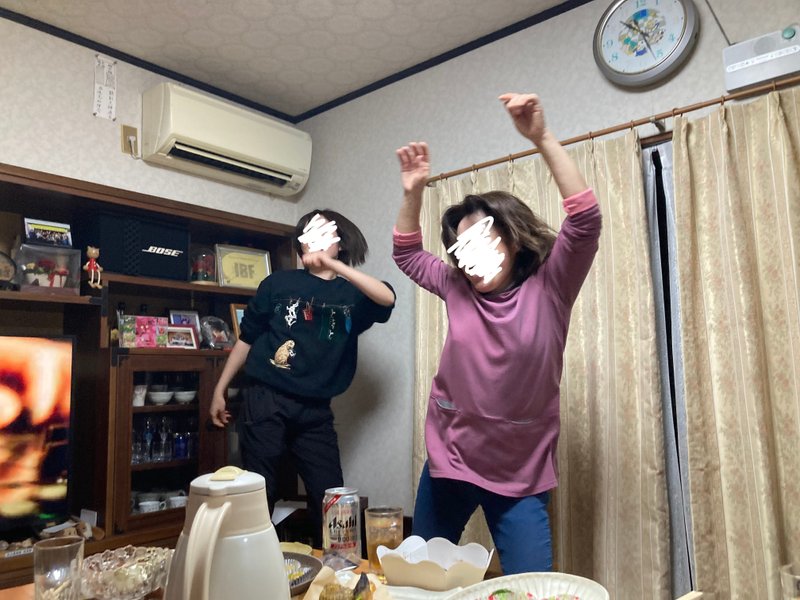
じゃあ学生にしかできないことはなにかと言えば、学生証を振りかざして学割の恩恵に預かること・〇〇大学の学生という肩書きを振りかざすこと。
社会人になると、〇〇大学卒という表記になってしまい、これを強調すると過去の栄光に浸っている感が否めない(個人の意見です)。
ということで、修了はしたものの、まだぎりぎり会社名と役職より学歴が先行する今、東大生という肩書きを使っておこうではないか。ということで、東大という言葉を無駄に繰り返しながら、東大生活6年間で学んだことを振り返っていきます。自己啓発本みたいなことを書いているので、好きじゃない人は読まないでちょ。
女子校12年からの男子校
noteを初めて書いたとき、たしか見出しのようなタイトルだった気がします。筆者はタイトル通り12年間女子校に通った後、男女比9:1の理科一類中国語クラスに進学しました。内容的には、女子校で純粋培養された結果、男子からの見え方を全く考えない人間が生まれたよ、的な話。
根っこの性質は今も変わっていませんが、少しはお上品な人間になったかと思います。
鼻が折れると痛いて
もうすぐまた東大にも新しい1年生が入ってくるということで、読まれるかもわからないけれど、結構大事だと思っていることを少しだけ真面目に書いておきます。
おそらく東大に入る人々、特に現役の人々は、小さい頃から優等生(Adoではない)だったり、勉強に苦労したことがなかったりという人が多いと思います。
ただ、自分の自信になるものが成績しかないとか、やりたいことがわからないけれど流されて大学受験をした、みたいな人(筆者)は、そこそこの割合で入学後に一度はメンタルをやられると思います。
というのも、東大はやっぱり今までの人生で出会ってこなかった人たちが本当にウジャウジャいて、〇〇オリンピック出ましたって自己紹介で言う人が片手には収まらなかったり(筆者は入学後初めてスポーツのオリンピック以外のオリンピックがあることを知り、完全になにそれおいしいの?状態になった)、同い年のはずなのに既に社会人レベルの専門スキルを持っている人がいたりと、え?どうやってこの人達と戦えばいいの?となるわけです。別に戦わなくてもいいんですが。
実際に授業が始まると、自分が理解できない内容をみんなすんなり理解できていたり、そもそも知ってたみたいな人もいたり、これで周りが単位を取れているのに自分だけ落単なんてしようものなら、あれれれれ???って感じになります。
筆者は実際、高校までは普通に勉強して学年10位以内はキープできるくらいのレベルだったのですが(この後の話のための前提共有)、東大に入ってまず勉強面でだいぶ挫折し、必修科目の単位を落としました。じゃあサークル活動でも頑張ろうかなと思ったら、みんなどこかの企業でインターンをしていて、同期のはずなのに既に自分より何歩も先を行っている状態。
ということで東大合格で伸びた鼻は折れるどころか、もう治らないので手術で切除するしかありませんという感じになり、夏休みはサークルにも顔を出さず、とりあえず遊んでいました。
上を見過ぎると首が痛いて
とにかく何が言いたいかというと、精神衛生を保つことを最優先にするならば、まず器用貧乏でもいいからこんなこともあんなこともできる、みたいな状態を目指す方がいいんじゃないかということ。
私が大好きなハイキューのシーンのセリフに
「絶対に”1番”になんかなれない どこかで負ける それをわかってるのに皆どんな原動力で動いてんだよ!?」
「そんなモンッ プライド以外に 何が要るんだ!!!」
というのがあります。これは、2つ目のセリフが熱くてかっこいいというのでよく取り上げられますが、個人的には1つ目のセリフに物凄く共感するからこそ、原動力はプライドだけでもいいんだ、と安心できるのです。
そして筆者個人の意見を述べると、なにかひとつの物事で高みを目指すというのは、もちろんかっこいいことだし素敵なことなのですが、同時に1番になれないというのも紛れもない事実で、人と比べて負けて挫折するくらいなら、初めから総合力勝負にすればいいのではないかと思うのです(この考え方をしてとりあえず色んなことに手を出していた結果、こんな感じの人間になった)。
もしそれでも周りの人と比べて心が壊れそうなときは、自分は視点をめちゃめちゃ広げて、「自分が比較して落ち込んでいるこの人だって、世界レベルどころか市区町村レベルで見たって全く名前を知られていないし、上には果てしなく上がいるんだから比べたところできりがないな、やーめよ」というかなり性格の悪いことを考えて心を落ち着かせています。
悩んでいるとき、ものすごく極端なところまでネガティブな方に考えると、逆にくだらなく思えてくるというのを、ちょっとしたライフハックとして置いておきます。
建築学科こと文理芸の狭間学科
さて、男子校から建築学科に進むと、学科最初の授業で後ろの男子がファッションブランドの話をしているのが聞こえ、即座に振り向いて「そのブランド!好きなの!?」と叫びたくなるくらいには嬉しかったのを覚えています。
理科一類は工学系か理学系に進む人がほとんどで、ファッションに関心のない人もかなり多かった中、建築学科という、文系出身者も割と多く、かつ理系の中でもかなり芸術系に近いなかなか特殊な学科に進んだ結果、「1, 2年の頃どこにいたん?」みたいなオシャレな人や垢抜けた人だらけで感動したのを覚えています。
100%を目指して終わらないより80%で終わらせる
建築学科といえば、徹夜で製図室にこもって模型や図面を製作している…というイメージがあるのですが、意外と実態としてはそうでもない気がしています。またそれをやる人が偉くて必ず評価されるというわけでもありません。
これはかなりよく話題にあがっていたのですが、100%を目指して終わらないより80%で終わらせることのほうが社会では重要だということです。筆者は後者タイプで、「最後までこだわり抜ける人強い、妥協しちゃうオレ弱い…」みたいな気持ちだったのですが、何回か設計課題をこなして感じたり、仕事をしたことがある人と話したりしてわかったのは、結局締め切りに間に合って完成していない時点で評価はしてもらえないということ。
といっても、設計課題では頑張ったね、という話にはなるのですが、中間講評でかなり褒められていた人が結局失速して完成しなくて教授に残念がられていたり、逆に途中までそこそこの評価だった人が最終講評できちんと完成させて評価されるということはよくありました。
留学生と話したときも、仕事ではスピードが遅い成績Aの人より、サクッとCを出せる人間が必要とされているんだみたいな話になりました。もちろん業界によっても異なりますし、スピーディにAを出せたらそれに越したことはないのですが、期限を守って形にすることの重要性を学ぶ良い機会でした。
継続するだけで武器になる
1つのことだけ続けるのは、精神衛生上も応用のしにくさ的にもややリスキーなのですが、逆に細々と続けていると、気づくと周りのライバルがみんなやめていて、自分がその分野代表になっているということもあります。
例えばデザインサークルでは、初めは何歩も先を行く同期に一生追いつけない気分でしたが、人と比べるのをやめて、ただ楽しくて6年デザインを続けた今となっては、小さな世界の中では、デザインといえばこの人と思われるくらいになっていました。
また建築学科でも、面白くて1年ほど竹を使った建築ばかり設計していたら、竹に関する質問が定期的に同期から飛んでくるようになっていました。
好きこそ物の上手なれ、というのは、好きだと熱中するから自然と上達も早くなるよ〜的な意味だと思いますが、好きだと人と比較せずに淡々と続けられるために、やめていった他の人達を経験値で上回っていつの間にか相対的にスキルが上になっている、という側面もあるんじゃないでしょうか。知らんけど。
東京大学自己分析学科
結局東大では、もちろん色々な授業を受けて知識も身についたり身につかなかったりしたのですが、どうやっても勝てなさそうな優秀な人たちに囲まれることで、自分ととことん向き合うきっかけになったのが、1番の収穫だったような気がします。
もちろん、そのくらい刺激的な環境だと、薬をもらわないといけないくらい心が疲れてしまう人も周りに一定数いて、悩み続けることがいいことだとは決して言い切れないのですが、自分の機嫌の取り方、メンタルケアの仕方を知ることは一生分の財産になる気がします。知らんけど。
最高学府感のある話(なにそれ)ができなくて申し訳なーい。
結局、東大の肩書きをフル活用することはできなかった。さようなら学生証。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
