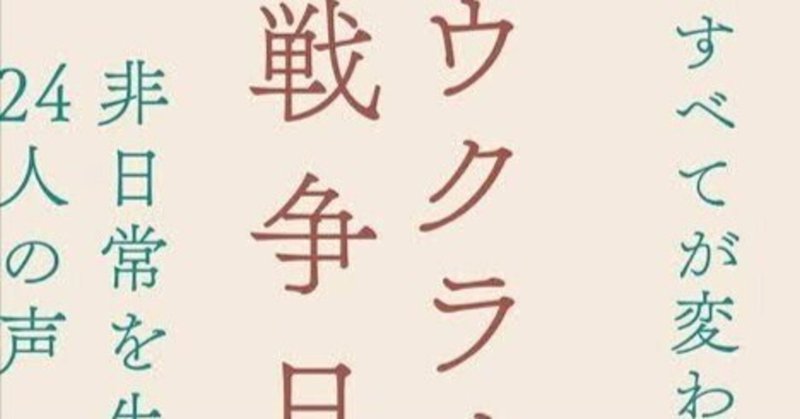
365日後に育休復帰する父(45日目):『ウクライナ戦争日記』
本当は4月に読み終えるつもりだった『ウクライナ戦争日記』。

チマチマと読み進めていましたが、ようやく今日読み終えたので、感想を書いていこうと思います。
○ウクライナについての知識
この本を読んで、単純にウクライナについての知識や、今回の戦争でどんな事が起こっているか、2022年7月までの情報ですが知ることができました。
ウクライナの簡単な歴史や地理などについても掲載されていたので、建国されてから親露派と親米派が代わる代わる政権を担ってきたとか、市民革命によって政権を打倒してきたとか。
中高社会科免許を持っているくせに、恥ずかしながら2014年にロシアがクリミア半島を強引に併合していたことすら知りませんでした。なんならポーランド以東〜中国以西の、東ヨーロッパ・西アジアの地理すらあやふやです。
こうしたウクライナについての知識および、戦争で起こっていること、戦時下の人々がどのような暮らしを強いられているかを知れたことは良かったです。
○想像力の乏しさ
知識を得た一方、24人分の日記を読んでも自分の中でこの戦争がまだ他人事、対岸の火事のように感じられ、自分の想像力のなさに少しがっかりです。
日記自体はとても読み応えがあり、それぞれの人が思ったことが赤裸々に書いてありました。
「ロシア人は絶対に許さない」「ロシアは悪魔だ」といったストレートな憎悪や、戦争を機にロシアにいる親戚や友人とわかりあえなくなってしまった失望、なんてことない戦争前の日常への渇望など、様々な感情が文章にはこもっていました。もちろん負の感情だけでなく、生き抜こうという強い意志や助けてくれる人への感謝なども。
ただこれだけストレートな感情を浴びても、どうも自分の中では読み物として終わってしまうのが、自分自身に対して残念です。
戦争が身近になんて感じたくはありませんが、実際に経験している人の数%でも切迫感のようなものを感じられれば、授業にも説得力が出るのかなと思っていたのですが。
まあこれを読んで「戦争の辛さが身に沁みてわかりました」と知った顔するよりは、自分が無知ということをわかっていた方がマシだと思うことにします。ソクラテス先生もきっとそう言ってくださることでしょう。
○終わりに
こういうと不謹慎ですが、やはり実際に体験しないと戦争の恐ろしさって実感できないものなのでしょうか。
自分が小学校の時は夏休みの宿題の鉄板だった、「戦争についての話を聞いてくる」というのも、今は生き証人がかなり減ってきてますもんね…。身近な人から話を聞くことも難しい。
そろそろ戦後80年、日本が兵器を輸出できるようになったなんてニュースも聞きますが、唯一の被爆国としてのアイデンティティはどこに行ってしまったのかと憂うばかりです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
