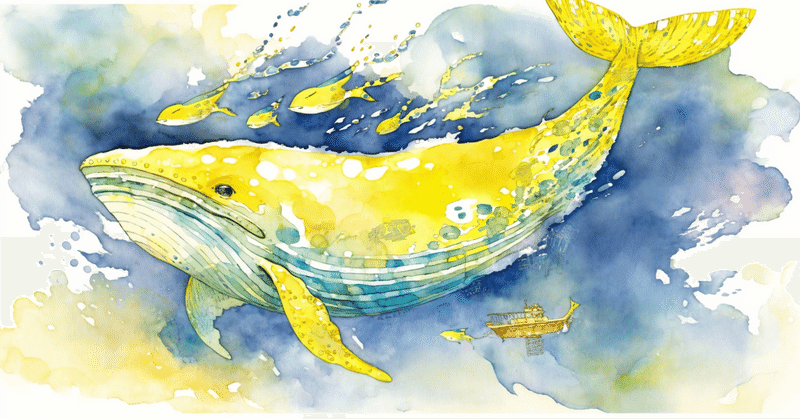
52ヘルツのクジラたち、よく考えたら課題山積み/感想追記
月初に52ヘルツのクジラたち/マイノリティを扱う物語の罪と意義という記事を書いた。観終わった勢いのままに書いたので、熱をふんだんに帯びた感想であったが、その後時間がたち平熱に戻ってきた頭でもう一度よく考えてみたら、なんかまたちょっと違った感想を抱いたので記しておく。
そうでもねえぞ。
以下ネタバレを含みます。
ただし先に断っておくと、私はこの作品が大好きだ。この作品の加害性を最小限にしようとする姿勢や、それを実現するための取り組みは素晴らしいと思う。間違いなく業界におけるマイノリティの表象の現在地を一歩上へと押し上げてくれている。これからもこのような取り組みが、すべての作品や物語の作成において当たり前に取り入れられ続けられるべきだと思う。杉咲花さんの本作品への姿勢は本当に尊敬していいる。彼女はこの作品について様々な議論が巻き起こり対話が生まれることを覚悟し歓迎しているので、私はあえて、「うーん、そうでもねぇぞ」と思ったところについても言及したい。
そうでもねぇぞ。と思うのは以下の4点。
1.トリガーウォーニング、表示小さすぎて警告する気ない
トリガーウォーニングとは、映画や本などの作品で、その内容が一部の人々の感情を害したり、気分を悪くさせたりする可能性があることを事前に警告することを指す。52ヘルツのクジラたちのHPでは、「本作には、フラッシュバックに繋がる/ショックを受ける懸念のあるシーンが含まれます。ご鑑賞前にご確認ください。自死、自傷、DV、児童虐待、トランスジェンダー嫌悪、など」と記されいている。大切なことだと思う。
しかしである。HPの中でも一番隅の隅。小さすぎて見えないような表示なのだ。

小さい。読めない。これはリンクになっていてクリックすると詳細ページに飛べるのだが、リンクボタンになっていることがわかりづらく、情報に辿り着きづらい。
要は、トラウマを呼び起こすような描写が、視聴者の目に入る前に「事前警告」するつもりはないのだろう。なぜなら、「ネタバレ」になるから。資本主義だから。「なんだか暗いな、社会問題系か、もっと気楽に観れるやつがいいな」と避けられるかもしれないから。トリガーウォーニングは動員や収益においてはマイナスにしか働かないのかもしれない。
ネタバレを徹底排除して映画を初見第一主義で楽しむことが出来るのって、警告されるようなトラウマや傷を持たないで済んでいる者の特権だと思う。そしてその特権側が圧倒的マジョリティである。特権を振りかざすマジョリティほど怖いものはない。
公式サイトにトリガーウォーニングを掲載すること、パンフレットに用語集や相談窓口などを記載することなど、方向性としてはとても素敵だと思う。でも、表記が小さすぎて見えない。情報が必要としている人にリーチされない。それでは、トリガーウォーニングに警告としての役割は果たせない。警告に「免罪符」「ちゃんとやってる感」の役割を期待しているとしか思えなかった。
個人的には、トリガーウォーニングは予告の段階で示されるべきだと思う。予告動画、予告編で。
2.インタビューで杉咲花さんが話していることの素晴らしさと作品の内容・質に乖離がある
本作素晴らしい大好き!と思ったのは、杉咲花さんに依拠するところが大きい。大きく分けて、「演技」と「覚悟」である。
主演の杉咲花さん、演技が素晴らしかったのには、ワケがあったんだな。ただ技術としての演技が優れているだけではなく、作品に描かれるマイノリティの現実や自身の特権性について自覚し問い直し、考えて想像して勉強して、さらに当事者による監修をこの作品に必要であると提言し実現するまでの、本作への真摯な向き合い方が、あのとんでもない演技を可能にしているのだと思った。
なんといっても、インタビューで彼女が述べていることに感銘を受けた。パンフレットが素晴らしいらしい。(まだ購入していないが欲しい…)でも素晴らしいことを述べていれば述べているほどに、作品の内容との乖離が気になり始めた。例えば先述の「トリガーウォーニング」のように、方向性としては素敵だが、実が伴っていないような、そんな感覚だ。
3.結局装置になっているのではないか
映画やドラマの中で、物語の展開をドラマティックにするために性的マイノリティの方を登場させてきた歴史がある。現実では誰にも言えない“秘密”を抱え、差別や暴力にさらされながら、物語では多数派の人々を楽しませるために笑い物やモンスター、または、ただ可哀想な人のように描かれることもある。そのように物語の“痛み”を背負わされる存在だったことを知ったとき、言葉にならないほどのやるせなさを抱き、いかにマジョリティが自分たちのためだけに物語を描き、自分たちを優遇してきたのかということを考えさせられました。そして、無意識のうちに自分がそこに加担してしまっていたかもしれないということも。
このように「物語をドラマティックにする装置としてマイノリティに悲劇を背負わせる」ことのグロテスクさについてインタビューで言及しているにも関わらず、映画52ヘルツのクジラたちでは、性的マイノリティである安吾がアウティングされた挙句自死してしまう。さらに自死の場面を、結構鮮明に描いており(自死の方法もわかるし、血も見えるし、亡骸も見える)悲劇として主人公や視聴者の心を揺さぶろうとしている思惑がわかる。
うーん?!と思わざるを得ない。きっとこの点については製作陣や杉咲花さんも納得行っていないんじゃないかな。現時点では、まだ、こうしてアウティングや差別が人をも殺す、ということを描くに留まったのかな。
歴史として振り返った時に、当時はまだここで悩んでいたんだ、こんな苦しみがあったんだと知る過渡期の作品として。未来ではこんな悲劇が語られることのないように、歴史の1ページとしてこの物語が生まれたと信じたいんです。
トランスジェンダーの表象と、日本映画界の課題
4.結局当事者性はどの程度反映されているのか
本作では、「トランスジェンダー監修」「LGBTQ+インクルーシブディイレクター」等当事者による監修が入るという一歩進んだアプローチ(というか遅れまくっていたアプローチがマイナスからゼロ地点になった)が成されている。でもやはり、「安吾」というトランスジェンダー男性役は当事者であるトランス男性の俳優ではなく、シスジェンダー男性が演じている。これもまた、動員数や収益の問題だろう。
より広く作品を届けるために知名度のある俳優の起用が必要という制作側の意見をよく耳にする。でもそもそも影響力を持つ俳優のなかに、なぜ当事者が含まれてないのかを見つめ直す必要がありますよね。それは当事者に実力がないのではなく、業界や社会が活躍できる環境を整えてこなかったからで。それは自分も含めた制作側が重く受け止めていくべきことだと思うんです。そしてこれからは当事者が活躍する場を増やしていかなくてはいけないと思います。
一方で、自分のなかで変化を感じた部分も本作にはあって。これまでの映像作品では、例えばトランス女性役をシス男性が演じることが多かったと思うのですが、トランス女性を知らない人からすると“男性の女装”という偏見を助長してしまいかねない危険性がありますよね
そういった意味で、本作のトランス男性をシス男性が演じるということは、一歩だけ進んだアプローチなのではないかと感じています。そして、批判を受けることも理解したうえで、自分が演じる意味があるかを葛藤した末に、安吾という役を引き受けた志尊くんに対して、私は敬意を抱いています
トランスジェンダーの表象と、日本映画界の課題
シスジェンダー男性がトランスジェンダー男性を演じる上で、当事者の監修を受け対話を重ね二人三脚で「安吾」という人物を演じ上げたのは、本当にすごいことでこの映画の根幹を支えたのであろう。「当事者が演じる」ことは叶わなかったながらに「当事者と二人三脚で人物を演じ上げる」ことができたのだ。
そして「トランス男性は男性」だから、「トランス男性俳優の起用が難しいならせめてシス男性」と私は当たり前のように思っていたが、そうか。「トランス男性」を「シス女性」が演じてきた過去があり(金八先生とか)、それはあからさまな差別の助長だったんだな、と衝撃だった。
課題は残る。
本作は、全ての課題をクリアにした画期的な映画ではない。だがきっとこの残った課題についてもちゃんと向き合ってくれるのが、杉咲さんや志尊淳さんであり、監修の若林佑真さんやミヤタ廉さんであり、彼らへの信頼が、映画業界の未来への希望である。製作陣の熱意と誠意に満ち満ちた作品だ。
ただ、製作陣の方々の真摯な姿勢に、作品が追い付ききれなかったのだ。そしてそこは、ちゃんと問題だと思う。
映画業界のマイノリティ表象の現在位置として、本作が達成できたこと、できなかったこと。私はまだ脚本家にも小説家にもなれないが、イチ国民として、社会を変えていくことはできるはずだ。それは投票であったり、デモであったり、シェアや発信であったり、不買だったり、署名だったりするだろう。身近な人との対話であったり、自身の普段の言葉遣いを正すことかもしれない。何より勉強と対話は、生涯続けていきたい。私はまずはそういうアプローチで、課題に取り組んでいきたい。
