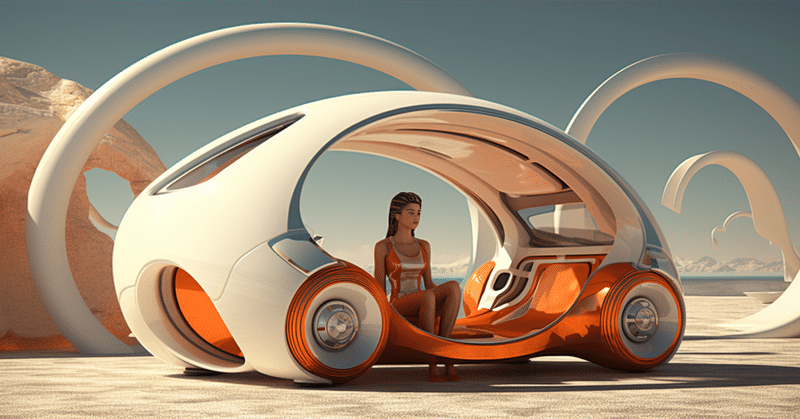
長沼伸一郎『経済数学の直観的方法 マクロ経済学編』読んだ
経済学は日本では文系の学問ということになっているが、それは大変な誤りである。
しかし学部は文系ということになっているので、たいして難解な数学は要求されない。ところが大学院になった途端にそういう遠慮は一切なくなり、急に難しくなるのである。
そういうわけで何年も前からマクロ経済学のお勉強が停滞してしまっている。。。
最近思うところがあってブルーバックスのライブラリをつらつら眺めている。ほとんどがKindle Unlimitedになっているのが良い。そして私のような人間にぴったりと思われる本を見つけたのである。
著者の専門分野は物理学とのこと。だから物理学から経済学へと数学が輸入されていくプロセスがわかりやすく解説されている。
そういう背景を知らないと、いきなりラグランジュアンとかいう観念が経済学に登場して戸惑うことになる。
本書は三部にわかれている。上級編は大学院レベルになるので、ここは興味のない人は読まなくていいだろう。
初級編と中級編はおもに物理学と経済学の歴史の解説で、ここまでは文系の人でも楽しく読めると思う。どうして中世までアラビア世界や中国に技術で劣っていた西洋が、工学や経済学で世界を制覇するに至ったかよくわかる。
物理学の世界史的重要性
江戸時代の日本は和算が有名なように、それなりに数学が発展していた。またからくり人形にみられるように技術の水準もけっして低くはなかった。
しかし数学と技術をつなぐ物理学が存在しなかったため、それらは工学たりえず、たんなる知的ゲームに終わってしまい、技術において西洋に遅れをとることになった。
西洋ではむしろ物理学の必要性から、数学が発展していった。そして工学は物理の思想を体現するモデルだった
経済数学は、自然科学の圧倒的成功をみて、スピンオフのような形で導入された。だから経済学に持ち込まれた数学が、物理学においてどのように用いられていたかを知っていると理解しやすい。
例えば市場の均衡は、惑星運動の均衡と相似形である。ニュートンの天体力学はアダム・スミスに多大なる影響を与えている
ルネッサンス期にアラビア世界から高度な科学を吸収し、それを次の次元に発展させえた鍵は天体力学であった。天体力学の使命は惑星の未来の位置を知ることである。そのために微積分が開発されたといっても過言ではない。
このようなミッションをもたなかった非西洋世界は科学においてキャッチアップされただけでなく、工業力で大きく遅れをとることになった。微積分を手にした西欧文明は地上の覇者となったのであり、その歴史的意義は極めて大きい。
微積分の発見の200年前までは西欧はアラビアから学ぶ立場だったのである。
経済学と物理学、ケインズ経済学と古典派経済学
単体力学のような未来位置の予測という発想は経済学とも相性が良かった。典型的にはワルラスやパレートら古典派の一般均衡理論であるが、この時期にはまだ微分方程式を使えていなかった。
大恐慌期におけるケインズ経済学は1回限りの理論であった。ケインズ自身は数学を深く理解していたがニュートン力学の体系を持ち出さず、大雑把に把握して現実の経済政策を導くという手法を用いた。
そもそもニュートン力学は扱う天体は2個だけ、たった3個になるだけで解けなくなるいわゆる三体問題があった。
太陽系は太陽がずば抜けて大きいので、他の天体はいったん無視して、太陽と地球、太陽と木星のような形で解いてから、寄せ集めればよかった。しかしそれでもわずかにずれている。
これを経済学に導入するとき、そのずれを大きいと見積もるかどうかで道が別れた。
個々の均衡を足し合わせれば良しとするのが古典派。
一つ一つの均衡は正しいとしてもそれをつなげたときの誤差は大きいとみなすのがケインジアン。
ケインズはマクロの事象から、経済政策に使える理論を作り上げようとした。大恐慌時代において正しかったのはケインズであり、ミクロの均衡を寄せ集める古典派経済学は、デフレを悪化させた。
ケインズが勝利したことで、経済学はケインズ的なマクロ経済学と、ミクロの均衡を下から積み上げていくミクロ経済学に分離することになったのである。
これによりミクロ経済学は現実の経済政策に使えなくてもよいことになった。アカデミックな世界における思考実験として生きることが許されるようになったのである。まだこの時点では、高校生の微積分レベルの数学にとどまっており、肝心の微分方程式が使えていなかった。
これに関連して等比級数の和が説明されているが、それは乗数理論の解説のためである。例の、1億円預金があって準備率が10%ならば銀行はいくら貸し出せるかというやつである。正解はもちろん9億円だが、本書ではちゃんと9000万円と間違えている。これは経済学の教科書が間違っているからしかたがないことである。
ここまでが初級編。そしていよいよ動的モデルの説明に入っていく。
新古典派経済学と物理学
初歩的な古典派経済学のモデルがニュートン力学だったとすれば、動的均衡は解析力学がモデルである。解析力学の先代にあたるフェルマーの原理に動的一般均衡理論の思想的エッセンスが集約されている、らしい。
フェルマーの原理とは、光はその通過時間が最小になるような経路を選んで通る、というもの。
経済学ではカクカクシカジカを最大化または最小化するような均衡を決定するという問題がしばしば登場するが、フェルマーの原理からの類推であったようだ。
初代=フェルマーの原理
二代目=解析力学
三代目=最適制御理論(と量子力学)
四代目=動的一般均衡理論
フェルマーの原理は、ミクロの原理から演繹的にマクロの理論を導けるという発想のもとになった。つまりラムゼイモデルにおける異時点間の均衡みたいな問題である。
2代目の解析力学、最小化すべきものは光以外にも拡張される。
経済学の教科書で唐突に登場するラグランジュアンだが、物理学においては最小になっているサムシングのことらしい。知らなかった。フェルマーの原理では、光の通過時間がラグランジュアンである。
なおラグランジュアンはなんでもいいわけではなくて、「ラグランジュアンは基本的に2個の変数で書かれ、それらは一方の変数がもう一方の変数になっている、という関係を満たしていること」という大事な条件があるのだが、これまた経済学の教科書にはあまりちゃんと書いてなかった気がする。
3代目の最適制御理論になると、最小化(あるいは最大化)すべき量は神ではなく人間が決めることになる。この精神性の変化が工学の発展と軌を一にしている。
4代目の動的一般均衡理論は、その工学的発想を経済学に移し替えたもの。効用を最大化したり、コストを最小化したりするのである。
しかし経済学では上述のラグランジュアンの条件を満たしていないものが知りたいこと(最大化または最小化したいもの)になりがち
しかしルーカス批判以降、変化率が重要なファクターであるということになり、つまりある変数とその変化率のペアが重要な変数として隠れているはずだということになった。なんでもラグランジュアンのツールで定式化する可能性が開かれたのである。
なおルーカス批判は、どんな政策を発表しても人々はそれを折り込んで行動するので政策効果が相殺されてしまうという批判でもある。これは量子力学の不確定性原理のようでもある。
動学モデルの発展
ラムゼイモデル、消費と貯蓄の均衡、つまり経済成長モデル。
RBCモデル、これに消費と余暇(非労働時間)の効用、マクロでは労働投入まで予測できる
ニューIS-LMモデル、IS-LMにインフレ率という「変化率」を加えたもの
第4世代のDSGE
まずラムゼイモデルはオイラー方程式の形になっていることが大事で、これによりラグランジュアンから知りたいことが一発でわかる。というかラグランジュアンからこの微分方程式を導くのだが、ラムゼイモデルだとそこまでしなくてよいことが多い。
次のRBCになると、労働か余暇か、消費か貯蓄(+利息)か、みたいに変数が増えて冗長性が増す。最初の式が冗長であるほど、いくつもの式をひねり出すことができるので都合がいい。
私のような初心者は式が長くなるとウゲーとなってしまうが、そのほうが逆に都合がいいと思うとちょっと抵抗は減るかも。
ニューIS-LMとかDSGEもRBCとほぼ同じ。インフレ率だったり債権だったり変数が増えて見た目はいっそう複雑になるが、冗長性が増えると微分したりしていっぱい式を導出できるから都合がよいともいえる。
ラグランジュアンとハミルトニアン
物理学ではラグランジュアンだけでなくハミルトニアンという量もしばしば使われる。ラグランジュアンは最大または最小にしたい量だが、ハミルトニアンは一定になる量である、エネルギーとか運動量とか。
経済学ではGDP一定のもとでの無差別曲線みたいになるかな。ただし経済学の目的は一定ではなくて、成長を追求することであることが多いのであまり相性はよくなさそう。ただし持続可能性が重視される時代ではハミルトニアンの有用性が増すかも知れない。
微分方程式
速度がわかれば位置がわかるのが物理学だが実際はそう単純な話ではない。速度を知るには位置情報が必要で、位置情報を知るには速度が必要という堂々巡りになっている。金利は貯蓄で決まるが、貯蓄量は金利が決まらないとわからない、みたいなループ構造はこの世界にはあふれている。
これを突破するのに微分方程式が必要であった。位置情報X(t)を2回微分すれば加速度の関数が出てくるが、これだけではどうしようもない。そこで万有引力の法則からわかる加速度とそれを式の左右にならべると、X''(t)=aX(t) となって、じゃあ自然対数を使えばいいねとなるわけである。
こういう背景を知らずに大学院レベルのマクロ経済学の教科書を読むと、なんの脈絡もなく登場する微分方程式とかいうものに意識を飛ばされてしまうのであった。
和算はなにがダメだったのか
西洋代数のすぐれているところは、記号を積極的に用いて簡略化していることである。工業などへの汎用性を考えれば、簡単であることは非常に重要である。オッカムの剃刀だ。
西洋代数学が日本にもたらされたとき和算家たちは、その簡素性をみて大したことないなと思ったらしい。それで彼らはいつまでも和算にしがみつき、これをみた明治政府は和算そのものを切り捨てるという英断をくだした。
簡略化の極致が行列とその固有値であり、もちろん経済学においても大事なツールだ。
著者は、和算は歴史の中に消えていったと言っているが、中学受験ではみんな必死こいて和算やってる、、、馬鹿げているというほかない。
おまけ
著者によればミクロ的原理から全体の均衡を知るこの理論の重要性は、それが世界の主流であるからだ。
日本ではルーカス批判以降の経済学理論の受容に拒否反応を示してしまい、政策現場の主力はこれを学びそこねている。今さら難解な数学を学ぶわけにはいかず丸暗記で乗り越えるしかいないという情況だ。
ジョーン・ロビンソンが言うように、経済学を学ぶ目的が経済学者に騙されないようにするためならば、とりあえず丸暗記という状態は非常に危ないと著者は指摘する。
実際こういう場合には、相手の解釈や思想を無防備にまるごと受容しやすいのであり、なまじ何も知らない状態よりも危険だということになりかねないのである。
実際、新古典派経済学はアメリカが自国に都合の良いように理論を組み立てている側面があり、歴史的背景を知らずに受容するのは危険といえる。
サポートは執筆活動に使わせていただきます。
