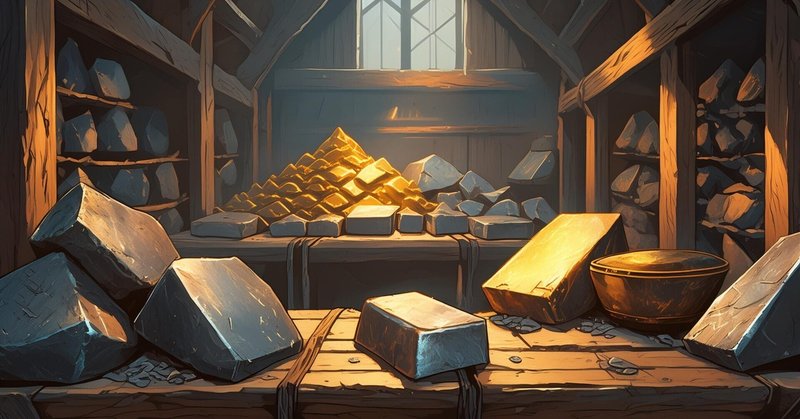
『レアメタルの地政学』資源をめぐる地政学とテクノロジーの危うさ
ギヨームピトロン氏の『レアメタルの地政学』は、一見地味な題材から、現代社会の根幹を揺るがす重大な問題提起を導き出す、衝撃に満ちた書だ。本書を通して私たちは、エネルギー転換とデジタル革命を支える「レアメタル」という資源が、新たな国際対立の火種となっている現実を知ることになる。
著者は世界各地の鉱山や工場を訪ね歩き、レアメタルを独占する中国の戦略、そして欧米諸国の危うい依存状態を克明に描き出す。ルポルタージュとも評論とも呼べるスリリングな筆致で、資源の奪い合いが地政学的緊張を生んでいく過程を浮き彫りにしていく。
「レアアース戦争」の勃発
本書で特に印象的なのは、中国によるレアアース輸出禁止という「リアルな脅威」だ。日本などへの禁輸措置を通じて、中国は欧米のハイテク産業を脅かす力を見せつけた。各国は代替資源の確保に血眼になるが、レアメタルの採掘と精錬を支配する中国の優位は揺るがない。
「中東には石油があるが、中国にはレアアースがある」
鄧小平の予言めいたこの言葉が示すように、レアメタルは21世紀の石油とも呼ぶべき戦略物資になったのだ。資源ナショナリズムが台頭し、覇権をめぐる暗闘が世界規模で展開される。まさに「レアアース戦争」の幕開けである。
テクノロジーと環境破壊のジレンマ
しかし本書が突きつけるのは地政学だけの問題ではない。より根源的なのは、私たちが目指す脱炭素社会や利便性の向上そのものに内在するジレンマだ。
「グリーンな資源とエネルギーには陰の部分がある」
風力発電や電気自動車、スマートフォンなどに不可欠なレアメタルは、その採掘と製錬の過程で深刻な環境破壊を引き起こす。豊かな先進国が汚染を中国などに押しつけ、美しい理想を語る一方で、途上国に多大な犠牲を強いている現実がある。テクノロジーは私たちを救うのか、それとも破滅へと導くのか。本書はその危うさを見事に喝破している。
著者の真摯な探究に感銘
ピトロン氏の真骨頂は、グローバルな視座と、ディテールへのこだわりの見事な融合だろう。世界を股にかける取材と、現場のリアリティを丹念に積み重ねることで、レアメタルという一見ニッチな素材の重要性を説得力をもって伝えることに成功している。
個人的には、現代のジャーナリズムのあり方を示す好例としても本書を高く評価したい。難解な事象をあますことなく掘り下げつつ、断定は避け、読者との対話を重視する著者の姿勢に感銘を受けた。あくまで私見だが、メディアへの信頼が揺らぐ時代だからこそ、ピトロン氏のような誠実な探究者の存在は貴重だ。
より良い未来へ向けて
本書は危機感を煽るだけではない。再生可能エネルギーへの移行やデジタル化の重要性は疑いようがない。だからこそ、負の側面にも正面から向き合う必要があるのだ。
「人類が7万年もの間採掘してきた量以上の鉱物を今後30年間で採掘しなければならない理由のひとつがそれだ」
大量消費と環境保全の両立は簡単ではない。しかしピトロン氏が説くように、認識を新たにし、英知を結集すれば道は開けるはずだ。一人一人が資源の問題を自分ごととして捉え、より賢明な選択を積み重ねていくこと。『レアメタルの地政学』はそのための第一歩を私たちに促してくれる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
