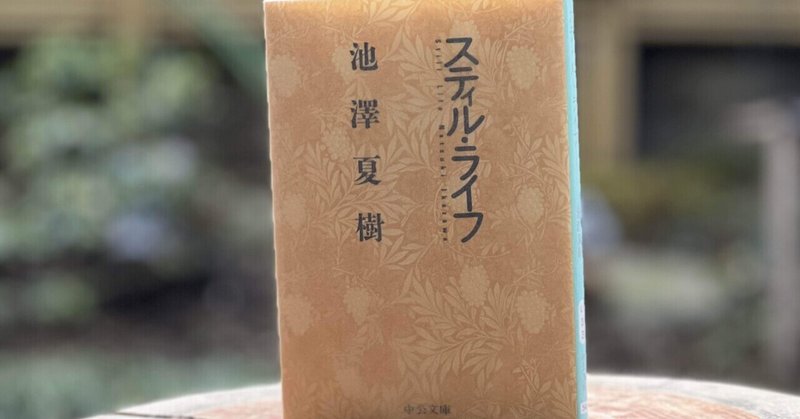
『スティル・ライフ』 池澤夏樹
僕の好きな世界感、感性、知性、美で僕をとりまく世界を埋めたい。
言葉は使い古され少しずつ変化してゆくものでもあるかもしれないけれど、感じたことを浅はかなものや真似で安直に陳腐化したくない。
消耗的であったり感情を感傷や浅はかな知や美で陳腐化させるものに、僕自身の言葉含めて、うんざりすることがある。
そうしたとき、音を立てずに雪のように天に上昇して、消えたいという言葉が胸をいっぱいにする。
池澤夏樹さんの『スティル・ライフ』を読んだ。
この世界がきみのために存在すると思ってはいけない。世界はきみを入れる 容器ではない。
世界ときみは、二本の木が並んで立つように、どちらも寄りかかることなく、それぞれまっすぐに立っている。
きみは自分のそばに世界という立派な木があることを知っている。それを喜んでいる。世界の方はあまりきみのことを考えていないかもしれない。
雪が降るのではない。雪片に満たされた宇宙を、ぼくを乗せたこの世界の方が上へ上へと昇っているのだ。静かに、滑らかに、着実に、世界は上昇を続けていた。
この方は旅が好きなのだろう。
どこか、星野道夫さんを彷彿させる自然の中での事物の捉え方だ。
河出書房新社の池澤夏樹=個人編集 世界文学全集を何冊か持っている。
時々、この編者である池澤夏樹さんは僕の好きなセンスを持っていて、いいな、と思いながら全集リストを眺めていることがある。
また、どれも訳はかなり精度がよくきちんと訳された原著に忠実なものや作者が決定版としていたらそれに忠実にその版の訳を入れている。
フォークナーの『アブサロム!アブサロム!』やクンデラの『存在の耐えられない軽さ』、最近読んだバオニンの『戦争の悲しみ』など。
他、僕の好きなフランス文学もいくつか入っていたりするから、いつか全集を集めきりたい。
ぜんぶで30巻くらいあるから、集め終わるのはまだまだ先かもしれない。
だから「池澤夏樹」という名前を見ると全集がパッと思い起こされる。
池澤夏樹さんが詩人から出発した作家だと知ったのは、須賀敦子全集からだった。
アントニオ・タブッキの作品『インド夜想曲』を媒体として、池澤夏樹の書くものを知り、たちまち、そのとりこになった。
僕は須賀さんのエッセイを媒体としてさまざまな作家の作品を知った。
この本もそんな経緯のひとつだった。
見たものを見たままに描くというより、自然科学的な要素と自然とを言葉で詩人らしい池澤さんなりの感性で繋げているせいか、宇宙的な広がりを感じる。こういう感覚は僕もとても好きだ。
読んだあと、こうしたことを考えながら僕は僕の世界の湖のほとりで春を待つ。
時々、思う。消えたいという感覚。
言葉、音楽、絵、空間、顔が映し出されたフィルムを断片化しガラスに知らない誰かが映す。僕の好き嫌いによらず、否応なくそれらが僕の湖に落ちてきて、湖面にヒビを入れていくから僕がポイっとイイネだけして、向こう岸の原っぱに投げこむ時もあれば、好きなものは波紋を静かに広げて水の底に落ちていくものもある。
とりとめもなくこのSNSにこれまでの僕の大事な
想いを拙い言葉にして違う世界に置き去りにしてきたこと、
考えたことのない世界をまるで自分だけで思いついたかのようにして飛びついて、いとも簡単にそれらを奪い去られたり、
丸められて塵のように消えていったりすること
つまり僕の軽蔑することへのような、宛先のない馬鹿げた憤りを書いた手紙みたいな感情が漠然と僕の周りに広がりはじめた。
クリーム色の紙に万年筆で書いたものだけで良いじゃないか───すべてにおいて理知的で痛いほどの美しさをもつものが好きだ。
ぼんやりと壁に寄りかかる。
妻は写真に僕を切り取る。
そうして、ポイって僕とは違う世界に投げ込むと
壁が乳白色の宙になって僕はそこへと帰っていく。
世俗的なものから離された世界、僕のいくつかの世界のひとつ。でもすべての僕をとりまく世界に横たわる世界。
『スティル・ライフ』の主人公の発する「そう、大熊座から来たんだ」、という言葉に、キリスト教の三位一体を須賀敦子さんは彷彿させられたのだろうか。
須賀さんは池澤さんの『スティル・ライフ』を新しい救いのかたちと評していた。
そう捉えるならば、そうかもしれない。
円と直角の接点(タンジェント)。高次の秩序が低次の秩序において無限に微小なかたちをとって現前する例。
キリストは人類と神とをつなぐ接点、すなわちタンジェントである。
いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。
