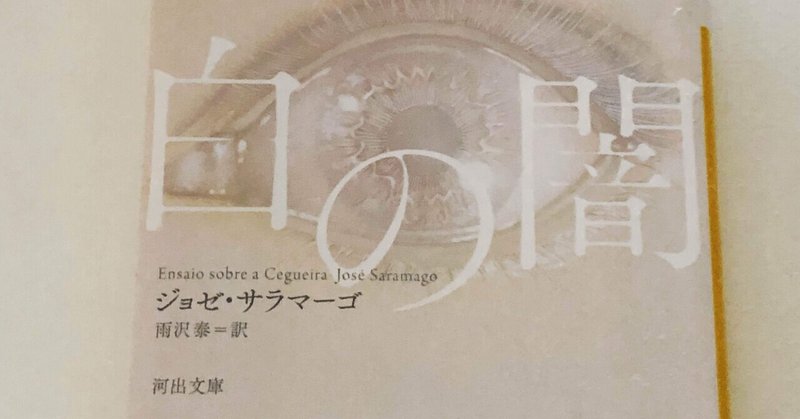
白の闇
著者 ジョゼ・サラマーゴ
訳 雨沢泰
出版 河出文庫2020/03/20発行 2021/03/30 4刷
この本は1995年に刊行されたノーベル文学賞作家(1998年受賞)ジョゼ・サラマーゴの作品です。
軍事政権やファシズムといった政治情勢の不安定な時代背景を持つポルトガルで生まれ育ち、かなり高度な視点から物事を見つめ、愛情深いサラマーゴだからこそ書けた作品であり、迫真に迫るものがありました。
サラマーゴ自身は政治的なものではなく、「理性」についてテーマとしているとインタビューで答えてもいます。
あらすじ
唐突に車の運転中白の世界へ行った男。
その男を助けて車を自宅まで代行で運転してあげて、車をパクり白の世界へ行った窃盗男。
イッたと思ったら白の世界だった事に気づき絶叫する娼婦の女の子。
白の世界へ行った人々を診察した医師も白の世界へ。
病に翻弄される周囲の人々を彼らの眼の代わりとなりじっと見つめる女
伝染病のように広がってゆく謎の失明。病に翻弄される社会。
崩壊してゆく社会の中での失明者たちの様子が、改行も少なく会話に括弧もない、怒涛のように溢れ出る文章によってリアルに描かれている。
見えない者に名前は必要なく、ただ声だけがある白の闇。
失明する謎の病
目が見える、目の見えない人々。でも、見ていない。
世界全体が盲目的になる=人間の本性が剥き出しにされた世界。
この病気は「とても論理的な病気」と作中で言われます。
なぜ、医者の妻だけは失明しなかったのか?
テーマ
対応できない災いが起こった時の社会の変貌
社会や政治に対して人々が盲目的であるという風刺
人間が理性、尊厳、互いへの尊重を見失った時の悲劇
対応できない災いが起こった時の社会の変貌
突然、目の前全てが眩しいほどのミルク色の海のようになる症状に陥る失明が流行し、人々にとって世界は、これまでの世界から白の闇の世界に変貌します。著者はその世界の変貌を描き、ある時には医者の妻の眼を通して、語らせます。本書のテーマに流れているものは現在の現実の世界にも通じるものを感じました。
カミュがペストで描いた病の流行による人々の変貌に対し、サラマーゴは社会の変貌として描いています。
世界に対し人々が盲目的であるという風刺
「目が見えない人のなかで最悪なのは、見たいと思わない人」
白の闇 ジョゼ・サラマーゴ(河出文庫p371)
黒い眼帯をした老人が最後に見た絵画について語りながら、盲目であることの真実の意味を問います。
(中略)それから恐怖におののく馬がいました。(中略)馬を見たとたん、見えなくなったのです。(中略)われわれは失明したとたん目が見えなくなる。恐怖が目を見えなくするのです。恐怖が目をくらませつづけるのです。
白の闇 ジョゼ・サラマーゴ(河出文庫p166)
人間が理性、尊厳、互いへの尊重を見失った時の悲劇
医者の妻は、この物語の主要登場人物の中で唯一失明しない人物です。
なぜ、彼女だけが失明しなかったのでしょうか。
医者の妻は、最初、夫の眼の代わりとして、ある時点からは同じ病室の人々、周囲の人々の眼として、全てを見ようとし続けます。
(医者)もしふたたび視覚が得られたら、人の眼を注意深く見るよ
白の闇 ジョゼ・サラマーゴ 河出文庫(p344)
目が見えない人のなかで最悪なのは、見たいと思わない人
白の闇 ジョゼ・サラマーゴ(河出文庫p371)
(医者の妻)目が見えない人の場合は、その人の持っている物をそのまま認めるのがいちばん自然だわ
中略
わたしたちには形容詞などなんの役にも立たない。たとえば、ある人が人殺しをしたとする。その場合、事実を隠すことなく率直に話すほうがいいし、その行為自体の恐ろしさがとても衝撃的だから、恐ろしいと言う必要はないと思うけど。
(作家)あなたがおっしゃるのは、わたしたちは必要以上に言葉を持ちすぎている、ということですか?
(医者の妻)わたしたちは感情に乏しすぎると言ってるの。
(作家)なるほど、あるいは感情を持っているのに、それを表現する言葉を使うのをやめているのですね。
(医者の妻)だから感情をなくすのよ。
(作家)自分を見失わないでください。見失わされないでください、と作家は言った。
白の闇 ジョゼ・サラマーゴ(河出文庫p364-367)
僕は、医者の妻がサラマーゴの代弁者のようにも思えます。盲目の中で起こる暴力やその暴力による制圧、統制、人間の尊厳や互いの尊重を無視した者たちの顔を医者の妻は覚えておくと言い放ち、彼女は歪んだ社会をじっと見据え続けました。
おわりに
本質的なことは見ることを学ぶことだ
考えずに見ることを
見ているときに見ることを学ぶことだ
見ているときに考えたり
考えているときに見たりしないで
「不穏の書、断章」 フェルナンド・ペソア
物語全般に渡って読んでいる最中、僕は、ペソアの言葉が脳裏に過りました。
ジョゼ・サラマーゴは著書「リカルド・レイスの死の年」(1986年刊行)(リカルド・レイスはペソアのペンネームの一つ)を同じくポルトガル出身の詩人ペソアへ献花を捧げるかのように書いています。献花でありながらも、その一方で、ファシズムに対してペソアほどの知性がありながら、なぜペソアは傍観者的であったのだと訴えています。(ペソアは貴族的軍事政権を支持していたが、サラザール政権の実情を知り、のちに撤回している)
ポルトガルの歴史を辿り、1910年に王政が崩されてから1917年までのブルジョワ階層による第一共和政、クーデターによる軍事政権、1932年からのサラザールによるファシズムなどを考慮すると抑圧と恐怖によって人々は盲目的にされていたことは想像に難くありません。こうした背景を持つポルトガル人作家ジョゼ・サラマーゴは体制に批判的な立場を貫いていました。
2021年の今現在、他国においても未だ、抑圧的な政治や情勢の不安定な国々が残されています。また、民主主義といえども、国家単位ではなく、ボーダレスな目には見えない支配が始まっているような錯覚を時々感じます。ビッグデータを扱う企業に、SNSなどで個人が喜んで様々な情報を無償で常にアップロードし、それらが各々のアルゴリズムでデータマイニングされ、勝手にトレンドが作り上げられてゆくことに、何の疑問も持たずに過ごしている時がありませんか?
そして、そうして作りあげられ続ける、そのトレンドに、時には感情まで入り込まれて、物事の「善/悪」の判断まで左右されかねないと危機感をたまに感じます。
目が見えているのではなく、真実を客観的に見ようとする事、見たいと思う事。そして、自分を見失わない、見失わされない事。
とても大事な事だなと再実感させられました。
目の見えないものにとって、名前は意味をなさない。聞こえてくるものが真実となる。
盲目的である現代社会への強烈な風刺の物語でした。
余談
2008年にブラインドネスというタイトルで映画化もされています。
本書の続編Ensaio sobre a Lucidez (見える事の試み)も刊行(未邦訳)されており、この物語の結末から4年後の舞台だそうです。邦訳されたら、ぜひ読んでみたいと思いました。
ジョゼ・サラマーゴ略歴
略歴といくつかの代表作
1922年11月16日
ポルトガル リスボンから100キロほど離れた村にて農家の息子として誕生
1975年
ジャーナリストとして活動していたが、政治事件により職を追われる。
1980年代
精力的に職業作家として活動し始める
1982年
修道院回想録
1986年
リカルド・レイスの死の年
1995年
白の闇
1996年
あらゆる名前
1997年
見知らぬ島への扉
1998年
ノーベル文学賞受賞
受賞理由
「想像、哀れみ、アイロニーを盛り込んだ寓話によって我々がとらえにくい現実を描いた」
2003年
複製された男
2004年
Ensaio sobre a Lucidez 本書の続編 未邦訳
2010年6月18日 86歳にて永眠
#白の闇
#ジョゼサラマーゴ
#河出文庫
#海外文学
#ポルトガル文学
#読書
#本
#読書好きな人と繋がりたい
#本好きな人と繋がりたい
#本の虫
いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。
