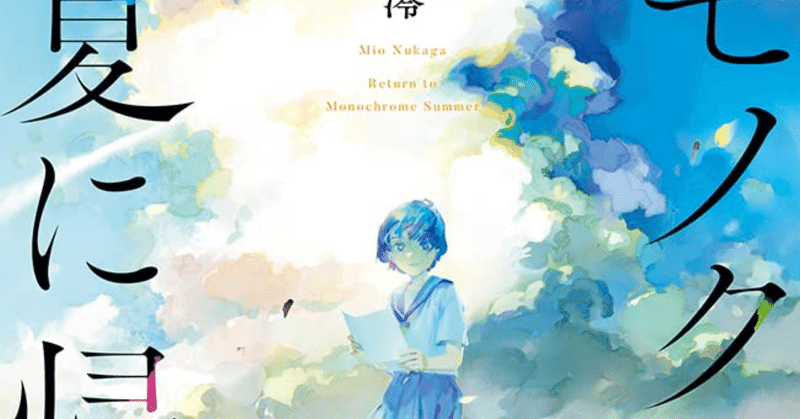
地続きの“歴史” モノクロの夏に帰る 額賀澪
海の向こうでは、戦争で毎日人が死んでいる。 でも遠くない将来日本からは、戦争を経験した人がいなくなる。 まだ若い僕たちは、この事実とどう向き合えばいいのだろう。 「僕は祖父の戦争体験を捏造したことがある」 戦時中のモノクロ写真をカラーにして掲載した『時をかける色彩』という写真集が刊行された。祖父母ですら戦争を知らない二十代の書店員がそれを店頭に並べたことで、やがて世界が変わり始める。保健室登校の中学生、ワーカホリックのテレビマン、アメリカから来た少年と、福島で生まれ育った高校生。遠い昔の話のはずだった「戦争」を近くに感じたとき、彼らの心は少しずつ動き出す。 平和を祈る気持ちが、小さな奇跡を呼ぶ。 読み終えたとき、少しだけ世界が優しく見える感動の青春小説。
一冊の写真集をきっかけに、様々な立場の人物たちが戦争というものを自分に引き寄せて考えるという連作短編集だ。各話の終わりに、そのエピソードにつながる戦時中の物語も語られている。
ここで取り上げられている戦争は、もちろん第二次大戦だ。この場合は太平洋戦争と言った方がいいかもしれない。
私の年齢だと、祖父母が戦争体験者だ。私の実家は何度も書いているとおり、田舎なので空襲もなかったし、食糧難もそれほどでもなかったと父方の祖母から聞いている。父方の祖父は徴兵されたものの、訓練中に肺炎を患って家に帰され、療養している間に終戦を迎えたそうだ。
母方の祖父は満州に送られたそうだが、詳しいことは話してくれなかった。
今はどうなのか知らないが、学校でもわりと平和教育的な授業があったようにも思うし、国語の教科書にも戦争文学が各学年に一つは載っていたように思う(一年生ではさすがになかったが)。幼稚園の絵本にも『おこりじぞう』や『ふたりのイーダ』などがあったんじゃないだろうか。対馬丸撃沈のアニメ映画を学校で見たような気がする。
私の母も戦争については知っておくべきだという考えの人だったので、戦争関連のTV番組をよく見させられた覚えがある。1番記憶に残っているのはNHKの『戦争を知っていますか』だ。夏休みの午前中にやっていたこの番組は、銃後にいた女性やまだ子供だった人たちの戦争体験を語る番組だ。スタジオにも子供がいて、質疑応答があったように思う。
正直、楽しい経験ではない。怖いし辛いし、聞きたくなかった。半ば強制的に見させられていたが、この中で一つ母に感謝しなくてはいけないのは、何を感じるか、何を考えるかを子供に丸投げしてくれたことだ。母は自分が何を思ってこうしたものを見せるのか、言わなかった。戦争というものを自分がどう考えているか、それも言わなかった。なぜ戦争というものが起きたのかという問いにも答えを明示しなかった。糸口になる番組や本を薦めたり一緒に見たり読んだりするだけだった。
母のそのスタンスのおかげで、右にも左にもよらず、比較的フラットな位置から戦争というものを学べたように思うので、このことには感謝しなくてはいけないと思う。
本の内容と関係ない思い出話が長くなってしまったが、こうした学びの体験が下敷きにあったため、本書に出てくる戦争体験者とも時間的な距離が離れてしまった世代の戦争というものの受け取り方を新鮮に読めたということがまず一つある。
どのくらいの年齢の子供達から祖父母も戦後世代になっているのだろうか。晩婚化が進んでいるので一概には言えないが、三世代同居の家庭も減っているし、戦争経験者から直接話を聞くという経験はもうないのかもしれない。戦争経験者でしかも当時18歳以上だったとなると、もう元気にしていらっしゃる方のほうが少ないだろう。あの戦争と地続きだった世代は減っていき、教科書の中の歴史になっていく。
そんな中でどうあの戦争を自分に引き寄せて考えるのか、今、日本が平和だというだけで、ウクライナを始め戦火の中にある国は今もあるのだ。それをどう考えるか、感じるか。
そのことが登場人物達を通して語られていく。
モノクロだった写真に、色がつくことで遠い昔の事に思われたことが少しこちらに近づいてくる。そしてその物語を描くのは、それぞれ少しずつ“普通”からはみ出している者たちだ。
祖父母から戦時中の話を聞いて作文を書けと言われたが、祖父は戦時中まだ3歳程度で何も覚えていないと言う。そこで様々な戦争関連の本を読んで祖父の体験を捏造した作文が賞を取ってしまい、両親にそのことが知れて叱られた経験を持つゲイの書店員が、写真集を推して欲しいと担当者から頼まれることから物語は始まる。彼は以前に推した本を話題書にした実績があるので、帯文もぜひ欲しいと言われるのだ。しかし彼は作文捏造の過去から、自分にそんな資格があるのかと悩み、それを書くことを躊躇うのだ。そんな彼の心を動かすのは、実は祖父にはわずかながら戦時中の思い出があったのではと思い始めたことと、ナチスのホロコーストの中でゲイもまたその対象だったということを知ったことだ。もしも、あの時代に自分がいたなら、ナチ統治下に生まれていたなら、生きることすら許されなかったのだ。家族にカミングアウトもせず、ひっそりとパートナーと暮らしているが、それすらもできない。差別よりももっと苛烈なもの。それを思った時、彼とあの戦争が少しつながる。
歳よりも聡明で大人びた考えを持つ少しひねたところのある中学生は、この写真集をきっかけに、同じ保健室登校でできた友人と地元の戦前と戦後の地図を比べる自由研究をすることになる。読書感想文もこの写真集で書き、賞を狙って内申を稼ぐのだとあっけらかんと語る。しかしそのうちに、自覚せずに自分が抱えていた鬱憤を知ることになる。そしてある出来事から、今も残っている戦火にあった地蔵を見にいくことで、崩れ落ちて焼け落ちてなおそこから立ち上がったものの力強さを知る。大人受けを狙って書いた感想文を捨てて、自分に引き寄せた感想を書き始める。
広島に生まれ、毎年原爆投下の日には登校して黙祷を捧げ、資料館にもたびたび連れて行かれ、語り部の話を聞き、平和教育を嫌と言うほど受けてきたが、どうにも馴染めなかったドキュメンタリー制作会社のディレクターの女性。終戦記念日の番組の企画出しも広島出身ならいいアイデアが出るだろうと言われうんざりしている。
しかし彼女もまた、この写真集に出会い、冷めた目で見ていた彼女と違って平和を考えるかつどうに熱心だった姉夫婦を通して、再び考え始めるにいたってまた彼女も戦争を自分に引き寄せる。押し付けられたものではなく、じぶんの頭で考えて番組を作ると決めるのだ。
日米ミックスで日本の高校に通う男子生徒は、文化祭でこの写真集のように戦時中の写真を集めてカラー化するという企画に今ひとつ乗り切れない。浮かないようにヘラヘラと誤魔化すように級友と付き合っていたツケがまわってきて、クラスの中心の女子に日本での戦争史観を押し付けられ、居心地の悪い思いをしている。そんな時に逃げ込んだ図書室で、同じクラスでその文化祭の企画をサボっている男子と少しずつ仲良くなっていく。また家では母と話し、少しずつ自分の抱えている違和感や憤りに気づいていく。対象的な2人の間にあった出来事を知り、自分の考えを話すことがやっとできるようになっていくのだ。
どの物語も、遠い出来事であった“戦争”というものを引き寄せてくることで、自身の抱えているものと向き合い、どう生きていくか、どう考えていくか、に気づくということが描かれているのだが、この中に政治的なものや思想的なものはほとんど入れ込まれていない。
だからこそ、彼らの変化をより瑞々しく感じられるように思う。ここで語られているのは、戦争はしてはいけない、平和を守ろうというテンプレートではない。
時が過ぎることは誰にも止められない。何をどうしたって過去の出来事は遠ざかっていき、“歴史”になっていくのだ。しかしその時、借り物の言葉でなく語り繋いでいくにはどうすればいいのか。紙の中にあるだけの“歴史”ではなく、その時に生きていた人達と地続きで今があると感じるためには何ができるのか。そのことを問うているのだ。
そしてなぜあの戦争をただの“歴史”にしてしまってはならないのか、という問いも含まれている。
4話目のミックスの生徒が、911をアメリカで経験し、戦争はなくなったりしていない、今だって平和じゃない、戦争をしていなかったことなんて第二次大戦以降もない、と感じているとおり、どうにかこうにか平和を満喫して戦争が“歴史”になりかかっているのは日本ぐらいなのだ。彼がクラスメートがいうペラペラな「戦争はいけない」「平和を守らなくてはいけない」というテンプレートに苛立ちを覚えるのは当たり前のことなのだ。
戦争というものは捉えるのが難しい。なぜ日本は戦争へと進んだのか、なぜ今も戦争は起こり続けるのか。
立ち位置が少し変わるごとに見えるものが変わってくる。右にも左にもよらず、フラットにこのことを説明することは困難だ。
それでも、変わらないことは、“戦争は、してはならない”ということだ。そしてこの言葉をテンプレートの薄い言葉にしないために、あの時代と地続きでなければならないのだ。
書店員が書き上げたPOPの言葉の力強さが胸に残る。
綺麗事だとしても、言い続けなくてはならない言葉がある。そしてそこに、その言葉を口にする自身の実感という肉付けがなければならない。
それを得るための“学ぶ”ということの深さを感じるのだ。勉強として学ぶのではなく、何かを知り、思い、惑いながら得る学び。
知る、感じる、学ぶ。押し付けられたものではなく、与えられただけのものではなく、自分のものとして考える力を得た上での言葉の持つ力がそこにある。
現代史を多少でも学校の勉強よりも深掘りしたことのある人には物足りない内容かもしれない。爽やかな書き口を軽いと感じる人もいるかもしれない。が、この物語は戦争を学ぶためのものではなく、そこへつながる糸口なのだ。
あの時代を生きた人たちを感じる、そのことから始まる戦争というものの捉え方があってもいい。小難しく考えて、左右どちらかの考えに偏るのでもなく、ただ、あの時代を生きた人へ思いをはせ、その時代と自分たちが繋がっていることを感じる。教科書の“歴史”になりかかっているものをそう感じることは簡単ではない。
それを感じることができた彼らはきっと、これからも考えることを放棄しないだろうし、知ることを大切にしていくだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
