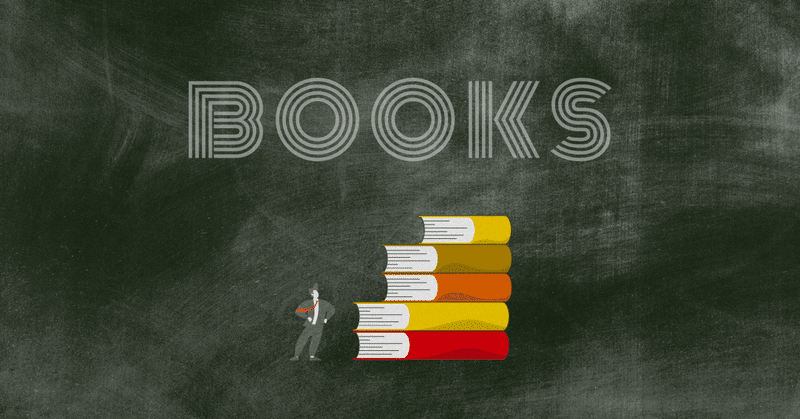
2023年の読書。
今年読んだ小説(初読みに限る)の中で、印象的だったものを読んだのが近い順に紹介していきます。詳しい内容を忘れているものもあるので、その時の読了ツイートを添えておきます。
マルドロールの歌 ロートレアモン伯爵
BOOKOFFの100円コーナーで見つけて、どこかで名前だけは知っていたので購入した本。(あとでギュヨタ『エデン・エデン・エデン』の解説だったことが分かった。)ジャンルで言えば散文詩で、初めての読書体験だった。残酷だったり狂気に満ちたイメージが並んでいて、一読して理解は出来なかったが、読んでいて不思議と活力が湧いてきた。読んだのは集英社文庫の前川嘉男訳で、他の訳も読んでみたいと思い、ちくま文庫の『ロートレアモン全集』(石井洋二郎訳)も後日BOOKOFFで購入した。
ロートレアモン伯爵『マルドロールの歌』読了。パワフルで破壊力抜群の文章。幻想的だったり悪夢的だったりするイメージの連なり。正直理解することは出来ないが、読んでいて楽しいし、不思議と活力が湧く。他の翻訳でも読んでみたい。#読了
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) October 29, 2023
シンプルな情熱 アニー・エルノー
2022年のノーベル文学賞を受賞した作家で、たまたま見つけたので何の気なしに購入し読んだら、物凄く面白かった。妻のある男を愛する女の心情が書かれているのだけれど、その細かさと豊かさには感服するしかなかった。普通の恋愛小説とは違った書かれ方で、それもある種勉強になった。
アニー・エルノー『シンプルな情熱』読了。のめり込んで一気に読んでしまった。著者の自伝的作品で、妻帯者の男に対しての生々しいほどの《情熱》がつぶさに描かれる。後半では何故この《情熱》を綴るのかと、書くこと自体を自問する重層的な構造になっている。いつかの恋愛を思い出したりした。#読了
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) October 16, 2023
タタール人の砂漠 ディーノ・ブッツァーティ
名前だけは知っていて、友人から面白いと紹介されて読んだ本。国境沿いのはずれにある砦に配備された若き主人公。その砦は戦局上あまり重要視されることもなく、何も起こらないと言われながら、それでも何かを待ち続けてしまう。残酷な結果を伴う大人の寓話とでもいう小説。
ブッツァーティ『タタール人の砂漠』読了。砦の警備に配属させられた若き中尉。いつ敵が攻めてくるかも分からぬ砂漠を前に、ただそれだけを望みながら単調な日々を繰り返していく。何か起こるのではないかという期待と、そして残酷なまでに費やされた時間。物凄く意地悪な展開に笑ってしまった。#読了
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) September 23, 2023
年老いた司令官が敵襲かも?って時に、周りはざわめいているけど、自身はその期待に何度も裏切られてきたから最後まで飲み込めないってのがなんかリアルだなって思った。
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) September 23, 2023
さかしま ジョリス=カルル・ユイスマンス
読んでみたいと思いながらも、少し難しそうなイメージがあったが、ウエルベックの『服従』を読み、その主人公がユイスマンスの研究者であったことから興味が湧いて手に取った。『さかしま』のなかで言われている哲学や思想は難しい部分もあったが、金持ちのインテリ引きこもりが自分の思う世界を家の中で構築していくさまが面白かった。旅に出ようと決意し、少しは足を伸ばすのだが、途中で嫌になって帰ってくる場面が好きだった。
ユイスマンス『さかしま』読了。面白かった。都会を離れ、ただ一人の世界に浸るデ・ゼッサント。自らの思想、哲学によるもので作られたある種の楽園のなかで滔々と語られる芸術論。小難しくもあったが彼の言葉の奔流に巻き込まれるが如く読めた。旅に出たけど途中で冷めて帰ってくるとこ好き。#読了
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) September 13, 2023
無数の註釈があるように、膨大な情報量が詰め込まれている。宗教から絵画、文学、音楽とさまざま。ちょっとした百科事典のよう。
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) September 13, 2023
プラットフォーム ミシェル・ウエルベック
久しぶりにウエルベックでも読もうと思って買った本。内容がタイへの売春ツアーを企画するというたいへんスキャンダラスな話。さえない主人公の前になぜか彼と良い感じになってくれる美女が現れるのはいつものことだが、現代社会のいわゆる性愛が行きついてしまった壁、そこにある虚無を上手く書いていて、小説に打ちのめされるとはこういうことかと思った。
ウエルベック『プラットフォーム』読了。またしてもウエルベックに打ちのめされた。売春ツアーという大胆なテーマのなかに、現代の虚無と行き場の無い欲望の最後のはけ口を見る。果たして幸福はどこにあるのか。性愛でしか埋められないものもある。#読了
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) August 9, 2023
少将滋幹の母 谷崎潤一郎
五月くらいに個人的谷崎ブームが来て、その流れでまだ読んでない谷崎を読んで行こうと思って手に取った。谷崎の作品群の中でも、私が好きなのは『痴人の愛』や『春琴抄』と言った耽美でマゾヒズム的なものが多く、平安時代を舞台にした小説とあってわざと避けていた感じはあったのだが、この機に読んで本当に良かったと思った。喜劇チックな話の導入から、最後の美しい場面に読者を持って行く谷崎の手腕が凄い。
谷崎潤一郎『少将滋幹の母』読了。平安期の古典を題材としていて取っ付きにくいと思っていたが意外とそうではなく、北の方という女性を巡る滑稽とも言える恋愛譚、そして母への慕情を鮮やかに描いている。幻想の中で女性を想うと言うのが「春琴抄」と通じていて、両者で書き方が違うのも面白い。#読了
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) June 25, 2023
幼い頃に母を奪われた滋幹とその母である北の方との関係、さらに若き妻の北の方を奪われた老いた国経が彼女への強烈な想いで苦悩するさまが物語の主軸となってくるが、小説は彼らに関わる人物の挿話から始まり、それらも群像劇的に書かれるので、小説全体の細かなところにも気を配っている印象。
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) June 25, 2023
幼き滋幹と国経が夜な夜な話する奇怪な場面の鋭さと、大人になった滋幹が桜の樹の下で迎えるラストシーンの幻想的な美しさの対比がとても良くて、それもあってかラストシーンは感動した。
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) June 25, 2023
神曲 地獄篇 ダンテ・アリギエーリ
このあと紹介する『懐かしい年への手紙』の中で、大きく引用されていたので気になって読んでみたのと、私の好きな映画「ハウス・ジャック・ビルド」で主人公が最後行く場所がまさに地獄篇の世界なので、今年手に取ってみた。読んだのは河出文庫の平川祐弘訳で、これは訳文も平易な文章で注釈も多く、とても助かった。ダンテとウェルギリウスの師弟関係が一種のバディものにも思えてきて面白かった。
ダンテ『神曲 地獄篇』読了。ダンテはウェルギリウスに導かれ地獄巡りへ向かう。地獄は九つの階層に分かれていて、罪によって行き先と刑罰が違う。刑罰は惨たらしくもあり、その多様さに驚く。註釈も充実してたが、キリスト教はもちろん、古代ギリシアやローマの知識があると、なお楽しいかも。#読了
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) May 3, 2023
河出文庫で読んだが、翻訳も平易な言葉なので読みやすく、挿し絵もあって良かった。最下層の第九の圏谷は「裏切り」を犯した者が罰せられてるのだが、ジュネが『泥棒日記』で裏切りを美徳としてた理由ってこれなのかとか思った。
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) May 3, 2023
懐かしい年への手紙 大江健三郎
今年三月に大江健三郎が亡くなり、哀悼ということでもないが『万延元年のフットボール』を読み返した流れで手に入れて読んだ。以前に『燃え上がる緑の木』を読み始めたが挫折し、それが『懐かしい年への手紙』の後日談であると聞いて、これを先に読まなければと思った。これを書いた時点での大江健三郎の集大成とでも言えるような内容で、過去の小説に触れて添削したり、それでも未来へ書き続ける意志が最後に見られて、とても良かった。
大江健三郎『懐かしい年への手紙』読了。作家である「僕」と「ギー兄さん」との交流を通じて、虚実入り混じってはいるとは思うが、この小説が書かれた時点での、大江健三郎が大江健三郎である所以がよく分かるというか、その当時の現在地と、それから未来を見据えたラストが心地よかった。#読了
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) April 15, 2023
イェーツやダンテの引用が難しかったけど、著者の『懐かしい年への手紙』以前の著作をいくつか読んでいたので、そこへの言及とか、「万延元年のフットボール」の逆説的なプロットの引用とかあって、その辺りは楽しく読めた。
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) April 15, 2023
「根を下ろす」という言葉があるけど、「僕」も「ギー兄さん」も、それぞれの存在が一本の樹木のようなイメージがあって、二人がどこに「根を下ろし」て生きていくのか。一方は東京に居を構え作家として生き、一方は谷間の村の森にある種の理想郷を作ろうとした。
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) April 15, 2023
ウォーク・ドント・ラン―村上龍vs村上春樹
三月に珍しく図書館へ行き、蔵書の中から見つけたので読んだ。流通している古本は高価になっていて、なかなか手が出せなかったので助かった。村上龍が『コインロッカー・ベイビーズ』を出した前後くらいの時期に行われた対談をまとめたもので、小説のことに限らず、映画や音楽についても話がされている。今年両者が新刊を上梓したが、世間的な反応は春樹に大きく傾いていて、龍ファンの私としては少々寂しい部分もある。
『ウォーク・ドント・ラン―村上龍vs村上春樹』読了。1980年に行われた2回の対談をまとめた本。小説やらジャズやら同時代的なことやら。話が噛み合ってたり、いなかったり。やはり龍はジュネ激推しで、一方春樹は読んだけど覚えてないらしい。図書館にて読みたかった本が読めた。#読了
— 鋤名彦名a.k.a.燦州ポポポ呪師 (@book_dividual) February 28, 2023
いかがでしょうか。気になるものがあったら、ぜひ読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
