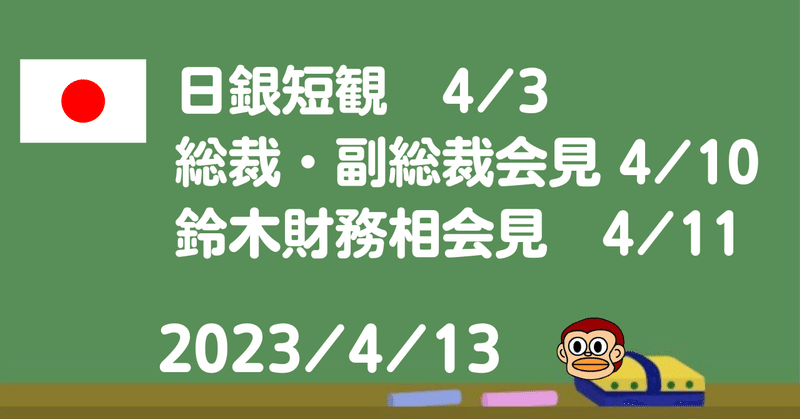
2023/4/13 日銀短観、日銀総裁・副総裁記者会見、鈴木財務相会見
⭕ 4/3に公表された「日銀短観」、4/10の「日銀総裁・副総裁記者会見」、4/11「鈴木財務大臣会見」を簡単にまとめてみました。
① 日銀短観 4/3
✅ 日本の景気はどうでしょうか?企業へのアンケートで日本経済の先行きを予測してみましょう。数値と表しか出ていないので、人によって意見は様々だと思いますが、概ねの景況感は知る事が出来ると思います。
1. 業況判断
製造業の景況感は低下気味、非製造業(サービス業)はコロナ明けの影響が大きいと感じられ上昇基調。

2. 価格判断
価格はまだ上昇する、せざるを得ない、と思えます。直近の消費者物価指数は+3.3%、生産者物価指数は+7.2%。数値だけを見れば、ピークアウトしたと捉える企業担当者は多く、ディスインフレに向かっている。

3. 売上高判断
売上高成長率は前年より大幅に鈍化予測、全規模合計で前年比+1.1%。インフレが一周した事も大きい。

4. 雇用人員判断
全体的に人手不足、特にサービス業、飲食、宿泊など新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込んだ業種が、今春のコロナ明けと共に人手不足となっています。

日銀短観とは、日本銀行が年4回(3、6、9、12月)、景気の現状と先行きについて企業に直接アンケート調査をし、その集計結果や分析結果をもとに日本の経済を観測するもので、正式には「企業短期経済観測調査」といいます。
調査では全国の大手企業と中小企業、製造業と非製造業などで分けて、約1万社以上を対象に、業績や状況、設備投資の状況、雇用などについて実績と今後の見通しを聞きます。短観は回収率が高く、調査の翌月に公表(12月調査のみ当月に公表)されることが特徴で、この結果は景気動向を占ううえで重要な経済指数となっています。
② 日銀総裁・副総裁就任記者会見 4/10
✅ 4/10 19:15から日銀総裁・副総裁就任記者会見がありました。結論として金融政策は現状維持ですが、植田新総裁の基本指針となるような回答を抜粋してみました。
⭕ 物価の安定と金融システムの安定の実現に向けて尽力する。
(植田総裁)
この度、日本銀行総裁を拝命しました植田でございます。日本銀行の 5 千人の役職 員と力を合わせて、日本銀行の使命である物価の安定と金融システムの安定の実現に向け、力を尽くしてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。
⭕ 欧米の銀行破綻が日本経済に大きな影響を与える事は今の所無い。
(問)
2 月の国会での所信聴取後の経済の大きな動きとし て、欧米での金融不安があります。アメリカの中堅銀行の破綻やスイス大手銀行の 救済などが相次ぎましたが、日本経済への影響をどうみているか、金融環境は不安定さが残っていますが、日銀として取るべき対応をどのように考えているか、ご見 解を教えて頂けたらと思います。
(植田総裁)
欧米の金融不安の 日本経済への影響いかんというご質問だったと思います。これについては、3 月中 旬以降ですか、アメリカ・ヨーロッパで、一部の金融機関の経営問題を背景に、不安感が広がる動きがみられたわけですけれども、各国当局が迅速な対応をしたこと、 それもあって個別先の問題であるという認識が広がったということで、市場は落ち 着きを取り戻しつつあるというふうにみております。日本の経済、日本の金融シス テムへの影響ですけれども、日本の金融環境、依然として非常に緩和的な状態が続 いているということ、それから日本の金融機関が、充実した資本それから十分な流動性を備えているということを考えますと、金融仲介機能は今後も円滑に発揮され ていくというふうに評価しております。従って、現時点でこの問題がわが国経済に大きな影響を与えるというふうにはみておりません。この間、日本銀行と米欧の中 銀が協調して、米ドルの資金供給オペの実施頻度を引き上げるような対応も行って おります。ただ、市場における不透明感・不安感が完全に払拭されたという状態で はないと考えておりますので、今後の状況についてしっかりと注意してまいりたい というふうに思っております。
⭕ 現行のYCCを継続するのが適当であると考えている。
(問)
異次元緩和を支えている長短金利操作、YCCについて伺います。国会でもご答弁 されていますけれども、その効能、必要性、副作用について、どのようにお考えで しょうか。もう一点ですね、市場ではこのYCCについて、早い段階で修正するこ ともあり得るのではといった観測もあります。どのような状況になれば修正といっ たことが選択肢に上がるのか、お話できる範囲でこのお考えについて伺えますでし ょうか。お三方に伺います。
(植田総裁)
まず私から、長短金利操作についてということだと思いますが、市場機能への影響 という意味では、日本銀行は昨年来、国債の補完供給の制度を柔軟に運用している ということ、あるいは昨年 12 月に長期金利の変動幅を拡大したような措置、更にこ このところ一か月くらいですかね、先ほどお話に出ましたような金融システムに対するストレスの問題の結果もあって、海外金利が低下したという中で、イールドカ ーブの形状は総じて前よりもスムーズになってきているという認識でおります。こ うしたこれまでの措置の効果とか、市場の動向については、今後も見極めていく必 要があるというふうに考えています。ただそのうえでイールドカーブ・コントロー ルは、市場機能に配慮しつつ、現状では経済にとって最も適切と考えられるイール ドカーブの形成を実現するための仕組みです。現状の経済・物価・金融情勢にかん がみると、現行のYCCを継続するということが適当であるというふうに考えております。
⭕ 2%の物価目標を 10 年で達成できなかった要因は、物価や賃金が上がらないということを前提にした物価や賃金の設定行動あるいは企業行動が広まってしまっていた事が大きかった。
(問)
総裁に伺います。2%の物価目標を 10 年で達成できなかった要因をどうみていらっ しゃるのでしょうか。また、今後達成するに当たっての最大のハードルと、目標達 成は金融政策だけでできるのか、そうでないとすればどういったことが必要なのか も教えてください。
(植田総裁)
10 年で達成できなかった理由でございますけれども、それについては一つ前のご質 問に対する答えで二つくらい申し上げたかと思いますけれども、達成を難しくする ような外的なショックの存在というのが大きかったというのが一つでございます。 詳しく申し上げれば、90 年代の不良債権問題から始まって、それは 10 年の話より前 になってしまいますが、足を引っ張るような外的ショックは大きなものがいくつか あったということが一つでございます。それから通常であれば金利の引き下げ余地 がかなりあるというはずなのに、ゼロに近いところから始めたということで、引き 下げ余地があまりない中での金融緩和政策であった過去 10 年、この二つは大きかっ たと思います。それから、これは黒田前総裁もよく言われていたことですが、デフ レあるいはゼロインフレに近い状況は長く続けば続くという中で、物価や賃金が上 がらないということを前提にした物価や賃金の設定行動あるいは企業行動が広まっ てしまって、それ自体が次に物価や賃金が上がりにくくするという結果に残念なが らなってしまったということも大きかったかなというふうに思っております。
⭕ 金利操作、ETFの購入については、たまたま副作用が目立っているからというだけで、それの導入がまずか ったという結論にはならないのかなと思います。
(問)
長期金利操作とETFの買入れについてです。総裁、所信表明でイール ドカーブ・コントロールについて様々な副作用を生じさせているという面は否定で きない、ETFについては大量に買ったものを今後どういうふうにしていくのかは 大問題とおっしゃっています。現在導入している以上、すぐに出口を探すのは難し いと思うのですが、いずれの政策も導入したこと自体適切だったのでしょうか。総 裁のご見解をお聞かせください。
(植田総裁)
金利操作、ETFの購入ですか、これについておっし ゃるように副作用、私はある、あるいはあったかというふうに考えてございます。 そのうえで、そういう副作用のあるような政策をそもそも導入したことは良かった のかどうかというご質問だったと思いますけれども、その点については、おそらく、 それぞれ導入した時点で私はボードメンバーではなかったのであれですけれども、 効果と副作用について十分考慮し、議論されたうえで導入されたのだと思います。 ですので、たまたま副作用が目立っているからというだけで、それの導入がまずか ったという結論にはならないのかなと思います。
③ 鈴木財務相会見 4/11
✅ 植田日銀体制のスタート後、初の鈴木財務相の会見ですが、緊縮財政の強化と捉えられる発言が見られます。景気後退の引き金となるでしょうか?
⭕ 政府としては日銀が国債を買い入れるとの前提に立った財政運営を行うことが適切とは考えておりません。
⭕ 今後とも財政健全化に向けて、プライマリーバランスを2025年度に黒字化すること。
景気対策縮小、増税の匂いがとても漂っています。
問)
日銀の植田新総裁の体制がスタートしたことに絡んで金融政策による財政への影響について伺いたいと思います。
答)
一般論でしかちょっとお答えできないと思うんですが、一般論で申し上げますと金利が上昇すれば利払い費が増加するおそれがありますが、一方、金融政策が財政に与える影響は様々であるために、一概にお答えすることは難しいと思っております。
また、金融政策の具体的な手法につきましては日銀に委ねられるべきと、そのように考えておりまして、どういった金融政策が財政的な観点から望ましいかといった点について我々の立場からお答えすることは差し控えなければならないと思っております。
いずれにいたしましても、政府としては日銀が国債を買い入れるとの前提に立った財政運営を行うことが適切とは考えておりません。また、市場からそのような疑いを持たれ、市場の信認を失うような事態を招くことがないようにしていく必要があると、そういうふうに考えます。
このため、政府としては、今後とも財政健全化に向けて、プライマリーバランスを2025年度に黒字化することなどの方針のもと、引き続き、責任のある経済財政運営に努めていかなければならないと、そのように考えております。
④ まとめ
⭕ 日銀短観から読み取れる景況感としてサービス業、特に飲食や宿泊の売上増と人手不足による賃金の上昇が予測される。全規模として、成長率は鈍化傾向を日本企業は織り込んでいる。
⭕ 日銀総裁・副総裁の会見は「具体的にどうする」という発言は無く、粛々と市場の混乱も誘わず終わった印象でした。一番の焦点は「イールドカーブコントロール」の見直し検討があるかどうかでしたが、現状維持を貫いた形になりました。5/8、新体制初の金融政策会合に注目。
⭕ 財務省が以前から主張している、財政健全化、プライマリーバランスの黒字化を今回も発言しています。国債の発行に消極的で、政府日銀連合軍の解体ともとれる発言もあり、実質的に景気対策は縮小すると思われる。需要が強すぎるのであれば、正しい選択だと思いますが、2023年度予算の予備費も4兆円と需給ギャップを埋めるには少なく、GDP成長率は鈍化する予想がつき、日経株価も低迷するのではと感じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
