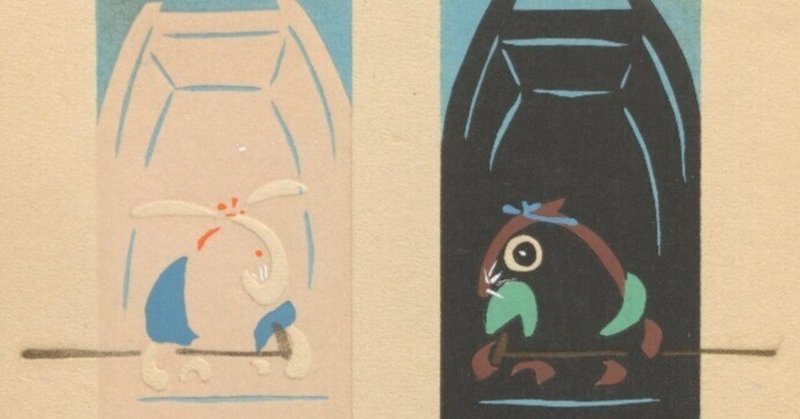
読む習慣を身につけるのに図書館が適切な理由
図書館に通うようになってから本を読む習慣が身についた。
図書館シリーズのアウトプットを書こうと思っての第二弾を試みる。
前回は、図書館にそもそも行くことや住むことやきっかけに借り方を簡単に説明した。また、カーリルなる便利なサイトがあり、欲しいものリストならぬ借りたいリストを整える案内をした。
あとは借りるだけだ。
そもそも何を読めばいいのか
さて、ここでいきなり問題なのが読んだことも借りたことも習慣として持っていない場合は、そもそも何を借りればいいのかとなる。そのために借りたいリストなるカーリルの存在を伝えたわけだが、何を読めばいいのか。
この何を読めばいいのかは結局のところ、自分がどうありたいかというアイデンティティや生き方といった話になる。手に取りたい。欲しい。気になる。この辺りはインプット習慣でありアンテナ作り次第となる。
私は、仕事の課題をきっかけに本を探したタイミングで本屋に出会い図書館を使うといった順序だった。ネットでも新聞でもテレビでもニュースでもなんもいいが入り口がどこかにあるはずだ。
そうやって、きっかけの記憶やメモを片手に図書館を練り歩けば自然と欲しい本は見つかるはずだと思う。Amazonのレビューを参考にしたり、本屋の売れ筋をチェックするのもいいだろう。技術書でもなんでもいい。
Amazonのほしい物リストをのぞくのもいいだろう。買おうと思って躊躇していた本のリストも見つかるはずだ。必ずどこかで、何かのきっかけで本を読もうとした痕跡はどこかに残ってるはずだ。
その中から、まずは読みたい一冊を見つければいい。
読む一冊が決まりさえすれば関連書籍を読めばいい
図書館の活用で何がいいのか。借りるよさは何かというと、一冊の本に出会えたらあとは芋蔓式に欲しい本に出会える点だ。一冊の本から、知りたい情報に加えて、知らない単語やキーワードが目につくものだ。
そのキーワードをネットで検索したり、それこそAmazonで検索するとまた欲しい本が見つかる。そしてまたカーリルのリストに突っ込んでを繰り返せばいい。つまり図書館で延々と借り続けるループが産まれる。
私の最近の場合だと、初めは簡単なリーダーシップ論のお話を読んでいると、巻末の参考書籍が気になってくる。次に、組織行動論や社会心理学といった専門書やその初心者向け本を手にするようになる。
これはその本のその本のその本の書いていることをと延々として、キーワードだけでも図書館でとりあえず借りるを繰り返してれば自然と読むたい本が積み重なっていく。中身が全くわからないタイトルチェックだけでもいい。
ちゃんと読む本を決めたい場合はレビューなり目次なりをしっかり読めばいい。なお、欲しい本の検索方法は図書館の流儀に沿えば、NDCやらOPACとなるが、今時はネット検索で初めの頃は大丈夫。図書館でも紹介している。
借りた本を必ず全部読まなくてもいい
図書館で借りた本は2週間もすれば返さなければいけない。
返さなければいけないが、読まなければいけないではない。読まなくてもいい。ちょっとだけ読むだけでもいい。それこそ目次だけ見たってかまわない。本を読むこと自体は別にはじめから最後まで全部読む必要もない。
この辺りは読む習慣によって人それぞれとなるが、それぐらいスナック感覚で借りてちょっと読んで返しちゃおうぐらいのハードルで本は読んでいいと思う。それこそ図書館ならなおさらで、借りているだけなのだ。
読み方については、定番の独学大全の目次の「第12章 読む」にあるように、いろんな読み方を試してみればいい。そもそもこの独学大全から借り始めるのもいいかもしれない。
借りた期間の間でなんとか読もうとするのか。計画を立てて読むのか。気になる章だけ読むのか。けっこう分厚い本なので、あえて読み切らなくてもいい本(本当は全部読むと楽しいけど)として手に取るのありかもしれない。
借りた本を必ず返すという習慣がまずは身に付く
これで借りて返すという習慣が身に付くようになるはずだ。
1ヶ月も続ければ、二週間いっぱいいっぱい一冊だけ借りたとしても二冊の本を月に読むことができるようになる。なお、借りたい本は予約がいっぱいなので、じゃこれも先に借りとくかと自然とストックが溜まってくる。
気がつけば、最近はメール通知などの機能が基本なので、借りたい本の予約ができたとの通知も来る。その通知をきっかけに借りるついでに返すというループが産まれるようになる。
そして、ついでに最近だと運動するという名目で散歩がてらに行くのもいい。遠い場合はわざわざになるが、このわざわざも健康につながる。わざわざ借りて返す。
そのうち、一度も読んでないけど期限だから返さなければなんてことも起きてくる。図書館を使い倒す手前でもそれだけの体験をするようになる。まずはこれで、読む習慣の前に通う習慣ができるようになる。
あとは回数なので、図書館の本を見るようになったり、その日返した本なんてあるんだと発見したり、そもそも図書館の使い方を知るようになるはずだ。
ちなみに次借りたい人がいなければ延長することも可能だ。これは図書館のある市区町村によるのだが一週間だったり二週間だったりする。つまり、一ヶ月借りることができる場合もある。
次こそは図書館インプットからのアウトプットの話をする
次回は、この辺りを工夫して仕組みにしている点を補足してインプットから次はアウトプットに繋げる方法を紹介したい。
図書館で本を借りるなら図書館の近くに住んでカーリルを使おう
このように書いたけど、やはりまだまだあれもこれもと思いついたまま書きたいことがたくさんである。次回に続くというか、延々と頭に思いついたことをこのシリーズに関しては書き続けていくことになりそうだ。
ちなみに次話したいことは、ブクログや読書メーターを通じて読んだ記録を身につける習慣の話をしたい。一番小さなアウトプットはメモにあると見ている。
引用画像:https://dl.ndl.go.jp/api/iiif/12864477/R0000010/952,2018,2720,2504/,766/0/default.jpg
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
