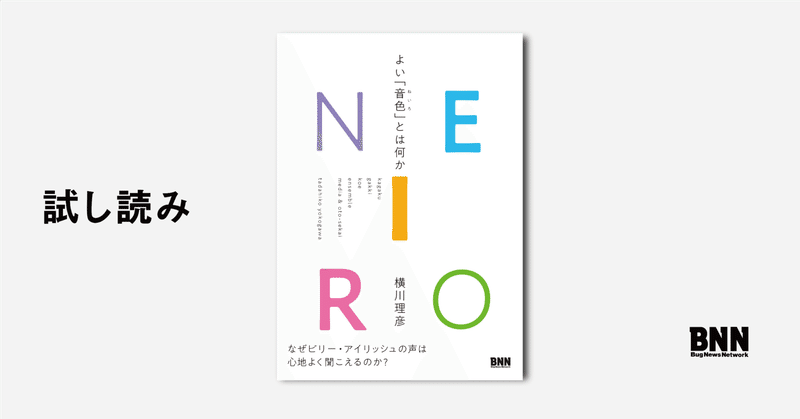
試し読み:『NEIRO よい「音色」とは何か』
2024年3月に刊行した『NEIRO よい「音色」とは何か』(横川理彦 著)。「はじめに」と、第3章「声の音色」から「声の仕組みと言語」のパートをご紹介します。演奏すること、聞くこと、音楽全般に興味がある方々に、ぜひご一読いただきたい一冊です。
※横川理彦氏の前著『サウンドプロダクション入門 DAWの基礎と実践』の試し読みはこちら。
はじめに
「音色」について考えてみましょう。
音楽を聞いていると、「いい音だなあ」とか「この声が好き」と感じることがあります。この「いい」とか「好き」と思う音楽の実態が「音色」(英語だと「timbre」)です。「ビリー・アイリッシュの声が好き」というとき、ほかの人とは違うビリー・アイリッシュの声の音色を聞き分けて、それに惹かれているわけです。
それを説明するには、音色というものが科学的にどういう仕組みになっているのか。楽器や声はどんな特徴を持っていて、どのように使われてきたのか、などを見ていく必要があります。
この本では、これらの事柄を順番に分析していきます。分析の道具として、DAWを使い、音が画像化された例も確認できるようにしました。DAW(Digital Audio Workstation)とは音楽制作用のソフトウェアです。また具体例には、YouTubeやSpotifyのリンクを掲載しました。
第1章は「音色の科学」として、科学的に音色を分析する方法を説明します。「音」を科学で記述するならば、「周波数の時間変化」と定義づけることができます。周波数というのはどういうことか、それが時間的に変化すると何が起こるのか、ということですね。先に結論を書いておくと、楽音(音楽で使われる音)を分析するときに、音の立ち上がり(アタック)と音の持続部分(サステイン)を区別し、それぞれがどのような変化をするのかを見るとわかりやすい、ということです。
第2章は「楽器の音色」です。楽器の音を「打つ」「擦る」「吹く」「弾く」「電気を使う」の5種類に分け、それぞれの特徴を見ます。シンセサイザー、サンプリングといったコンピュータの手法も併用して、パーカッション、バイオリン、サックス、ピアノ、エレキギターなどの楽音の仕組みや成り立ちを一つ一つ分析するのと同時に、その楽器の名演奏家の音色の特徴も探ってみます。
第3章は「声の音色」です。楽器の中でも、「声」は特別です。歌は歌詞を伴って意味を伝えるので、ほかの楽器とは異なるたくさんの論点を持っているのです。現在のポピュラー音楽はコンピュータで作られるようになりましたが、大抵のヒットソングは相変わらず人が歌っています。他方、「初音ミク」のようなバーチャルシンガーも急速に広がり、今のAIの発達を見ていると、将来はシンガーのキャラクターもコンピュータで合成することが当たり前になるでしょう。
第4章は「アンサンブルの音色」です。音楽は複数の楽器で合奏するアンサンブルの形を取ることが多く、その音色は楽器単体のものとは随分違います。また、音楽ジャンル(クラシックとかジャズとか)によって、同じ楽器でも演奏法・音色が違うことも見ていきます。
第5章は、「メディアの音色と、音世界全体」について。あわせて、従来の音楽とは異なる音の捉え方をしているいくつかのジャンルについても解説しています。
第3章 声の音色
楽器の中でも、人間の歌は特別な位置を占めています。生まれてから最初に経験する楽器であることと、歌詞で意味を伝えることから、コミュニケーションでの優先順位が高いです。
音楽を聞いている時に人の声が入ると、途端に一般の聴取者の注意は歌に集中します(ギタリストは、しばしば歌を聞かずにギターを聞きますが)。ですから、音楽の種類を大きく2つに分けるなら、歌曲(ソング)と器楽曲(インストゥルメンタル)ということになるでしょう。このように人にとっての重要度が高いので、本書ではまるまる1章を声の音色に充てることにしました。
歌のあり方もほかの楽器と同じく、録音物を再生利用するメディアの発達で、随分変わってきました。最近の大きな変化は、何といっても人工の音声合成技術が発達したことです。ボーカロイド(初音ミクなど)や「Synthesizer V」といったコンピュータソフトで説得力のある歌が披露されるようになり、人間が音楽を演奏する最後の牙城と思われた歌声にも、AIの波が押し寄せています。
声の仕組みと言語
人間が言葉を話すようになった歴史的起源には、直立歩行により咽頭の位置が安定し、多様な音を発生させやすくなったことが大きな要因だといわれています。
人間の体から声が出る仕組みを解剖学的に見ると、まず肺から出る息で声帯(木管楽器でいえばダブルリード)を振動させます。声帯から出る声の元の音は三角波で、これを喉・口・鼻に共鳴させることで、様々な音色を作っていきます。
言葉には母音と子音があります。母音(a・i・u・e・o)と、子音のうちの有声音(b・d・g・v・z・m・n・l・r)は声帯を振動させ、子音のうちの無声音(破裂音p・t・kや摩擦音f・s・hなど)は声帯を振動させません。
子供は親や家族などの発音を真似て喉・口・鼻の使い方を学習し、言葉を覚えていきます。外国語学習においても、ネイティブスピーカーの発音を体得することが重要事項で、母音と子音の数や区分は言語によって随分違うために、母国語の発音のままでは発音の違う外国語は意味が通じません。
英語の発音を説明する動画。
『【英語耳】10分で分かる英語の子音と母音のすべて【発音】』
また、音節言語(「yesterday」は「yes・ter・day」の3音節)か、モーラ言語(日本語だと仮名一文字が一単位「きのう」は「き・の・う」の3単位)かの違いも歌に大きく影響します*。
*音声と歌詞については木石岳『歌詞のサウンドテクスチャー:うたをめぐる音声詞学論考』(白水社)が詳しく刺激的だ。
中国語と英語は共に音節言語です。リズミックなロックやヒップホップのスタイルをモーラ言語の日本人が真似るときに漢字熟語をよく使うのは、その発音が中国由来で子音を含んだ音節として英語と似た響きになるからです。「くに」は「く・に」の区分けですが、「国家」は「こっ・か」となって、「cock」の2音節(co・ck)に近くなります。
また人間の歌には、歌詞に意味があるものと、意味のない音だけのものがあります。最近のポップソングでも、歌詞の一部分が「ラ・ラ・ラ」だったり、アース・ウィンド&ファイアーの「September」のサビの「Ba de ya」のように、音だけで意味のないものもありますが、それで不自然に感じたりはしません。
宇多田ヒカルの「One Last Kiss」。
サビが「オ・オ・オ・オオオウ」と歌われる。
・話し声と歌声
普段他の人とのコミュニケーションで使う話し声と、歌を歌うときの歌声は、同じ人物であってもかなり違います。俳優・声優・アナウンサーといった話すことが職業の人たちは、綺麗で聞き取りやすく音量も豊かになるように訓練しますが、歌の訓練のように広い音域や正確なピッチ(音程)を実現しようとするわけではありません。また、歌声にはクラシックやロック、ポップスなどの音楽ジャンルによる正統な発声法があり、ジャンルと発声がマッチしていないとおかしく感じられます*。
*言葉と歌のボイストレーニングについては、福島英『ヴォイストレーニング大全』(リットーミュージック)が詳しい。
言語と歌声も大きな関係があります。例えば、主に北米とイギリスで発達したロックは英語の発音を基本としていたので、日本語でロックを表現するのに、矢沢永吉や桑田佳祐は随分工夫をして日本語を英語風に発音しました。これは日本だけではありません。フランスやドイツ、イタリアのロックは母国語とロック的表現がなかなかマッチせず、カン(ドイツ)やショッキング・ブルー(オランダ)は歌詞を英語にしています。
エルヴィス・プレスリーのスタイルで歌うフランスのジョニー・アリデイ。
『Johnny Hallyday “Pony Time” on The Ed Sullivan Show』
面白いのはヒップホップで、北米からスタートしたこのジャンルは、その後各国で母国語を使うやり方をそれぞれ開発して成功しています。ヨーロッパでは、外国からの移民系の人たちがヒップホップで活躍しているのが印象的です。
トルコ系ドイツ人ラッパーのアパッチ207のヒット曲。
『Apache 207 - ROLLER prod. by Lucry& Suena (Official Video)』
また、アラビア語には、喉の奥を使う発音がたくさんあり、喉の奥を広く使う言語なので、この言葉を使う人たちの歌声が朗々としていて美しい理由になっていると思われます。
アラビア語紹介動画。
『アラビア語ってどんな言語なの?【世界の言語001】』
余談ですが、たくさんのクリック音(吸着音・舌打音)を使う南アフリカのズールー語を見てみましょう。
『Incredible Zulu click language - The ultimate tongue twister.』
2024年現在、K-POPは世界規模での成功を収めています。2022年デビューのNewJeansは、音楽性も高く期待を集めていますが、面白いのは歌詞に英語が多く、また韓国語の部分の発音が英語に近い響きになっていて言語の切り替えに違和感がないことです*。これは、スペイン出身のロザリアがスペイン語のままで北米のチャートに入っているのとは随分違うように思います。
*K-POPの発音については、言語学者の野間秀樹による『K-POP原論』(ハザ)が詳しい。
ロザリアの「LA FAMA」は、逆にゲストボーカルのザ・ウィークエンドにスペイン語で歌わせている。
『ROSALÍA - LA FAMA(Official Video) ft. The Weeknd』
・声の可能性
近年のヒューマンビートボックスの人たちを見ていると、彼らは(マイクをうまく使って)出したいと想像する音はすべて出すことができる、ということが伝わってきます。リズムマシンの正確なシミュレーションはもちろん、これと同時にシンセベースや様々なシンセ音を出し、並行して普通に歌も歌ってしまいます。
驚異的なヒューマンビートボックスの例。
『SHOW-GO - Silver (Beatbox)』
また、モンゴルのホーミー、トゥバのホーメイやカルグラー(低音)、チベット密教の声明(低音)などを聞くと、普段ポップミュージックで聞くのとはまったく違う声の音楽があることを実感します。
モンゴルのホーミーの紹介ビデオ。
『モンゴル ホーミー 「ホーロイン・ホーミー(喉のホーミー)」』
トゥバのカルグラー。
『canto difonico Tuvano - Dag Kargyraa (Tuvan throat singing)』
チベット密教の声明(しょうみょう)。
アフリカのピグミー族の人たちが歌っているフィールド録音を聞くと、地声と裏声を交錯させながらソロボーカルが始まり、それに見事なリズムで別のメロディが答えるポリフォニーが完全な形で実現されており、とても美しいです。歌詞のないインストゥルメンタルということもあり、現代のクラブミュージックに慣れた人達には即座に「カッコいい音楽」として認知されると思います。
フィールド録音によるピグミー族の歌。『Bobangi』
Amazonページはこちら。Kindle版(リフロー形式)もあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
