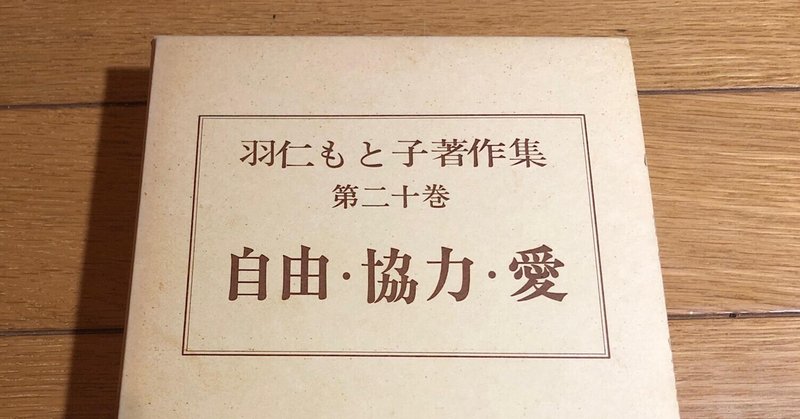
「類的存在」と「靴を揃えて脱ぐ自由」 #雑感1
先日、内田樹先生のマルクス本「若者よ、マルクスを読もう」(石川康宏氏との共著)を読んでいて、面白いところを見つけた。
アメリカの人権宣言も、フランスの人権宣言も、実際には多くの人々が祖国と同胞のために、おのれの命も財産も自由も捧げた政治闘争の成果として得られたものでした。にもかかわらず、これらの英雄的・非利己的な献身の目標が、「利己的人間の権利承認を堂々と宣言」(「ユダヤ人問題によせて ヘーゲル法哲学批判序説」)することだった点にマルクスは納得がゆかないのです。もちろん、市民社会においても、市民たちは自己利益の追求だけをしているわけではありません。政府に私権の一部を委ね、法律を制定して、それに従い、自分の懐から税金を払い、徴兵制があれば、武器をとって祖国のために戦ったりもします、こういう市民のありようをマルクスは公民と呼びます。公的な機能からとらえられた市民のことです。私利私欲をはかる市民を「本音の市民」とすれば、ルールに従って義務を果たす「建前の市民」のことです、つまり、市民は「私人」と「公民」の二つの顔をもっていることになります。私人としては自己利益を追求し、公民としては共同体の利益を追求する。(中略)近代市民社会の成員たちは、「私人」と「公民」の二つのありように分裂している。そして、私人であることの方が本来的なあり方だと、ぼくたち自身も深く信じています。マルクスは「それはおかしいのではないか」と言うのです。「自分さえよければそれでいいが、いろいろうるさいから法律に従う」というような人間を作り出すために人類は営々と努力してきたわけではないだろう。人間が真に解放されるというのは、そういうことではないだろう、と。
一人の人間が公私に分裂していることもおかしいし、分裂したうちの「より利己的な方」が本態で、「より非利己的=公共的な方」が仮の姿というのも、おかしい。そうじゃなくて、真に解放された人というものがあるとすれば、それは分裂してもいないし、隣人や共同体全体をつねに配慮し、そのことを心からの喜びとしているはずである。そういう人間が今どこかにいるということではなくて、論理的に言って、そういう人間をめざさなければならないのではないかとマルクスは言うのです。
マルクスはそれを「類的存在」と呼びます。「類的存在」、聞き慣れない言葉ですけれど、いったい何でしょう。「類的存在」とは、マルクスの定義によれば「現実の個体的な人間が、抽象的な公民を自分の中に取り戻し」た状態のことです。市民社会的な「公私混同」があくまで「私に公が従う」ことであるのに対して、公私が文字通り一つになった状態のことだと考えてもらえばいいかと思います。(そんなこと言っても、ぼくたちは実際には「公私が一つになった人間」なんか見たことがないので、想像することはきわめて困難であるとは思いますが)マルクスは人間が自己利益の追求を最優先することを止めて、自分の幸福と利益を気づかうのと同じ熱意をもって隣人の幸福と利益を気づかう「類的存在」になることを「人間的解放の完遂」だと考えました。
これを読んで、母校の自由学園でよく聞かれた言葉の一つである「靴を揃えて脱ぐ自由」(羽仁もと子著作集・第二十巻所収)を思い出した。創立者の羽仁もと子がよく言っていた言葉であるという。自由学園に在籍したことがある人なら、この文章を読めばすぐにパッと思い出すに違いない。内田先生は実際には「公私が一つになった人間」なんか見たことがないとおっしゃているが、靴を揃えて脱いでいる人は公私が一つになった人間であるかもしれない(特に学生とかは)。何故なら自由に靴を脱いで良いのであれば、汚く脱ぎ散らかしても良いのである。そういう自由もある。一方できちんと揃えて靴を脱げば、玄関は美しく整頓され、履くときにも気持ちが良い。自由学園の自由には「靴を揃えて脱ぐ自由」でありたいという希望が込められていたのである。学生時代に聞いた時にはああ、そうかとは思いはしたものの、なんとなくの理解であり、確かに自由だからといってやりたい放題というのはみっともないくらいにしか思っていなかった。自分自身を律することが必要なんだなくらいの理解であったと思う。だが、この文章を読んで、実は人間が自己利益の追求を最優先することを止めて、自分の幸福と利益を気づかうのと同じ熱意をもって隣人の幸福と利益を気づかう「類的存在」になること=「人間的解放の完遂」という高い人間的成熟を要求されていた行為なのだということに気付かされた。
マルクスのいう「類的存在」とはどのような言葉なのかも気になって調べてみた。人間とは自己意識をもって他者や自然との関係性の中を生きる存在であるということであり、それは人間が社会的な存在であるということである。もっと噛み砕いて言えば、人間はお互いの強い結びつきを基にしてはじめて生きることができる共同的存在である。それを類的存在という言葉で表しているのだ。
確かに私達は、利己的な私人と共同体の1員としての公人の二つの顔があると思う。そして私も私人と公人が一つになる類的存在として生きることに憧れる。だが、その判断は時にとても難しいものにもなる。例えば、戦争中に徴兵されたとすると、国のために闘うことは国民の義務ということになる。しかし、私人としての自分に人を殺さないという信条があれば、良心的兵役拒否という手段を取る方法もなくはない。しかし、それが許されるかどうかは国や時代などによっても違ってくると思うのだ。(場合によっては処刑される)また、そういう手段が取れたとしても、社会的な圧力は相当なものがあると想像することができる。私達は時に私人として己の幸福を追求し、時に共同体の一員としてやりたくないことをやらなければならないような状況もでてくるが、あたり前のことだがその時には自分自身が判断して決断するしか方法はない。そして、生きるか死ぬかという大げさなものではなくても、私人としての自分を生きるのか、公人としての自分を生きるのかを判断しなければならない状況というのはけっこう多いような気がしている。(そして、この問題はいくらコンピュータが進化しても決して答えてはくれない問題である)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
