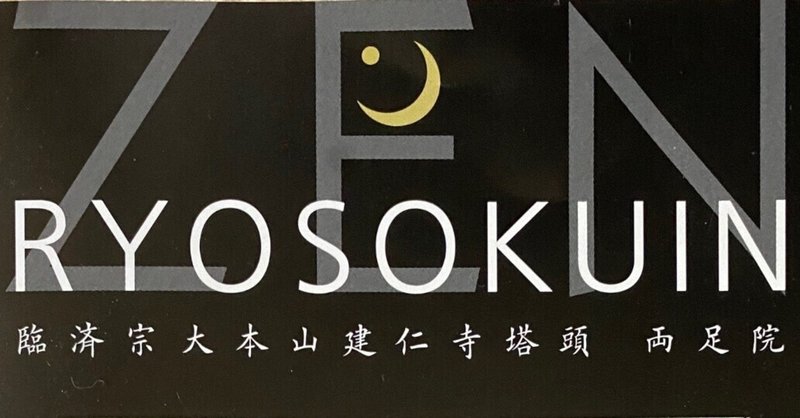
京都旅行 2023.5 両足院(建仁寺)
さて、今回からは5月に京都に行ったことについて書いてみます。
今回の京都旅行、出だしはヒヤヒヤでした。
予定通りであれば、18時前に退社し、特急と新幹線を乗り継ぎ、24時前には京都のホテルにチェックインする予定だったのですが。。。
ダイヤが大幅に乱れ、①途中で引き返す、②京都にたどり着く手前で急遽ホテルを探して泊まる、⓷イチかバチか行けるとこまで行く、といった三択を迫られました。
一時は弱気になって選択肢②を選択しそうになったのですが、結局、車掌さんに助言いただき、京都に向かうことにしました。
強行したのには理由がありました。
翌朝、建仁寺の塔頭寺院、両足院の禅体験を申し込んでいたのです。
NHKの「ドキュメント72時間」で、京都の禅体験ができるお寺(両足院ではありません)が取り上げられていたのを見て以来、禅の体験してみかったのです。
そんな折、テレビ番組「日曜の朝は旅に出よう」で両足院が取り上げられており、衝動的に禅体験を予約したという経緯です。
幸いにも最終の2本前の電車に乗ることができ、どうにか寺町通り沿いのビジネスホテルにたどり着くことができました。
夜の京都タワー。初めて間近で見たのですが、とても綺麗でした。

そして翌朝、予定通り禅体験を受けることができました。

先に述べましたが、両足院は建仁寺の塔頭。
両足院は、建仁寺の開山・明庵栄西(みんなんようさい)禅師の法脈・黄龍派(おうりょうは)を受け継ぐ龍山徳見(りゅうざんとっけん)禅師を開山とする臨済宗建仁寺派の塔頭寺院です。
開山当時は「知足院」と号していたのですが、1536年の火災から再建した際に両足院と改称したとのこと。
「半夏生の寺」とも呼ばれており、毎年6月下旬から夏にかけては、書院前庭の池畔で半夏生の葉が白く色づくそうです。
受付を済ませて方丈へ。
そして8時30分、禅体験がスタートしました。

まずは座り方などの説明を受けてから、禅の手ほどきを受けました。
数息観という呼吸法も教わりました。
鼻から息を吸い込み、数を数えながら口から息を吐きます。(腹式呼吸です。)
10まで数えたら、また1から数えます。
これを繰り返すのですが、日常生活、例えば仕事で緊張した時なんかに活用できそうです。
ここまでで1時間程度。
その後は、自由時間。好きな場所で座禅するもよし、お寺を見学するもよし。

私は庭の方を向いて座り、ゆっくりとさせていただきました。

外を眺めていたところ、鳥がふわりと着地。
しばしお庭に滞在してました。
何かの吉兆か、歓迎の意を表していただいのか…と都合よく解釈することにしました 笑笑
前庭や中庭も拝見しました。



お寺のHPをよると、この座禅体験は1stSTEPであり、このあとに2ndSTEP、3ndSTEPが用意されているようです。
自分を観察して、それを受け入れる 。
今回、座禅とは「自分と向かう時間」であることを学びました。
しかし、禅体験してから約半年が過ぎ、正直なところ、その時に感じたこと等、記憶は薄れています。最近はここ両足院で改めて禅体験を受けたいと思っています。
そう言えば、参加された方からの質問で、初めて知ったことがありました。座禅の時にお線香を焚くのですが、その意味について。
お線香はタイマーなんだそうです。香りがなくなったら30分経過したことがわかるとのこと。
この答は意外でした。香りに何らかの意味があると思っていましたので。
今日はここまでです。
ここまてお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
