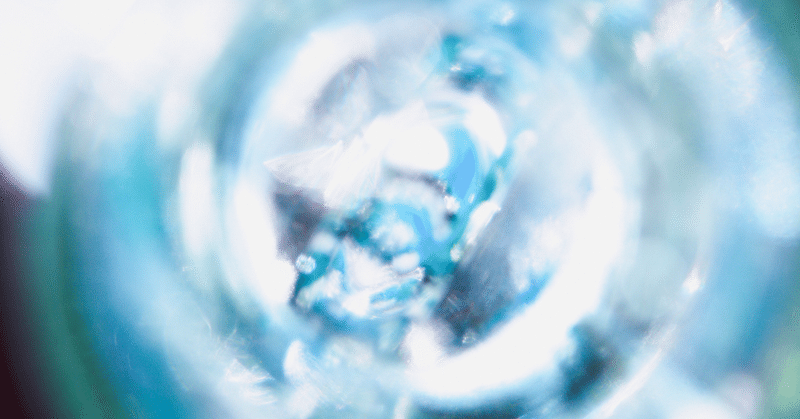
雨宿りの方法は、眩い。
「キミってさ、おもしろいよね」
そう言って振り返った君の顔を、
「手ー出してー!チョキ!勝ったぁー!」
そう言って戯けた君の顔を、
「これ、やばいね、、すご、、」
そう言って空を見上げた君の顔を、
僕は直視できなかった。
何故ならそれは眩しすぎるからで、
僕の目に映るのは勿体無いからで、
僕の目に映っていいものではないからで、
それでもやっぱり一番の理由は眩しすぎたから。
君の全てが。
「あ、ねぇ、キミ!何見てんの?」
「ふぇ?!」
アガツマカメラという老舗のカメラ屋で中古のカメラを物色していた時、そう声をかけてきたのが彼女。
彼女は背中に大きなギターケースを背負っていた。
「え?それってさーMINOLTAのAUTOCORD CdS III 3型の二眼レフカメラじゃない?めっちゃフォルム良いよねー!そういうの好き?それ好きだったらさ、MAMIYAのC330 Professionalも好きでしょ!ね!後は、、」
「え、あ、ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいっ!」
「ん?どうしたの?」
「えーと、ちょっとほんとに待ってくださいね、あーと、、整理しますね、、えーと、、まず、どなたですか?」
「んーと、名乗るほどのもんじゃないよー」
「いや、名乗るというか、、見知らぬ人に声かけてる訳ですから、、」
「え、知り合いでしょ?私たち」
「はい?」
「私、何度かキミのこと、この店で見かけてたもん、私知ってるもんキミを」
「あーと、それは【知り合い】という括りには入らないかと、、、」
「カメラ好きなんでしょ?」
「まあ、、はい、、そうっすね好きっすね」
「どんくらい好き?」
商店街のアーケードにあるアガツマカメラ。店の前には当然、たくさんの人が行き交う訳だが。
「私はねぇ、、、こんくらいっ!!!」
そう言って彼女は店内を飛び出し、アーケードのど真ん中に立ち叫んだ。手を目一杯広げて。風に靡く真っ白なTシャツ。上下する胸。私は生きてるんだ!そう言わんばかりに誇らしげな様子。
突然の出来事に街ゆく人たちは、呆気に取られていた。というよりも異常者を見るような目つきで軽蔑していた。
突然の出来事に僕は、呆気に取られていた。というよりも完全に心を奪われていた。今までごく平凡に生きてきた僕にとって彼女は眩しかった。眩しすぎた。その眩しさは燦々と輝く太陽の下の向日葵のような眩しさだった。古びたアーケード。牛肉しか置いていない精肉店。談笑中のマダム達。体の傾いたお爺さん。閉店セールが終わる気配のない婦人服屋。子供が入り浸る駄菓子屋。壊れかけの三角コーン。なんの変哲もない見慣れた景色が、見知らぬ景色に思えた。そしてひとつひとつが温かく、魅力的に感じられた。
「ねぇ、キミはー!!?どんくらい好きー!」
道のど真ん中からこちらへ向かって叫ぶ声。
「え?、、僕は、、」
そう言おうと開いた唇に水が落ちてきた。程なくしてそれが雨だと分かった。晴れているはずなのに、雨が降っている。稀有でもあるが、誰もが経験するであろうこの風景が僕には新鮮に感じられた。空はどこまでもやさしい青色で、ラムネみたいに透き通っていた。ラムネ色の空から降ってくる雨粒はラムネ瓶に入っているビー玉のようなまんまるの陽の光を浴びて、輝き、煌めく。炭酸の泡のように細かく繊細な雨粒だった。
「これ、やばいね、、すご、、」
そう言って空を見上げるキミの顔は直視できないほどに綺麗で、咄嗟にカメラで顔を隠す。ファインダー越しに見える彼女。焦りで手元が狂う。フラッシュと共に辺りに閃光が走る。そのせいで彼女が振り返った。
「ちょいーー!何撮ってんの?」
「え、あ、いやあまりにも、、」
「え?」
「あまりにも、、君が輝いてたから、、」
「え?」
「君が、綺麗だった、、から」
「ははっ!カメラ好きのくせに、鈍感ー」
「、、?」
「こんな光景二度と見られないよ、ちょー綺麗な青空から霧雨降ってくんの。なのにキミ全然空撮ってないじゃん!私撮ってんじゃん!笑える!キミってさ、おもしろいよね。私撮りたいんだったらさこれからいくらでも撮れんじゃん、どこへだって行けるし。でもさーこの空と雨撮りたい!って思ってもさ、もうこの空もこの雨も今日しか無いんだから。一度っきり!きり!霧雨!一度っきり!のじん!じん!せい!せい!」
「のじん!って何だよ」
思わず笑ってしまった。
「あのさー、これからさ、いっぱい撮らせてよ」
「何を?」
「キミを」
「私を?」
「うん。さっき言ってたじゃん、ちゃんと聞いてたよ」
「えー言ってたかなーそんなこと、、じゃあさ、手出してー!」
「手?、、はい」
「チョキ!勝ったぁー!撮らせてあげませーん」
「は?ズルいとかも言えんくらいにひどいぞそれ」
「ふふふ」
「ははっ」
いつの間にか雨は止み、空が朱く染まり始めていた。
「んじゃ!私向こうだから」
「あぁ、うん、また」
「またね」
肩にかかった栗色の髪の毛を揺らし、彼女は駆け出した。そして立ち止まり何か思い出したように振り返った。
「キミ、名前は?」
「れ、蓮!楠木蓮!」
「楠木蓮!さよなら!」
「まっ、、名前は!!!」
「ふふっ」
彼女は何も言わず、微笑み、夕日に溶けて消えていった。
夕日が輝いている。君は今どこで何をしているのだろう。
「パパー、早くおうち帰ろうよ!」
────────────────
初めてキミを見た瞬間のことを、私は一生忘れない。
あの日は、、、雨が降っていた。土砂降りだった。私の心もびしょ濡れだった。顔もぐしゃぐしゃだった。泥まみれだった。泣いた。泣きまくった。
そう、いわゆる、失恋をしたからだ。
まさか自分が失恋ごときで泣く奴だなんて、思ってもいなかった。
恥ずい。無念。
通行人に気づかれないように、傘で顔を隠した。でもビニール傘だったから意味はなかった。
いいんだこれで。
百均で買ったビニール傘は小さすぎて、ギターケースが濡れてしまう。だからギターケースを守ろうとして傘を動かすと、靴がびちょびちょになる。
些細なことに苛立つ。
恋を失ったってめちゃくちゃ嫌な感じだと思った。嫌な漢字。感じ。うるせえわ。なんか誰かに心を取られたみたい。
喪失感。無念。
彼の家から私の家まで、10分もかからない。でも今は果てしなく長く感じる。
中学校の持久走、校庭の周りをぐるぐる回るあの感じ。どこまで走っても同じ景色、終わりが見えない、あの嫌な感じだ。
その時、後ろから足音が聞こえてきた。
どんどんと近づいてくる。どうやら走っている。しかもかなりのスピードで。
私はドギマギした。
そして髪を整えた。
もう一度やり直そうと言われて、うんと返事をする準備をした。
もうすぐそこに彼が迫っている。
勢いよく振り返った。
そこに彼はいなかった。
走り去るキミがいただけだった。
ずぶ濡れのキミがいただけだった。
キミは傘を持っていなかった。
代わりにカメラを持っていた。
カメラを自分の上着に隠して、濡れないように守っている。
私は今まで、あんな風に守られたことがあっただろうか。
ほんの数秒間、一瞬の出来事が、私には何故かスローモーションのように映った。
気づくと、キミはもうずっと先にいて、私はキミを追って駆け出していた。
”アガツマカメラ”と書かれた電光看板が光を放っている。
雨はいつしか霧雨になって、光を空間に解き放つ。
見慣れた商店街の見慣れた景色のはずなのに、異世界に迷い込んだような感覚に襲われた。そっと店内に足を踏み入れる。独特な香り。
店内には所狭しとカメラが並んでいて、まるで美術館だった。カメラの美術館。
「アガツマさんーーーーーやっちゃいましたぁあああ」
そうだ、私はキミを追いかけてきたんだった。
美術館で大声を出すキミは大人のふりをした子供みたいだった。
「どーした」
「今日、雨降るって知ってました!?」
「ゆーとったやろ、お前まさか」
「…まさかです」
「まさかか!?」
「まさかです…」
「ちょお早う貸してみい」
店主のアガツマさんがキミのカメラを奪うように取り、店の奥に消えていった。
キミはソワソワしている様子で、店内を右往左往している。
私はカメラを見るふりをして、キミの様子を観察していた。
キミはショーウィンドーに飾られたカメラを食い入るように見つめ、おでこをガラスにくっつけ動かなくなった。
私は思わず笑ってしまった。
「おい、おい何しとんや」
「治りましたか?…」
「こりゃな、流石に無理や」
「ですよねぇ…」
「これ処分するか?」
「あ、いや頂きます。情があるんで」
「情か、あいよ」
あいよ、愛よ、愛情よ。うるせえよ。
壊れたカメラを首からかけ直し、店内のカメラを物色するキミ。
丸く折りたたまった背中は抱き枕みたいでふわふわに見えた。顔をうずめたい。泣きたい。
いつの間にか、空は晴れていて綺麗な天色の空が広がっていた。私の心は晴れないのになと空にケチをつけたくなった。私の心も晴れさせてほしかった。誰でも良いから誰かと話したくて。だからキミに話しかけてしまったんだ。
カメラの機種の名前を適当に並べて、カメラが好きなフリをした。
キミのことを何度も見かけたというウソをついた。
なんかほんとにどうでも良くなって、店の外ででっかい声を出してしまった。
泣きそうだったけど、必死に笑顔を見せた。
でも空が泣き始めた。晴れているのに雨が降り出した。綺麗な涙だった。煌めいていた。私はあんなに綺麗に泣くことが出来ないだろうと思った。
キミがシャッターを切った。「君が輝いていた」と言われた。素直に嬉しくて、今の私にはどんな言葉よりも重くて、大切で、意味の分からない言葉を並べて遠回しに告白した。初めて会ったキミに告白した。キミは満更でもない様子で、「これからも撮らせてよ」と言った。頭がこんがらがって、キミが優しくて、やっぱり泣きそうで、適当な理由をつけて逃げた。名前を聞いた。キミはクスノキレンというらしかった。クスノキレンは名前を聞いた。私は答えなかった。答えられなかった。真っ赤な夕日が私を照らしていた。
夕日が輝いている。キミは今どこで何をしているのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
