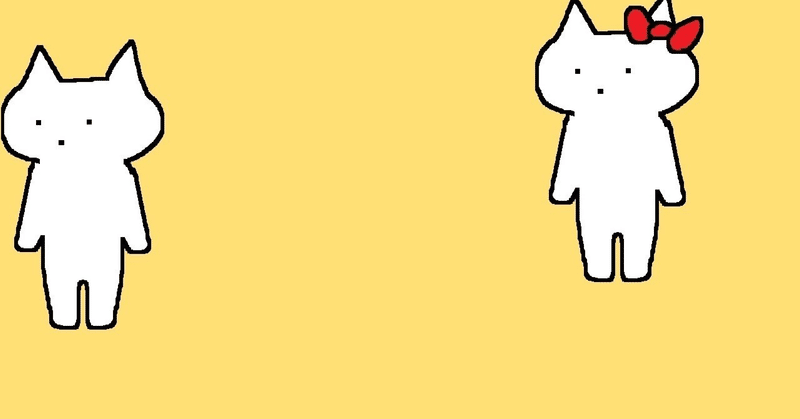
企業が避けるべき「嫌われる」コンテンツ「5つの兆候」
企業にとってコンテンツマーケティングは重要な戦略ですが、時には間違ったアプローチで「嫌われる」コンテンツを作成しまって逆効果になることがあります。これは、ブランドに大きな悪影響を与えることになりかねず、絶対に避けたいものです。「読者に嫌われるコンテンツ」の傾向とはどんなものでしょうか。いくつかその兆候を挙げてみましょう。
一方的な宣伝
常時インターネットとつながって情報に触れている現代の生活者は情報取得のリテラシーが高く、一方的な宣伝には極めて敏感です。一方的に自社製品やサービスの優位点を並べ立てるコンテンツは顧客との対話が成立せず、顧客の課題や悩みに寄り添っていません。顧客との対話を育むためには、ソーシャルメディアやウェブサイトのコメントセクションの活用など、顧客の声に耳を傾けるチャネルを持って、課題や悩みに寄り添うことが必須です。
技術的な専門用語の過剰な使用
技術的な専門用語は、エントリーユーザーなど、新規に自社の顧客になってくれそうなリードのアクセスにとって、大きなハードルになりかねません。興味や課題意識を持って自社サイトやSNSに接近してきた顧客は、難解な専門用語にうんざりして、コンテンツの価値を感じる前に離脱してしまう可能性があります。コンテンツをよりアクセスしやすいものにするためには、専門用語の使用を抑え、平易な言葉を使用することを意識しましょう。
顧客の悩みや課題に関連性のないコンテンツ
顧客の悩みや課題に関連性のないコンテンツは顧客の興味を引かず、ブランドの信頼性を損なう可能性があります。顧客の声をリサーチし、そのフィードバックにもとづいてコンテンツをチューニングする必要があります。
価値提供が不足しているコンテンツ
価値提供が不足しているコンテンツは、読者にとって「読み進める意欲」を減退させる要因になり、自社ブランドの魅力を伝えるに至らない可能性があります。読者の関心を引き付けるためには、他社にはない学びがあり、連続的に有益なコンテンツが投稿される「意義ある情報提供者」になることが求められます。
情報過多と情報の過少
情報過多や情報の過少は読者の混乱を招き、コンテンツの信頼性を損ないます。過多の場合はうんざりして読む気が失せますし、焦点がぼけてしまいます。また過少の場合は、読者に物足りなさを感じさせてしまいます。バランスの取れた情報提供は難しいものですが、同じテーマについて、視点を変えたコンテンツをいくつか並べることで、より多くの顧客のちょうどよい満足感を得るという方法も有効です。また、本文では端的に重要な情報のみを提供し、追加情報はリンクによって別ページで提供することもできます。
まとめ
「嫌われる」コンテンツを避け、企業がコンテンツマーケティングで成果を上げるためには、顧客との対話を重視し、エントリーユーザーでもアクセスのハードルが低いコンテンツを提供する必要があります。顧客の悩みや課題に寄り添ったコンテンツを継続的に提供し続けることで、自社に対する信頼感が高まり、競争力を維持することができるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
