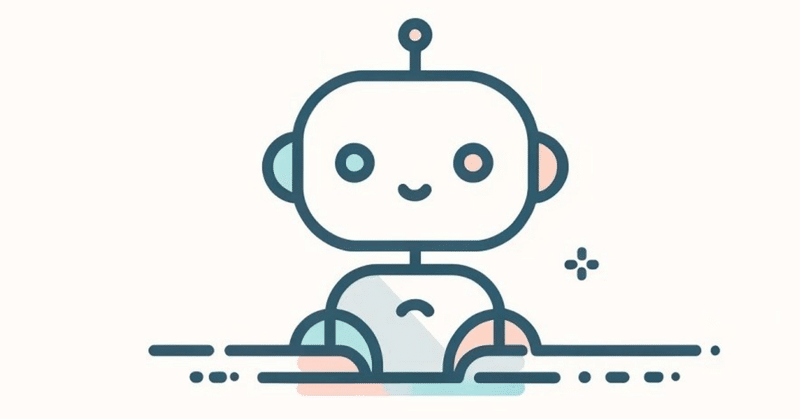
【マンガ紹介 #11】宙に参る【小ネタバレ】
亡くなった夫の遺骨を地球へ届けるため、長い帰り道を人工知能搭載のロボットの息子と共に、宇宙とシステムを考えながら面白可笑しく歩む物語。
作品データ
巻数:4巻(連載中)
作者:肋骨凹介 (著)
あらすじと1話
ロボット頭に伸びた触手が器用にマイクを持ち、葬式の挨拶を始める。平然と自身を「息子の宙二郎」と紹介を済ませつつ、母親の鵯ソラの隣に立つ。
会場全体には"人影"は無いが、代わりに安そうなパイプ椅子に人々の顔が全面的に映った小型ディスプレイが並べられる。そして順が来た時に、会場の真ん中に居る歩行型ロボットにディスプレイが取り付けられ、ロボットが代わりに焼香を行い、歩行ロボットが合掌させた状態でディスプレイの人が目を瞑る。
淡々と進んだ葬儀に涙一つ流さなかった鵯ソラ、この会場で唯一流し得る存在だと思っていたが、自身の薄情さを気にかけるが、すぐさま息子のフォローで「薄情な人は睡眠を削ってあーゆーの仕上げないと思うの」先ほどの歩行型ロボット通称焼香ロボがカタログスペックと共に紹介される。
「ご焼香が私ら二人じゃぁよ、あいつ(夫)が向こうで泣くぞ」リモートで済ませたがきちんと葬儀を挙げ且つ立てられた焼香は「二人」だけではなかったとしても特殊な人間のカウントをしている。これから葬儀関連の書類を行い遺族らしいことをする必要があるため、忙しくて泣く暇も無さそうと二人で簡単に議論する。
そのまま淡々と時が進み、市斎場まで訪れ地球に住む独り身の義祖母を心配する。返答に困る宙二郎が遺族らしく棺桶の前でもそもそするが「私にゃあんたがいるだろ」と互いを支えあう。そして少し時が進み休憩所でオンラインになったと後に、その祖母からの連絡があったことを伝える息子。
録音になれない祖母の覚束ない音声と、祖母自身も初めてではない葬儀に関して色々アドバイスをする。何より元気そう、と思った矢先に逆にこちらの心配もしてくれる。「かくいう私も寂しいですからね、義娘と孫の元気な顔がみたいな、と」ハッキリと要望を伝える。込み上げる涙を上を向くことで必死にこらえながらその場ですぐに返事を録音、思ったが吉日という奴だ。
今までの宙二郎との会話とは打って変わった、礼儀正しい文章が並べられる。そして「宙二郎と宇一さんも一緒に」の文言で締め、地球に帰ることを伝える。
今日の便を逃せば1週間後、急がば回れとはいかず、便利な息子を焼香ロボにリモート接続もといセカンダリー化させ明日の残りの事務手続きを任せ、とっとと荷造りを終えてコウア宙港へと急ぎ足で向かう。
軌道リフトに乗りながら、映像上では夜化した筒状コロニーに、先ほどまで居た街の100万ドルを優に超えた人工夜景が広がる。シャトルへと搭乗し、遠く映った地球にある選り鵯家の墓へと向かう、遺灰を届けに。翌日飛び立ったコウアコロニーにて、セカンダリ及び子機の宙二郎が「続柄の所、【故人の息子の子機】でいいですかね?」と突拍子もない台詞で1話は完結。
惹かれた点
日常性と近未来性の調和具合がえぐい。1巻の表紙の宇宙とコロニーとロボット開発が進んだ世界であると表示しながら、1話の葬儀や市役所の単純さも持ち合わせつつ、義祖母の宇宙間電子環境の慣れなさも表す。煌びやかな近未来性の中に強かに生き続けた人々の軌跡もそこかしこに見られる。
また1話の時点で見せつけた息子の宙二郎と鵯ソラの、互いを尊重しロボットと人の垣根を超越した立派な自我を持った二人のやり取りは、ロボット大三原則だとか人工知能だとかありきたりなSF設定を披露することなく二人は淡々と会話を続ける。
ただ焼香ロボットやリモート葬儀がそうであったように、確実な近未来性もまったく頭を隠す気等なく堂々と現れる。リモート飲み会があるならリモート葬儀もまったくもって夢じゃないが、宗教性がある程度一新されてそうではあるが儀式性を維持してる人類らしいことを成し遂げている。
俗に言うSF界隈によくある「新しい技術による旧慣習の淘汰から保証される優位性」が無く、再三になるが、人類の強かな感性が働いている。
そして漫画の演出として、コロニーの夜景が見える場面を除いて、大きな1枚絵で派手に日常性と近未来性を語ることはせず、あたかも普通の葬儀を行った二人のように披露される1話のトレンドは以降の巻でも続く(それにこの夜景の絵は、ただ綺麗だから映したと解釈できなくはない)。
絵柄が和やかでSFらしい角ばった建物や特殊な色彩を感じることも無く、俗に言うiPhoneの一桁前半世代にあった変に立体的なGUIのような、無理に着飾ったような装飾感も無い。ガンダムシリーズのアムロレイが「2丁ライフルではなく2丁バズーカ」を選んだのと同じように、人類が見た目や近未来性に囚われ過ぎず技術を突き詰めていった証左でもある。
文化と技術開発の解像度高すぎ(ネタバレ付きコメント)
AIの開発以外にも基底倫理に関する内容、ユニーバーサル航宙の施設案内もそうだが使われている単語や「船内各所の私に御申しつけください」と言ったように確実に新しい用語を用いる文化の浸透を行っている。昨今でやれSDGsだやれAIだのIoTだの流行語を、ごく一部の技術者や知識人だけ除いて、用語だけが独り歩きしてる感が、この漫画内にあるのも現代らしい。
そして上記の惹かれた点では触れなかったが、登場するキャラクターが様々な技術者相を出していて、恐らく私はかなり「マダン寄り」な思想と態度を持っていたりとキャラそれぞれの個性と彼らが寄り添ってきた文化並びに技術も見え隠れするのも良い。
何よりも又肩さんの「無理があるは夢がある」は、技術者としては理解できなくはない理念だが、実用性の側面からは誰も逃れられないハズなので、大きすぎる浪漫に対して皆訝しんでる様子は五臓六腑も笑い転げる程。
再三になるが日常性を常に覆いかぶせているので、ギャグ一辺倒にはならないが特殊な環境の特殊なジョークも欠かさないので時折渇いた笑いも提供させつつ、上記の又肩さんのようなゲラ笑いも誘う。
ただこれも全て、今までゆる~~~~く紹介された技術が如何に日常に溶け込んでいるかを理解した上で笑える材料なので、とてもウィットに長けているだけでなく、読者が展開される社会性に順応させる必要がある。なので漫画を2巡3巡は当たり前、気づけていなかったコマだけでなく、最新刊を読んだ上での意味の深さは「複線があった」という漫画考察勢特有の感覚は無くとも、文化背景を再認識する形でアハ体験も楽しめる。
なぁに言うほど難しくはないさ、絵柄の馴染みやすさも宙二郎の可愛さも鵯ソラの計画性の高さと滲み出るゴリ押し具合を追いかけるだけでも楽しい。
最後に
特異な技術が現れてデーンって感じの漫画からは程遠いが、様々な技術と思想が織りなすこの舞台は大変想像力を膨らませてくれる。
そしてオムニバス形式のように見せた様々な技術紹介が自然と主人公二人の母子に着目されるのも作者の手腕の良さが垣間見える。
是非とも皆さんも手に取った上で、1巡した後に考え尽くして、2巡3巡する形で読んでみてください。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
