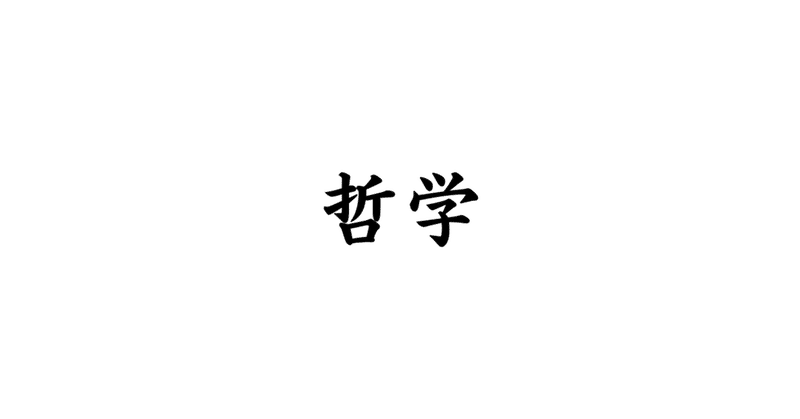
Q:椅子は椅子でも、溶けちゃう椅子ってなーんだ?〜フリーター、大学院を目指す【試験まで46日】
ほしい物リストから『存在論的、郵便的』という書籍を贈っていただいた。(ありがとうございます!そして本文の最後にリンクが貼ってあります。)難しくて、そして面白いので、普段は電車の中で哲学書を読まないようにしているにもかかわらず、この本に限っては移動中にも持ち運んで読んでいる。
昨日、『存在論的、郵便的』を読みながら電車に揺られていると、親子4人の家族が乗り込んできた。子供が二人で、小学生くらいの姉弟だ。姉が弟にクイズを出す。
Q:椅子は椅子でも、溶けちゃう椅子ってなーんだ?
弟は苦心して、そしてヒントを求める。なんとも愛らしい姿だった。小学生の夏休みとして100点のコミュニケーション。しかし、そんな幸せなワンシーンをよそに、俺の頭の中は哲学的言語に支配されていた。そしてこのクイズが脳内で自動翻訳された。
Q:家具でありながら、それをふと目に留めた時、それがまさに溶けつつあるものであることが了解されてしまうような、そのようなシニフィエとして機能してしまう、あるいはその記号性が示唆されてしまうような当のシニフィエとは何か?
哲学の難しさはここにあるかもしれない。つまり、日本語であるにもかかわらず、日常とは別種の独特の語法があるというのが、理解を難しくしている。とはいえ、「だから哲学はもっと平易に語られるべきだ」というのではない。それはある種の「外国語」なのであって、「外国語」には「外国」の文化が染み付いている。そして文化は保存されるべきだ。なぜなら、文化が多様であればあるほど、そのそれぞれに関心を持つ価値が生まれるからだ。ありふれたものは好奇心を駆り立てない。
「外国語」というのは、たとえば「哲学」のように、ある領域を指す。しかしそれだけではない。突き詰めて言えば、他人の話す言葉は全て「外国語」だし、自分が過去に発した言葉、これから発する言葉も「外国語」だ。そして「外国語」を学ぶことは、そこに潜む価値観や欲望を学ぶことでもある。また、その学びを通して、自らの言葉は「外国語」化していく。俺の価値観も欲望も、あるいはもっと表面的には、単なる言葉遣いやイントネーションも、「外国語」に触れ続けることで変容していく。
そう考えると、「自分を持て」とか「自分を信じろ」と言うときの「自分」というものが曖昧になっていく。「外国語」との不断の交渉の中に「自分」というものがあるのだとすれば、「自分」というのはほとんど「外国」と区別がつかない。俺がいま発している言葉は、俺が発明したのではない。無数の「外国語」(=日本語)に囲まれて産み落とされてしまい、仕方なく使い物になりそうな「外国語」を習得した。それは全く俺のものではない。にもかかわらず、それを使ってものを考えたり、人とコミュニケーションを取ったりする。もし「俺が考えている」と言う時、本当に、純粋に、この「俺」が考えていると言えるだろうか?むしろ、無数の他人の結節点として、何か思考のようなエネルギーがうごめいているだけではないか?
そうすると、「自分」なんてものはまったく凡庸なものだ。全面的に他者に彩られている。しかし、俺は、一つの美的感覚として、この「自分」をよりカラフルにしたい。いまの「自分」を絶対化するようなプライドは採用しない。果てしない量の「外国語」を聞き取り、身につけていく生き方が美しいと思う。その一つの方策として、諸々の哲学を、哲学者を、読んでいくことは、美しいことのように思う。
哲学とフランス語を勉強しています。
ほしい物リスト(教材)↓
https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/1HJEAN0ZHX6GM?ref_=wl_share
学費ピンチなのでお金ください🙏ナムナム。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
