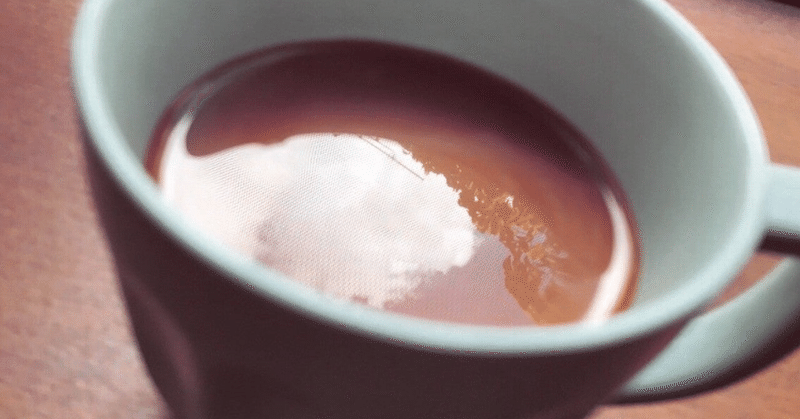
【掌編小説】苦い珈琲よりも甘いココアを#シロクマ文芸部
(読了目安2分/約1,600字+α)
珈琲と、ほのかなバニラビーンズの香り。
アパートの玄関扉を開けた瞬間、俺の胸に頭突きをした凛花は無言だった。喫茶店の香りをまとった彼女は、声を殺して泣いていた。
ああ、いつものだ。
内心の安堵を悟られないように、俺はため息をついてみせる。風呂あがりで良かった。外気で冷えた彼女の頭を軽く撫でる。外は小雨が降っていたらしい。肩にかけていたタオルを彼女の頭に被せる。
「とりあえず、髪拭けよ」
彼女を玄関に残し、顔を見ないように廊下へ上がる。脱衣所からもう一枚タオルを取り、自分の髪を雑に拭いていると、彼女がのろのろと靴を脱ぐのが見えた。
「なんか飲むか? 麦茶か牛乳、ホットなら……紅茶とか」
思わず珈琲と言いかけ、踏みとどまる。そのことに気づいたかどうかはわからない。低く、かすれた声が、俺の予想通りの答えを返す。
「ココア。あったかいやつ」
「りょ」
「甘めで」
「へい」
「ちゃんと鍋でつくる美味しいやつ」
「わかったから座ってな」
タオルを被ったまま凛花はリビングソファに座る。ストンと腰を下ろしたまま微動だにしない。彼女を視界の隅に捉えたまま、俺は鍋でココアパウダーを煎り、少しずつ牛乳を足していく。
ココアは得意だった。凛花は落ち込んでいる時には必ず俺にココアを淹れさせる。香り高く、温かくて甘い彼女好みのココアは、何度も作っている。
茶こしでダマを取り、タータンチェックのマグカップに蜂蜜をひとさじ追加する。
うつむいたままの彼女の前にマグカップを置いた。俺は凛花の隣に腰かけると、自分のマグカップに口をつける。出来はそれなりだ。スローモーションで手を伸ばした彼女も、両手でマグカップを抱えた。
「うまい」
「なら良かった」
「瑛弦」
「ん?」
「私ってこどもなんかな?」
「どうだろうな」
俺は熱いココアをすすり、短く答える。
いつものはじまり方だった。
凛花は、いつも一回りも歳の離れた男を好きになる。小学校の時は近所の大学生、中学では教師、高校の時はバイト先のオーナーを好きになり、玉砕しては俺に泣きついた。
「最近、よく行ってたカフェ、オーナーさんのこだわりで、珈琲豆の焙煎からしててさ、すごくいい香りなの」
知っていた。どんなお店なのか気になり、一度だけ行ったことがある。背が高く、お洒落な丸眼鏡をかけた、ヒゲのある男だった。
「うん。でもお前、珈琲ブラックじゃ飲めないだろ」
「バニラアイス頼めば、なんとか」
「それ、アリなん?」
「笑ってた。無理しなくていいですよって。サービスでクッキーとかつけてくれて。いつも来てくれるからって。名前、憶えてくれて。色々、話してくれて。他の、いつもカウンターに座ってる常連さんとも仲良くなって。でも、いざ、言ったらさ、困ったなって」
ココアに口をつける彼女は震えていた。心の芯からの震えをココアでは温められない。そのことに気付いていないように、続きを促す。
「僕はおじさんだからって、どういう意味? これから先、きっと良い人に出会えるって、どういう意味? 私には未来があるって、どういう意味?」
俺は凛花の手からマグカップを取りテーブルに避難させると、彼女の頭をそっと抱き寄せた。嗚咽を漏らす彼女の頭を落ち着くまで撫でる。彼女の髪についた珈琲の匂いが早く消えればいいと思う。
「瑛弦、ごめん」
「ん?」
「服、汚れた」
「すぐ乾くから」
「鼻水、ついた」
「また洗うから」
「よだれもつきそう」
「ココア風味だな」
「ごめん」
「いいよ」
「ありがと」
「ん」
「こういうとこがこどもなんかな」
「凛花」
俺は、彼女の頭を手のひらで包むように、少しだけ力を込める。
「お前は大人だよ。それに俺も、もう大人だ」
彼女が少しだけ身を強張らせたのが伝わる。だが、もう手を放すつもりはない。彼女の後頭部に、俺はココアの匂いがする唇を押し当てた。
シロクマ文芸部の企画応募です。
今回のテーマは「珈琲と」。短いのに締切間近になってしまった……。
最近寒くなってきたので、温かくなりそうな話にしてみました。
よろしければサポートをお願いします!サポートいただいた分は、クリエイティブでお返ししていきます。
