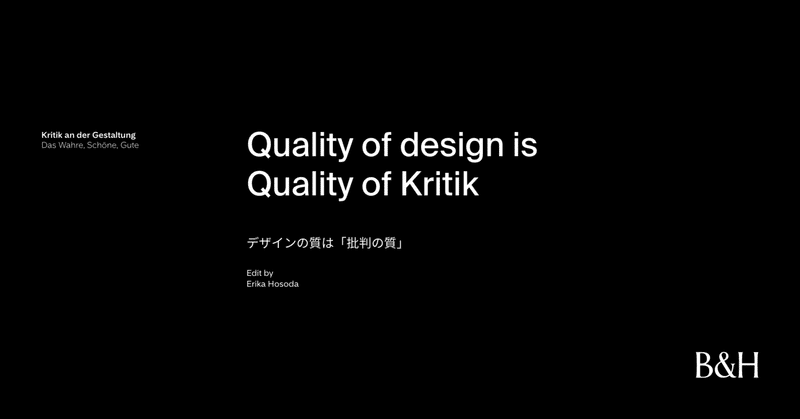
デザインの質は「批判の質」
デザインの質は「批判の質」で決まると考えています。
「批判」という言葉だけ聞くとなんとなくネガティブな印象を抱かれるかもしれませんが、B&Hでは着実なアウトプットや成長のために必要な「良質な問い」として、どちらかというとポジティブな意味合いで捉えています。
ビジネス文脈で語られる「批判的思考(クリティカルシンキング)」もおそらく本質的には同じことだと思います。それをブランドやデザインの文脈で私たちがどう解釈しているか、というのが今回のお話です。
なお、文中で取り上げる事例の解釈はその信憑性を保証するものではありません。あくまでもB&H独自の考察をご紹介するためのものとしてお楽しみいただければ幸いです。
仕組みを考えることはデザインを考えること
デザインとは「機能させること」です。衣食住に関わる身近なアイテムから、道路や信号をはじめとする交通機関、学校、企業、国といった組織のあり方まで、私たちの生活様式や社会を支えるシステムのすべてがデザインで成り立っています。
この商品はどうしてこの素材でこんな形をしているのか、今どうしてこれが社会問題になっているのか。世界のあらゆる事象についてどうしてそうなっているのかと考えることは、デザインについて考えることと地続きであると思っています。
逆になぜそうなのかという問いを持たないとデザインはできません。そうしたものの考え方に長けている人のことを、私たちは「デザイナー」と呼んでいるはずです。そんな彼らのおかげで、デザインする側ではないユーザーや市民の私たちは苦労せず快適に暮らすことができるのです。
そしてデザインの良し悪しはこの問いのレベルに左右されます。
優れたデザインには「批判」がある
良いデザインには必ず理由があります。その理由の多くは、既存の概念や前提に対する疑いと、そこから生まれた発見のうえに成り立っています。
「そもそも携帯電話にボタンは必要なのか?」という視点からiPhoneが生まれ、深澤直人さんが「壁から15cm離れた7mmのタイル目地は傘立てである」と言ったように、優れたデザインやデザイナーの思考には、当たり前すぎて見えなくなっている共通認識を手に取り、いろんな角度から観察するようなプロセスがあります。
混同しやすい概念として、Why(という問い)を繰り返す思考法があります。「批判」も繰り返し問うことではあるので、その字面だけ捉えると動作の性質としては同じことのように見えるかもしれません。
あえて違いを定義するならば、それは最終到着点の違いだと考えています。いわゆる「Whyを繰り返す思考」は問題解決をゴールにしていて、「批判」は根本的に新しいものを生み出すことを目指しているのではないかと。
Whyを繰り返す思考は、前提を揺るがすというよりも因果関係を明らかにすることに主眼が置かれます。それに対し「批判」は、これで果たして良いのかと、その前提にメスを入れます。どちらが優れているかではなく、対象とするレイヤーが異なるのです。
この”前提にメスを入れる”問い方は「哲学的な問い方」とも表現できるかもしれません。
私は仕事柄、何のためにデザインするのかを常に考えてきました。デザインに限らず言えることだとは思いますが、この「何のために」を突き詰めていくと結局、何のために生きるのかを考えることなり、哲学にもヒントを求めるようになります。
特に近代の認識論に大きな影響を与えたカントや、何事も鵜呑みにせず考え続けることの意味を論じたハンナアーレントの思想は、批判の有用性やデザインの存在理由を考えるうえで参考にしています。
経営と哲学を結びつけて語ることが当たり前であるように、デザインと哲学も結びつけていけばもっといろいろ見えてくるのではないか。ここでお伝えしたい「批判」にはそんな期待も含まれています。
世界を動かすのは「批判の実践」
批判の質から成るデザインがきちんと施されていて、作品自体やプロダクト以外の面においても、一貫してそのデザイン意図を体現できている人、組織やブランドは常に第一線で活躍しています。
歴史を振り返ってみてもやはり、「批判の実践」はありとあらゆる分野で起きています。
たとえば産業革命により工業製品が世に出始めた頃。労働者がホワイトカラーとブルーカラーに分類され、手仕事をしない人が増えることによって労働に喜びを感じる人が減ってしまうと懸念したウィリアム・モリスはアーツ・アンド・クラフツ運動を起こしました。
その後設立されたバウハウスは、モリスの根本思想を引き継ぎつつ、大量生産だからこそ多くの人が快適に使え、世界標準の品質を高められるような、きちんと設計したものを作ろうというデザインのアプローチが生まれました。経済発展という大きな流れ自体には逆らえないものの、その中で何ができるかを突き詰めた末の一つの解答だったのでしょう。
工業化への批判からデザインの役割を追求する、そんな熱量を持った人材が集まる場所を運営し、教育機関として成立させていたというのも大きな功績です。デザインの重要性を体系化し、知識として広められるように整備したこと、世界中から集まった学生がそこで学び、また各地に散らばっていくことで、バウハウスの思想、デザインを重視するという概念が広まりました。国内外の有名なデザイナーたちのルーツを辿ると必ず行き着くのが、この時代、この学校だというのが何よりの証拠ではないでしょうか。
さまざまな意見を持った人が集まり、議論が起こりやすい環境だったというのも「批判」とデザインの繋がりを考えさせられる点です。簡素な美しさを追求したインダストリアルデザインが生まれた一方で、ルールを決めていくことが良くないと主張する人たちもいました。いろんな視点から思考を深め、ぶつけ合う場が築けていたからこそ、最終的にナチスも無視できないほどの影響力を有していたのではと想像します。
第二次世界大戦以降、ニューヨークを中心に勢いが増していったアートの世界にも、同じ傾向が見られます。ピカソもデュシャンもウォーホルも、それまでの型(表現方法や固定観念)をいかに破るかを追求することで、新しいものの見方を世に投げかけてきました。
ファッションにおいては、メゾンブランドがその代表例です。常に注目を集める作り手である彼らは、既存の概念に疑いの目を持ち、その批判から斬新なデザインを生み出しています。上流階級の女性たちの価値観や、男性が女性に着せたいシルエットがデザインの中心だったことに疑問を持ったシャネルは、着心地とセンスの良さで楽しむデザインで、女性服に対する認識を大きくシフトさせました。
コムデギャルソンやヨウジヤマモトの「黒の衝撃」は、それまで主流であった西洋的なトレンドを覆すほどのインパクトを起こし、その影響は今も続いています。マルジェラの「デストロイ・コレクション」は、その高級志向へのカウンターパンチで熱狂的なファンを生み出しました。こうしたメゾンブランドが「批判」を原動力に起こしたデザインを、セカンドブランドが一般のマーケットにフィットするよう再生産することで、新しいスタイルが世の中に浸透していきます。
IT業界でも同じことが起きています。これだけ当たり前になったソーシャルメディアも、その幕開けに至るまでには、人の繋がりはどうあるべきか、そこにデジタルはどう介入すべきかといった社会学的な批判があったはずです。その概念の普及に伴い批判の対象は少しずつ変わり、フェイスブック、ツイッター、インスタグラムにとどまらず、次々と新しいサービスが生まれています。ブロックチェーンの台頭はまさに中央集権的な構造への批判を体現しています。
ポジティブに「批判」することから始める
アートもデザインもビジネスも、あらゆる領域において「批判」は創造の起点となっています。各々の分野でインパクトを起こしたい人は、まずこのことを一つのメカニズムとして念頭に置くと、新たに見えてくるものがあるのではないでしょうか。
たとえば経営者には自社が作り出すものついての説明責任があります。なぜそれをやっているのかを明確に伝えるためには、自分が抱いた疑問に対する自分なりの答えを持っている必要があります。その思考プロセスがこそが「批判」なのです。マーケティング優位でユーザーが求めているものから考え始めると、どうしても問いが浅くなるため行き詰まってしまいます。日本のスタートアップのほとんどがタイムマシン経営であり、イノベーションが起こりづらいのも同様です。
また本来デザイナーはその職務の性質上、批判を意識的に行うことが求められるため、他の職業に比べるとそうした思考に慣れている人が多いはずです。デザイナー経験をバックグラウンドに持つ経営者に成功例がよく見られるのはそのためです。
経営者であれば良いプロダクトやサービスを作れるか、デザイナーであれば表層的なデザインに陥らないアウトプットができるか、アーティストであれば人工知能にはできないような表現を生み出せるか。それぞれ挑戦するフィールドや役割は違っても、何かを前進させるためにはやはりより良い状態を目指して現状を見直す「批判」が不可欠だと考えています。
Edit by Erika Hosoda
ブランド戦略に関わるご相談はこちらから
