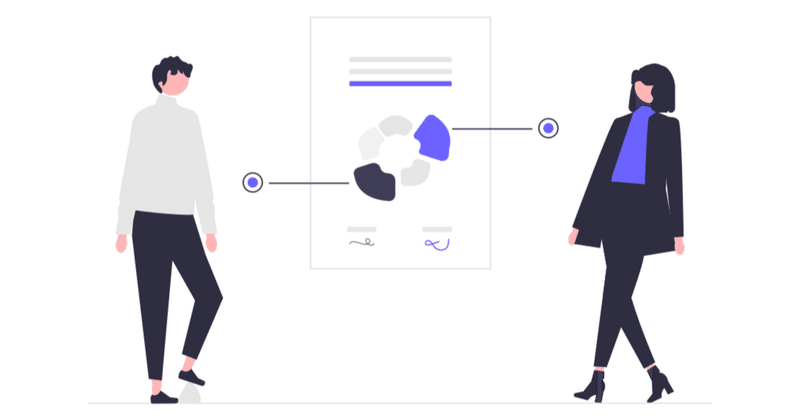
「積極的是正です」と叫んだ日
今年3月のとある日。
ある会社でB Corp認証取得に必要な自己採点アセスメント・BIAを2日間くらいの合宿形式でざーっと見ていくセッションをしました。社長さん含め取締役、各部署の部長総勢15人くらいも参加してくれました。さてB Corp認証を検討するような会社です。その中に女性役員・部長は何人いたでしょうか?
正解はゼロです。全員男でした。良くも悪くも、私は幼稚園の頃によく男子集団に1人とか2人しか女の子いなくてもドッチボールしていたので個人的に違和感や威圧感はないのですが、B Corp、「ここからですね」とど真ん中で言える状況だったかもしれません。
奇しくもその日は国際女性デー。BIAを読み上げながら「これは積極的是正ですよ」と叫んでいました。
BIAにはダイバーシティに関して踏み込んだ内容が出てきます。
□ 全ての求人広告にダイバーシティ・公平性・インクルージョンにコミット
するという宣言を含めている
□ 応募書類や履歴書を、氏名などの情報を伏せて匿名・ブラインド評価を
している
□ 求人広告の文言や要求が包括的で公平かを分析している
□ 性別や人種/民族、その他の属性別に等しい給与か分析し、必要あれば
公平性を正す計画や方針がある
□ 過少評価グループ層がオーナーのサプライヤーを優先するポリシーがある
□ 仕事のプロセスや職場の方針において、学習障害や情緒障害に対応
そして具体的に職場に女性管理職はどれくらいいるのか、その他の過小評価グループは従業員の何割いるのかも聞かれます。女性管理職は10%いても得点になりません。
よく「社内でダイバーシティを推進していきましょう」というと、「それって逆差別じゃないですか」?と言われてしまいそうだ、という不安、よく聞きます。
時代の流れ的に、女性も社会で活躍するようになったのだし、まぁ徐々に管理職も増えていくんじゃないか。と自然に数が増えていくのを待つばかりでは何百年経っても変わりません。これを積極的に是正していこうという気負いをB Corpのコミュニティから感じます。
それがよくわかるのはこの絵です。
Interaction Institute for Social Change (IISC) という団体が、画家Angus Maguireに依頼して作成したもので、ネット上によく出回っています。

一番右のReality(現実)は、富める者は富み、恵まれない人はその穴から抜け出せない状態であり、みんなが同じ状態で野球を楽しめるようにするには、Equity(公平)に台を提供する必要があります。Equality(平等)に台を渡す場合は皆1個ずつですが、状況に応じてもしかしたら何も与えない人もいるかもしれないし、苦しい状況にある人には2つの台を与えることが、ダイバーシティ施策でよく使われる言葉「DEI」のE=公平性というものです。公平性を目指すために積極的是正が時には必要になるということです。
BIAに出てくる施策は実は欧米企業が今や結構当たり前のようにやっているものだったりします。
求人広告のDEIコミット
例えばGoogleの求人をどれでもいいので見てみると、1番下にこんな文言が書いてあります。
Google は、雇用主として機会均等とアファーマティブ アクション(積極的差別是正措置)を実施していることを誇りとしています。Google は、サービスの提供対象であるユーザーを代表する人材の育成と帰属意識を持てる文化の醸成に取り組んでいます。また、人種、信条、肌の色、宗教、性別、性的指向、性同一性またはその表現、国籍、障がい、年齢、遺伝情報、従軍経験、配偶者の有無、妊娠またはそれに関連する状態(授乳を含む)、親になる予定、犯罪歴(法的要件に一致する場合)、法律によって保護されるその他の状態にかかわらず、均等な雇用機会を提供すべく尽力しています。
欧米では求人広告には必ずデフォルトでこんなような文章が書いてあります。むしろデフォルトすぎて形骸化していないかチェックする必要はあるかもしれないですし、定型文ぽいからこそ、各社の色が出ているか分析しやすいかもしれません。Googleは以前、妊娠中、これから親になる方も安心してくださいと別で記述されていたので、配慮されている印象を持てました。
過小評価グループとの取引
BIAには過小評価グループという言葉が出てきます。企業の社長や政治家、学校や自治体などあらゆる社会的集団の中で、これまで何かの「長」について代表を務める機会に恵まれなかった人たちのことを指します。日本では「長」が専ら日本人男性だとすると、それ以外の姓・国籍・年代ということになります。例えば女性が社長(正確には株主)の会社からの仕入れを優先しているか、と問われると、「いやそもそもこの技術で作れる会社は限られているのだから、女性社長の会社と取引しようなんて言ったら取引できる会社がなくなっちゃいますよ」と言われたこともあります。これは社会全体で底上げしていく必要があります。
ちなみにアメリカでは、大手スーパーのウォルマートが「サプライヤーインクルージョン」というプログラムを実施し、女性、国籍上のマイノリティ、退役軍人、LGBTQ、障害者が大株主の会社との取引をウォッチしています。

日本人の女性社長の会社も、とある欧米企業から取引の声がかかり、それはもちろんその製品自体の価値もありますが、女性やアジア人というマイノリティとの取引を優先する施策の一環でチャンスが巡ってきたというのもあるそうです。
給与差の分析
これは日本でも、いわゆる「女性活躍推進法」で301人以上雇用する会社では義務となってきました。BIAで男女ごとに給与の差を分析しているか聞くと、よく「うちの会社は男女別に給与テーブル分けていませんから、平等ですよ」と返ってくることがあります。しかし、会社丸ごと男女で分けて平均給与を算出すると大体の会社は男性の方が高くなります。元々スタートの給与は男女同じはずなのに、なぜか男性の方が稼いでいることになってしまうのは、容易に想像できる通り、男性管理職が多いことが要因の1つです。さらには同じ職位の中でも給与バンドがある場合にやはり女性の方が「評価が低い」となりがちです。メルカリさんは「説明できない格差」と呼び、日経などでも取り上げられました。
女性は男性よりも謙虚な姿勢で話す傾向があるため、評価の際、簡単に言うと不利な状況に陥りがちです。これは日本女性に限ったことではなく(正確に言うと欧米人と日本人の間でも差がありますが)、世界中の女性がそうです。少し昔ですが、コンサル会社のBain&Companyが示した調査はとてもわかりやすいです。新卒時(上)では、Aspire(志)は女性の方が高く、Confident(自信)も男性と同じくらいあったのに、社会人経験を積むと、志も自信も男性より明らかに低くなってしまっています。

故に、男性と比べたときに、同じ事柄に対して女性がなんと表現しているか気をつける必要が出てきます。単純に「下駄を履かせる」とか「男性が気を遣う」ということではなく、公平に評価する積極的是正が必要になりますし、女性自身が上手に自分を表現できるように学ぶ必要もあるかもしれません。
「でも女性自身がそこまで頑張りたくないって、管理職を望まないケースがあるんですけど」もよく聞きますよね。今の上にあがった時のリーダー像が、人1倍働いてなんでも責任を取る必要がありそうだからです。
最近の日経新聞にも「同意なき働き方」の多さが取り上げられていました。残業・転勤に「Yes」と答えられる人でないと管理職は難しいという実情から変える必要がありそうです。

先の研究例も男性脳・女性脳として挙げていますが、それ以外の性自認のことも考えればもっと実情は複雑です。子どもがいるから〇〇、男だから〇〇、18時以降は絶対残業NG、週末は家族のためにあるもの、いろんな固定観念を取り除いていくことが第一歩なのかもしれません。
先日大阪のルクア で開催されたB Corp認証のいいものマルシェは、B Corp認証企業を切り口に、みんなにとっていい働き方のヒントを与えてくれそうです。
