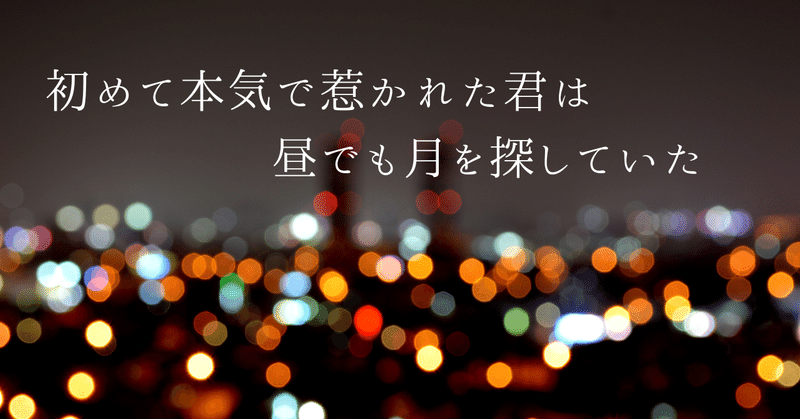
月みたいな人
1月17日。
例年よりも寒さを感じない、なんだか冬らしくない1月。
僕の目の前にいる彼女は、鎖骨まで伸びた黒髪に、切れ味のある一重がなんだか誰にも飼われない猫のような子だ。
そんな彼女だが、会う時はいつも、周りにたんぽぽを咲かせられるんじゃないかと思うくらい、明るい笑顔で駆け寄ってくる。
多分、彼女の周囲の空気は常に28℃くらいある。
だから、今年の冬は例年よりも暖かく感じるのだろうか?んなわけないか。
彼女はいつも美味しそうにご飯を食べる。
「おいしそう~!」「おいしいー!」
を一人で繰り返している。家で一人で食事をとる時もこんなにリアクションをするのだろうか?僕の前だからオーバーにしているのだろうか?
きっと、一人でも、誰の前でも、変わらないんだろうな。
君は自分だけが美味しく食べるだけでは満足できないらしく、
いつも「おいしい?」と満面の笑みで聞いてくる。
君よりいい反応ができないのを分かっているから、ちょっとプレッシャーに感じつつも、少しぶっきらぼうに「おいしいよ。」って返す。
僕の不躾な「おいしいよ。」でも君は満足そうに頷く。
例えば僕が、「そんなに美味しくないかも」って答えたら君はどんな顔をするんだろう?
悲しむのかな?変わらず頷くのかな?
悲しむ可能性があるのなら、これからも僕はぶっきらぼうでも「おいしいよ。」って答えておこう。
君と出会って半年が経とうとしているけど、未だに僕らは名前のない関係を続けている。いや、一般的に言う「友達」になるのかな?
初めて会ったあの日から確実に僕は君に惹かれていた。
今まで出会ったどの異性とも違う。
凛とした姿勢は、君が今まで生きてきた道がまっすぐで綺麗な花が沢山咲いた1本道であることを教えてくれた。
光射す道を背筋の伸びた姿勢で歩き続ける美しい君。
その周りには、四季を超えてたんぽぽや向日葵や椿やクリスマスローズが一面に咲いている。そう、君の前では季節さえも本来いるべき場所を忘れて一同に集ってしまう。
そんな強い吸引力のある君は、話し始めると思ったよりおちゃらけていた。
すぐ冗談を言うし、意外とふざけたりもする。その度に漫画みたいな表情で目をまんまるにして驚いたり、手を叩いて笑う姿は、
僕でも仲良くなれるかもと錯覚しそうなほど親近感の湧くものだった。
途中でお手洗いのために席を立った君はなかなか戻らなかった。
8分後、顔を真っ赤にして戻ってきた君に訳を聞くと、
トイレの前で中に入っている人が出てくるのをずっと待っていたらしい。
誰も中にはいないのに。
そもそもどうしたら、そんな勘違いが起きるんだろう?かなり疑問に思ったけど、それ以上に君の頭の中を覗いてみたい気持ちの方が膨らむのを感じた。
君がこの世界をどう見ているのか、気になった。
僕と同じものを見ても、君はもっともっと面白く魅力的にこの世界を捉えられるんだろうな。羨望の気持ちってこういうことなのかもしれない。
そんな君と毎日メッセージで連絡を取って、月に2回くらい出掛ける。
僕が毎日の中で君を思い出す回数は、きっと1日に運行される山手線の本数より多い。微妙な例え方でごめん。結構、かなり思い出しているってこと。
君はどうなんだろう?そもそも、君だけが存在する世界がこれほどまでに完璧で美しいのに、君は誰かを思い出すことはあるのかな?
君一人で十分に世界は完結するというのに。
誰も君の世界に立ち入れない、そうであってほしいという僕の願望から、君の過去の恋愛について触れたことがない。触れられない。
分からないけど、どんな話だとしても確実に僕は大きなダメージを受けるだろうという確信がある。確実な確信。変な日本語だね。
その確信は現実のものとなった。
どうしてだろう、急にどうしても君の過去に触れたくなってしまった。
きっと、いつも君が美味しそうにご飯を食べるのに、ふと視線の落とした先に底の見えない暗闇が見えたからかもしれない。
暗闇を見る君は、真顔なのに辛そうで、虚無だった。
僕は言葉に詰まった。
君を目の前にして言葉に詰まったのは初めてだった。
いつもなら湧き出る泉のように言葉が出てくるのに、この時ばかりは何も出てこなかった。
だからかもしれない、ずっと聞いてみたかった言葉を口にしてしまったのは。
「今まで付き合った人はいるの?」
うわーーー。自分でも気色悪い質問だって分かってる。
せめて、もっと聞き方を工夫できただろう、なんでこんな直球で投げたんだよ。一気に後悔の念が押し寄せてくる。
「いるよ。」
後悔の念が何十倍にもなって更に押し寄せてくる。
聴かなきゃよかった。分かっていたことなのに、改めて聞いたことでもう戻れないところまで自分は押し寄せられてしまった。
「どんな人だった?」
聞いてしまった。
「うーーん。月みたいな人だった。」
月???それはいい人だったのか、性悪なやつだったのか、どちらとも取れない。こういう時、僕は想像力と読解力のなさを心底恨む。
「というと…?」
あーあ。もうなんかあほっぽさが丸出しじゃないか。悔しい。
でも聞かずにはいられなかった。
「月。私とは近いようで、正反対。生きる時間が違うの。でも、明るくて、導かれるような瞬間も沢山あって、満たされたかと思えば次の時にはもう欠けている。それでたまに見えなくなっちゃうの。近くて遠い。赤くて青い。
丸くて欠けてる。みえているのに見えない。そんな人。」
次の日。僕は毎朝欠かさず送っていた君へのメッセージを初めて送らなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
