
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】グローバリズム
ニュースでよく耳にする言葉に、グローバリゼーションがあります。
グローバルは、英語で、
「地球規模の」
「世界的規模の」
を意味することから、何となく理解している人も多いかもしれません。
グローバリズムとは、一般的に、国境という物理的な垣根を越えて、経済、政治、文化などを地球規模で拡大させる考え方や姿勢のことを指し、英語で地球を意味するグローブ(globe)が元になっており、日本語で、地球主義と訳されます。
そして、グローバリゼーションとは、国や地域の垣根を越えて資本や労働力の移動が活発化し、社会や政治、経済、文化が地球規模で拡大する、ことを指す言葉です。
グローバリゼーションは、16世紀、ヨーロッパの大航海時代に始まり、1760年代の産業革命で一気に拡大したと考えられています。
第一次世界大戦、第二次世界大戦の時期は、一旦停滞しますが、20世紀の後半からさらに、進展しました。
戦後の日本経済も、グローバリゼーションにより、世界経済とのつながりを深めて、急速に成長(高度経済成長)を遂げました。
輸送手段や交通機関の発達に加えて、インターネットの普及をはじめとする技術革新が、グローバリゼーションを、大きく進展させています。
今後は、Aiやロボット技術の活用により、国境を越えたバーチャルワークや労働の自動化が進み、その動きは、一層、加速する見込みです。
ここで、国際化との違いに触れておくと、国際化とは、国境があることを前提とした自国と他国の相互作用を表す言葉です。
一方、グローバリゼーションとは、資本や労働力の流動性が高まり、国境に関係なく移動する状態を指している言葉です。
【参考資料】
【関連記事】
歴史をいかに学ぶか?
https://note.com/bax36410/n/n7e9e01ef3591
【レポート】感染症と世界史
https://note.com/bax36410/n/n3a574ae7ab76
【一冊一会】橋川文三「歴史と危機意識―テロリズム・忠誠・政治」
https://note.com/bax36410/n/nbadce796d84d
【選書探訪:有難い本より、面白い本の方が、有難い本だと思う。】「集中講義!アメリカ現代思想 リベラリズムの冒険」仲正昌樹(著)(NHKブックス)
https://note.com/bax36410/n/ne6c2e038cf5f
さて、グローバリゼーションには、どのようなメリット、デメリット、及び課題があるのでしょうか。
■メリット
大きなメリットといえばコストダウンです。
製造業の場合、先進国の企業が人件費の安い新興国や発展途上国で生産活動を行えば、商品を安価に製造できます。
商品がローコストで生産されれば、消費者も今までより安い価格で購入できるようになります。
一方、生産工場が建てば現地での雇用が拡大し、経済が潤います。
先進国のノウハウを新興国や発展途上国が活用し、後進国の発展につながるメリットもあるでしょう。
また、かつては自国だけだった商圏が世界に広がるという利点もあります。
ビジネスチャンスも大きく拡大するでしょう。
さまざまな技術や商品に触れる機会が増え、さらなる技術革新や新商品、新サービスにつながる可能性もあります。
■デメリット
一方、デメリットは、市場競争の激化による価格競争のヒートアップや、貧富の差の拡大が挙げられます。
生産拠点が海外に移ることで自国の失業者が増加したり、産業が空洞化し衰退したりする可能性もあります。
文化や価値観の違いによる対立や、技術や優秀な人材の流出などの問題も起こりえます。
そして、新型コロナウイルスの世界的な流行に見られるとおり、感染症の拡大も、グローバリゼーションのデメリットの一つと言えます。
この様に、グローバリゼーションには、経済成長や技術革新などさまざまなメリットがあります。
一方で、価格競争の激化や感染症の拡大などのリスクがあることも忘れてはなりません。
■課題
カネ(資本)や企業がうみだしたモノが国境を越えて移動するしくみと、ヒト(市民)が国境を越えて移動するしくみは同じようで異なる面があります。
また、それらが市民社会に与える影響も異なっています。
更に言えば、社会的再生産に関わる領域も、重大な影響を被っています。
現実には、グローバル化を担う主体毎に、「複数の (multiple) グローバリゼーション」が存在しおり、それゆえ、また、その影響も複数的である点が、問題を複雑化しているます。
大局的にみれば、モノ、カネ、さらには、情報のグローバル化は、過去100年、あまりに大きく進展したものの、ヒトのグローバル化は、依然として道半ばというところであると推定されます。
それは、主権国家システム、ないし国民国家という政治システム(あるいは社会統合)のあり方(政治哲学)と無関係ではありません。
足元の2020年代においては、この存在感がふたたび高まっている状況であり、グローバル化も足踏みしている状況であると考えられます。
ようするに多様な主体が、社会領域の多様な次元において、多様な思惑をもって推進しているのが、実は、グローバル化(ないしは脱グローバル化)なのだと、知識人達は指摘しています。
この意味において、これらのグローバル化現象の内実に接近するためには、政治学、社会学、歴史学、哲学等の経済学以外の知見も借りながら、グローバル化のさまざまなかたちを考える必要に迫られているのが、私たちが生きる現代社会です。
その種々の課題を考えるときに注意すべき点として、目先の利益を追うのではなく、公私において、その影響を考慮し、多角的、長期的な視点に立って進めていく姿勢が大切だと言えるでしょう。
その流れの中で、この様な世界情勢に合わせた今日の政治体制は、近代政治哲学が構想したものです。
【参考図書】
「近代政治哲学 自然・主権・行政」(ちくま新書)國分功一郎(著)
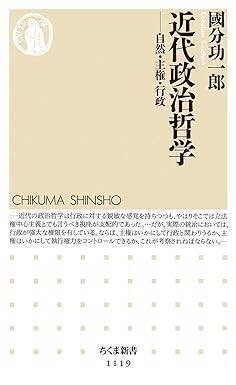
「はじめての政治哲学」(岩波現代文庫 学術)デイヴィッド・ミラー(著)山岡 龍一/森達也(訳)

「よくわかる政治思想」(やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)野口雅弘/山本圭/髙山裕二(編)

ならば、その基本概念を再確認すれば、いま私達の体制が抱える欠点についても把握できるはず。
グローバル化のなかの共生倫理を考える指標として、以下の政治哲学に関して、
■功利主義
■プラグマティズム
■リベラリズム
■リバタリアニズム
■コミュニタリアニズム
これまで【関連記事】の通り、省みてきましたが、
【関連記事】
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】クリスチャンリアリズム
https://note.com/bax36410/n/nacae111ee25b
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】功利主義
https://note.com/bax36410/n/n8cfc4f589169
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】プラグマティズム
https://note.com/bax36410/n/nd8eab49c931f
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】リベラリズム
https://note.com/bax36410/n/n1d572d4c196e
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】リバタリアニズム
https://note.com/bax36410/n/nb7400429866e
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】コミュニタリアニズム
https://note.com/bax36410/n/n9db59c1ae0cc
最後に、その当時に発刊されていた新書をテキストにして、今回は、「グローバリゼーション」について省みます。
【テキスト①】「テロ―現代暴力論」(中公新書)加藤朗(著)

[ 内容 ]
国際社会への暴力的な示威・脅迫行為である現代テロは、一九六八年のイスラエル航空機ハイジャック事件によって幕を開けた。
冷戦時代は東西の代理戦争的側面を持っていたテロだが、冷戦終結後、かえって規模が拡大し、手段も過激化している。
一般市民を巻き込む非常識的な方法で世界観の対立を表現してきたテロ。
その事例から学べることは何か。
現実のものとなりつつあるメガデス・テロを防ぐための要点を示す。
年表つき。
[ 目次 ]
序章 「目的なきテロ」の時代
第1章 テロとは何か
第2章 現代テロの始まり―一九六八年
第3章 現代テロの衰退
第4章 イスラム・テロの勃興
第5章 冷戦後のテロ―ポストモダン・テロの登場
第6章 二一世紀のテロ
[ 発見(気づき) ]
一部で、9・11をはじめとする冷戦後のテロのことを、これまでのテロと比べ、政治的な原因に還元できないのが特徴であり、文明の持つ複雑さに対する苛立ち、合理主義に対する思想的な反発、情報化社会における感情の統御不可能な傾向を原因とする「二十世紀型社会病理としてのテロ」と呼んでいる。
すなわち、9・11は目的なきテロとしか表現しようがなく、ニヒリズム・テロであると。
冷戦終焉までのテロは政治的であったのに対し、その後のテロは反近代的で(ユナボマー、環境保護テロ、動物擁護テロ、反中絶テロ、原理主義テロなど)、性格が異なるっている。
9・11後、多くの論者がテロの原因を様々な構造的暴力に求めた。
例えば、パレスチナ問題、貧困問題、反グローバリゼーションなどである。
これらの議論に対し、ウォルター・ラクォールも述べているように、「テロは絶望から生まれ、その原因は社会あるいは国家にある」、あるいは「人々に希望を与え不正や貧困を排除すれば、テロリズムとの戦いにも勝てる」との考えは、1970年代に生まれたマルクス主義に基づくイデオロギーにしか過ぎないとし、その反証として、そういう論者が、貧しいネオナチの人間によるテロに対しては構造的暴力を持ち出さないことを挙げている。
オウム真理教がそうであったが、冷戦後、確かに単なる破壊を目的としているとしか思えないテロが増えている。
9・11もその一つ。
これはかつての政治テロとは区別されるべき、ニヒリズム・テロの登場と捉えることができる。
このようなニヒリズム・テロはなぜ生まれたのか?
それは、文明の持つ複雑さに対する苛立ち、合理主義に対する思想的な反発、情報化社会における感情の統御不可能な傾向が挙げられ、最近のテロは20世紀文明の鬼っ子であるか、冷戦後の共通の世界観の喪失と、そこから生じた世界観の対立が背景にある。
[ 教訓 ]
このような背景を持つニヒリズム・テロに対してどのように対処すればいいのか。
対症療法として「妥協するな」ということか?
長期的観点から、テロ根絶は無理でも管理は可能だとして、新たな世界大の紛争管理体制の早期構築をすることも必要か?
一方で、目的のないニヒリズム・テロには断固たる態度で臨み、他方では、新しいテロ管理体制構築を急ぐべき。
しかし、どうも世界大のテロ管理体制作りが進んでいるようには見えない。
欧米対立が大きな原因の一つと思われるが、ここは何としてでも早急にそのような体制を構築して欲しいものである。
日本がそのために貢献すべきなのは言うまでもない。
結局、犯人の意図と関わりなく、第三者が目的をどのように解釈するかが、テロか犯罪かを決めることになる。
「テロ」というものが初めから独立して存在するわけではなく、当事者の関係によってある暴力行為に「テロ」という言葉がかぶせられる。
「誰」が「誰」を「テロリスト」と呼ぶのか。
そしてそのプロセスに自由民主主義がどのように関係するのか。
[ 一言 ]
テロリズムの定義付けが困難な理由として、 次の三つを挙げることができるという。
第一は、 どのような目的で定義を行うかによってテロリズムの範囲が異なってくるからである。
例えば、 いかにテロリズムを防ぐかという目的で定義する場合は、 取締りが容易になるように、テロの範囲を広くしがちである。
逆に、 外交上の目的で定義する場合には、 自国の暴力行使をテロリズムの定義から外すために定義が狭くなりがちとなる。
第二に、 テロリズムとされる行為の政治的な目的性をどのように評価するかによって、 その行為をテロに含めるか否かが変わってくる。
ある行為をテロリズムと定義する際、 その行為の目的が政治的であることを前提にしていると考えられる。
それゆえ、 定義する者の政治的立場によって評価が異なり、 その行為をテロリズムに含めるかどうかが違ってくる。
第三に、 上記第二の理由と関連するが、 テロリズムは、 政治的目的性を達成するためにきわめて有効な手段であるがゆえに、 自らに有利になるように定義しようとするからである。
このような困難が存在しているが、 それでも国際法レベルにおけるテロリズムの定義付けが必要なことは確かであろうと思われる。
【テキスト②】「親米と反米 戦後日本の政治的無意識」(岩波新書)吉見俊哉(著)

[ 内容 ]
日本社会は、特異なまでに深く親米的であり続けたのではないか。
その感覚は、「反米」世論が高まったときすら、通奏低音として流れ続けていたのではないか。
戦前戦後にわたる、大衆的なレベルでの親米感覚に焦点をあて、日本の近代や戦後天皇制、ナショナリズムの構造との不可分な関係について考察し、それを超えていく視座を模索する。
[ 目次 ]
序章 戦後日本は親米社会?
第1章 アメリカというモダニティ―「自由の聖地」と「鬼畜米英」
第2章 占領軍としての「アメリカ」
第3章 米軍基地と湘南ボーイたち
第4章 マイホームとしての「アメリカ」
終章 「親米」の越え方―戦後ナショナリズムの無意識
[ 発見(気づき) ]
戦後から現在に至るまで、日本は一貫して「親米」であり続けた。
米軍基地問題やベトナム反戦運動などで幾度か噴出した「反米」意識が、主流になることは決してなかった。
イラク戦争以降の世界各国におけるアメリカの評判は芳しいと言えず、また「グローバリゼーション」が孕む諸問題の源泉として、頻繁に指弾もされている。
それでもなお、日本国民のアメリカ支持率の高さは他国を圧倒している。
太平洋戦争で完膚なきまでにやっつけられ、戦後も国際問題や貿易関係において基本的に牛耳られてきたのに、なぜ日本人はここまでアメリカ贔屓なのだろうか。
この問いに、日米の政治史や経済史だけでは十分に答えることはできない、というのが気鋭の社会学者である著者の見立てだろう。
[ 教訓 ]
代わって本書が描き出すのは、身近な文化現象やメディアを通じた、大衆の「アメリカ」受容の歴史である。
まずは出足で、近代日本のスタート地点とも言うべきペリー来航以降、「アメリカ」から次々にもたらされたインパクトが語られる。
「自由」や「都会的」といったさまざまな近代的イメージは、大正デモクラシーから太平洋戦争に至るまで、文学者や知識人たちの言説はもとより、舞台やファッションなど日本の大衆文化に反映されていった。
この時期に、海の向こうの外部として存在した「アメリカ」は、華々しいハリウッド映画や街を闊歩するモダンガール/モダンボーイなどを通して、徐々に内なる存在として日本に浸透していったのだ。
そして、本書の眼目である、戦後日本での「アメリカ」の受容のされ方に論は進む。マッカーサー率いる占領軍は、検閲などを用いメディアにほとんど姿を見せずにいたことで、日本人から「占領下である」という意識を消去していった。
他方で、横須賀が日本のジャズの中心地帯となったように、米軍基地周辺では米兵が持ち込んだ音楽や食事が若者たちの文化に影響を与え、「名犬ラッシー」「奥様は魔女」などのTVドラマや、広告・漫画で描かれるアメリカン・ライフスタイルは憧れのものとして摂取された。
こういった私たちの日常生活と地続きの興味深い論点を軸として、主に戦後の占領期から高度経済成長期までを俎上に載せていく。
「アメリカ」が日本に根づき、もはや意識もされず、空気の如く自然に存在するものとなっていったプロセスが読み解かれるのだ。
「アメリカ」が内なるものとして日本に定着し、大衆意識と強固に結びつく一方で、しばしばナショナリズムや市民の草の根運動などとシンクロしながら湧き上がった「反米」は、最終的に国民的な心情と乖離し、孤立していった。
かくして、マクドナルドで食事を済ませ、休日にはハリウッドの娯楽大作やディズニーランドを楽しむという、「親米」であるとの自覚もほとんどないような、現代の私たちの生活が出来上がったわけだ。
[ 一言 ]
だが、最後に著者は「時代は大きな一つのサイクルを終えつつあるようにも見える」と言う。
世界的な嫌米感情のうねりや、統一歩調が目立つ米軍と自衛隊がクローズアップされることなどから、この国の親米感覚も変容する可能性を指摘するのだ。
そのうえで、日米の蜜月によって見えにくくなっていたアジアとの諸問題と向き合うことの重要性が喚起される。
あまりにも自明のものとして受け止められていた「親米」感覚を問い直す一助となる内容である。
【テキスト③】「ベネディクト・アンダーソン グローバリゼーションを語る」(光文社新書)梅森直之(著)

[ 内容 ]
二四年前、ナショナリズム研究の最重要書のひとつである『想像の共同体』を著したベネディクト・アンダーソン。
彼が二〇〇五年、早稲田大学で行った二つの講義を収録するとともに、そのメッセージを丁寧に解説する。
世界の見方が変わる、アンダーソンとナショナリズム理論への最適な入門書。
[ 目次 ]
第1部 ベネディクト・アンダーソン講義録(『想像の共同体』を振り返る アジアの初期ナショナリズムのグローバルな基盤)
第2部 アンダーソン事始(アンダーソン、アンダーソンについて語る 『想像の共同体』再説 グローバリズムの思想史にむけて)
[ 発見(気づき) ]
「国民という概念や、それをもとにしたナショナリズムという思想は、大昔から人びとに受け継がれてきたような代物ではない。
それは近代になってから資本主義と出版印刷との結びつきによって創造されたものである。」
そう喝破したナショナリズム研究書「想像の共同体」は、
「定本 想像の共同体―ナショナリズムの起源と流行」(社会科学の冒険)ベネディクト・アンダーソン(著)白石隆/白石さや(訳)
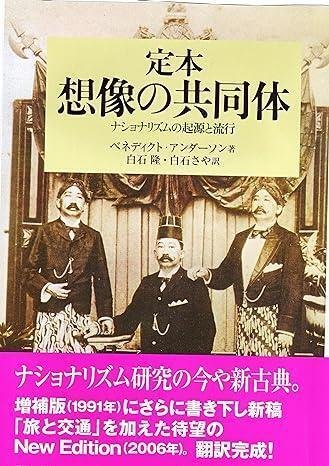
刊行後四半世紀を経たいまなお、政治学のみならず歴史学、社会学、果ては文学理論の分野にいたるまで大きな影響を及ぼしつづけている。
その著者ベネディクト・アンダーソンが2005年に来日し、早稲田大学において講演を行った。
本書は、アンダーソン本人の講義録に加えて、編著者による解説を収録した非常にお得感の高い一冊である。
[ 教訓 ]
そのお得感は、具体的には以下の3点にある。
ひとつめは、高名であるにもかかわらず――いや、それだからこそ(?)――実際に読まれているのかはなはだ怪しい『想像の共同体』に向けて、本書が格好の道案内をしてくれるだろうという点。
平明さとユーモアを兼ね備えたアンダーソンの語り口によって、読者は知らず知らずのうちにナショナリズム研究の核心へと導かれていくだろう。
ふたつめは、「想像の共同体」の、その後の動向が生き生きと語られる点。
本書では独自の歴史的視点からグローバリゼーションとナショナリズムの関係が論じられる。
通信・交通技術の世界的普及によって、すでに19世紀後半には最初のグローバリゼーションが達成されたというのがアンダーソンの主張だ。
彼はこれを「前期グローバリゼーション」と呼ぶ。
そして、世界各地に点在する植民地のナショナリストたちは、グローバリゼーションをもたらした張本人たる通信・交通技術を活用することで連帯を強め、自由と独立を求めて闘いはじめることになる。
グローバリゼーションとナショナリズムは、たがいに補完しながら拮抗し合ってきた。
これは、両者の葛藤をごく最近の現象と考えるわたしたちの常識をくつがえす歴史観だ。
さらに興味深いのは、この時代にはテロをも辞さないアナーキストたちがナショナリズムを鼓舞してきたという事実。
アンダーソンは、彼らを現代の反グローバリゼーションの闘士たる自爆テロリストたちと重ねあわせてもいる。
講演と同時期に書き上げられた「Under Three Flags」の邦訳も刺激的な講義だ。
「三つの旗のもとに―アナーキズムと反植民地主義的想像力」ベネディクト・アンダーソン(著)山本信人(訳)
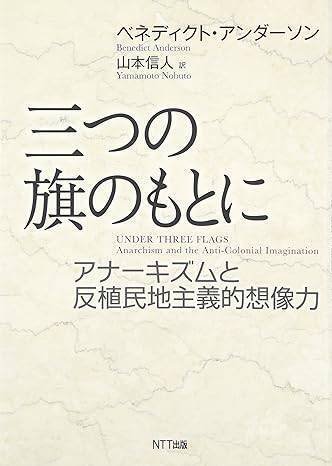
みっつめは――これが最も重要な点と思われるが――本書がわたしたちに非常に困難かつ喫緊の問題を提起しているという点。
それは、現在の「後期グローバリゼーション」状況ならびに世界各地のナショナリズム運動とどのように向きあえばよいのかという問題だ。
アンダーソンはただ、他者の言語理解、それに異言語間コミュニケーションの重要性を強調して講義を終える。
具体的な処方箋の提示はない。
だが、その空白が逆に問題の大きさを物語る。
[ 一言 ]
現在進行中であるグローバリゼーションとナショナリズムの補完・拮抗の関係ははなはだ錯綜している。
そこで起こるりうる混乱や紛争を未然に防ぐためには、わたしたちの生活を成立させているマクロな基盤を認識する必要がある。
本書はそのための格好の出発点となるだろう。
【テキスト④】「異文化理解」(岩波新書)青木保(著)
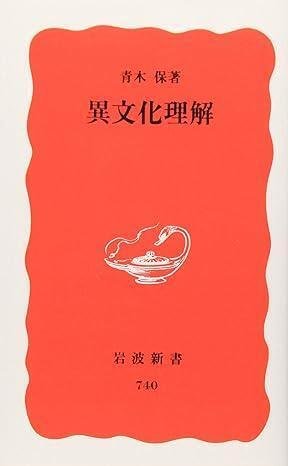
[ 内容 ]
IT化、グローバリゼーションが進み、日常的に接触・交流が増大した「異文化」を私たちは理解しているだろうか。
異文化間の衝突はなお激しく、ステレオタイプの危険性や文化の画一化がもたらす影響も無視できない。
文化人類学者としての体験や知見を平易に展開しながら、混成化する文化を見据え、真の相互理解の手掛かりを探る。
[ 目次 ]
1 異文化へ向かう(文化は重い 異文化を憧れる)
2 異文化を体験する(バンコクの僧修行 境界の時間 儀礼の意味)
3 異文化の警告(異文化に対する偏見と先入観 ステレオタイプの危険性 文化の衝突)
4 異文化との対話(文化の翻訳 「混成文化」とは 文化の境界に生きる 自文化と異文化)
[ 問題提起 ]
異文化理解って、大切だと思うけど難しい。
必要だってことはわかるけど、どこから手を付ければいいかわからない。
複雑怪奇っていうか、こんがらかった糸みたい。
昏迷を解きほぐす糸口を求めて、「あらためて異文化理解について考え、その理解の重要性を論じ」(はじめに)たこの本を読んだ。
まず、なぜ異文化理解が必要か。
この本の著者の青木さんの説明を私なりに整理すると、こうなる。
文化を均質化しなきゃいけないという立場と文化の異質性を維持しなきゃいけないという立場を縦軸にとり、自文化の維持が大切だという立場と他文化の尊重が大切だという立場を横軸にとる。
すると、「均質化+他文化尊重」(均質化が進んで他文化そのものがなくなり、それを尊重するか否かはどうでもよくなる)はグローバル化だし、「異質性+自文化維持」(異質性を維持しながら自文化が一番って考える)は文明の衝突だ。
でも、どちらもぱっとしないし、あまり嬉しくない。
「均質化+自文化維持」(文化が均質化するなかで自文化を維持する)と「異質性+他文化尊重」(文化の異質性を認めた上で他文化を尊重する)が同時に必要だ。
そのための手段が異文化理解だというわけだ。
[ 結論 ]
それじゃどうすれば異文化を理解できるか。
青木さんは、その手段として、急がないこと、異文化教育といった環境を整備すること、文化は純粋じゃなくて混成だって覚えておくこと、新しく普遍的な文化を作ろうとする「ディアスポラ」現象を支えること、「自文化を発見して異文化へ到達する」こと、この五つを挙げる。
この本を読んで、私の頭はかなりすっきりした。
青木さんの説明は、それほど明快じゃないけど、繊細だしバランスが良い。
たとえば、異文化に対する憧れは理解につながる場合もあれば軽蔑につながる場合もあるとか、異文化に対する偏見は好ましくないけど理由もあるとか、グローバル化には理由があるけど限界もあるとか、ものごとの両面を見て、極論を戒める。
明快な、つまりわかりやすい説明に飛びつくのは、実は危険なんだろう。
でも、この本に不満がないわけじゃない。
二つ挙げておこう。
第一、異文化理解の方法として、青木さんは自文化を発見することを重視する。
でも、自文化の発見って難しい。
たとえば、ここしばらく日本史をどう記憶するかが論争になってるけど、論争してる自虐史観派と自由主義史観派って、どちらも自文化を発見しようとしたけど、まったく違った自文化を発見した感じがする。
我が身を振り返るって大切だと思うけど、それがすぐに異文化理解につながるかっていうと疑問だ。
第二、青木さんは、異文化理解をめぐる日本文化の特徴を二つ挙げる。
まず、開かれた受容性と、同化や消化による閉鎖性が共存してること。
異文化を受容して、同化して、吸収すると、また異文化に対して閉鎖的になったり無関心になったりするわけだ。
[ コメント ]
でも、異文化の受容や同化や吸収って、別に悪いことじゃない。
問題は、それが閉鎖性や無関心につながるメカニズムだろう。
次に、すぐ基準を当てはめて序列化したがること。
新しい文化を目にすると、すぐに、あれよりは上だけど、これよりは下だ、とか考えてしまうわけだ。
でも、基準なしで理解するのって難しい。
それじゃ、基準を使いながら、でもあわてて序列化しない方法って何だろうか。
日本文化にどっぷり漬かってる私は、こういった点を知りたい。
【テキスト⑤】「グローバリゼーションとは何か」(平凡社新書)伊豫谷登士翁(著)

[ 内容 ]
一九七〇年代以降、近代世界は新しい世界秩序への解体と統合の時代に入った。
国民国家に編成されてきた資本と労働と商品は、国境を越え、ジェンダーや家族の枠組みを壊し、文化と政治・経済の領域性や時空間の制約すら越境し、新たな貧富の格差の分断線を引き始めている。
あらゆる領域を越え、社会の再編を迫るグローバル資本。
その新たな世界経済の編成原理とは何か。
[ 目次 ]
はじめに(時代を切り取るキーワード 二〇世紀という時代 ほか)
第1章 グローバリゼーションの課題は何か(用語としてのグローバリゼーション 「インターナショナル」から「グローバル」へ ほか)
第2章 時代としてのグローバリゼーション―空間と時間(グローバリゼーションのタイムスパン グローバル―近代のメダルの表と裏 ほか)
第3章 グローバリゼーションをマッピングする(グローバリゼーションの場と対抗 グローバリゼーションを具体化する「場」 ほか)
第4章 グローバル資本の世界経済秩序―資本のフレキシビリティの回復(転換期としての一九六〇年代 多国籍企業の台頭 ほか)
第5章 グローバル化の脱統合と再統合(排除による新しい貧困 グローバル化によるローカルな空間の崩壊 ほか)
[ 問題提起 ]
「グローバリゼーション」。
おそらく現代を読み解くための最良のキーワードの一つであろう。
様々な論者がこのキーワードを述べるが、この本の著者は、「グローバリゼーションという語によって何か共通した了解が論者の間にある」わけではないとする。
帝国主義や植民地支配など、越境した支配は、近代史上にみられることを挙げながら、著者は「グローバリゼーションは、近代における不可避的な過程であるとともに、各時代における超境空間の形成される状況を示し、さらにそうした超境空間を創り出す機構やイデオロギー等の企図」でもあるいう。
即ち、著者は、単に現代的な現象としてではなく、近代を通底するものとしてグローバリゼーションの問題を取り上げる。
そのため、著者は、安易にグローバリゼーションの定義の詳細化を急ぐことはしないで、替わりに現代におけるグローバリゼーション研究の課題について章を設けて、経済、政治、文化といった多面的な問題状況を明らかにする。
[ 結論 ]
本書の指摘でまず重要なのは、「グローバルとナショナルは相互に自立している、あるいは対立するように誤って考えられる」ことがあるが、「ナショナルが構成されるからグローバルがある」のであって、「両者は対立する概念ではなく、メダルの表と裏の関係にある」という点。
近代の国民国家成立が前提となって、グローバリゼーションが問題となるのだということ。
次に、現代とは、「こうした国民国家という世界システムそのものが流動化しつつある時代」であるということ。
この点、著者は、「近代世界において、経済的には世界的な統合化が著しく進展したが、政治・文化的にはナショナル的な枠組みが強化された」とするウォーラーシュテインの世界システム論を取り上げ、かような「経済と政治・文化の二元的な世界像」は、強国にのみ成立しえる立論であるとして批判する。
実際には、現代の経済の担い手である多国籍企業の営為などによって、文化的な側面でも越境が為され、その点でもネーションは流動化しているという。
そして、著者は現状分析として、「グローバリゼーションは政治や文化から人々の日常生活まで「規制緩和」と「民営化」というイデオロギーと権力を通して浸透し、グローバル化の過程にアクセス可能な主体とそうでない主体との区分を急速に推し進めて」きた。
「一言でいうならば、近代を特徴づけてきた差異化と均質化の過程が国境を越えて浸透し、人々を分断する境界線が世界中のいたる所に張りめぐらされている」という。
それによって、かつての第三世界に第一世界が現れるのに対して、先進国内に第三世界が現れるという事態が生じている。
「排除された新しい貧困層は、国境を越えてグローバルな規模で現れている」とする。
[ コメント ]
現代におけるグローバリゼーションがもたらす問題は、私たちの日常に直結しており、それは私たちの皮膚感覚で実感できるものである。
いまの時代というのは、世界的な規模で起こっていることが、即、自分の身近な問題として迫ってくるという恐ろしさがある。
この本はグローバリゼーションを考えるうえで、最初の一冊として適切だと思う。
【テキスト⑥】「<ぼく>と世界をつなぐ哲学」中山元(著)(ちくま新書)
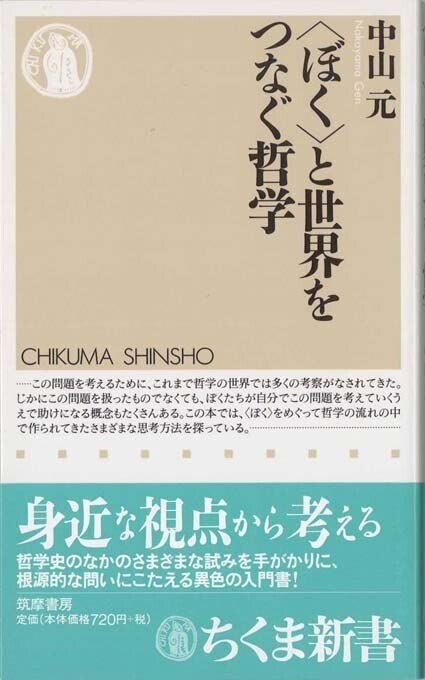
[ 内容 ]
グローバリゼーション、IT革命、ボーダーレス化によって、私たちの社会は深刻で劇的な変化を遂げつつある。
これまでの枠組みはほとんど無効になりつつあるが、新たな座標軸はまだ見出せていない。
本書では、「アイデンティティ」「言語」「他者」「共同体」など身近な問題意識に沿って哲学者たちの仕事の軌跡とその到達点を整理し、不透明な時代の〈ぼく〉について考える。
哲学史の中のさまざまな試みを手がかりに、素朴で根源的な問いにこたえる異色の入門書。
[ 目次 ]
第1章 アイデンティティの迷宮
第2章 記憶の思想史
第3章 言語と独我論
第4章 言語の起源
第5章 他者と相互承認
第6章 他者の異貌
第7章 共同体と友愛
第8章 共同体の内と外から
[ 問題提起 ]
数十本の映画の予告編もしくはハイライト・シーンをジャンル別に編集して一本の映画にまとめあげたような作品。
あるいは数十冊の哲学本のサワリ(概念)を別の文脈とテーマに応じて数珠繋ぎにした哲学的概念の見本帳もしくは概念のテーマパーク。
[ 結論 ]
この種の本は概念移植の手捌きとその連結・並べ替えのセンスが決めてで、ややもするとお気軽で浅薄なテツガク本に堕してしまうものだけれど、サイエンス・ライターならぬフィロソフィー・ライターとして新境地をひらきつつある著者はそのあたりの勘所を心得ている。
「〈ぼく〉とは誰だろうか。〈ぼく〉はどのようにして〈ぼく〉となり、〈ぼく〉とし持続することができるのだろうか」。
この「自分が宇宙の妖怪の幻ではないか」と本気で考えた学生の頃の問いをもちだして、可能世界・分身の問題系から記憶、言語、他者、共同体、身体、環境、媒介と、〈ぼく〉と世界をつなぐ絆をめぐる問題群に即して猛烈なスピードでもって数々の概念(思考の道具としての)を自在に繰り出していく。
この叙述の順序、問題と概念の配列そのものに著者の「思想」は語らずして示されている。
とりわけ最終章に出てくる「肉」の概念をめぐる考察──メルロ=ポンティの「世界の〈肉〉」をレジス・ドゥブレの「社会の〈肉〉」(象徴的な〈肉〉)に連結し、身体・環境・媒介という「共同体の内と外」をめぐる考察に一本の線を引いたもの──は刺激的で、今後の展開の可能性に期待できる。
読み尽くすことのできない深みをそなえた〈ぼく〉という書物=肉。
「この本では宇宙の妖怪のような〈ぼく〉から考察を始めた。
そして自己について、他者について、共同性について考察するうちに、〈ぼく〉というものが、他者や共同体の存在のもとでしか生まれず、存在しえないことを確認してきた。
〈ぼく〉のうちには、他者や共同体が不可視の形で畳み込まれているのである。
〈ぼく〉を読むこと、それはぼくのうちに畳み込まれた他者や共同体や風土を読むことでもある。
ぼくたちにとっても、自己はまだ読み尽くすことのできない深みをそなえているのだ。」(212頁)
例えば、Web.革命・グローバル化・ボーダレス化が進み、社会は劇的な変化を見せ、これまでの枠組みは次々に無効になっている。
[ コメント ]
新たな座標軸は、今はまだ見出せない。
そんな時代にあって、〈ぼく〉を巡る状況をどう捉えればいいのか?
「ぼく」というアイデンティテイの再確認から始めて、「言語」「他者」「共同体」「身体」等の問題意識に沿って、「ぼく」を巡る思想史の変遷を概観していく。
先の見えない現代をどう読み解けばいいのか?
「メディア」「環境」等の現代的問題についても、より深い哲学的思考からの言及が見える。
【テキスト⑦】「戦後世界経済史 自由と平等の視点から」(中公新書)猪木武徳(著)

[ 内容 ]
第二次大戦後の世界は、かつてない急激な変化を経験した。
この六〇年を考える際、民主制と市場経済が重要なキーワードとなることは誰もが認めるところであろう。
本書では、「市場化」を軸にこの半世紀を概観する。
経済の政治化、グローバリゼーションの進行、所得分配の変容、世界的な統治機構の関与、そして「自由」と「平等」の相剋―市場システムがもたらした歴史的変化の本質とは何かを明らかにする。
[ 目次 ]
第1章 あらまし
第2章 復興と冷戦
第3章 混合経済の成長過程
第4章 発展と停滞
第5章 転換
第6章 破綻
むすびにかえて
[ 問題提起 ]
本書は、自由と平等のトレードオフを軸にして、戦後の世界経済を概観したものだ。
平等という言葉には曖昧さが含まれており、著者も指摘するように「法の下の平等」という意味での機会均等は近代社会の絶対条件だが、みんなの所得を同じにする結果の平等は、しばしば自由を侵害し、貧困をもたらす。
ところが著者もいうように、「平等」への情熱は一般に「自由」へのそれよりもはるかに強い。
すでに手にした自由の価値は容易には理解されないが、平等の利益は多くの人々によってただちに感得される。自由の擁護とは異なり、平等の利益を享受するには努力を必要としない。
平等を味わうには、「ただ生きていさえすればよい」(トクヴィル)のである。(372頁)
分配の平等を求める感情が合理的な計算より強いことは、行動経済学の実験でも確かめられている。
これは進化の過程で「古い脳」に埋め込まれた本能なので、文化の違いにかかわらず見られる。
それが市場経済の基礎にある「自由な利益追求」の原則と矛盾することは、アダム・スミスの時代から認識されてきた。
戦後の世界でも、自由の拡大によって経済が発展すると平等を求める感情が強まり、規制や過剰な再分配によって経済が行き詰まると自由主義的な改革が行なわれる、というパターンが各国で繰り返された。
そのもっとも劇的なケースが社会主義である。
分配の平等によって目の前の貧しい人が救われるメリットは誰にもわかるが、そういう政府の介入によって市場がゆがめられ、経済の効率が落ちる弊害を理解するためには教育が必要だ。
社会全体が破綻するという結果が誰の目にも明らかになるには、社会主義のように70年以上かかることもある。
1980年代までの日本では、こうした矛盾を年率10%以上の成長率が帳消しにしてきたが、成長の止まった90年代には利害対立が顕在化し、政府がそれをバラマキで解決しようとして、問題をさらに大きくしてしまった。
財政と年金の破綻は、個人金融資産1400兆円をすべて吹っ飛ばす「時限爆弾」に膨張したが、政治家は与野党ともにその破壊力を理解せず、さらなるバラマキを「成長戦略」と称している。
著者もいうように、平等化の進展が自由を浸食して効率を低下させやすいのは「人的資本の水準の低い国」だとすれば、日本の知的水準はまだ先進国には達していないのだろう。
[ 結論 ]
書名だけを見ると、ありきたりの概説書と映るかもしれないが、さにあらず。
はっきりとした主張の込められた通史である。
それにしても、世界経済の通史を一人で書き切るというのは、並大抵のことではない。
戦後のほぼ六〇年と時間幅こそ限定されているものの、対象となっているのは、日本はもちろんのこと、アメリカ、ヨーロッパ諸国、旧社会主義圏、中国、東南アジア、南アジア、さらには中南米とアフリカ諸国までを含む全地球というのだから、ともかく腕力なくしては不可能なこと。
しかし、これだけ対象を拡げるとなると、たいていは平板で型どおりの説明となりがちだ。
だからして、メリハリのきいた通史となるためには、魅力的なストーリーに仕立て上げる工夫が必要。
つまり、腕力だけではなく、眼力が求められることになる。
そこで著者は、サブタイトルにあるように、「自由と平等の視点から」戦後六〇年を読み解くという手法を採った。
戦後史が抱える難問の底流には、自由と平等という価値選択が潜んでいると見たからである。
かくして、腕力と眼力に支えられた戦後世界経済史が生まれた。
ところで、「自由と平等の視点から」という手法をどう具体化するのか。
五つの軸を著者は設ける。
第一、「経済の政治化と脱政治化」のせめぎ合い。
第二、世界的な市場の拡大、つまり「グローバリゼーション」の進展。
第三、「平等と公正」あるいは「所得と富の分配」の推移。
第四、経済的摩擦や対立を裁定する「世界的な統治機構」の実態。
そして第五、市場システムを支える「資本主義のエートス」の問題。
教条的な単線史観の立場からは退けられがちな五つの軸を組み合わせながら、世界経済の推移を淡々と書き連ねる。
読み進むうちに、私は二冊の本のことを思い浮かべた。
C・P・キンドルバーガー「経済大国興亡史」と、森嶋通夫「なぜ日本は行き詰まったか」。
「経済大国興亡史 1500-1990 上」チャールズ・P・キンドルバーガー(著)中島健二(訳)

「経済大国興亡史 1500-1990 下」チャールズ・P・キンドルバーガー(著)中島健二(訳)

「なぜ日本は行き詰ったか」森嶋通夫(著)村田安雄/森嶋瑶子(訳)

前者の中で、キンドルバーガーは、性急に結論を急ぐ理論家たちをたしなめるように、歴史の本質はその複雑さにあることを諄々と説く。
また後者の中で、森嶋氏は、経済を支える社会的信条や倫理的慣習、つまりエートスが劣化していることに注目して、二一世紀の日本を「悲愴」のシンフォニーに喩えた。
そんな書きっぷりと著者のそれとが重なってくる。
この本の特徴がもう一つある。
抽象的な議論を連ねるのではなく、具体的な「事例を語る」こと。
例えば、政治的安定、私的所有権の確立、法の支配が経済的豊かさの前提となると述べて、こんな事例を語る。
一九八〇年、ジンバブエはイギリスから独立した当時、アフリカで最も豊かな国であった。
しかしムガベ大統領の独裁政治が、自由と法を踏みにじり、「法の支配」から「人の支配」へと転換し、制度としての自由を破壊した。
以来二〇年ほどの間に、一人当たり所得は半分以下となり、失業率は七割、インフレ率は年五百%という悪夢のような状況を迎えた、と。
あるいはまた、経済的豊かさの源泉は、自然資源を十分保有しているか否かではなく、いかなる人的な資源を育て上げ、いかなる制度を整えたかによると述べて、自然資源の乏しいスイスやルクセンブルクの経済的豊かさを挙げ、あるいは面積の狭い香港と広大なロシアのコントラストを語るといった具合だ。
最後に、現代社会の基本理念として掲げられてきた自由と平等は、果たしてどのような形で両立しうるのかと問いかけ、こんな感慨を語る。
戦後六〇年の世界経済史をたどってみると、「平等化の進展は自由の侵食を生む」という、かつて一九世紀にトクヴィルが提示したアポリア(難問)は、つまるところ、人的資本の水準の低い国に起こる可能性が大きいのではないのか、と。
この場合の人的資本とは、単に学校教育だけではなく様々な中間組織を通して醸成される市民道徳を中心とした「知徳」が重要な構成要素となる。
そうした意味での人的資本の蓄積が不十分な(つまり、知徳水準が不十分な)国におけるデモクラシーは「全体による全体の支配」を生み出しやすいというのである。
しかしこれは、実は、経済的に後れた国だけの問題なのではない。
むしろ著者が強調したいのは、「不足と過剰の六〇年」を経た日本の現状に向けてであろう。
「日本のような経済の先進国でも、市民文化や国民の教育内容が劣化してゆけば、経済のパフォーマンス自体も瞬く間に貧弱になる危険性を示唆している」。
「戦後世界経済史」の最後を、著者はこう締めくくっている。
まさに、前出の森嶋氏の主張と響き合う指摘である。
[ コメント ]
「大学の反省」でも、
「大学の反省」猪木武徳(著)
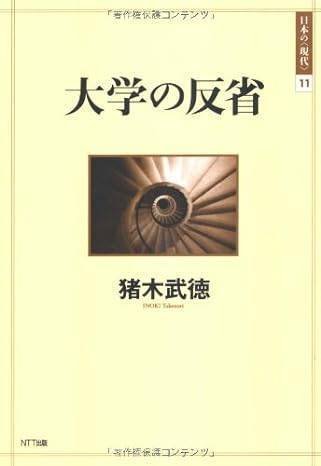
「国家の大計の根幹は教育にある」ことが繰り返し強調されていて、「なぜ日米開戦に至る一連の過程で、その結末を予知しうるだけの『才』や『智』を有していた人びとが、開戦に向けて国内の『大勢』に抗しえなかったのか」と問いかけている。
これまた本書の主張と、しっかりと響き合っている。
【テキスト⑧】「現代帝国論―人類史の中のグローバリゼーション」(NHKブックス)山下範久(著)
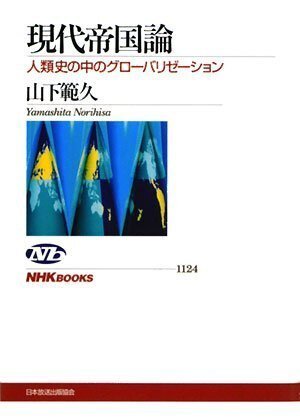
[ 内容 ]
アメリカの一極化、EUの拡大、BRICsなどメガ国家の台頭…世界は「帝国の時代」を再び迎えようとしているのか?
今後、国民国家に代表される従来の秩序は変質し、グローバル・スタンダードという新たな普遍的秩序の下で、私たちの生もまた、変質していくのか?
ポランニーからネグリ=ハートまでの様々な言説の分析や、清帝国やムガール帝国など諸帝国が並立した近世との比較をふまえ、世界の深層で起きている変化を、人類史的パースペクティヴで捉え直す。
グローバル化する時代の倫理的・思想的課題に鋭く迫る力作。
[ 目次 ]
「新しい近世帝国」の誕生?
1 人類史の中のグローバリゼーション(超越性なき世界-「帝国」を考える ポランニー的不安の時代-「大転換」は本当に起きるのか 「近世帝国」再論?清朝の統治システムに見るメタ普遍性)
2 ポランニー的不安にどう向き合うか-三つの普遍主義(国家の下に集結せよ!-ネオコン周辺の普遍主義 不安を前提に連帯せよ!-シニカルな普遍主義 「空虚な普遍性」に耐えよ!-メタ普遍主義)
3 帝国の倫理(「国際社会」とはなにか-現代に蘇るメタ普遍性 「戦争」の時代をどう生きるか-自然と社会の流動化を踏まえて)
[ 問題提起 ]
現在が「歴史的転換期」だという話は、いつも語られてきた。
そういうときよく引用されるのがウォーラーステインだ。
彼の歴史理論は、ここ500年ぐらいの世界史を包括的に展望する荒っぽいものなので、なんとでも解釈できるのが取り柄だが、逆にいうとほとんど実証的に検証可能な命題が導けない。
本書はウォーラーステインとネグリ=ハートを中心として、いろいろな世界史理論を雑然と並べたものだが、一種のサーベイとしては役に立つ。
ウォーラーステインの理論の元祖は、1970年代にフランスで、エマニュエル、アミン、フランクなどによって提唱された従属理論である。
エマニュエルの理論は、グローバル資本主義を不等価交換を作り出すシステムとして数学的に定式化し、国際経済学に影響を与えた。
そしてフランクがウォーラーステインの「ヨーロッパ中心主義」を批判したのが「リオリエント」で、
「リオリエント アジア時代のグローバル・エコノミー」アンドレ-グンダー・フランク(著)山下範久(訳)
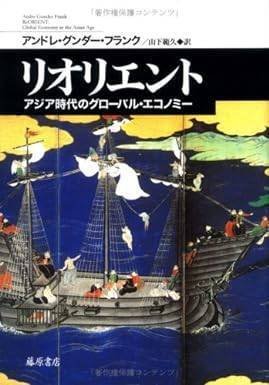
本書の議論も両者の比較が軸になっている。
[ 結論 ]
ウォーラーステインは、近世の世界=帝国システムが、ヨーロッパを中心とする世界=経済システムに取って代わられる過程として近代世界システムを描いた。
これに対してフランクは、歴史上の大部分において世界の富のほとんどは(中国を中心とする)アジアによって生み出されてきたのであり、ヨーロッパはそれに寄生して、ここ100年ほど世界の中心になったにすぎないという。
そして21世紀には、ふたたびアジアが歴史の中心になるだろう。
こうした歴史観を検討する上で本書がコアにするのが、ポランニー的不安の概念である。
これは「大転換」でのべられた、
「[新訳]大転換」カール・ポラニー(著)野口建彦/栖原学(訳)
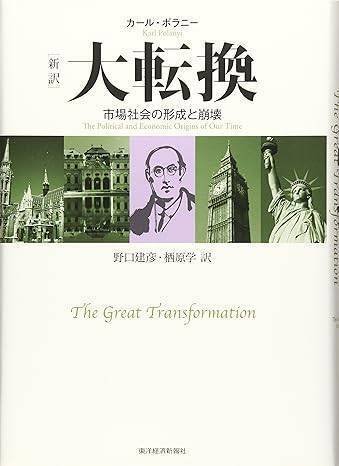
本源的な自然や人間が市場メカニズムに飲み込まれて「商品化」されることがもたらす不安だ。
近世帝国では市場の力は世界=帝国の中に封じ込められていたが、世界=経済システムは市場を中心にすえて効率を上げる一方、ポランニー的不安を全世界に拡大した。
日本の非正規労働者をめぐる問題も、その一環である。
しかし世界=経済システムの中核にある市場の等価交換システムは、その上に構築された不等価交換システムとしての資本主義をつねに脅かす。
国内で競争が激化して利潤機会が消滅すると、資本は海外に拡大し、軍事的・経済的な植民地化によってアジアを搾取してきたが、新興国が自立すると不等価交換は不可能になる。
そこで新たにレントの源泉となったのが情報技術と金融技術だが、金融技術による鞘取りで市場が効率的になると、鞘は失われる。
その実態を投資銀行は複雑な「エキゾチック金融商品」によって隠してきたが、今回の金融危機はそれを一挙に明らかにしてしまった。
投資銀行のポンジ・スキーム(※)が破綻したこと自体は望ましいのだが、それによって新興国の過剰貯蓄をアメリカの過剰消費が吸収する「グローバルなケインズ主義」の構造が崩壊すると、世界経済が縮小することは避けられない。
※:
ポンジ・スキームとは、投資詐欺(詐欺的な投資勧誘)のひとつです。
集めたお金を実際には運用せず、配当金という名で還元することで投資家の信用を得てお金を騙し取る詐欺の手口です。
具体的な手口としては、月利30%といった高配当を掲げて投資家からお金を募り、お金を運用するふりをしてそのお金を配当として還元します。
そしてインターネットは、「知的財産権」によってレントを独占してきた既存メディアを破壊しようとしている。
[ コメント ]
現代が近代世界システムの崩壊過程だという点では、ウォーラーステインもフランクも著者も意見が一致しているが、それがどこに行くのかは誰にもわからない。
おそらく世界は相互依存をさらに深め、市場メカニズムが世界をおおい、ポランニー的不安が新興国にも広がるだろう。
著者はそれを「新しい帝国の再構築」の過程だというが、旧秩序の解体は明らかでも、新秩序が再構築される兆しは見えない。
【テキスト⑨】「二十一世紀をどう生きるか 「混沌の歴史」のはじまり」(PHP新書)野田宣雄(著)

[ 内容 ]
「混沌の世紀」が到来する―クローン・グローバリズム・フリーター…科学技術・経済・個人のあらゆるレベルで混乱が起きている中で迎える二十一世紀は、不安定な末法の世になる。
そう予見する著者は、そこではもはや職業も家族も国家も、生きるうえでの拠りどころにならないと説く。
その時、人は何を頼りに生きればよいのか。
著者は、啓蒙主義、近代進歩史観への懐疑を経て、ブルクハルト、ヴェーバー、そして「現世は不安定きわまりない世界」とした親鸞の思想に辿りつく。
際限ない混迷の世紀を生き切る人生観の提示。
[ 目次 ]
序章 「混沌の世紀」―二十一世紀
第1章 「新しい中世」の到来
第2章 職業中心の人生観の崩壊
第3章 「新しい中世」の生きがいをもとめて
第4章 なぜ中世に学ぶのか
第5章 二十一世紀によみがえる親鸞の教え
第6章 二十一世紀の東アジアにおける人生と宗教
[ 問題提起 ]
「二十世紀が幕をあけたとき、世界にはまだいくつの有力な帝国が存在し、地球上の大きな部分を支配していた。・・・」の書き出しでこの本は始まる。
今生きている二十世紀とはなんだったのか、二十世紀史の入門書である。
家族も職業も国家も拠り所にならない、不安と混乱の時代が到来する。
ブルクハルト、ヴェーバー、親鸞の思想に混迷の世紀を生き切る智慧を見出す。
「混沌の世紀」が到来するクローン・グローバリズム・フリーター……科学技術・経済・個人のあらゆるレベルで混乱が起きている中で迎える二十一世紀は、不安定な末法の世になる。
そう予見する著者は、そこではもはや職業も家族も国家も、生きるうえでの拠り所にならないと説く。
その時、人は何を頼りに生きればよいか。
[ 結論 ]
金融崇拝・日本経済のグローバル化が起こり、悪が噴出し、末法思想に覆われた中世。
そこでは「その日暮らし」が人々の生き方であった。
「現世は不安定きわまりない世界」とし、中世の人々の救いとなった親鸞の他力思想こそ、現代の「混沌の時代」を生きていく智慧を与えるのではないか。
浄土真宗の寺院に生まれながら、西欧の歴史・哲学を極めた著者は、やがて啓蒙主義、近代進歩史観への懐疑を抱く。
最終的にブルクハルト、ヴェーバー、そして親鸞の思想に辿りついた著者の深い哲学と思想を通して混迷の世紀を生き切る人生観を提示。
私たち戦後の世代は学校で明治以降の近代史を授業時間不足・入試に出ないということで、勉強が尻切れトンボで終わっている。
今の50歳代の人々はどれだけ学校で近代史、特に二十世紀の歴史を身につけているか、心もとない。
今小児科の医者が不足しているように、二十世紀史を教える事のできる教師が不足、いや居ないのではないか。
私の親が生き、そして自分が生きている時代を生きる知恵として知っておかないと、将来を語れない。
自分の出自を知ることによって、人間は自分の帰属本能を満たし、心の安定を得る。
二十世紀は日本に於いては江戸幕府が崩壊し、今の日本の基礎ができた時代である。
世界においても産業革命、植民地経営、第一次世界大戦、第二次世界大戦、民族独立、社会科学、共産主義、民主主義、弱肉強食、人道主義、人権主義等めまぐるしく環境・価値観が変化した。
人類6000年の歴史を振り返っても、これほど変化が激しい時代はなかった。
日本は明治維新、第二次世界大戦敗戦の国難を乗り越えて今の繁栄を築いた。
筆者は二十世紀初頭「帝国」が崩壊し民族独立、国民国家の時代を経て、今再び帝国の時代に戻りつつある、そして復活しつつある帝国の時代に日本が対応していけるか、日本は明治維新、敗戦時以上の危機に面していると論じている。
二十世紀初頭、ドイツ、イギリス、オーストリア=ハンガリー、トルコ、日本等の帝国は民族をまたいで植民地統治をおこなっていた。
民族を複合的に纏めていたのが帝国である。
しかし近代の大量生産技術の発展により、国民に同質性をもとめた統治方式が国力増強の基礎条件となった。
国家は「政府」「民族」「領土」三位一体の凝集力を競いあった。
日本は「国家」・「民族」・「領土」が一体な世界でも稀な国である。
ドイツは日本と良く比較されるが、「国家」「民族」「領土」が一体としなって出現した国家でない。
ドイツ民族は中世の数世紀間に渡って東欧諸国に移民し散らばっていた。
筆者はドイツ民族を一体化させるのが、第一時世界大戦、第二次世界大戦を起こした一つの理由であると論じている。
ナチスドイツの敗戦により、東欧諸国から1400万人のドイツ人が数世紀に亘って住んでいた郷土からドイツ・東ドイツに追われ、そのうちの200万人が移動の途中で命をおとした。(167頁)
戦後満州からの引き上げの比ではない。
中国は多民族、多文化、多言語の影響で、日本のように自国を効率よく統治できない混乱の時代が続いた。
筆者は「孫文・蒋介石・毛沢東は中国を国民国家に変革させるため渾身の努力をしたが結果は失敗に終わった」と冷たく切り捨てている。
帝国崩壊後、三位一体の国民国家・富国強兵に向かって各国は走った。
ヒットラーの民族浄化運動、日本の台湾・朝鮮の二等国民としての日本語化政策、フランスの三色旗、ラ・マルセイエーズの歌、ラルースの百科事典等の文化運動は国民国家を作っていく「富国強兵」、「国家生存」を追求した産物である。
筆者は帝国の意味を「帝国というものは普遍性を標榜するところにその特徴があり、その版図も民族の壁を意に介せず拡がってゆく傾向をもつ(160頁)」と述べている。
情報技術・交通手段の進歩・生産技術の革新により世界が狭くなりグローバル化が急速に進んでいる。
今話題になっているSARSの世界的感染もグローバル化の結果の一つである。
人、物、金、企業、情報、犯罪、病気、思想、文化、技術が国境を簡単に越えて世界中を駆け巡ることができるようになった。
この結果、国家の徴税権、裁判権の枠が不明確となりつつある。
企業・人は最適利益をもとめて国を超えて世界を動き回っている。
生まれは中国であっても、アメリカに住んでいるときはアメリカ人、中国に住んでいるときは中国人と複数のアイデンティティーを持って企業・人は営んでいる。
国家を超えて自由に動き回るエネルギーが満ちている現実の世界、そして長い歴史の中で醸成されて世界の至る所にある複雑な人種構成、多言語・居住地域の混在状態の下で「民族自決」が現実的な選択であるのか?
筆者は疑問を提起している。
東欧・中近東・中国・アフリカ等悠久な歴史を持つ地域では、人種と地域がモザイクのように分布している。
単に線を引けば民族の住む場所が固定される訳ではない。
アフリカの地図を見てみると、国境が直線となっている国が多い。
旧宗主国が人為的に国境を引いたためである。
アフリカで頻発している内戦の遠因は民族・文化を無視して旧宗主国が勝手に国境線を引いたところに起因している。
言葉も文化も違う地域が無数にある。
そのうえ地域毎の自然環境・資源・富の地域差を考慮すると単純に「民族自決」・「民主主義」といっても巧くいくはずがない。
「覇権国を中心に多くの国家の境界を超えて放射状に広がる帝国的秩序が求められている(180頁)」。
最後の章「中華帝国と日本」のなかで、ヨーロッパにおけるドイツと同様に東アジアにおいて、
「帝国」を志向しているのは中国であって日本ではない。
(途中略)
中国は日本とは対照的に国民国家形成の条件に欠け・・・・国民国家が世界の大勢であった近代史の局面にうまく適応できなかった。
だが、多くの事柄が国民国家の枠をこえて急速にボーダレス化しつつある状況のもとでは新たなタイプの「中華帝国」形成の条件が生まれつつあるように見える」。(181-182頁)
「日本には、確定した領土の上で官僚制度を通じて緻密な統治のノウ・ハウはあっても、広漠たる多民族的な領域の秩序を大まかに取り仕切ってゆくためのノウ・ハウは無い」。(206頁)
と筆者は言い切っている。
最後に、
「すべてに受け身の姿勢をとり、現世に程良く順応して幸せに生きようとする日本の若者たちを見れば、気分はすでに帝国の時代の末端に位置する者のそれである」
と日本に警鐘を発している。
複数のアイデンティティー、名刺、国家、文化背景をもつ人々にとって、この本は説得力をもちえる。
[ コメント ]
残念ながら「他者」を認識できない読者にとっては筆者の意図を正確に理解できないであろう。
徳川幕府が黒船来航の意味を見抜けなかったように。
近代史入門書としてお勧めの一冊である。
【テキスト⑩】「アダム・スミスの誤算 幻想のグローバル資本主義 上」(PHP新書)佐伯啓思(著)

[ 内容 ]
自由主義市場経済の父と称されるアダム・スミス。
しかし彼は最初に「グローバリズム」について警告した人物でもあった。
スミス、ケインズの思想を問い直し、グローバリズムの本質的矛盾と危うさを抉り出す。
[ 目次 ]
序章「誤解されたアダム・スミス」
第1章「市場における「自然」」
第2章「道徳の基盤」
第3章「富の変質」
第4章「徳の衰退」
第5章「経済と国家」
[ 問題提起 ]
以前、いろいろなところで、「グローバル資本主義の中では、株主重視の経営がグローバル・スタンダードであり、過剰な従業員は、解雇もふくめてどんどん削減すべきだ。
それで失業率が上がるとしても、その方がかえって構造改革も進展する」という意見を聞く。
どうも釈然としない、乱暴な議論に思える。
そんな気分で、佐伯啓思「アダム・スミスの誤算/幻想のグローバル資本主義(上)」、「ケインズの予言/同(下)」を読んだ。
かなりわかりやすく説明してくれる本である。
その論理のつなげ方には納得のし通しである。
[ 結論 ]
著者は、アダム・スミスとケインズという巨人の膨大な文献に正面から相対し、通説にとらわれずに自身の視点から解題を試み、それをふまえて現代の「グローバル市場経済という幻想」を解き明かして見せる。
社会思想家としての力量の確かさがもたらす、飛ばし読みを許さぬ迫力がある。
そして著者は、金融と資本のグローバル市場の膨張が、実体経済と国家経済を従属させるという奇妙な転倒と、これが「市場の声」を通じて国家と人々の生活に大きな混乱を与えるメカニズムを分析してみせる。
これは、数年前に発生したアジア各国の通貨危機とそれに続く経済危機などで現実になっている。
市場経済の重要性に懐疑的になることはないし、経済成長を悲観しなければならないこともあるまい。
市場原理や自由競争のもつ活力を上手に生かすことで、まだまだ経済成長は可能である。
問題は、いかに上手く、人間のためにこれを生かすかという、人間の知恵である。
結局のところ、企業経営とは、グローバル・スタンダードとか、市場の声とかいったものに惑わされることなく、信念をもって行われなければならない、ということなのだろう。
そういう意味では、漠然と感じていた疑問に確かな回答を与えてくれる本である。
ケインズはなぜげんざい不人気である公共事業などによって有効需要を増大させようとしたのか、当時の時代背景や貨幣とは何かといったことから説明し、なぜ国民経済主義者(エコノミック・ナショナリスト)に変貌していったのか、といったことなどを説得性のある論理で展開してくれる。
イギリス経済の不況の原因は海外投資の過剰にあると見て、国民の産業や生活を向上させるためには国内投資つまり公共事業が必要だと説いたようである。
投資家の利益は国内であろうと海外であろうと関係ない。
しかしそれは国民生活の安定にはならない。
だから国内の需要を政府が増やすべきだと考えたようである。
この金融と産業の対立はげんざいでもつづいていて、グローバリズムの時代には資本は短期的な利益をもとめて世界中をかけめぐる。
おかげで国内の産業や経済は長期的な展望を持てずに短期利益に支配されることになる。
金融はわれわれの生活を破壊してしまうということだ。
ケインズの予言というのは絶対的な貧困が去り、ありあまる消費物資の中で過剰な生産能力をどうするのか、人びとはいかに経済を運営するのかということであった。
豊かさゆえの停滞というものだ。
つまりほしいモノがなくなれば、つくるモノがなくなり、雇用がなくなってしまうということだ。
そのときに人はどうやって生計の糧を得るのか。
というようなことをこの本ではいっているように私には思えたのだが、こんなまとめ方でいいのだろうか。
グローバルな市場の力に任せていたら、国民の生活や経済は破壊されてゆくばかりだということだろう。
といっても公共事業はもう悪と腐敗のなにものでもないし、これ以上の消費の欲望も喚起されるわけでもない。
需要と雇用が人為的につくられなければならないということなのだろうか、公共事業ではないやり方で。
[ コメント ]
自由主義のアダム・スミスは読む気がしても、ケインズなんて読む気がまったくしなかった。
反対意見にも耳を貸すべきだと思ってこの本を読む気になった。
[ 関連図書 ]
「ケインズの予言 幻想のグローバル資本主義 下」(PHP新書)佐伯啓思(著)

[ 内容 ]
「大きな政府」がもたらす非効率的な経済ゆえに、もはや破綻したとまでいわれるケインズ主義。
しかし、ケインズが自由な市場競争主義を批判したのは、確かな基礎を持たないグローバル経済への危機感からであったと、著者はいう。
また、豊かさの中の停滞と退屈が人間を衰弱させるという、今から70年近くも前の彼の「不吉な予言」は、「自立した個人」が「経済の奴隷」と化しつつあるこの世紀末の世界で、きわめてリアリティを帯びつつある。
今、われわれがケインズから学べることは何だろうか?
アダム・スミス、ケインズという両巨人の思想を読み直し、グローバリズムへの幻想の超克と、新たな社会秩序の可能性を論考する意欲作。
[ 目次 ]
序章 凋落したケインズ
第1章 国民経済主義者ケインズ
第2章 「確かなもの」への模索
第3章 グローバリズムの幻想
第4章 隷従への新たな道
第5章 「没落」という名の建設。
[ コメント ]
「大きな政府」がもたらす非効率的な経済ゆえに、もはや破綻したとまでいわれるケインズ主義。
しかし、ケインズが自由な市場競争主義を批判したのは、確かな基礎を持たないグローバル経済への危機感からであったと、著者はいう。
また、豊かさの中の停滞と退屈が人間を衰弱させるという、今から70年近くも前の彼の「不吉な予言」は、「自立した個人」が「経済の奴隷」と化しつつあるこの世紀末の世界で、きわめてリアリティを帯びつつある。
今、われわれがケインズから学べることは何だろうか?
【テキスト⑪】「ルポ貧困大国アメリカ」堤未果(著)(岩波新書)

[ 内容 ]
貧困層は最貧困層へ、中流の人々も尋常ならざるペースで貧困層へと転落していく。
急激に進む社会の二極化の足元で何が起きているのか。
追いやられる人々の肉声を通して、その現状を報告する。
弱者を食いものにし一部の富者が潤ってゆくという世界構造の中で、それでもあきらめず、この流れに抵抗しようとする人々の「新しい戦略」とは何か。
[ 目次 ]
第1章 貧困が生み出す肥満国民(新自由主義登場によって失われたアメリカの中流家庭 なぜ貧困児童に肥満児が多いのか フードスタンプで暮らす人々 アメリカ国内の飢餓人口)
第2章 民営化による国内難民と自由化による経済難民(人災だったハリケーン・カトリーナ 「民営化」の罠 棄民となった被災者たち 「再建」ではなく「削除」されたニューオーリンズの貧困地域 学校の民営化 「自由競争」は生み出す経済難民たち)
第3章 一度の病気で貧困層に転落する人々(世界一高い医療費で破産する中間層 日帰り出産する妊婦たち 競争による効率主義に追いつめられる医師たち 破綻していくアメリカの公的医療支援 株式会社化する病院 笑わない看護婦たち 急増する医療過誤 急増する無保険者たち)
第4章 出口をふさがれる若者たち(「落ちこぼれゼロ法」という名の裏口徴兵政策 経済的な徴兵制 ノルマに圧迫されるリクルーターたち 見えない高校生勧誘システム 「JROTC」 民営化される学資ローン 軍の第二のターゲットはコミュニティ・カレッジの学生 カード地獄に陥る学生たち 学資ローン返済免除プログラム 魅惑のオンライン・ゲーム「アメリカズ・アーミー」 入隊しても貧困から抜け出せない 帰還後にはホームレスに)
第5章 世界中のワーキングプアが支える「民営化された戦争」(「素晴らしいお仕事の話があるんですがね」 「これは戦争ではなく派遣という純粋なビジネスです」 ターゲットは世界中の貧困層 戦争で潤う民間戦争請負会社 見えない「傭兵」一元化される個人情報と国民監視体制 国民身分証法 州兵としてイラク戦争を支えた日本人:「これは戦争だ」という実感)
[ 関連図書 ]
「ルポ 貧困大国アメリカ II」(岩波新書)堤未果(著)
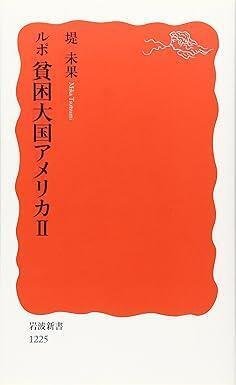
「(株)貧困大国アメリカ」(岩波新書)堤未果(著)
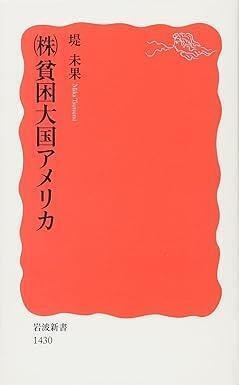
[ 問題提起 ]
衝撃的な本である。
二重の意味で。
本書は、アメリカという国全体がもはや「貧困ビジネス」で回っているおそるべき実態を、現地の取材をメインに伝えたものである。
著者の堤未果は、ワールド・トレード・センターにほどちかい米野村證券に勤めていたときに9・11テロに遭遇、イラク戦争に突き進んでいくアメリカの姿に疑問を抱きジャーナリストに転身したそうだ。
レーガン大統領の採った経済政策、いわゆる「レーガノミックス」以降、アメリカは市場原理主義をひた走り、福祉や教育にまで民営化を推し進めてきた。
その結果、「格差」と「貧困」が深刻化しているわけだが、かの国の現状は想像をはるかに超えており日本の比ではない。
その重篤な“症例”が、本書を構成する5つの章で問題別にレポートされている。
[ 結論 ]
具体的には、貧困により児童に肥満が蔓延していること(第1章)、ハリケーン・カトリーナによる被害が実質民営化された連邦緊急事態管理庁(FEMA)のもたらした“人災”だったこと(第2章)、マイケル・ムーアの映画「シッコ」でも取り上げられた医療崩壊の現状(第3章)、貧困層の学生と軍のリクルート・システム(第4章)、民営化された戦争と戦地へ派遣されるワーキングプア(第5章)という内容である。
どれもこれも酷い話ばかりで気が滅入ってくるのだが、貧困と肥満の相関、カトリーナの被害、医療問題については比較的知られていると思うので、本書の特色でもある第4章と5章、アメリカ格差社会と軍および戦争の問題を少し詳しく見てみたい。
ブッシュ大統領の肝いりで2002年「落ちこぼれゼロ法」が施行された。
全国一斉学力テストを義務づけ教育に競争を導入することで高等学校における学力の低下に歯止めをかける、というのが表向きの目標として掲げられていたが、この法律の本当の狙いは生徒たちの個人情報にあったという。
全高校に生徒の個人情報の提出が要請されており、拒否した学校は助成金をカットされるという条項が織り込まれていたのだ。
裕福な子女が通う高校にとっては助成金などどうということもないが、貧しい地域の高校は存続にかかわるため提出せざるをえない。
つまり貧困層がターゲットだったわけだ。
個人情報収集の目的は何か?
軍へのリクルートを効率的におこなうための素地づくりである。
「米軍はこの膨大な高校生のリストをさらにふるいにかけて、なるべく貧しく将来の見通しが暗い生徒たちのリストを作り直す。
そして七週間の営業研修を受けた軍のリクルーターたちがリストにある生徒たちの携帯に電話をかけて直接勧誘をするしくみだ」
入隊すると、大学の学費負担や家族までふくめた医療保険といった特典が得られるのだが、なかでも市民権を取得できることが大きな魅力として高校生を惹きつけているという。
07年に交付された「夢の法律2007」では、これまで合法的移民に限られていた市民権取得が、不法移民にも適応された。
軍にとって「国内に約七五万人いる不法移民はまさに「宝の山」だ」と著者は表現している。
狙われているのは高校生だけではない。
教育予算削減にともない、大学の学費が高騰し、学資ローンの民営化も急速に進んだ。
就職難にくわえ初任給も低下しているため、卒業するや返しきれない借金を抱えたままワーキングプアになる大卒、院卒が大量に発生している。
ロクな職もなく借金まみれになった卒業生たちの行き先は、といえば、もちろん軍だ。
学資ローン返済の肩代わりをしてくれるのである。
が、入隊してもやっぱり貧困からは抜け出せないのだ。
安い給料からあれこれ天引きされるためカネはほとんど残らない。
戦地で患ったPTSDが原因でホームレスになってしまう者も少なくない。
アメリカには、その当時、350万人以上のホームレスがいるが、その3分の1は帰還兵だという。
イラク戦争は初の「民営化された戦争」といわれる。
1990年代後半以降急成長した、民間軍事会社(PMC)や民営軍(PMF)に依存しているためだ。
大雑把には、PMFはいわゆる「傭兵」の現代版、PMCのほうは非戦闘業務一般を請け負う業者である。
このPMCが、高額なペイをエサにワーキングプアを続々と戦地へ“派遣”しているのだ。
しかし、勤務の実態は悲惨で、丸腰で戦場に立つにちかい状況も珍しくなく、米軍が使用した劣化ウラン弾の影響で放射能に汚染された現地の水を飲むことを実質的に強要されるため身体も壊す。
当然ヘタしたら死ぬわけだが、派遣社員は民間人扱いになるので戦死者には数えられない。
戦地に“派遣”されるのはアメリカ人とはかぎらない。
途上国からの出稼ぎ社員も少なくなく、賃金のダンピングが起きている。
民間軍事会社は、その当時で全世界に500社以上あるそうだ。
第5章は、日本人ながら米軍に入隊しイラク戦争へ行った加藤さん(仮名)へのインタビューで締められている。
月に一回、週末に訓練を受ければあとは自由という「ワンウィークエンド・ア・マンス」に、戦地に行くことにはならないだろうと応募したのだが、9・11後イラクに派兵された。
暗闇のなか無線機から聞こえてくる爆音や、イラク武装勢力が民間人の自動車や犬猫の死骸に仕掛ける爆弾に接し、ようやく死をリアルに感じるようになったという。
「マスコミは兵士たちの愛国心やこの戦争の正義について書き立てていたようですが、格差社会の下層部で苦しんでいた多くの兵士たちにとって、この戦争はイデオロギーではなく、単に生きのびるための手段にすぎなかったのです。
さっさとやって早く家に帰りたい、怪しい奴がいたらすぐ発砲する、死体は黙って片づける。
兵士たちは皆、そうやって機械的に考えていました。僕自身も含めてね」
著者は「加藤さんにとって日本の憲法はどんな存在ですか」と尋ねる。
いちばん聞いてみたかったことだそうだが、つまり、憲法9条を持つ日本国民として、イラク戦争に参加したことをどう考えているのかという質問である。
「アメリカ社会が僕から奪ったのは二五条です。
人間らしく生きのびるための生存権を失った時、九条の精神より目の前のパンに手が伸びるのは人間として当たり前ですよ。
狂っているのはそんな風に追いつめる社会の仕組みのほうです」
そう答える加藤さんの姿から、著者は「時代が、世界の構造が変わってしまった事実を知る」。
そして、9条が変わるよりはやく、日本の貧困層も戦争ビジネスの市場で売り買いされ使い捨てられる「商品」になるだろう、と予言するのである。
このくだりを読んでびっくりした。
といっても、加藤さんの醒めっぷりにではない。
唐突に憲法9条を持ち出す著者の思考形態に、である。
こ、これは……と思いつつエピローグに進むと、案の定、グローバリズム批判が展開されていた。
第三国の搾取をはじめ、環境破壊や食糧危機などグローバリゼーションが引き起こしたとされる問題を解決するべく「地球市民」として連帯することを呼びかけ、日本もアメリカの二の舞になるぞ!と脅すという、サヨクの人たちがこれまで繰りひろげてきた基本フォーマットを忠実になぞったものである。
冒頭に戻って確かめると「世界を覆う巨大な力」というフレーズが見つかる。
レーニン以降アントニオ・ネグリまで連綿と受け継がれてきた「帝国主義」史観だ。
[ コメント ]
著者のグローバリズム批判はどれも、経済学のほうからすでに(本書の刊行よりずっと以前に)反論が出されている、いわばFAQといっていい。
たとえば、ノーベル経済学賞のジョセフ・E・スティグリッツの「世界を不幸にしたグローバリズムの正体」や、
「世界を不幸にしたグローバリズムの正体」ジョセフ・E. スティグリッツ(著)鈴木主税(訳)
「世界に格差をバラ撒いたグローバリズムを正す」をひもとけば、
「世界に格差をバラ撒いたグローバリズムを正す」ジョセフ・E. スティグリッツ(著)楡井浩一(訳)
本書の批判に対する反論および合理的な処方箋――グローバリゼーションをあるべき姿にちかづけるための――を一通り見つけることができるだろう。
搾取されてきたはずの国インド出身の経済学者ジャグディシュ・バグワティ「グローバリゼーションを擁護する」などには、
「グローバリゼーションを擁護する」ジャグディシュ バグワティ(著)鈴木主税/桃井緑美子(訳)
サヨクな方々がどうしてまるで進歩せず同じ批判をエンエンと繰り返すのか、その理由まで載っている。
彼らがすべて正しいというつもりはないけれど、彼らは問題のひとつひとつについて解決のための具体的なビジョンを提示している。
それに対し、著者(ふくめた左派系文化人知識人)はいつもいつも「もう一つの世界」とかなんとかおそろしく漠然としたイメージしか説くことができないのである。
どちらがよりよき世界を実現するためにちかいところにいるか、理性的に判断すればあきらかというしかない。
そうしたことを頭に置き、イデオロギーに染まった部分については読み手がチェックを入れるという前提に立てば、本書はきわめてすぐれたレポートであると思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
