
【GW期間中の自由研究(その6)】ヒトはなぜ夢を見るのか(その1)
うさだだぬきさん撮影
[テキスト]
「ヒトはなぜ、夢を見るのか」(文春新書)北浜邦夫(著)

[参考図書]
「ヒトはなぜ夢を見るのか 脳の不思議がわかる本」千葉康則(著)

「人はなぜ夢を見るのか―夢科学四千年の問いと答え」(DOJIN選書)渡辺恒夫(著)

「夢の正体 夜の旅を科学する」アリス ロブ(著)川添節子(訳)

「眠っているとき、脳では凄いことが起きている 眠りと夢と記憶の秘密」ペネロペ・ルイス(著)西田美緒子(訳)

「夢を見るとき脳は――睡眠と夢の謎に迫る科学」アントニオ・ザドラ/ロバート・スティックゴールド(著)藤井留美(訳)

眠りは動物のエネルギー代謝に関係がある。
われわれ人間のように「眠る」動物は進化的にみて、哺乳類以降にならないと現れず、体温調節と深い関係があるらしい。
爬虫類らの原始睡眠は「行動睡眠」と呼ばれる。
「ヒトはなぜ夢を見るのか 脳の不思議がわかる本」は、日照や温度の季節変動の睡眠に及ぼす影響から、眠りや夢の状態において脳のなかで何事が起こっているのかを紹介する本である。
内容はいきなり難しくなったり身近になったりと、不思議な印象を受ける。
面白い話は山盛りだ。
いくつか紹介しておく。
春になるとメラトニンが減少する。
メラトニンには生殖腺を萎縮させる働きがあるのだそうである。
日照時間が長くなってくるとメラトニンの分泌量が減る。
すると生殖腺が発達してくる。
その結果、春と夏は繁殖の季節となる。
秋と冬はその逆で、性行動も抑制される。
もっとも人間はかなりおかしくてクリスマスも繁殖しているが、それでも何らかの関係があると思っている研究者は多い。
季節性感情障害などが人間にも見られるからだ。
午後眠気がくるのは半日のリズムがあるからだが、これは、熱帯地方に住んでいたころのなごりと考える研究者も多いそうだ。
熱帯に住む哺乳類の多くは、昼間は暑いので体の働きを低下させて暑さをやり過ごすことが多い。
その名残りではないかというのである。
著者は逆説睡眠は、
「『じっとしている爬虫類のように、脳幹や古い脳(辺縁系)がある程度活動している準覚醒状態』であって、原始覚醒のような状態と言えるのではないか」
と想像しているという。
つまりいわゆる古い脳だけが働いている状態が夢ではないかというのだ。
著者自身も言うように、これを証明するには多くの実験が必要だろう。
現在では、ウリジンやグルタチオンなど様々な睡眠物質があって、それが脳脊髄液や脳に溜まることで睡眠が促進されたり、体温を低下させるプロスタグランジンD2といった物質が睡眠を促進させることなどが分かっている。
また、逆に覚醒させる物質もある。
「覚醒剤」がそれだ。
そもそも覚醒とは何か。
「擬人的に表現すると、覚醒とは、大脳皮質と視床がペチャクチャと会話をしている状態である。
この活動をほどほどに抑えることも必要で、それには視床の周囲にあって編み目の形をした視床網様核が一役かっている。
このおかげでヒトはほどよい覚醒状態になる」
なお視床とは感覚の中継中枢だと思えばいい。
睡眠は、ブレーキである視床網様核が視床と皮質の会話レベルを抑えることによって引き起こされる。
基本的に意識の水準をコントロールするのは脳幹網様体と視床である。
そしてそれを支配するのが前脳の覚醒中枢と睡眠の中枢だ。
視交叉上核にある体内時計の働き、あるいは先に触れた睡眠物質が蓄積されてくると前脳基底部と視床下部前部にある睡眠中枢が動き出す。
その結果、後部の覚醒中枢や、脳幹網様体の活動が低下してくる。
さらに視床網様核がブレーキを効かせはじめ、皮質と視床の間の「会話」が抑えられる。
これが眠りである。
さらに眠りが深くなってくると脳幹網様体の働きも低下してくる。
脳幹網様体は外界に注意を払う役目を担っている。
そこが働かなくなると、ゆすっても起きない、という状態になる。
このあと、新・夢判断と題された章立てでは、夢独特の身体感覚、話の脈絡のなさや明晰夢など二重の意識などと現在の知見を合わせ、脳の働きに思いをめぐらす。
もちろん状況証拠でしかないのだが、これはこれで楽しい。
最終章は<夢はなんの役に立つのか?>といういつもの疑問。
「機能的な意味などない」というものも含めて、いろいろ説はある。
これも科学的思考の遊びとしては楽しい。
というわけで、まあ、楽しいといえば楽しい本だ。
全7章のうち最初の3章では、季節の変化と昼と夜という日内変化にともなう生物の活動変化から睡眠が生まれ、さらに多様な生活環境に適応する必要性から様々な睡眠が進化したという考えを、睡眠と呼べるのは魚から、夢を見ている可能性があるのはワニからであるとか、イルカは脳を半分ずつ眠らせているなど多くの動物の睡眠を紹介しながら述べている。
第4章、第5章は、神経生理学者である著者が自身の専門分野である、脳における睡眠と夢の発生の仕組みを詳しく語る。
たいへん興味深い内容であるが、脳の基本的な仕組みを知らない人には難しいかもしれない。
さらに第6章と第7章では、夢がなぜ特殊な体験なのか、なんのために夢を見るのか、推測も交えながらとにかくできるだけ生物学的、生理学的に説明しようと試みている。
あとがきにおいて著者は、夢を、
「心のはたらき」
から説明しようとする立場と、
「神経系のはたらき」
から説明しようとする立場に大きな溝があると感じてきたが、
「そろそろ『神経系による心のはたらき』として説明する材料がそろってきたのではないか」
という思いから本書を書きはじめたと述べている。
睡眠と夢についてできるだけ生物学、神経生理学的に説明しようとした本ではあるが、睡眠と夢に関心を持ちつづけた人間の歴史や文学作品における睡眠と夢の記述なども多数引用しており、著者の幅広い関心と知識に裏付けられた、意欲的で読み応えのある本である。
「夢」の部分は最後の数ページで、本書の大部分は世間によくある「脳」についての疑問誤解を解説する内容になっている。
例えば、
「頭は使えば使うほどよくなるのか?」
とか、
「頭の回転が速いってどういう状態か?」
といった具合である。
よく世間ではアインシュタインの脳が一般人より重かったとか、脳の大きさが話題になったりする。
男性と女性では男性の方が重く、しかし体重比で言えば、体の小さい女性の方が脳が小さくて当然なのだ。
重要なのは頭の大きさで賢さが決まるわけでもなく、鍛えれば脳細胞が増えるというわけでもないことだ。
それは、
「脳の発達と子どものからだ 改訂増補版」(みんなの保育大学 5)久保田競(著)

で久保田競氏が書いていたように、生まれた時からニューロンの数は一定で、しかもそれは回路が設定されているというだけで、電流が走って始めて使われるように、使わなければ死滅してゆくというものでした。
以前問題になっていた『あるある大辞典』のような健康食品を紹介するテレビ番組は多数あって、その中で「脳に良い食べ物」「記憶がよくなる食べ物」というものが紹介されたりすることがあるが、脳がほとんどの物質を通さないという構造を知っていれば、ある特定の食べ物で記憶など脳の機能に効果があがるというものではないということが分かる。
本来脳は堅固に外界から防御されていて、異物が入ってこないシステムになっている。
ところが狂牛病では、プリオンが脳を破壊する細胞であるにも関わらず侵入を許してしまう。
一体どうしてなのか?
実はそれが分かれば狂牛病をくい止めることができ、人類の朗報、ノーベル賞ものの発見なのであるが。
何らかの食品を摂って脳を良くしようと思っても、脳は食品の成分そのものを通過させたりはしない。
まあ、そういった内容が簡単に分かりやすく書いてある本なので、もっと深く「脳」について知りたいと思う人には物足りないかもしれない。
一つ面白いと思ったのは、
「真剣に本を読んでいても、いつの間にか字面しか読んでいないのはなぜか?」
という解説であった。
確かに読んでも読んでも頭に入らないという経験があった。
実は、
「ことばは非言語機能と結びつくことによって、はじめて生かされるのです。」
とある。
「ミカン」ということばは、実際の「ミカン」を「見る」「触る」「食べる」という経験と結びついて初めて、色や形、手触り大きさ、味といった「ミカン」全体を“生きた言葉”として認識する。
なので、特に数学の公式や英単語の丸暗記、テスト勉強などは著者が言うように、
「ことばをことばの世界の中だけで習得してゆくような場合は、いわば字面だけの勉強ということになります。」
ということになってしまう。
ただ丸暗記する知識というのは、体感した“生きた言葉”ではないので、身に付かないのである。
さて、
「ヒトはなぜ夢を見るのか」
という本題については、よく言われている「レム睡眠」、浅い眠りの時に夢を見ることが分かっている。
「なぜ夢には脈絡がないのか?」という項目では、
「しかし、目ざめているときにも、脈絡のないことを考えるときもあります。」
とあり、私たちの脳は思考しながら、ふと目に入る別のことに気をとられたり、考えたりする。
本書に書いてあることではないが、ミンスキーの『心の社会』には、この「割り込み」(interruption)ということが書いてあった。
「心の社会」マーヴィン・ミンスキー(著)安西祐一郎(訳)

まあ、夢も同じなのであろう。
考える順序、思考する流れに制約がないだけ、夢の中の方が奇想天外になったりするのであろう。
なぜ人は夢を見るのか、夢は何を意味するのか-という夢の謎については、これまでもさまざまな分野から研究がなされてきた。
「夢は無意識への王道だ」と説いた夢解釈の先駆者フロイトや心理学者ユングの研究からはじまって、現代もさらなる夢の解明がクローズアップされている。
脳生理学から見た夢の仕組み、心理学、精神分析学から見た夢の解読など、脳を舞台にして繰り広げられる夢との対話は、一体私たちに何を教えてくれるのだろうか。
「夢分析」(新宮一成著、岩波新書)の著者は、夢を見る理由を「忘れていた幼年期の記憶を呼び戻し、自らの存在の根源を再確認すること」と考える。

例えば、
「乳幼児期に初めて言葉を話せるようになることが空飛ぶ夢の源泉である」
という。
つまり、
「新しい人生の段階にさしかかり、その段階にふさわしい言語活動に参入できるかどうかが不安になった時、かつて言葉を話せるようになった時の記憶が呼び戻される。そして、空を飛ぶ夢を見ることで、かつてはできたではないか――と自分に言い聞かせている」
というわけである。
「夢は無意識の欲望」というフロイトの夢理論を踏まえ、夢がどのような仕組みによって欲望を満たし、夢に出てくる物は何を象徴しているのかなど、数々の実例分析をもとに夢の本質に迫っている。
「夢診断」(秋山さと子著、講談社現代新書)では、ユング研究所に在籍していた著者自身の夢ノートを手掛かりに、ユング独自の夢分析の考えを取り入れながら夢について語る。

文学作品などにおける夢診断もあり、興味深い。
文学作品の夢を主に取り上げているのが、「源氏物語」「今昔物語」など古典に出てくる夢を解釈した「「夢」で見る日本人」(江口孝夫著、文春新書)だ。

私たちの祖先の夢をはじめ、祖先が夢に対してどう考えていたのか、夢とどう向き合ってきたのかを考察。
ひいては日本人の心の奥を探る。
また庶民の夢、貴族の夢など時代ごとに取り上げた夢の見方が一風変わっていて面白い。
夢分析を研究した本は専門用語が多く、説明が難しくなりがちだが、「夢の読み方夢の文法」(川嵜克哲著、講談社+α新書)は、夢や心理療法について、現代の身近な問題と関連づけてわかりやすい言葉で表現している。

一つの夢を題材にしてフロイトとユングに仮想インタビューをし、著者のフロイト観、ユング観を表すなど切り口はユニーク。
本書は「関係性」という視点から夢を考えていく「夢の文法」を提唱しており、人気漫画の主人公の夢を例に親しみやすく解説している。
脳生理学的研究から捉えた夢や眠りの本も多い。
再確認すると、「ヒトはなぜ、夢を見るのか」(北浜邦夫著、文春新書)は、魚がするように、
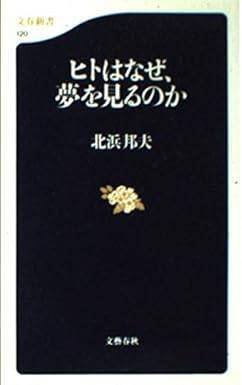
「身体を不動化させることによって脳を休ませる」
ことを眠りの基本とし、両生類、爬虫類、哺乳類の脳の仕組みから人類の進化に眠りが組み込まれていると説明する。
また、覚醒と睡眠時に脳で起きていることや、夢の意味を探る。
「夢」(宮城音弥著、岩波新書)は、心理学による夢の解釈と脳波の研究など生理学的研究によって夢みる作用を解明しているロングセラーの一冊。

「夢を見る脳 脳生理学からのアプローチ」(鳥居鎮夫著、中公新書)は、夢を見る睡眠=レム睡眠が発見されて以降の夢の不思議な性質を説明する。

夢は何のために見るのか、脳にとってどんな意味があるのかに至るまで、数々の実験結果などから眠りと夢と脳との関係をまとめている。
【関連記事】
【GW期間中の自由研究(その1)】可能性よ遠くをめざせ!
https://note.com/bax36410/n/n2f973a8fd480
【GW期間中の自由研究(その2)】きょう、だれかを、うれしくできた?
https://note.com/bax36410/n/n95e7483a0f4c
【GW期間中の自由研究(その3)】わたしが見ている世界の外に
https://note.com/bax36410/n/n3d7152f4dcb4
【GW期間中の自由研究(その4)】あたらしい自由
https://note.com/bax36410/n/n7322d56932f7
【GW期間中の自由研究(その5)】学問の春(知と遊び)
https://note.com/bax36410/n/n58236e322301
【GW期間中の自由研究(その7)】ヒトはなぜ夢を見るのか(その2)
https://note.com/bax36410/n/n121742029d2e
【GW期間中の自由研究(その8)】ヒトはなぜ夢を見るのか(その3)
https://note.com/bax36410/n/nc60ec6c4b06b
【GW期間中の自由研究(その9)】ヒトはなぜ夢を見るのか(その4)
https://note.com/bax36410/n/n8d6e472dbaac
【GW期間中の自由研究(その10)】ヒトはなぜ夢を見るのか(その5)
https://note.com/bax36410/n/nc1f5db09d354
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
